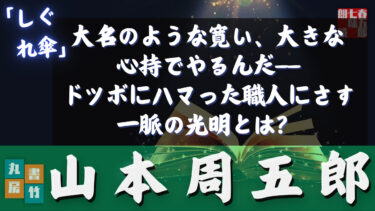戦災に消えた長編
山本周五郎先生の最初の新聞連載であった、「安永一代男」の朗読連載を開始したいと思いますが、こちらは昭和八年仙台で発行されていた河北新報に、百二十一回にわたって連載しれていました。
河北新報は戦災にあい、古い新聞がのこっておらず、安永一代男は長らく読者の目にふれることのない幻の長編となっておりました。
ところが、国会図書館に保存されていることが判明し、「浪人小説集」に掲載されました。
作中に、重要な位置をしめる人物で、田沼意次が登場いたしますが、作者は連載に先立って、河北新聞に寄せた言葉に「徳川中期における不世出の政治家」とあります。悪評の多かった田沼意次に当時から、好感を寄せていたようで、その後の【栄花物語】においても、主要な人物として活躍しております。これも朗読連載しておりますので、一聴いただければ幸いです。
作者二十九才のときの作品。「畢生の力をこの一作に傾倒すべく」の言葉通り、熱のこもった筆運び。けれど、後年の作品とちがって、記号が多いなど黎明期の作者を連想させます。山本周五郎はこれより先、千葉県浦安市に起居していたころ、
田沼意次の親子の史劇を習作していたそうで、本作はこれが元にしたそうです。が、主人公はあくまで安芸新太郎。田沼親子の一層の活躍は、昭和二十九年に週刊読売に連載された「栄花物語」を待たねばなりません。
本作の収録された「浪人小説集」には他に、五十三右衛門、おもかげ抄、がございます。五十三右衛門は昭和十五年「雄弁」四月号掲載。おもかげ抄は昭和十二年「キング」七月号に掲載です。どちらも戦前の作品。
安永一代男の翌年には、「明和絵暦」をこれも新聞連載することになるのですが、ともあれ、復活した安永一代男も楽しんでいただけたらな、と思っております。
安永一代男 前編
闇しぐれ
一
「先生、先生!」
雨戸を破れんばかりに叩く音だ。
「先生は、いらっしゃいませんか。お明けなすって、辰でございます先生!」
「おう」
安芸新太郎は盃をおいて立上った、玄関の格子を明け、棧(さん)を外して戸を明けると、転げるように跳びこんで来た男、
「辰か」
「先生、お逃げなすって」
と男はそこへ意久地なくへたりこんで、
「やって来ます、七人ずれの侍が斬り死にの覚悟、水盃をしているところを見ました、早くお逃げなすって」
「あわてるな、そんなところへ坐って騒がずと、まあ上へあがれ」
「だ、伊達にいたってるんじゃねえんで、腹をやられて、先生」
と辰は片手を下しながら、
「私や、もういけねえ」
「腹をやられた?」
新太郎は辰のうしろへ廻って抱え起すと、片手で押えている腹の傷へぐっと手をやった。ねっとり温かい血の手ざわり。
「辰!」
「へえ」
「蚤に刺された程の傷だぞ、ばか奴! こんなことでもういかんなどと、江戸ッ児の面汚しだ、しっかりしろ」
「面汚しでもいけねえ」
辰は口惜しそうに、
「もう眼が見えねえ、先生!」
「さあ拙者につかまれ」
新太郎は辰の片手を肩に、担ぎあげるようにしながら座敷へあがった。
「私なんかにゃかまわねえで、お逃げなすって先生、もうやって来ます」
「黙っていろ」
そこへおろすと手早く取出した外科薬と巻木綿、馴れた手順で、辰の着物を脱がすと、脾腹を横に三寸ばかりの傷。
「ざまあ見ろ」
と新太郎が笑った。
「腸の面も見えぬではないか、辰!」
「へえ」
「是でも眼が見えぬか」
「へえ、どうやら、見えて来ました」
「笑わせるな、さあ此方を向け」
薬で洗って木綿を巻く、荒療治だが生命に別状なしと知れたから歯を喰いしばって我慢する辰だ、
「痛いか」
「むーなあに、蚤の喰った程も感じねえ――ふう」
「脂汗が出ているぞ」
「それや駈けて来たからで――」
「はははは」
手当が終ると、新太郎は辰をそこへ仰臥させ、軽く夜着をかけてやる、
「あ、そこへ坐っちまっちゃあいけねえ、先生!」
新太郎は再び酒の膳に向う、
「お逃げなさらねえと――」
「もういうな」
新太郎平然と盃を口へ、
「貴様今日までに一度でも、安芸新太郎の逃げるのを見たことがあるか」
「へえ、そ、それやあ有りません」
「それ見ろ」
はぜの煮びたしを摘まんで、
「拙者は母の胎内にいる時分から逃げるのは不得手であった!」
「誰が」
と辰が苦しさを忘れて、
「胎内で逃げたり、隠れたり――」
「あははは、誰でもそうかの」
新太郎は笑って、
「それは不思議」
と澄ましている。
二
「全体」
やがて新太郎が振返って、
「その腹の傷、どこで受けた」
「今日」
辰は低い声で、
「出羽邸で、また賭場が立ちましてね」
「こいつ」
「まあ、お聞きなすって、例の通りすっかり剥がれての帰り、三平と二人で金杉の『裏松』で一杯ひっかけていると、対立の向うで九曜星、九曜星と云う声がするんで」
「む!」
「この辺で九曜星と云えば業平浪人……じゃあ無え、先生だ」
「そんな事を云い直すな」
「先生の外にゃあねえ筈、何を吐かしやあがるかと聞いていると、これが斬り込みの相談だ」
辰は息をついだ。
「槍二人、鉄砲一人、刀四人、ふた組に分れて裏と表から討入る、一人も生きて帰るな、時刻は四つ半(午後十一時頃)と、水盃をしていやあがる、尚よく聞くと鉄砲を持った野郎は、裏庭の束の樹に登っていて隙があったらぶっ放すと云う計略、裏庭の棗の樹と云えば此家に定っている、こりゃ直にお知らせしなけりゃあーと」
辰はふと口をつぐんで、
「先生、外で、何か音がしやしませんかい」
「大丈夫、拙者がついて居る」
「もう四つは廻っているでしょうねえ」
「いましがた聞えたようだな、まあ話を続けろよ」
「へえ」
とまだ戸外の物音に耳を澄している、
「どうした」
「なんだかどうも、今たしかに変な物音がしたようなんで」
「臆病な奴だな、そんなに外が気になるなら、雨戸をみんな明けといてやろうか」
「否々それにゃ及びません」
辰慌てて手を振った。
「それからね、三平の奴にそっと耳うちして私だけ外へ出たんで、急いで橋を渡って、方へ曲がる暗がりへ来ますとね、闇の中から誰だか知らねえが、
(若いの待て)
と出やがったんで、
「何だ」
訊くと、いきなり、
(八荒不破!)
と云やあがって居合抜かなんかやりゃあがった、畜生と思って横っ跳びにとんだが、ここん所が焼火箸を当てられたような具合、やられた、と思うと無我夢中で、
『野郎名乗りやあがれ」
と怒鳴りながら、後も見ずに此所まで、駈けつけて来たんで――」
「相手は名乗ったか?」
「へえ、どうだかよく知れねえ」
「あははは」
新太郎は笑って盃をなめる。
「名乗りあやがれと云って置いて韋駄天に逃げたのでは、相手も名乗りようがあるまい、はははは」
「笑いごっちゃあ有りませんぜ」
辰は不服そうに口を尖らした、新太郎は声を改めて、
「しかしその男、八荒不破と云って抜討をかけた奴、何者であろう」
「私あ、裏松にいた七人組の同類が、私の腕けたのをみつけて追いうちをかけやがったのだと思いましたが――」
「それなら直ぐにも斬り込んで来る筈」
「辻斬にしちゃあ妙だ!」
云っていると、表の戸を静かに叩く音がした。辰は首をすくめて、
「そら来た」
と願え声である。
三
「お頼み申す」
戸を叩いては、低くおとずれる声。
「辰、起きろ」
「へえ」
「窮屈だろうが暫く我慢しろ」
助け起して、戸棚の中へ辰を入れる、あとを閉めると、刀架から愛刀武蔵国宗二尺七寸という大業物を取って抜く、右手に提げて玄関へ下りて行った。
「お頼み申す、お頼み申す」
「――」
無言で棧を外す、雨戸へ手をかけると、がらり明ける、同時にさっと斬った。
「わっ!」
といってのめり込んだ覆面の一人、前のめりに倒れた頸から、とくとくと溢れ出る血だ。
「掛れ!」
外の声。
「――」
新太郎無言で身を退いた。戸袋の蔭にいると見たから、敢て踏込む者がない、と――不意に水口の方の雨戸をばりばりと蹴放す物音がした。
「踏込め!」
もう一度下知の声がした。
「やっ!」
といって一人が槍を、此所ぞと思う壺を狙って突出す、とたんに新太郎、そのいくかを?んでぐいと引いた。相手は引かせまいと操込む、刹那、新太
郎はその力につれてぱっと外へ出た。
「えい」
槍もろ共突放されて、後ろざまに倒れる奴には眼もくれず、とび出るが否や、右側にいた一人の面へ横なぎをくれた。
「あ!」
とたじろぐ。
「うぬ」
残った一人が無法な突き、弾丸のようにとびかかるのを、さっと開いて探しざまひっ払った、脾腹を充分に裂かれて、
「がっ!」
異様に喚きながらつんのめる。
「外だ」
裏から入ったのが、家の中で叫んだ。
槍と共に突きとばされたのは、立直って構えているが、もう積極的に突掛る気力がない、先に面をはらわれたのは、暗がりに跨んで呻いているばかり
だ。
「安芸新太郎は此所に居るぞ!」
新太郎が叫ぶ。
「掛れ!」
と二人が、一人は槍をふるって玄関から外へ出て来た。
「待て」
新太郎が――、
「名乗れ、名を聞こう」
「――」
「名乗れぬか」
「――」
「然らば意趣を聞こう、頼まれてか、遺恨あってか、どうだ!」
と、槍を持ったのが、それには答えずさっと突きを入れた、咄嗟に右へ、大きくとんで避ける新太郎、
「云え!聞こう」
と促した。とたんに、いかん! と耳を劈く声、しまったと思ってすくめる首、耳元をびゅんと弾丸は外れた。
「うぬ、我慢ならぬ」
呻くように、新太郎つつと寄りざま、突きかかる槍をはねあげて足を払う、
「うう」
だだだと横ざまに倒れる。刹那! 後から拝みうちに斬りつけるのを入身に体当り、どしんとくれて身を沈めると、
「やっ!」
振向きながら斬った。
雨がしずかに降りだして来た。
四
五人を倒して、
「まだ居るか、居たら出て参れ!」
大声に呼ぶと、東の樹陰から、同じ覆面の者が一人、ぬっと出てきた。
「貴公か、種ケ島は?」
「――」
「三十匁強薬(ごうやく)、腕がよかったら二丁は利くやつを、惜しかったな、どうだ」
「――」
何を云われても無言、小太刀を青眼にとって、じりっ、じりっと詰寄って来る。
「ほう、是は出来る」
新太郎は左へ廻りながら、
「いままでの奴らは藁人形を斬るようであったが、貴公は少し手応えがありそうだ」
「――」
「むざと殺すには惜しい」
「――」
「退かぬか、六人も倒れて居れば斬り込みの名目はたっている、退け!」
突然陰の気合。小柄な体が躍ったと思うと真正面から突きだ、全くの捨身、合討に死のうという必死の業だ。
「おっ!」
危く身を転じた新太郎、
「待て!」
といいざま相手の利腕を逆に取った。同時に蹴上げてくる足を、さっと掬って、
「待てというに」
とそこへ捻伏せた。
「――」
無言で呼吸を忍ばす曲者、新太郎はその衿を掴んで引起そうとしたが、思わず手をひいて、
「貴公、女だな!」
と叫んだ。衿へやった手に、ふっくらと弾力のある乳房が触れたのだ。そういえば腕などもむっちりと脂ぎって柔かい。
「さ、いわれい」
新太郎は声を改めた。
「何の為の暗殺だ、遺恨あってか、討たれる筋があれば安芸新太郎、逃げも隠れもせず討たれてやる、意趣を聞こう」
「お起し下さいませ――」
覆面の女が、弱々しく、
「お話し申します」
喘ぎながらいった。
「さ」
と新太郎が身を退ける、油断! 身を起した女は、ぱっと横へとんだ、
「あっ」
と新太郎が手を伸ばすと、危くすり抜けて脱兎の ように闇へ、
「待て!」
と五六間追ったが、足の早いこと、闇にまぎれて忽ち見えずなって了った。
「残念なことを――」
呟きながら戻って来ると、
「先生、御無事ですか」
と玄関内から辰が覗いている。
「拙者は無事だが、ここに無事でないのが五人ばかり居る」
「へえ五人やりましたか」
「二人は逃げた」
「五人とも皆のびてますかい」
「一人は助かるまい、だが四人は片輸になる位のことだろう、どういう訳で、拙者の首を狙ったか、それを知り度いのだが、此奴らとても饒舌るまい、大体見当はついているが――」
新太郎は刀に拭いをかけた。
「や、降って来やあがった」
「入ろう」
「此奴らをどうしましょう」
「うっちゃって置け、誰か来て拾って行くだろう、あ、酔いが醒めた!」
新太郎は寛々(かんかん)と家の中へ入って行った。雨は次第に降りつのるばかりである。
五
「ひどい血ですぜ」
内へ入ると辰が、新太郎の衣服の裾を見て声をあげた。
「返り血だ心配するな」
新太郎帯を解きながら、
「それより貴様横になって居れ、傷口を縫うまで動いてはいかぬ」
「あ痛たた」
辰は矢庭に眉をしかめて、
「そう云われたので急に痛くなってきた、あ痛たた」
辰を横にして、汚れた衣服を脱ごうとすると、ばたりと衿元から落ちた物がある。
「何だ――」
と見ると、銀平打の釵。
「はて妙な物が」
拾いあげて検めると、片面九曜星、片面が丸に二引の比翼紋だ。
「九曜星は拙者の紋だが、丸に二引は――、丸に二引――」
暫く考えていたが、はっと胸にこたえたらしく、思わず釵を握り緊めて、
「それでは彼の女が!」
と呟いた。
この安芸新太郎は何者だろう。
越後野本の小藩、林田備前守の国老次席安芸銑造は新太郎の父である。故あって家を勘当され、江戸へ出て早くも五年になる、今年二十八歳。色が白くて、眉秀で、眼涼しく髪濃く、身丈抜群にして弁舌能く――と何拍子も揃った男振りだ、芝新銭座(しんせんざ)の浜よりに、空地のまん中に立腐れ同様な家を借りて住むこと半年にして、
「新銭座の色男」
「業平浪人」
と綽名がきまって、その喧嘩っ早さ、義気の強さと共に、わっと人気が集った。殊に近くの娘や浮気な女房連は、新太郎の通る度に胸をときめかして覗き見をする位、中にも新銭座の表通りにある小料理屋「よし田」の女主人、お園という中年増が大したのぼせ方、頼まれもせぬに押掛けて行って濯ぎ物から拭き掃除、飯、酒の面倒までのがさぬ親切、これでもかこれでもかと心中立をするがもう三年になるというのにものにならぬ。それもその筈、当の新太郎は男振りとはまるで逆に、剣は真影流を極めて、自分独特の一派を編出しているし、槍は佐分利流(さぶりりゅう)をよくし、おまけに顔真卿(がんしんけい)そこのけの書も書く、それでいてまだほんのぼっちゃん、嘘も隠しもない、母親以外には未だ、女というものに一度も触れたことがないのである。
この新太郎、今年の春、安永八年の頃から、何となく様子が違ってきた。
今までは喧嘩口論、我勝に買って出て、強いという奴を片端から挫き廻り、弱い者、虐げられる者には着ている物を脱いでも之を助ける、来る日も来る日もその事で夢中だったが、ばったりそれがやんで了った。
「業平浪人どうかしたぜ」
と皆が首を傾ける程、毎日酒びたり、時々出掛るかと思うと、二三日何処かへ見えなくなって、いつかふらっとまた帰って来る。
女どもはやきもきして、
「いいのが出来たんだよ」
というし、やくざ共は口を尖らして、
「焼が廻ったのよ」
とぼやいている。唯我が辰公だけは、誰が何といっても新太郎党で、
「今に見やあがれ、うちの大将がどんなに暴れだすか、その時吃驚して馬鹿にでもなるな」
と力んでいる。
辰公、通称「目貫の辰」といって、大きな声ではいえぬが、彼実は掏摸(すり)である。
さて――。
新太郎は、九曜星と二引の比翼紋(ひよくもん)を彫った奴を拾ったが――。
恋侍従
一
お坊主が襖際から、
「伊豆守様お詰めにござります」
と云った。
「伊豆?」
田沼意次は振返った。
「はい、松本様が」
「そうか」
うなずいて、再び調書に眼を戻しながら、
「此方へと申上げろ」
「はい」
お坊主が去ると、暫くして、色の浅黒い小柄な、眼の鋭い武士が足早に入って来た。勘定奉行松本伊豆守である。
意次は机に向ったまま、調書へ朱筆を入れていたが、伊豆守の坐る気配を知ると、振返って微笑しながら、
「首尾は?」
と訊いた。
「は、是に」
伊豆守は懐中から一通の書状を取出して意次に渡した。
「返歌かの?」
「御意にござります」
と伊豆守は苦笑しながら、
「案外に手強き女性、秀持いささか持て余し気味で恋ござりました」
「それはそれは、お骨折御苦労」
「しかし」
秀持は声をひそめて、
「美しゅうござりますな」
「貴公もそう思われるか」
「なかなかもちまして、あれ程の美貌、江戸中にも数ござりますまい」
「ふふふ」
意次は笑って机へ向直った。
「それから」
伊豆守は改めて、
「江戸屋八右衛門より嘆願書が参って居りましたが、如何にござりましょう」
「見たか――」
「は」
「明礬(みょうばん)専売のことだな」
「左様にござります」
意次は眉を寄せ、口をつぐんだ。
それは前々年、即ち安永六年秋既に三井家から願い出ている事であった。大阪の山屋でも二十万両の献納金を以て、この明礬専売権を自分の手に握ろうとしているのであった。これらはみな多額の献納金に依って、全く専売権を買取ろうとする運動であったが、最近になって豪商江戸屋八右衛門が嘆願書を上ったのは、専売権は幕府に於て握り、江戸屋がその管理を引受けて、年々租税を納めようと云うのであった。
「一度」
と意次は振向いて、
「江戸屋と会ってみて――」
「は」
「だがワシではまずい、伊豆殿が会われて、篤と吟味された上、その上で何とか考えることに致そう」
「は」
礼をして去ろうとする。
「あ、伊豆殿」
呼び止めて一綴りの書類を渡し、
「是を」
「金華山の件でござりますな」
「左様」
「試掘(しくつ)をさせまするか」
「そう考えているが、それに就ては意見を聞く者がいるで――」
「風来山人でござりましょう」
秀持が微笑しながら去った。
「どうして御存知だ」
「知友にござります」
そう答えて伊豆守は座を立った。
二
秀持が去ると間もなく、傍衆の一人が、
「上様お待兼ねにござります」
と知らせて来た。
「唯今、参上仕る」
不愛想に答えておいて、尚四半刻ほど、熱心に書類のあれこれに朱を入れたり、削除したり、算盤をはじいたりしていたが、やがて筆を摘いた。
「居るか」
と声をかけると、控の襖際で、
「旬市ござります」
「花を持って参れ」
「は」
意次は手を伸ばして、秀持の置いて行った例の書状をふところへ入れる。そこへ襖を明けてお坊主が、一茎の葛(くず)の花をさした花瓶を捧げて来た。
「お上へあがるからの」
「お持ちいたしましょうか」
「いやそれは儂が持って参る、直ぐにさがる故、後藤東が詰めたら待たして置け」
「は」
意次は花瓶を捧げて長廊下へ出た。
御居間の襖まで来ると、詰めていた傍衆の一人が、静かに襖を明けて、
「相良侯にござります」
と平伏した。
意次が入って行くと、こしかけに倚って支那風の卓に向っていた家治が、
「おお」
と云って頬笑んだ。
病弱の人で、眉の秀でた、額の高い、眸の鋭い相貌に、冴えた蒼味がさして、一種の凄愴な感じを接する人に与えた。
意次の手にある花瓶を見ると、
「其方達、遠慮せい」
と小姓の方へ振返った。両名の小姓は平伏して、滑るように退出する。家治は待兼ねたように、
「吉報だな」
と頬笑みながら云う。
「どうござりましょうか」
意次も微笑しながら答えて、葛の花を卓の上に置いた、
「凶報なれば花は白の筈ではないか、焦らさずと――」
「此の花、御存知にござりますか」
「花のことなど――」
「否、花などと仰せられまするが、此の花はさように疎かにはなりませぬぞ」
「何ぞ――」
意次は頷いて、ふところから彼の書状を取出し、それを静かに家治に渡した。
「是は?」
「御返歌にござります」
「彼女からか」
「御意」
ぽっと家治の頬が染まった。
閨室(けいしつ)は、才媛の聞え高き由紀子であるが、病弱な家治との間に子なく、その上、才媛がたの女性に多くあるように、彼女は理智の勝った、順序の厳しい女だったから後宮は極めて冷たいものだった。
将軍の職を襲って十有八年、今年四十になる家治が、頬を染めながら披いた薄葉(うすよう)には、みごとな筆跡で、
葛の花の色うすきは
おとずるる人もなく秋野に
痩せし心と思いたまわれ
そう云う意味の歌がしたためてあった。
家治はみたびまで読み返すと、卓の上に膝を突いて額を支えながら、
「相良侯!」
と云った。
「はあ」
「彼女に、いつ逢えるか」
三
意次はちらと家治を見上げて、
「まだ早うございましょう」
「何故――」
「あのような女性は、急ぎましてはことを損じまするで、いま三五度」
「歌か」
家治の額が雲る。
「是非に――」
「しかし、まごまご致して居って若し 誰ぞほかに」
いいかけたが、流石に口籠った。意次は微笑しながら、
「たそがれの少将――」
という。
「白河が、なにか」
「されば」
意次はいたずららしく、
「殊の外の執心にて、日毎の文を通わせ、物を贈りなどして、彼の女性の――」
「もうよい」
家治は眉を寄せながら手を振った。それを見ると意次はにこにこして、
「しかし御安堵遊ばせ、彼の女性には少将が別してお嫌いらしく、文は封のまま火中、贈物は手をつけず返さしめらるるとの事――」
「ほう」
家治は傍らを向いて、
「名うての白河が、嫌われてか」
「流石に、京の女子は眼が高うござりまするよ」
そういって意次は笑う、家治も苦笑しながら歌をしたためた紙を巻いた。その時襖の外に、
「申上げまする」
と声がする、
「紀伊中納言様、御参入にござりまする」
家治は眉を寄せて、
「会い度うない」
と意次に呟いた、意次は頷いて、
「私、おめに当りましょうか」
「うん、頼む」
「さようなれば、これにて――」
「しかし、いまの事は、どういたしたらよいか、それを」
「兎もあれ、いま一度、御歌を」
「いつまでに」
「今宵、私が直々に会いまして」
「うん、では二刻もしたら、其許まで持たせて遣わそう」
「は、では――」
意次は辞儀をして座をすべり出た。襖の外には、紀伊家参入を報じた傍衆の一人が平伏していた。
「中納言家にはお詰の間にか」
「は」
「わしが御挨拶申上ぐるで、よろしい」
「は」
意次はそのまま雁ノ間へ向った。
御錠口から、長廊下へ出てしばらく行ったところで、不意に背後へ人の駈け寄る気配がしたから、二三歩つつと出て、意次が振返った。すると、そこに白面の貴公子が、蒼白な顔をして、差添に手をかけて詰寄っていた、意次はちらと見て、
「これは、白河侯!」
と声をかけた。
定信は、じっとり額に汗をにじませ、殆ど差添を抜きかかったが、
「御座所間近にござりますぞ!」
と意次に一喝されて、そのまま動けなくなった。意次は声を低めて、
「御短慮はなりませぬ、主殿(とのも)一人を斬ったとて、御治世が良うなりまするか、御身分柄を篤と御思案遊ばせ!」
強くいいきると、そのまま振向きもせずにその場を去った。定信は狂ったような眼で、じっと意次の後姿を見送っていたが、その唇は口惜しさに、ぶるぶると願えていた。
四
「やあ恋侍従か」
入って来た意次をひと目見るなり、紀伊治貞が荒荒しく声をかけた。意次は微笑しながら進んで座につく、
「此頃は色道修業いっそう積んで日夜邸に芸者どもを呼び入れ、歌舞の賑わいに近隣をおどろかしているそうじゃが、わしなどもあやかりたく思うぞ」
「お戯れを仰せられまする」
「戯れ――? 戯れではない、世上もっぱらの評判じゃ」
治貞は皺面をこきあげこきあげ、言葉の裏に毒のあるだけを含めていいつのる。
「明和以来の御政治逼迫、商衰え農餓え、窮民は巷に御治世を恨み奉る折柄、老中筆頭の相良殿が放埒(ほうらつ)何ぞ景気直しの禁厭(まじない)でがなあろうかと、この老人かねて頭をひねりおるが、とんと合点せぬ、どうじゃ禁厭のいわれ聞かしてくれぬか」
意次は低く、
「世上の風評など、私の存じませぬこと、お聞きすて願わしゅう存じまする」
「ほう――」
治貞は大仰に眼をみはって、
「相良殿放埒の事、根もなき風評といわれるのじゃな!」
「仰せの如くにござります」
「さようか、ふむ、心得置こう」
治貞はうなずきうなずき、
「ま、それはそれでよしとして、今日は将軍家に謁見を願いとうて参入いたしたのじゃが、御都合はどうあろうか」
「上様には、御頭痛にて」
「又か――」
治貞は皺面をこきあげて、
「御虚弱もさることながら、来る日も来る日も、やれ頭が痛いの腰がつるのと、さようなこと故大事な政治向にも隙が多く、心黒の者がのさばる始末に相成るのじゃ」
意次は聞かぬ風で、
「いずれにもあれ、右ようの次第今日の御謁見はかないますまいかに存じまする」
「いや、もう一度お伺い申してくれ、今日は吃緊(きっきん)のことにて参ったれば、押して御引見下さるよう!」
「御謁見御強要はお差止めにござりますぞ」
意次の語気がぴっと鋭くなった。
「……」
治貞は気をぬかれて思わず口をつぐむ、意次はしずかに
「今日は御登城の御例日にはござりますまい、押掛御登城にもお咎めの定めある筈、憚りながら、軽がるしき御振舞はおつつしみあそばすよう、きっとお願い申上げまする」
治貞の拳がふるえた、性来の精癖がむらむらと胸へ盛りあがって来た、しかし営中の掟を動かすことが出来ないー。
「か――!」
咽喉も裂けよと吹を吐いて、青銅の啖壺の中へ吐きすてると、
「相分った、押掛登城はわしの失策、よくぞ教えてくれたの」
いいながら立つ、意次が、
「お坊主!」
と呼ぶのへ、
「聰明な聞え高い相良殿ゆえ、ぬけめ無う、そちこちと取繕うているじゃろうが。のう、諺にも縫うた袋は縫目より破るると申して、いつかは――」
意次は治貞の言葉には耳もかさず、平伏するお坊主に向って、
「中納言様御下城じゃ」
といってすっと座を立った。それを見ると治貞嚇となって思わず、
「待て!」
と叫んだ。お坊主は蒼くなって身をずり退ける。意次はそ知らぬ態で長廊下へ――。
「待てというに、主殿!」
治貞は遂に癇癖を発していた。
五
意次は尚も聞かぬさまで行く、
「待て!」
と追って出た治貞、大声に、
「待てと申すに待たぬか、この成上り者」
と怒鳴りたてた。
しかし意次は苦笑したまま、足早にお杉戸をぬけて、自分の溜間へ入って了った。
松平越中の、殺伐な振舞といい、紀州中納言の押掛登城といい、何か風をはらむ不気味なものが、身近に迫っているのを、意次はひしひしと感じた。
田沼意次が老中の職に就いたのは、明和六年のことであった。
既に時勢は宝暦初年より悪化し諸物価の騰落甚だしく、空米相場(くうまいそうば)を停止したり、万石以下に知行所の米を買い、米価暴落を防がせたり、高利貸を禁じたり、種々の方法を講じてみるが一向に思わしくないばかりか、明和に入ってより幕府の財政は窮乏に窮乏を重ねて来た。
意次が老中に任ぜられたのは、実に斯様(かよう)な危急の時機で、将軍家治の絶対的な信任を得ると同時に、極めて劃期的な手腕を発揮しはじめたのである。
意次の第一着手として、安永元年二月、江戸大火を機として、独特の通貨膨脹策を建て、先ず新鋳の南鐐二朱(なんりょうにしゅ)等の通用を令した。同時に銀及び銀箔の私売買を禁じ、諸種の会所を設置した。この会所は官民合同組合のようなもので、特に長崎に設けられた長崎唐船物売買会所というのは、幕府直属の役人を差遣わし、現在の関税と同じ組織をもって居った。秩父、桐生、伊勢崎には、絹物会所が置かれた、これは絹糸(けんし)一貫目について何程、絹布(けんぷ)一定について何程と、会所で捺印の上税をとる。また他に石灰会所、明礬会所などと、多くの会所を設けて、利準を官民折半にしようとした。
これらの新しい法政は勿論、いずれも富豪のよろこばぬところであった。
意次のとった会所の触手は、商人達のあらゆる事業に、あらゆる商品に、あらゆる取引に喰い入って来るのである。どんな些少な商売の中にも、必ず税が割込んで来る。
おのおの世襲専売の業を擁し、年々手を濡らさずして巨利を 基にして来た富豪達は遽に狼狽して、
「老中を更えよ!」
という運動をはじめた。
一方、卑賤より身を起して、君寵を専らにし、一代にして相良の城主七万五千石の高位に経登り侍従にまで任ぜられた意次の、異常な出世を苦々しく思う一派が陰々裡に幕府の内部に結合しつつあった。
殊には、安永五年、将軍家に子がないので当然継嗣問題が起った時、紀、水派の硬論を押切って、一橋治斎(はるさだ)の子豊千代を容れた。之は勿論、将軍家治の希望するところであったが、紀、水派は意次の専権によるものと深く恨んだ。
外には富豪共が暗黙のうちに、意次排斥の策を講じ、内には御三家をはじめ、譜代の重臣が、意次免ちゅつの機を窺っている。
年若き白河候、松平定信の如きは、血気に逸って、自ら幕府の奸賊を斃すべし、と、必死に意次の首を狙っていた。
四面楚歌!
まさに意次は楚歌に包まれていた。
「何ぞ、お間違い事にてもー」
意次のあとから、溜間へ入って来た勘定奉行松本秀持は、気遣わしそうに訊いた。
「なに、例の潮癖じゃ――」
意次はそういって机の前に座ったが、ふと秀持の方を見て苦笑しながら、
「じゃが、あの御人、なかなか答句を吐かれたぞ」
「何と――?」
「優をの、恋侍従と申されて、はははは」
「それは」
といって秀持も笑った。
秋の灯
一
よし田、と軒行燈の出ている、新銭座の小料理屋の暖簾をぱっとはねあげて、
「へ、面白くねえよ」
と入って来た男、
「おや辰さん」
お園が帳場から声をかけた。
「如何にも辰さ、辰で大きに悪かったね」
「まあ酔っておいでかえ」
「白面で――」
と辰公、まさにこれ、目貫の辰公、とっつきの敷板へどっかり、崩れかかりながら、臍まで浸み込んだ酒気を、ぷうと吐く、
「ねえ、白面でこんな世間が、歩けるかってえんだ、憚りながら、姐さん――いやさお園たぼ、米がね」
また咽喉をやけに鳴らして酒気を吐く、と片方の手を逆に、胸元から額の上まで、ぐいとこき上げながら、
「米が、両に八升てえんだ、米だぜ」
がくんと頭を垂れて、
「べら棒め、御入国以来、こんなばかげた値があるかてえんだ」
「へえ、是や驚いた」
お園は、徳利を燗鍋に入れながら、
「辰さんがお米の値を云うなんて大体その方が御入国以来と云う図だよ、そして、たいそう力んでいるが、両に八升てえのは高いのかえ、それとも安いのかえ」
「おうおう、ばかにしなさんな、いくら目貫の辰が、なんだっても、へん、江戸っ児だ、米の値ぐらい知らねえで、憚りながら、今日さまが、ねえ――」
「もう分ったよ」
お園は頬笑んで、
「おおかた何所かで聞きかじっておいでだろうが、どうせ知ったふりをする積りなら、おしまいまでよく聞いて来るもんだよ、だらしがない。高いか安いかを知らないで、両に八升と値ばかり聞いて来たって通用しやしないやね」
「へん、面白くねえや」
辰は肩を突きあげて、
「全くよ、全くのところ、面白くねえくれえのもんだ、へ! さようでございますかってえんだ、ねえ、それじゃあお伺い申し奉りますがね、姐さん」
「あいよ」
「へっへ、どうでえ今の返辞は、あれで取って二十六だってえんだからね、始末にいけねえ、世の中に色気っくれえ怖えものはねえよ」
「年のことを云いなさんな」
お園は眉を寄せて、
「楊貴妃は百六つで日本に生まれ更って、耀夜姫(かぐやひめ)になったと云うじゃあないか」
「ばかあ云いなさんな、百六つは三浦の大輔だあね、耀夜姫になったな姐妃(だっき)のお百さ、あれやあ九尾の狐の化けた奴で、今あ箱根で殺生石になってらあ」
「はははは」
お園も、流石に我慢できなくなって笑いだした。
「箱根の殺生石はよかったねえ、はははは」
「へ、面白くねえよ」
辰またふくれる。
「あい、ついたよ」
小女に徳利を渡しながら、
「辰さん、いまの話を、先生に話してあげたらどう、御褒美に一升はうけあいだよ」
「勝手にしやあがれ」
辰は小女から徳利を受取ると、ぐいっと二杯、続けざまに呷りつけて、
「先生まで持出されりゃあ世話あねえ、ますます面白くねえよ」
と、そのとき暖簾を分けて、
「何が面白うない」
と云いながら、ぬっと新太郎が入って来た。
二
「まあ先生」
とお園が。辰公はこきんと頸をゆすって、
「ちえっ、濡れ場の二丁が入った、こいつますます面白くないよ」
「何かぼやいて居るが」
新太郎ずっと入って、
「また骨まで剥かれたとみえるの」
「どうでも宜しゅうござんすよ」
辰公ふくれて、
「どうせ、あっしら風情、どこぞのお人のようにゃあ参りやせん、へい」
「僻め僻め」
腰掛へ片あぐらを乗せて、
「酒――」
と云う。
「あい、ただ今」
お園が浮き浮きと立つのへ、辰公舌を出して、さも忌ま忌ましいという声音、
「あいただ今――か」
口真似て、
「はてさて、年増の色気とフグの毒には、当ったら薬がねえと云うが、故人はうまく云ったもんさね、ああ桑原、桑原」
「などと吐かして」
新太郎が笑いながら、
「田町の薬店あたりで、なまこのようになっているのは誰であろう」
「じょ、冗談!」
辰公眼を割いた、
「あんなすぶたに、このお兄いさんが」
「ほう、すべたか――」
「ま、先生」
「よしよし、今度逢ったら訊いてやろうか、たしか小野松屋の」
「先生と云ったら!」
「小野松屋の――おおそれよ、お梅とか申したのう、うん」
うなずいて、
「辰兄哥が申していたが、お前すべたか、とな、たしかに訊いて遣わすぞ」
「冗談、これこそ本当の冗談です」
辰公、いくじなくも首を竦めた。
「辰まさに謝まりやした、本当に云いかねねえんだから、実に業平浪人――という人は。いいえこの通り、まさに兜を脱ぎました」
「ふふふふ」
新太郎は唇で笑う。
「さては年増の毒も、そう悪うはないとみえるのう」
「年増?」
「ではないか」
「可哀相にまだ四ですぜ」
「ほう、人は見掛によらんもんだな、あれで十四か」
「へん!」
頭をしゃくって、
「正真正銘の二十四、大きに悪うございました」
「はっはっは、到頭泥を吐き居ったな、藪をつついて蛇を出すというが、貴様のは他人の頭を叩いて己れの尻を割るというところだ、どうだ参ったか」
お園が燗徳利を持って近寄りながら、
「今頃は薬店あたりで、くさめをしているお人がございましょうねえ」
「それでも是で、辰公と雖も惚れられる女があるからな、世の中の面白いところだ」
「そねめそねめ」
辰公が盃を仰って、
「どうせ二人と一人、嬲り殺しは覚悟の上だ、さあ矢でも鉄砲でも――」
云いかけた時、門口で、大きく、
「安芸殿に御意得度い!」
と呼ぶ者があった。新太郎は片手の盃にお園の酌を受けながら、
「新太郎はこれに居る、入られい」
と答えた。
三
「御免!」
といってぬっと入って来た三名の武士、いずれも黒羅紗の眼出し頭巾を冠り、紫揃いの柄糸を巻いた無反りの長刀を帯した異様の風体だ、武者袴の裾を括って、足拵えも充分にいでたっている。
「安芸新太郎は拙者だが」
盃を甜めて、
「何か御用か」
「されば」
先頭にいた一人が、ずいと寄って一封の書面を差出した。
「この書状御覧が願い度い」
「――」
新太郎、右手で受取ると、封じめを口へもって行ってびりりと引裂き、中の書状を摘まみ出すより左手に持った盃をぐっとあおって、書状をぱっと投披いた。
「まずい字だのう」
とつぶやく。
(美酒一盞献じ度く、御光来待入る。日日八荒不破流開祖 吉川太伯)
「八荒不破流――?」
新太郎くびを傾けて、
「はて聞かぬ流儀だが、酒一盞に招ぜられて否みもなるまい」
書面を掴みつぶしてふところへねじこむと、三名の方へ振り向いて、
「して、貴公らが案内か」
「如何にも」
うなずくと、
「御都合がよろしくば、唯今これから御案内いたす!」
「参ろう」
新太郎は益を叩る。
「が――燗徳利一本、これを飲んで参るから、ちと待たれい」
「待ちましょう!」
「忝いのう」
新太郎はにやり笑って、
「お園さん」
「あい」
「久し振りで、聞かせようかな」
「あい、でもあのう」
お園は気遣わしそうに三人の方を見る、辰公もそわそわと尻が落着かぬ有様だ、新太郎ぐっと板の上へ膝をのせて、
「ははは、此の御三名に悪いというか、なあに、此の方々とて、縁もゆかりもない己に、酒を飲ませようという粋主人に使われる御仁達だ、端唄一曲を厭とも申されまいて、なあ御三名」
「――」
三名は無言で外向く。
「はははは」
新太郎笑って、
「それ見ろ、みんな御所望と仰有る、では新太郎自慢の端唄――四つの袖、だ」
と――眼をつむって、静かに――。
四つの袂に霜が降る
もう退け過ぎの仲の町
聞く人もない蘭蝶を
約束かため身をかため世帯
しょせんはつれ弾きが
結句気ままな悪のはて
今夜は月もまんまるな
ふたつ並んだ影法師
胸のすくような良い声、心ゆくままに唄い終ると、
「やんや、やんや」
お園が手を拍つのへ頷いて、
「では今宵はこれ限り」
と最後の盃をって描く。
「辰――」
呼びながら立って、辰公の肩を叩く。
「薬店へよろしゅう、はははは」
大きく笑った。
「さ、参ろうか」
四
木挽町から築地へぬけるところに、草茫々と生えた原がある。後に采女ケ原といわれたところ。その頃は原のまん中に、雨水が溜ったほどの沼があって、葭が身丈を凌ぐばかりに伸びていた。
その沼を背にして、五人ばかりの侍が、人待ち顔にたたずんでいる。
いずれも眼出し頭巾をかぶり、紫揃いの柄糸を巻いた無反りの強刀をぼっこんだいでたち、中に頭株らしいのが、ひどい癇症とみえて時折きくん、きくんと頸を痙攣らせている。
「おそいな!」
「は――」
「何をして居る!」
「迎えを出しましょうか」
「ま、も少し待て」
吐き棄てるように云い放って、苛々とその辺を歩き廻っていたが、
「佐伯!」
と一人に振り返って、
「何か焚かぬか」
「は――?」
「火だ、灯りがなくては足場を失う、同志討でもやったらお笑い草だ」
佐伯と呼ばれたのが、直ぐに焚き物を探しに行く。傍から別の一人が、
「先生、それでは、殺りますか」
「――」
きくんと頸を揺すって、
「彼奴、どうで、素直にうかと云う筈はない、手を引かぬ時は斬り棄てろと、お上の仰せだ。ふふふ久方振りで関物の切れ味をたのしもうて」
少し離れているのが、
「どうやら来たらしいぞ」
と闇をすかして見た。
佐伯と呼ばれたのは、焚き物を集めて火をつけていたが、湿っているので、なかなか燃え上らぬ、頻りに煙に咽ていた。
「来たらしい」
「先生、来たらしゅうございます」
と云う時――。
原の向うで、安芸新太郎の柔かく高い笑い声がした。
「背筋のあたりからのう、ぼんのくぽまで、ずんと何やら走ったと思ったのが病みつきよ、あははは」
「――」
「安芸新太郎源友正、生年二十八にして初めて恋の切なさを知り申した。いや正だよ、胸のあたりがこう、熱うくなって来てのう、あははは」
笑う鼻先へ、
「待ち兼ねたぞ!」
とつぶやいてスッと出た侍。
例の、きくん頭である。新太郎一歩退った。
「ほほう」
と見廻して、
「これは奇妙、いずれもお揃いで強盗頭巾に無反りの太刀、紫の柄糸、美酒一盞の客に新太郎を招いたは御辺達か」
「如何にも!」
「これは又意外な趣好」
新太郎ぐるりあたりを見廻して、
「枯れ葭に沼、闇夜、狐狸も棲まぬ荒地で酒宴とは、みかけによらぬ風流の仁達よ。面白い! 一盞頂戴仕ろうか」
「馳走申そう、が――」
と相手が出た。
「主人より客に所望の土産がござる、その土産頂戴した上で、のう」
「心得た、望まれい」
頸つれの侍、ちらと左右へ眼配せする、七名の部下らしき連中、さっと二人から遠退いた。
「安芸氏!」
声を低めて、
「葵坂の寮の御方より、手を退かれえ!」
「や!」
新太郎が叫んだ。
五
「承知か」
と詰寄る相手、新太郎は四辺に眼を配りながら、
「貴公、何者だ」
と訊く。
「書面の通り、吉川太伯!」
「誰に頼まれて」
「そのようなこという要はない、承知か不承知かそれだけ聞こう」
新太郎うなずいて、
「聞かそう」
と低く
「不承知だ!」
「よし」
吉川太伯一歩さがる。
「不承知とはかねて此方も察していたところだが、そうはっきりいいきるには、覚悟あってのことだろうの」
「改めて訊くまでもあるまい」
新太郎にやりとした。
「よし、では抜け」
「ほほう」
「抜け!」
「拙者はこれで結構だよ」
吉川がさっと左手をあげた。遠退いていた七名の者が、つつと寄る。焚く火が細く、枯れの底に沢の水を見せて揺れた。
「三人――五人」
新太郎は足場をはかって、
「八人か!」
という、
「見たところ胆のありそうなは吉川某一人、あとは木偶同様だな、では馳走の美酒、頂戴いたそうか」
吉川太伯が、
「いずれも、ぬかるな!」
と叫ぶ、
「――!」
無言のまま抜きつれて、一同ぐるり新太郎を取巻いた。焚き火の焔が細くなる――。
「安芸!」
太伯が冷然という。
「死出の餞別に聞かしてやる、今頃はな、葵坂のお邸に、別動組が十名あまり!」
「や!」
と新太郎。太伯つづけて、
「御命を申受けて参っているのだ」
「しまった!」
「ま聞け。留守は小侍両名に端下女、奥勤女合せて七、八人だ。寄せた奴輩は屈強無残のあぶれ侍、御方をそれと知らねば、さぞ痛快に働きおろうて」
「!」
新太郎つと左へ一歩、右手を柄へ、
「うん!」
という、刹那!
「えい!」
太伯の腰が落ちて、居合抜きだ、びゅっ! と鼻先へ空を切って飛ぶ剣、
「は!」
がつん、一髪の間にひっぱらった安芸、右足地を蹴って猛然と突きに出る。
「とう! とう!」
二段に外して退く太伯、
「かかれ!」
と叫ぶと、
「やっ! おう!」
うしろと右のが、餓狼の如く迫った。と知る新太郎、身を沈めざまぐっとふと振り向く擬勢を見せる、刹那! 逆に右のへ、
「いち!」
と叫びながらの突き。充分入る、
「があっ――」
死のうめきのたつ同時に、
「に、さん!」
新太郎の声、つづいて二人が倒れた。
焚き火の火は――絶え絶えに。
六
「残るは五人か」
と新太郎が低く。その声は、秋の夜の風にもまして、冷たく、鋭く相手を刺した。
「太伯どの」
「――」
「今宵お振舞の酒は」
云いかけてぱっと左へ跳ぶ、そっちにいた二人が慌てて避ける、とたんに身を転じて吉川へ下ざまの払いだ、危く避けたが、おっかぶせてひゅっ! ひゅっ! と縦横無尽に、電光のように、新太郎の刃風は魔気を発して肉薄した。太伯あおられて退る!
と一人が、
「わっ!」
必死すてばちの絶叫と共に、体ごと、太伯と新太郎の間へ、とび入って来た。
「邪魔だ!」
と躱していなす新太郎、
「え、やっ!」
と片手なぐり、脾腹を割られて前のめりにつっ倒れるのには眼もくれず、だだだと迫って太伯につけながら、
「今宵の酒は――」
と新太郎の声がひびく。
「いずれも、少々日が経ちすぎて折角ながら、拙者の口には不足でござるよ」
「――」
「お振舞、この位で、御辞退と致そう」
「――」
「如何?」
言葉尻へ、気合に乗った太伯、
「うぬ!」
喚くのと、突きを入れるのと同時だった、必殺の剣、眼前に閃めく、刹那! 新太郎は身を沈めて、
「うまい!」
云いながら左へ避けざまに、
「かっ!」
と太伯の肘へ一刀、
「つ――」
二三歩たたらを踏んで立直る太伯、その時既に新太郎は、
「ご! ろく!」
と叫んでいた。
六人めに斬られたのは、勢い余って、焚火を踏み越え、古沼の中へ上半身をのめり込ませて倒れた。
「もう宜かろう」
と新太郎。
「頭様まで膝の筋を斬り放されて是以上に闘う要もあるまい、八荒不破流という太刀筋も拝見したし、馳走充分に頂戴した、退かぬか、吉川氏!」
「――」
吉川太伯、刀をさげると、静かに四五歩うしろへ退いた。
瞬いていた焚火の焔が落ちる。
「流石にお分りが宜いのう」
新太郎にやり、
「先日もな、拙者宅へ斬り込んで参った仁があった、五人――七人であったかしらん、三人倒した時に拙者が、退かれい! と申した、ところが強情な仁達で、最期の一人は逃げたが、六人枕をならべて斬死にだ」
刀を押拭って鞘へ、
「あっぱれと申せば、あっぱれ、愚と申せば愚――はっは、それにひきかえ、太伯どのはのう」
云いかけたが、くるり踵をかえすと、
「いずれ」
そう云って、
「御用もあれば、又」
と云う声は、既に二三十歩も先から聞えて来た。
裾をからげて、左手に鍋元をしかと脳みながら、芝口御門の方へ新太郎は宙を飛ぶように、走っていた。
七
坂をあがって、右が島津家上邸、左が出羽の本間邸、邸はずれに空地があって、十五六本の赤松が樹っている。
松林を前に、石段を、七八つ下りると、質素な表構えで、黒塀を取廻した数寄屋風の邸がある。走って来た新太郎、表門を右へ廻って裏手へ来ると勝手知った木戸、拳をあげて三度ずつ二回叩いたが――内からは何の応えもない。
「遅れたか」
と足をあげて木戸を蹴放す、中へ、殆どのめり込むようにして、植込を、築山を、走り越えながら奥庭をめざして進んだ。
数寄屋の前まで来ると、
ちゃりん!!
という音、斬りむすぶ気配だ。
「新太郎、参上!」
喚きながら音のする方へ、走って行くと、ふいに煌々と灯明るい奥庭の有様が、眼の前にひらけて見えた。
「あ」
と足を止める新太郎。見ると縁先に、奥勤女たちが燭台を提げて立つ、中に、田沼意次をはさんで白髪頭の島津重豪(しげひで)、松本伊豆守がしずかに庭先の斬り合いを見物していた。
倒れている者四、五。残っている者は一人、例の黒羅紗の眼出し頭巾、太伯一味の装束である。これに立向っているのは、年の頃二十四五であろうか、色浅黒く、眉きつく、小柄だが、ひきしまった体つきで、一刀流をよく使うらしく、鋩子尖を下げ気味に、じりじりと敵を圧迫していた。
新太郎の姿を見ると、
「安芸か」
意次が声をかけた。
「はっ」
「宜い宜い、此方へ来て、見て居れ」
新太郎が縁先へ進むと、
「いま少し早く参れば、面白い勝負が見られたに、惜しいことをしたぞ」
「失態! ひらに――」
手をつくのを、
「いや、今宵は勤めの外、失態ではない――ま、見て居れ」
「皆様、御無事にて?」
「うん」
意次はうなずいて、庭先の勝負へ眼をやる、新太郎も沓脱ぎに腰をかけて見物になった。
黒頭巾は僅かに右へまわる、
「殿!」
若者が声をあげた、
「うん」
島津重豪が応える。
「此奴――どこを斬りましょう」
「そうだのう」
重豪が赭顔(しゃがん)に笑を含んで、
「立ちながら、首を刎ねる――も面白いが」
云いかけたが、
「いや、御庭前を汚すのう」
「では――」
「心の臓を一刺、ふた太刀まで用いずに斃して見せい」
「仕りましょう」
答える、隙!
「おっ!」
おめいた黒頭巾が、真向へぐわんと斬りつける、と見せてかえす、猛然と払いに寄る。
ちゃりん!
受けて、ぐぐぐと寄身に迫る若者、
「八幡!」
叫ぶとみるや、
「――!」
陰の気合だ。体がさっと沈むと思うと、きらり、闇に秋の灯の弧を描いて、ばっと、うしろへ跳びしさった。同時に頭巾の男は、
「うーむ」
呻いてそこに立竦んだ。
八
「みごと、みごとだ」
島津重豪がそう云って、意次に振返った、
「相良侯、如何?」
「あっぱれな若者、いかにも、近頃になく感服仕った」
重豪ほくほくと、
「竜次郎、近う!」
「はっ」
竜次郎と呼ばれた若者は、充分刀に拭いをかけて、灯にかざして歯こぼれを改めると、鞘におさめて縁端に進み寄った。
「潮田」
意次が呼ぶ。廊下の角に片膝立てのなりでいた用人潮田宗典が、
「は」
と云って立つ。
「その死体、表の松林へ取り棄てい」
「はっ」
退ろうとしたが、
「死体をあらためませんでも?」
「宜い」
意次うなずきながら、
「証固となるような物、持たせて寄来す筈はない、構わず抛り出して置け」
云うと重豪の方へ向いて、
「薩摩侯、入りましょう」
「やあ」
重豪が、
「竜次郎も参れ」
と云う、若者は手を下ろして、
「返り血で、衣服が汚れました故私はこれにて――」
「そうか、わっははは」
重豪笑って大きく手を振る、
「美しいお傍女が居ると、竜次郎なんども、衣服の事に気をつかうとみえる、いや宜い宜い、さらば先へ戻って居れ」
「殿」
竜次郎があわてた様子で、
「左様なことを」
「構わぬ、男が女に惚れること天地自然の理義じや、威張って申せ、そうではござらぬかのう、相良侯」
「薩摩侯はお分りがよろしゅうござるな」
意次頬笑んで、
「参りましょうぞ」
と云うと、すっと先に座敷へ入って行こうとした、がふと足を止めて、
「新太郎」
と振返った。
「――」
「後で頼みがあるから、お遠間で待っていて呉れぬか」
「は――」
意次と重豪は去って行く、新太郎は立上ると、
「失礼ながら」
と若者に声をかけた。
「島津侯御藩中にござるか」
「左様、諏訪竜次郎と申す」
「いや申後れた、拙者は市井の無頼、安芸新太郎、当時芝新銭座に住い居ります」
「お噂は――」
と竜次郎がうなずいて、
「かねがね、相良侯より承わって居りました。当代無双の剣豪に加えて江戸随一の美男――」
「猿若へなど出て、のう」
新太郎は打消し笑って答えた。
「いや真実」
竜次郎が、嫉ましげに、新太郎の横貌へ眼をやった。
「噂以上の男振りでござるよ」
「これで女に惚れられぬから、心得ぬことではござらんか、はははは。いや、これから諏訪氏と美男くらべ、ひと暴れ仕ろうか」
そして新太郎は数寄屋を表へ廻った。
こころ
一
新太郎は意次の言葉通り、自分に与えられてあるお遠間に待っていた。
壁のどこかで、さっきから細く、
ころろ、ころろ。
と虫が鳴いている。しみ透るような秋の夜気が、紙燭(しそく)の光輪にとけて、新しい備後表の上を、水のように流れるのが知れた。
新太郎はふと眸をあげた。帰雲行水の陰が眼前をかすめたのだ。
半年前までの酒は、世を捨て、人に拗ねた酒であった――が。この頃の酒は、胸の苦しさを忘れ、美しい幻をうち消そうとして飲む酒である。
春三月、十日頃のことであった。夜桜の酒に浮かれて、足もとも危く、赤坂山王の下を歩いてと、七八人の侍が、女乗物をかついで宙を飛ぶようにやって来るのに逢った。眼にとめるでもなくやり過すと、二三十間あまり後から、
「あの駕籠止めて――」
「狼藉者でござります、あの駕籠を――」
と必死の叫びをあげながら、二三人の端下女らしいのが追って来た。
前後、善悪の差別をつける暇もなく、
「よし!」
といって新太郎、踵をかえすと、
「その乗物、待て、待て!」
喚きながら追った。声を聞きつけて、 殿にいた四人ばかりが、足をとめて振返る、と新太郎を認めて、頷き合いながら手に手に抜いた。
新太郎は追いつくと、
「理非は知らぬ、女性の救いを求むる声によって罷り出た、その乗物止められい!」
叫ぶのに、耳もかさず、四人の者がいきなり斬りつけて来た。
「無法な!」
と新太郎、抜合せると手間暇なく、峰打で四人を倒す、乗物は早くも半丁余り遠くへ、
「待て!」
脱兎の如く追う。
見付手前二丁ばかりのところで逃げきれぬと見たか乗物を早く四人、そこへ駕籠を下ろすと抜きつれて新太郎を迎えた。
「止せ止せ!」
新太郎が駈けつけながら、
「先の四人も土をなめて後悔し居るぞ、下手に動かずと、乗物置いて退散しろ」
と云う。一人が声鋭く、
「控えろ、この内には身分高き姫君がいますのじゃ、みだりに手出しをすれば素首が飛ぶぞ、退け退け」
「ぬかすな!」
と跳び込んだ新太郎、
「や!」
叫ぶと脇の一人へ峰打をくれる、危く避けたが、足場をとられて溝の中へ、水音高く落込んだ。続いて残る三人、あっという間もなく打倒すと、
「うふん――」
新太郎、あっけなさに、かえって拍子ぬけの態だ、刀を拭って鞘に、おさめるところへ先刻の端下女と、おっ取刀の侍四五名が、血相変えて駈けつけて来た。
「や、御無事だ!」
「早く殿を!」
というところへ、馬をとばして乗っつけ来た老武上――それが田沼意次だった――が、馬をとび下りると、急いで果物の前に進み寄って両手を膝に、
「主殿にござります、御安堵遊ばせ」
と低く云った。果物の内からは、
「はい」
ひと言答えがあったばかり。
しかしその声の美しさ、僅かに離れて聞いていた新太郎の耳に、いまでも忘れられぬ響きとなって残っている――。
二
それが縁で――。
間もなく新太郎は三日毎に、葵坂の邸に警護の宿直を動める身となった。しかし飽くまで勝手気ままの新太郎、随身を嫌って、新銭座の住居は変えず、勤め外には荒屋のまろ寝を続ける約束であった。
邸のあるじは、あの夜の声の主だ。
宰領は田沼意次、付人として島津重豪t(しげひで)の藩中からも、交代に四、五名ずつ、眼立たぬように宿直しているらしい。
こんな厳重な警衛を要するこの姫は、そも何人だろう。奥動女たちの呼ぶ名も、ただおひいさまというばかり、いず方の如何なる身分の姫君か想像もされぬ。
その上に――。
左様な重い身分の姫が、乗物のまま奪われかかったり、御命を縮めよと斬り込みをかけられたりする、そもそもこれは何の意味だろう。
(不思議だ!)
新太郎は何度そうつぶやいたかしれぬ。
夏のことだった。
例日の動めで、お遠間に詰めていたが、ひどく暑い晩で、蚊やりの煙にも眼がいたく、つい風を吸い度くなってお中庭の方へ出て行った。すると山吹の垣越しに、お内庭のはずれ築山とお池に面して数寄屋の土庇を深く、なで髪に質素な黒好みの装いをした、年若のお端女とも見える乙女が立っていた。
新太郎はお端下女と思ったので、垣の此方からなに気なく、
(暑うござるな)
と声をかけた。
乙女は、池面をみつめて、うっとりと放心していたらしいが、新太郎の声を聞いてふと振返った。
(いま少しすると月が出る――)
重ねて新太郎がいった。乙女は振返ったまま暫く新太郎の顔を見つめていたが、
(はあ――)
と低く答えて、また池の方へ眼を戻した。無愛想な娘だな、と思ったが、新太郎にはかえってその方がよい。自分も胸を押しはだけて風を入れながら、
(下町と違って、山手がかりは涼しいと思ったが、かえって蚊など此方の方が多い位だ、これこのように縞模様のある奴なんどは、下町には居らんからのう)
などといった――が。
思えば冷汗、その乙女こそ邸の主、おひい様であったのだ。
それと注意されて、逃げるように自分の部屋へ引取った新太郎、何かしらん血がおどって、頬がほてって、心の底が焼けるような気持だ。眼を閉じれば、ひきしまった雪のような肌、新月のにおうかと疑われる眉、愁いを水晶に溶かして滴らせたような眸子。あのつつましい黒好みの、お端下女にさえ見あやまった程の衣装――、何ひとつとして思い浮かばぬものとては無い。
たまさかにもれ聞える琴の音にも、お端下女が心なく唇にするおひいさまという声にも、不覚や新太郎の胸は熱く騒ぐようになって行った。
酒――。此の頃の酒は、この苦しさ、胸の辛さを忘れるための酔いだった。壁からしみ出るような虫の音がふとやんだかと思うと、廊下を静かに近づいて来る足音がした――新太郎はその音で、回想の糸をぷつり絶った。
「新太郎、居るか」
襖の外で声をかける、意次だ。
「は」
「待たせたのう」
そういって意次はしずかに部屋の中へ入って来た。新太郎は火桶の傍を少し居退ってかたちを改めた。
三
座に就くと意次が、
「今日、何ぞ変った事はなかったか」
と訊く――。
新太郎は手短かに、先夜の斬り込みと、今宵木挽町の原へ誘い出しをかけられた始末を語った、しかし吉川太伯の名までははっきりといったが、第一の斬り込みに鉄砲を持っていた、男装の女の事は、何故か話すことが出来なかった。
「ふむ――ふむ」
いちいち頷いていた意次、
「して、八名のうち致命の者の数は――?」
「さあ――二名は、恐らく助かりますまいが、あと四名は当座の傷、太伯の左腕は最早役にはたたぬかと――」
「宜し宜し」
意次は眉をよせながら、
「惜しい奴だが、理否の差別がつかぬで」
「御存知にござりまするか」
「吉川かの?」
「は」
「知って居るとも、彼奴、以前神谷源心の道場に居ってのう、飛竜剣と自称する居合を以て江戸中に聞えた奴じゃが、それがいつか――さる方に買われて徒党を組み、表面は八荒不破流剣道指南と道場を構え、実は儂の首を狙って居るのだ」
「ほう――」
「愚かな奴らよ」
意次は冷笑した、新太郎つと顔をあげて、
「何か、御用にてもござりますか」
「うん」
と意次が、
「それが、のう。少々――」
と口を濁す。
「憚りながら、何事ないとも」
「それは分って居るが、別な話じゃて」
「はあ」
「実は――」
「――」
「おひい様がの」
新太郎の胸が、どきんと大きく波うった。意次は心を決したらしく、
「其許に会うて遣わそうと申される」
「――」
「生命を的の奉公」
「――」
「ひと言ねぎろうてやろうと、のう」
「は」
「お眼通り、願うか」
「――」
かっと耳鳴り。新太郎はじっとり腋の下に汗だった。
「御遠慮申上げるか、例の無い事で、些かも迷って居る、と申すのが……」
何か仔細ありげに云いかけたが、廊下を足早に来る人の気配、意次はきっと顔をあげた。
「申上げまする」
襖の外まで来ると、奥勤女の声で、
「お待ち兼ねにござります」
と低く云う。
「唯今」
意次は答えて、
「は」
と、女が去るのを聞き儲かめ、
「新太郎!」
「はっ」
「参れ、お眼通り仕ろう、その上の事だ、どうなるとも思案のほどはあろう、これ」
謎のような言葉、
「――」
新太郎、さすがに些かためらって、ちらと意次の顔を見上げたが、意次は外向いて座を立った。
「お待ち兼ねじゃ、来ぬか」
「はっ」
きっと唇をひき結んで新太郎は立った。生来二十八歳、初めて思いを焦がす人に、安芸新太郎は、逢えるのだ――。
四
古代更紗へり取、紙本石刷の襖に、殿上風の敷畳、仮構えの上段には御簾が下りている。十畳ばかりの小書院造りで、壁間(へきかん)には古い仏画が掲げてあった。
新太郎は意次の後から入って、下座に平伏した。意次が低く、
「安芸新太郎にござります」
と披露する。
御簾がきりきりと捲き上げられるのを、新太郎は殆ど夢心地に聞いた。
意次がささやき声で、
「御挨拶申上げい」
という、殆ど同時に、
「新太郎、久しい対面じゃな」
あの声だ。
「は――」
「顔を見しや」
新太郎しずかに面をあげた。夢に見、幻に描いたその御方が、いまそこにいる。胸をこがし、心を狂わしたあの眸子が、唇が、頬が、かがやくばかりに微笑しながら新太郎を視つめている――。
「御機嫌うるわしゅう」
新太郎の声はふるえていた。
「そなたも健固か」
「は――」
「警護の宿直、よろこばしく思います」
「は――」
御方の笑顔が、はっと消えた。澄みきった眸子が、生々とかがやきをました、そして無量の情怨をこめて、この思いを汲めといわんばかりに、ひしと新太郎の眼を視入った。
「新太郎!」
「は――」
「また、折々――」
「――」
「来て、たも――」
新太郎がはっと手を下すと、きりきりと御簾の下りる音がした。
「退ろう」
意次の声に、面をあげると、最早御簾の中にも、その人の気配はなかった。
廊下へ出ると、
「此方へ参れ」
意次がそういって、数寄屋の方へ新太郎を導いた。お端下女が紙燭を点じてさがる。
座につくと、意次が、
「近う寄れ」
新太郎思わず意次の眼を見上げた。意次は紙燭の火へ眼をやって居た。
新太郎はずいと居進んだ。
意次はしばらく、新太郎の面をうち見ていたが、やがてその眼を紙燭の火に向けた。
「新太郎」
「は」
「長らく、秘して居ったが」
意次の声は極めて低い、
「今宵、彼の御方の御身分を明かそう」
「は」
「実は――」
眼を、再び新太郎の方へ戻しながら、
「当上様の二の姫君――」
「え?」
「千代様と申上げる御方だ」
新太郎は千千仞の谷底へ突き落されたよう、しばしは頭をあげる気力もなかったが、
「しかし、当上様には」
とようやくに訊きかえす、
「万寿姫、御一人より外に、姫君ありとは伺いおりませぬが」
「それがな」
意次は太息と共に答えた。
「千代姫君の母公は御部屋於知保(おちほ)の方であった。しかるに御台所には、日頃から於知保の方を太く疎ませられ、千代姫君御成長をよろこばれず、尾州家と計って、幾度か姫に害を加えられんと遊ばされたのだ――」
意次は暗然と言葉を切った。
五
「要は――」
と意次が続けた。
「御台様の御潔癖、それに加えて御部屋様於品の方も御台様の御付女(おつき)として、京より下向された女性だからのう――、江戸育ち、営中古参の、それもひとしお御美しく利発の於知保の方が、煙たくあらせられるは避け難いことであろう」
新太郎は静かに頷いた。
「かててくわえて、竹千代君(家治嫡子)薨去(こうきょ)、御跡目直しを控えて、御三家二卿の策動となっては御聰明ながら御女性のこと、千代姫君の御身に如何なる御憎しみが加えられようも計られぬ仕儀。上様それと感ずかれて、表向の御披露もなく、ひそかに姫君をわしと、薩摩侯とに御托し遊ばされたのじゃ」
「しかし」
新太郎が、
「御跡目豊千代君の入らせられし上は、最早千代姫君の御身上も御安泰にござりましょうが――?」
「御台様御一党の思召しでは」
意次は声をひそめて、
「千代姫君をして、万一豊千代様御簾中にでも直さしめられては――と。のう、それを案ぜられて」
「それは、如何にも」
「勿論、当上様におかれても、殊の外千代姫君御鍾愛にて、豊千代様御簾中に直され度き思召しなしとは申されぬ、それ故にこそ――一層姫君の御身上が危ぶまれるのだ、高貴に生れ給うて、安らかに枕も温めまいらすることの出来ぬおいたわしさ――察せい」
「は――」
「御年頃にならせられても、月花の御慰めなく、たまさか遊山を楽しましめまいらせんとすれば、この春の山王の如く、のう――あの節も新太郎なくんば如何あらせられたか、考えるだに老の胆が縮む。今宵もふと、新太郎と申すに眼通りを――と仰せ出された時、――」
新太郎の胸はかっと熱く、
「儂には御心の程が知れた故、頓(にわか)にはお眼通り願わする気になれなかったのじゃ、御方は其許を通して、世の中の相を見られ度いのだ、其許を通して、人間の姿に触れられたいのだ、姫君も、最早十八に相成られたよ」
「――」
新太郎は自分の息吹の熱いのをうとましく、恥かしく感じながら、身動きもせずに頭を垂れていた。
「斯くうち明けて話す上は、此上とも出精頼み入るぞ」
「は、卑賤の私」
新太郎は両手をついて、
「望外の思召し、何ともなくただただ御方様の為に」
「うん、その一言何よりじゃ」
意次は頷き頷いて、
「何なりと望みがあれば、かなえて進ぜよう」
「思いも寄りませぬこと、しかし」
新太郎がずいと膝で寄る、
「御伺い申すことが一つござります」
「うん――?」
「御奥勤女に、佐賀とか申される者が居りまするな?」
「おお、居ったと思うが、それが――」
「素性の程はたしかにござりましょうか」
「と申すと、何か不審の事にてもあるか」
「いや――」
といいかけたが、何を思ったか新太郎すっと立って、廊下に面した障子を、不意にがらっと引明けた。
「誰だ」
新太郎が叫ぶ、
ばたばた――と、誰か廊下を、上へ走って行くのが見えた。
十夜くずれ
一
麻布月ヶ窪にある時宗の名刹、東光寺は、お十夜講で賑わっていた。
境内にある、厄除地蔵が、それに加えて例月の縁日というので、山門から執行院の前、ずっと出て谷町の方まで、昼からぎっしりの物売店、辻講釈、もぐさ売、綿温石、因果者の小舎掛までが、わんわと人を呼んでいる。
「三の字、さっさと歩びねえ」
「待てと云うこと」
三の字、実名松かさの三吉という、先に立って急っついているのは、例の目貫の辰公。三の字となら、手前が兄哥分だから、辰公も今夜ははばである。
「足に根が生えるぜ、さっさと来やな」
「そういうな、あの娘をあのまんま、そう素気なく見捨てて行けるものか」
「なにを、娘――?」
「それ見な、兄貴だって娘と云えば」
「むだあ云わずと、何所だ何所だ」
「それそこよ」
指さすところに、白髪まじりの老母が、もぐさを売っていた。
「百病に灸すべしとは、えへん、時珍が本草にも精しゅうござりやす、近松の浄瑠璃にも、ひと火すえたや切艾と申しやしてな、達者自慢の灸嫌いは、暦をひらいて吉日を難じ、二日と聞いてわがままを慎むのたとえにござりやす、えへん明堂灸経に、灸点三歩ならざれば孔六にあたらずと、えへん――」
辰がどんと三吉を小突く、
「へん、洒落にもならねえ、行くぜ!」
「邪険にしやすんな」
三吉が、
「ああ見えても、あの婆さん、まだ手入らずだぜ、そうとすればよ、皺は寄っても娘に相違は――」
「殴るぜ!」
「待ちねえということ」
人ごみにもまれて、無駄口がと切れる、が再び寄ると直ぐ燃える舌だ。
「こう見や、兄哥」
「なんだ」
「豪勢とでけえまんじゅうだぜ――」
「だらしのねえ野郎だぞ手前は、饅頭のでけえのなぞに眼をつけやがって、けっ、江戸っ児の面汚しだ」
「面汚しでも、でいえよ、何か口上をぬかしてるが聞いて行こう」「饅頭の口上なんぞ聞いてみろ、明日っから神田上水が腐っちまわあ」
「まあそういうなよ、見るは法楽、聞くは、聞くは――」
「絶句一分と定めたり」
辰公が手を出して、
「さあ一分!」
つい鼻先には、大きく幕に三階菱に『都』の字を染出した屋台、片方に蒸籠を三構え置いて、男三人、女一人が、せっせと饅頭を造っている。一方に――でっぷり肥えた中年男が、咽喉を嗄らせて口上を云う。
「うあ――遠からん者は餅搗く兎の耳にも聞け、近くは眼にも都饅頭。色気より先ず食物の世の中、よしや蛇の道は上戸が知るとも、餅は餅屋が理屈を申さば、そもそもこれは江都饅頭の本店にて、桃太郎が黍団子は、まま此店の勧進なり」
「来や!」
辰公がぐいと三吉の袖をひいた。
「猩々が饀の講釈を聞いたって、亡者が成仏しやあしねえ、全体手前は――」
云いかけて、
「――!」
ぐいと辰が、三吉の牌腹を小突いた。鴨がみつかった――という合図である。
三吉、辰公の眼のゆくところを見ると、年配は五十余り、頭巾を冠って黒羽二重の衣服、青貝を散らした贅沢造りの大小を、邸風に格式張ってさした立派な武家が、供もつれずに――寛々として行く。
二
「ぬかるな!」
と囁いた目貫の辰公。
人混みを押分けて、例の武家の向うへ、通りぬける、すれ違いざま当りをつけると、懐中にずしりと重み、板物に小粒をとりまぜ、五十両は欠けぬ――と見当をつけた。
「久し振りの鴨、お鴨様、様さま」
ほくそ笑んだ辰。
宜い程に踵をかえすと、左手でやぞうをつくって、人混の中を蹣跚と鼻唄――。
四つの袂に霜が降る
もう退け過ぎの仲の丁
業平浪人から聞き覚えの、端唄を低くうたいながら行く。頭巾があるから、よくは分らぬが、身分ありげな人品、
「しめた」
もう一度頷いて、近寄る。
三歩――二歩、よろめいて、僅かに肩を相手の腕へとん、当てる刹那、辰の右手がさっと閃いた。とたんに!
「慮外者!」
武家の口を衝く叫び。
体を捻って、むずと辰の右手を取る、
「畜生!」
辰が、取られた手を逆に廻してどーんと体当り、思わず放す手、ひらりと、燕のように身をかえした辰。三吉が右にいて、
「わあっ、仇討だあ――」
途方もない叫び。
わあっと人混みが一時に乱れ、崩れて、わきかえる中へ、とび込もうとすると、
「待て!」
と云って、どこから出たか七八名の侍。
「へい」
「殿、何か――?」
一人が、例の武家の傍へ走り寄った。殿と呼ばれた武家は、苦笑しながら近寄って、
「うん、ふところを抜かれたよ」
「おのれ無礼者」
二人が、そこに居竦んでいる辰の、衿髪をむずとつかんだ。武家はそれを制して、
「手荒な事をするな、余の油断じゃ、抜いたものを戻して放つが宜い」
「と申しまして、此奴――」
「邸へ引立て参ったが宜かろう」
「不届至極な、下郎め」
頻りにいきり立つ。殿さまが、
「人が立つ、みとうも無いでないか、早う取戻して放ってやれ」
「はっ」
衿髪とっているのが、
「これ賊!」
と怒鳴る、
「殿お忍びの折故、お慈悲をかけられるとの仰せじゃ、さ、御懐中の品を御返上申して、お詫を致せ」
「へ、へい、しかし私は」
「なに?」
辰ぶるぶる慄えながら、
「私は、な、何も存じませんのでへい、実にその、何も――」
「ほう何も知らぬ?」
武家が再び苦笑して、
「そ奴の懐中を検めてみろ」
「はっ」
二人が左右から、辰の手を取って引く、一人が、そそくさと体を改めた。
「な、何も、何も存じませんのでへい、酒に酔って、お殿さまに、つい突当って、へい、それ丈のこってございます」
ぶるぶる慄え――こいつが術で――ながら辰公、眼尻でちらと三吉の安否を見やった、とっくに代物は三吉の手へ渡っているんだ、へん! 殿さんか、障子の棧か知らねえが甘えものさ――。と胸の内に呟いたが。何をみつけたか、ぎょっと眼を瞠って、
「あっ、野郎!」
と呟いた。
三
「無いか?」
殿さまが、少し苛立たしそうに、
「はっ」
あわてて侍が、いろいろと探るが、手拭一本、紙一帖、唐桟縞の小粋な財布――勿論中身は小銭五六枚だ、――それっきり、外には藁しベ一本出て来ない。
「どうもこの外には、一向に」
「そ奴の仕業に相違ないのだ、よく検めて見ろ、早く――」
「はっ」
廻りは、わんわんという人集りだ。
「可哀相に、濡衣をかけられたんだぜ」
「見ろ、ぶるぶる慄えてらあ」
「なあに、ああいう手合は、哀れっぽく見せかけるのが術よ。抜いた品だって、どこへ隠すか、素人にゃあ分らねえ」
「おや、お前知ってるのかい」
「先ず足袋の中か」
「素足だぜえ」
「だから怪しい」
わっわと騒いでいる。
と――人集りをかき分けて、四十あまりのばかに身柄の大きい男、顎髯の艶々と黒いのを胸まで垂らし、眼光炯々とした奴が、右手に三吉の腕を捻りあげながら、
「どいた退いた」
とその場へやって来た。
辰公が、あの野郎! と叫んだのは、蓋しこの有様を見たからである。
「あ! 暫く」
髯が声をかけた。侍の二三人がばらばらと殿様の周囲をかこむ。
「何だ何だ?」
「掏摸にかかられた御仁は、貴公か」
「控えい!」
一人が威丈高に、
「これに在すは――」
いうのを制して殿さまが、
「待て」
と一歩前へ、
「如何にもわしだが、何か――?」
「御貴殿か」
髯がにやりと笑う。
「さぞ御迷惑でござったろう、拙者が取戻して進ぜたから安心さっしゃれ」
「ほう――其許が?」
「其奴を幾らはたいたところで、抜き取った品は疾く同類が持って逃げて居るじゃ。江戸の掏摸は洒落たものでなあ、はははは」
髯は笑いながら、
「それ、この品でござろう」
と紫帛紗包みの紙入をずいと差出した。
「うん、相違ない」
殿さまが受取る、そのままふところへ。
「過分の働き、添い」
「中身を検めたら宜しかろうが」
「いや別状ない」
さすがに育ちは争えぬ、と辰公いまいましいながら、感心して見ている、三吉は面目なげに、眼顔で頻りに辰公に謝っていた。
「品が戻る上は」
髯は改めて、
「この両名、拙者の方にお任せ下さるまいか、如何」
「結構じゃ」
うなずいて、
「たかの知れた鼠賊、だが番所へひくも大人気なき業、放ってやったら?――」
「これ!」
髯が、三吉の腕をぐいと捻じあげる、
「あ、つつつ」
「お赦しが出た、拙者と共に参れ」
「痛、痛い!」
「其方の奴も、此所へ!」
と髯が、辰公を抑えている侍へ云った。
辰公もがいたが駄目だ。
四
髯は両手に三吉と辰を提げて、
「こいつら、うるさくくと、一緒にいょかいて参るぞ!」
ぞろぞろと、物見高くついて来る群衆を追い散らしながら、執行院の前へやって来た。
松の根方に、ひしお売りと並んで、一基の見台の如きものが置いてある、上に一冊の書物を置き、もう毛並びの乱れた古い孔雀の羽根が一本、仔細らしくのせてある――のを前にして、むくつけな書生が一人、提灯を提げてぼんやり立っている。
「おい!」
髯が声をかけると、
「はっ」
書生は夢から醒めたように、
「せ、せん、先生」
と振返った。
「此奴ら二人、確と押えて居れ」
「な、な、何者で」
「今宵のな、宿賃だ」
「は?」
「宿賃の代だ、逃がすなよ」
「は、は!」
辰公は泣き声を出して、
「もうお赦しを願います、この通り、もうすっかり面は晒されるし、二度と悪事は働けません、どうかお赦しを――」
「めそめそ申すな」
三吉も傍らから、
「是以上は殺生でございますよ旦那、もう全く結構で――」
「貴様の方で結構でも、当方では未だ結構ではない。儂がな、いま少々稼いでみるから、そこで暫く待って居れ、えへん」
髯が見台に向った。
この時分には、もう、さっきから後をつけて来た群衆が、ひしお売りの前から、並び松三本を埋めてぐるり取巻いていた。髯は、漆黒の顎髯をぐいとつかんでしごきながら、ひとわたり人垣を見廻して、
「え――えへん!」
ともう一度咳をした、とたんに、人垣の後の方から大声で、
「よう風来山人!」
と叫んだ者があった。
「わしを見知る者があると見えるな」
髯は大きくうなずいて、
「それは愛い奴、風来も両国を喰い詰めてな、斯様に縁日講日を廻り歩く始末じゃ、志あらば聴いて行け、一紙半銭の報謝で古今の物識となる。風来の講釈はな、そこら辺りに読古した稗史小説の類でないぞ、東夷南蛮北狄(ほくてき)西戎(成獣)、四夷八荒天地乾坤、空、虚として究めざるなく、人運の律、時運の理、命数の規、さながら掌を指すが如く明記して聴かせる。今皆はな、前講として平家物語の中、哀れいと深き重衡(しげひら)斬らるる一条を読む、えへん!」
と髯をしごいた。
「野郎――」
辰公が三吉を小突いて、
「どじを踏みやあがって、この――」
「そ、そうじゃねえ兄貴」
「何を」
「あの髯野郎が、見ていやあがって、又ばかに足の早え畜生で――」
「だ、だ、黙れ」
書生が怒鳴った。この男吃りとみえる。
「へい」
首をすくめる、髯が振返って、
「やかましい、講釈の邪魔になる、天紅!」
「は、は、はい」
「貴様、帯を解いての、そ奴らを其所の松へ括しつけて置け」
「し、し、しょ、しょ承知―」
可愛相に、辰公、三吉の二人は天紅書生の帯で、松の木へ括しつけられて了った。
「さて、前講(ぜんこう)を始めるぞ」
等が声をはりあげた。
五
「もし、先生、先生!」
新太郎ふっと眼が覚めた。
「誰だ」
「私です、ちょっとお明けなすって」
「辰か」
「へえ」
「何か知らぬが明日にしろ、眠うて――起きるのが面倒だ」
頭もあげない。
「そうでもござんしょうが、ちょっとどうかお明け下せえまし、実は客――おきゃ、お客人をお連れしてめえりましたので」
「客――?」
「へい、是非どうか」
新太郎むくり起上ると、枕元の大刀を左手に、ずいと土間へ下りた。
「入れ!」
といいざまがらり戸を明ける。外は――いい月夜だ、青白い光に濡れて、四つの人影が立っている。
「へい―此方がその」
と辰が、低い声で、
「私の、お、お、親分で」
殆ど消えんばかり。
「何をぼそぼそやっている、いずれの仁か知らぬが、御用とあればむさ苦しゅうござるがお入りなさらぬか」
「ほう――」
髯が、大きく眼をむいて、
「掏摸の元締にしては人並な口を利くのう」
「叱っ、叱っ!」
辰が制すのを、ちらと見たばかり、
「如何にも見たところむさ苦しいが、露に打たるるよりはましであろう、御免」
「――」
呆れている新太郎の前へ、髯はずいと入った。あとから例の、天紅と呼ばれた書生が、見台を担いだなりで、これ又遠慮もなく入って来た。
「辰!」
新太郎が、
「この御仁らは――?」
「へい、その――」
辰が、三吉と一緒に、土間へ路みこんだまま頭へ手をやって、
「全体、この三公が、その」
「兄貴、おいらの名を出すこたあなかろう、このお二人の――」
「やかましい!」
髯が怒鳴った。
「つべこべと、いつまで口争いを致している。貴公」
と新太郎に向って、
「この両人を御存知であろうな!」
「――」
「どうだ!」
新太郎ぐいと帯をさげた。
「貴公、何だ?」
「わしか、ふむ、わしは見る通りの男だ」
「己も見る通りの男だ」
「――」
髯が眼をむいて、
「掏摸の頭などを致す分際で、人がましく高座にいるという法があるか、下に居れい!」
喚いたが、声の大きなこと。
「はっははは」
新太郎笑って、
「己が掏摸の頭なら、さしずめ貴公は押込の手下であろう」
「なに押込?」
「夜陰に他人の家へ踏込んで、大声に嚇しつけるなんど、正に押込夜盗の有様でないか、おお怖や」
ふざけた男だ、新太郎首をすくめて、一歩出るや、むずと髯の襟髪を掴んだ。
六
しかし、一刻の後。
新太郎と髯とは、辰、三吉、天紅を傍に置いて、大盃をあげていた。
「そう云う訳でな」
髯が、
「辻講釈一夜の鳥目が木賃宿の代にならぬ、ままよ露宿は貧の栄耀と洒落のめしての、夏のうちは濁酒ソウピィデリンケン、大いに惑星の研究を致し居ったが、斯様に秋深み風冴えて参ると凡夫の悲しさ、屋根の下が恋しゅうなる、それでのうても朝起きて、この髯に霜めが結び居るを見れば、人生四十年転(うろ)た落莫を感ずるでなあ、あはははは」
新太郎うなずいて、
「御尤も」
「幸い――と申しては悪いが、今宵の騒ぎじゃ掏摸と見て手を出したは、云わずと知れた仲裁役で、先哲安兵衛の故智にならい、一夜の宿を工面せんず窮法、先刻よりの無礼、淵源するところ如是じゃ。ま、赦されい」
「いや手前こそ」
盃をさして、
「ところで、不躾ながら」
と新太郎が、
「見受くるところ、下凡の講釈師とも見えぬが、差支えなくば御姓名を御聞かせ下さらぬか――?」
「名乗る程の名でもないがの」
髯がにやり苦笑して、
「姓は平賀、名は源内、福内鬼外とも風来山人とも号し」
「別に天浪人、松籟子の名も――」
と新太郎笑って、
「ござりましょう――が?」
「や、人の悪い」
髯が眼を剥いた、
「存じながら、ひとに名乗らせるなんど」
「いやお怒りなさるな」
新太郎は酒をさして、
「江戸の水を飲んでいて、先生の時と、放屁論を知らぬこそ不思議。――ただ、素直にお名乗り下さるか否か、それを知り度う存じましてな」
「益々人が悪いぞ」
「と申すも、志道軒などの薫育よろしきを得た結果にて」
「これは敵わぬ」
「ははははは」
快さそうに新太郎は盃をあおった。
平賀源内は讃岐の人、生来の英質を以て、はじめ藩の茶坊主にのぼり、儒書の研鑽に没頭、後同藩の薬草園を管理した。藩を致仕して長崎に遊び、蘭学を修め物産の事を究め、諸国を漫歴の後江戸に出た。儒と医とを業として居るうち館林侯に見出され、二百石を以て仕えたが辞し、巷間に流浪しつつ著述或いは物理化学に専心、酔って街頭に一世を罵るの言を放ち、転々として居を温めず、今日に至っているのである。
「此方は――?」
と新太郎が訊く、
「これはわしの弟子、東天紅と号する男、長枕得合戦などは此男の作でな」
「せ、せ、せ先、先生」
天紅は口を尖がらせながら、
「そ、そそそん、そんな、ででででたらめ、でたらめ、らめを、おっ、おっ」
真赤になって吃っている。
「いや承知して居るよ」
新太郎笑って、
「あのような作、お若い貴殿にものされよう道理もなし。当代、あれ程の洒落、山人を措いて外に――」
「先ず一蓋参ろう」
源内は盃をさして、
「業平浪人なかなか話せる、朋友のかためじゃ、ぐっとあけて呉れ」
西条癇癖候
一
治貞(はるさだ)は唾壺(だこ)と金腕(かなまり)を前に置いて頻りに口を漱いでいた。
それが自慢の質素な居間には、装飾らしい何ものも無く、襖絵の応挙の筆「虎渓三笑図」と、床の刀架にある黄金づくりの吉則の太刀とが、ひと際に厳しいものを思わせるばかりだ。
「誰ぞ居るか」
金椀を置いて怒鳴る、
「は」
言下に襖の彼方で答えるのへ、
「順庵を呼べ」
「は」
治貞は、がーと咽喉を鳴らせて、含み薬を唾壺へ吐き出すと、懐紙でぐいと口辺を押拭ってさも不快そうに眉を寄せた。
襖際へ走り寄る足音、
「順庵にござります」
「入れ!」
襖を明けて、医師羽田順庵が入って来る、治貞はたたきつけるように、
「しみるぞ」
「はー?」
「貴様、薬を変える折には、決してしみぬとぬかしたではないか、含んでみろ! 骨の髄までしみる!」
「それは、訝しゅうござりまする」
「訝しいか、訝しくないか、自分でやってみたらどうだ、貴様の調薬は識学で無うて口舌でごまかす術(て)じゃ、むねくその悪い――変えて来い!」
「は」
順庵は金椀を持って、滑るように退って行った。
治貞は見やりもせず二度三度、がー、がー、とけたたましく唾を吐いたが、
「これ!」
と襖の彼方へ喚く。
「は」
「江戸屋に会うと申せ」
「は」
行こうとする気配へ、浴びせるように、
「榊原は来んでいいぞ」
「は」
足音が遠のくと、治貞は机の上から一輯(ひとつづ)りの書物を取上げて、ぺらぺらとめくった。書物の表には、墨黒々と、
御献納金目録 江戸屋八左衛門
と認めてあった。
暫くすると襖際で、
「江戸屋八左衛門、推参仕りました」
という声がした。
「よい、入れ」
「は」
襖を明けると、御勘定方榊原庄兵衛が、江戸屋を後へ控えさせて平伏していた。
「江戸屋とか、許す、入れ」
「へへ」
「庄兵衛は控えて居れ」
榊原は平伏したまま、八左衛門は静かに座を進めた。江戸屋は五十あまり、小柄なひきしまった体全身これ胆と云った男だ。眉の薄い割に眼の鋭い、耳たぶの大きく張った、ひと癖もふた癖もある面構えで、当時江戸の豪商中、第一の指に折られる商人として恥かしからぬ偉丈夫である。
「江戸屋か」
と治貞、八左衛門は平伏したまま、
「へへ、下賤の身に御目通り仰せつけられましてーー」
「挨拶はぬきじゃ、寄れ!」
「へへ」
治貞はじろり江戸屋の顔を見た。八左衛門は恐れ気もなく、一膝、二膝すすむと、頭をあげて、正面から治貞を見上げた、鋭い眸子の光、治貞はっと外は向いて、
「書出の物を読んだぞ」
と云う。
二
治貞は唾壺を取って、がーと大きく唾を吐きすてると、心の動揺を知られまいと声づくろいをしながら、
「献納金五万両――だの?」
「へへ」
「じゃが――」
「――」
「斯様な金、故もなく――」
「否や」
江戸屋が低く制した。
「なんじゃ」
「は」
「何ぞ、申すことあるか」
江戸屋の眸子が、きらりと光を増した。治貞は又しても防ぎきれないで眼を外らした。素町人の眼を受けきれぬ自分が、ふしぎでならなかった。
なる程、紀州藩としては、江戸屋から莫大な借財がある。この四年来、利払いも思わしくゆかぬらしい。とすれば、五十万両の桁は疾うに越しているだろう。
しかし、紀藩の物産取捌方は、殆ど江戸屋が一手に締めている筈、是等年来の利潤をみれば、五十万や八十万の借財は――、
そこまで考えたが、治貞も流石に――それを押切って、
何でもあるまい!
と断定することは出来なかった。だが、眼前に並べられた五万両はどうだ。相手は商人、名目の無い金を、何の理由もなく持込む訳はない、――治貞はまた唾壺をとって
「うん?」
と江戸屋の舌を促した。
「実は」
八左衛門が口を切る、とたんに治貞は、無遠慮に喉を鳴らしてがーと唾を吐いた。
「うん?」
「手前、商いの手拡げ仕りまして」
「――」
「長崎表に海産物の、唐荷売買を目論み仕りました」
「唐荷売買?」
治貞は意外なと云い度げに、
「じゃが、それは大阪の山屋、渡辺なんどが黙っては居るまい」
「は――」
江戸屋の眼が笑う、
「それに就きまして」
「助言せいと云うか」
「否や、山屋、渡辺らとは、最早談合がついてございまする。しかし――」
八左衛門の声が、ぐっと鋭くなった。
「一の難関は、会所にござりまする」
「――」
「唐荷売買の商人は、御承知の如く会所の掟に依って定員にござりまする。しかし、頃日(けいじつ)唐船物の貿易は日々高きを加え、到底定員のみの扱いきれぬ数高と相成り居ります」
「多言は要らぬ」
治貞が制した、
「望むところだけ申せ!」
「へへ」
八左衛門は低頭しながら、にやりと苦笑を洩らした。
「就きましては、会所の掟表にござりまする定員の条、御修定相成りまするよう御言葉添え願えますれば――」
「うん――」
治貞は頷いた。
これで又、意次めをやり込めてやる手が一つ出来た。唐船物売買に定員を置くなんど、貿易の関を塞ぎ、国運を損うの悪策だ、恐らく商人共の専利に跟き、賄賂などをしこたませしめて居るに相違あるまい。
「宜い、聞き届けたぞ」
治貞はそう云って、またしてもがーと臭い唾を吐きすてた。
三
江戸屋が退ると治貞は、
「榊原を呼べ」
と命じた。
「お召しにござりまするか」
直ぐに榊原が来る。
「例の者、来て居るか」
「は、控えて居りまする」
「女も?」
「御意の如く」
「うん!」
治貞は頷くと、手筐を明けて二帖の紙包を取出し、すっと立って榊原庄兵衛のあとから部屋を出た。
書院を左に見て、控屋の方へ廊下を曲る、鍵の手に折れて、右へ厳丈造の杉戸、明けると左へ行く廊下の、右側が壁になっている。榊原が前へ出て柱を二三度叩くと、
かちり!
と鈍い音がした。
「御免」
といって、壁を、指加減に押す、低くきしりながら壁が右手へ滑った。
その当時、諸侯の邸には、いずれもあったぬけ部屋で、多くは非常の場合、脱出の道に造られてあったものだ。しかし平常は用がないから、秘中の秘にされてあるをよいことに、勝手筋へ金をまかなって、賭場に使ったり、もっと怪しからんのは、出会の隠家にしたりしていたものである。
ぬけ部屋の中には、左手を木綿で巻いて肩から釣っている武士と奥勤女風の女とが、黙って、坐っていた。
怪我をしている武士は、吉川太伯だ。
「シ――っ」
上手の壁の中から声があった。
太伯と女は、はっとそこへ両手を下ろした。壁が滑って、榊原と治貞が出た。
治貞が座に就くと、
「太伯か」
と声をかけた、吉川は平伏したままで、
「は」
「手を――どうした」
「は――」
「刀傷か?」
「は、先夜――仰せ付けの男を――」
云いかけて女の方へ眼をやる、治貞はうなずき笑って、
「宜い宜い、案ぜずと宜い女(もの)じゃ、其女(それ)も彼奴を狙うたことがある、まんまと仕止め損じたがのう、ははは」
「此の方が――?」
太伯が見る、
「新太郎を?」
「うん、尤も一人ではなかったがのう」
治貞の言葉に、女は何故か隠し難く耳を染めながら、ちらと太伯をぬすみ見た。
「して、其の方は?」
「は」
太伯は面目なさそうに、
「心利きたる者ども八名して、木挽町の原へ連れだした上、一応葵坂より手を退くよう申しましたが、勿論、承知せぬ故一刀の下にと、抜きました」
「斬ったか」
「否!」
太伯は頭を横に振る、
「不敵な奴、出来るな――とは存じましたが、抜き合せてみると段違いの腕、なかなか江戸剣客多くとも、彼に敵する者五人はありますまい、我師神谷源心ならば兎も角対等の立合もございましょうが、私如きが相手には過ぎまする――」
「で、どうしたのだ」
「必死必殺!」
といったが、太伯の声は暗かった。
「必死必殺と存じまして、捨身で斬りたてましたが、まるで――」
四
「まるで子供扱い、遂に手の者三名は死し、残らず手傷、拙者まで斯様に――」
太伯は苦笑しながら左腕を見た。
「面憎い奴のう」
治貞は唇を噛んで、
「佐賀!」
と女の方を見た、
「其方の時も四五名、取られたのう」
「はい」
女は手を下ろして、
「二人死に、三名は重傷にて――」
「ほう!」
太伯がうなずいた。
「彼奴それ程出来るかしらん」
「尋常一様の儀にてはー」
「暗討もかけてみたし、鉄砲も用いてみたし、太伯の飛竜剣も届かぬとなると」
治貞は少し苛々してきた。
「太伯」
「は」
「もう一度、やってみる気はないか」
「其儀に就きまして」
と太伯は手をつく、
「御願い仕つることがござりまする」
「願い――何じゃ」
「今日までの過分なる御手当、唯今限り御返上仕り度う存じます
「それは――」
治貞は訝し気に、
「どういう意味じゃ」
「源心道場において筆頭の腕、横紙破りと自負して、数多の門人を養い人がましゅう致したこと恥かしく、また上様御恩顧を被りながら己れの未熟より七名の門下を傷つけ、己れも左腕を失いし始末。実に慚愧に堪えませぬ儀――」
「うん」
「今日より御扶持を放れて身軽となり、安芸新太郎を斃す為には、豺狼とも相成る所存!」
「うん!」
治貞の眉が動く、
「また二つには」
太伯は胆太くいう。
「市井の暗に隠れて、九曜星 (田沼を指す)の治世を呪う一法、辻斬りー」
「や!」
「ひき剥ぎ!」
「――」
「追脅し!」
治貞は頷き頷く。
「窮民を煽動仕って、一揆も起すべく、打壊しも致すべく、縦横無尽に――」
「そうか」
治貞は拳で膝を打った。
「紫の柄糸いよいよ暗に跳るか」
「御聴許下さいまするか」
「よかろう」
治貞は機嫌よく、
「一揆、暴民の事は上に憚りも多けれど、暗に星を飛ばす風流も面白かろう、政治向の腐敗、士気の乱脈、市民の贅楽、上より下まで斯く汚れきった世は古今に例を知らぬ。やれ、飛竜剣を放って、飽くこと知らぬ世人の惰眠を醒ましてやれ!」
「はっ」
太伯は両手を下した。
「後始末は儂がつけてやる。勝手放題にあばれてみろ、うん!」
治貞はうなずいて、
「斯うしよう。其方これからむらさき組と名乗れ!」
「は――?」
「何か出来したら、紫の紐一筋を遺して置くのだ。のう――すれば後始末は儂が、よきに計ろうてやるぞ」
太伯は返答もせずに胸の内で考えた。
これが御三家の一、西条侯といわれる人か、と――。太伯の胸は何かしらん、もやもやと曇って来た。
五
「佐賀」
「は」
治貞は太伯を眼で示して、
「此の男、覚えていて呉れ。吉川太伯と申して、われらの腹心じゃ」
「はい」
佐賀と呼ばれる女、年の頃は二十六か、七ででもあろう、肉の緊まった体つき、肌の色浅黒く額高く、眸の内に光あって――美しさも美しいが、何か毒の閃きがある感じだ。太伯が会釈すると、細いかたちの良い唇で微笑しながら、女も目礼した。
「葵坂に、何ぞ変ったことでもあるか」
「はい」
佐賀は低く、
「御方には、この四五日、御微恙(軽い病)にて」
「風邪か――」
「それが」
佐賀の唇が笑う、
「何じゃ」
「御医者にお診せ申しても、一向に知れませぬようで」
「どのような」
「終日微熱、軽いお咳が出て、気鬱が晴れず御食事が進ませられず」
「うん?」
治貞の眼が光った。
「やったか?」
「いえ」
佐賀は静かに頭を振って、
「未だあれは、そのままに――」
「すると?」
「私には些か心当りがございまする――が」
「うん」
「御微態の因は、外に――」
「何じゃ」
「は――」
といったが、どうやら会いにくいらしく、ちらと太伯の方へ眼をやりながら、
「安芸新太郎が――」
「え?」
「ほほほ」
佐賀の笑いだ。
「新太郎が何か」
治貞は察しが悪い。しかし太伯はそれと気付いてちょっと鼻白んだ。
「新太郎が何か致したのか」
「御方の心を、悩まし参らせる相手かと」
「や」
「山王詣での折、危難を救われてより、何かと新太郎に心惹かれ給うようで、先日来――二度まで、御眼通り仰付られ」
「して、主殿(とのも)は承知か」
「初めての折は、主殿様が、強く御制止なされての上、たっての仰せで、主殿様御付添の上謁せられ、二度めは直々の仰付にて、御老女御付添のみ――」
「怪しからぬ」
治貞は大声に喚いた。
「無頼下賤の者を、間近に寄せて何たる不始末じゃ、汚らわしい、沙汰の限りじゃ――たとえ公の御披露はなくとも当将軍の」
「あ、上様」
佐賀が遮った。
「うん?」
「それを仰せられずとも、私に一案ござります」
「――」
治貞は眉寄せた、
「薩摩侯が、御方の盾となって、御警護につきましたこと、御承知にござりましょうか」
「存じている」
「薩摩侯御二男に、亘様と申されるのがござります」
「うん、して――?」
「重豪(しげひで)様の御目論みは、御方と――亘様」
「――」
治貞の眼が、再び光った。
六
治貞は居間へ戻って来た。
「順庵を呼べ」
順庵は直ぐに金椀(かなまり)と薬筐を持って来た。
「薬!」
「は」
「今度はいかぬであろうの」
「は、お試みの程」
手早く薬筐の中から、三帖の薬を取出して、金椀の中へ明け、香湯に調じて、恐る恐るささげた。
治貞は金椀を取って薬湯を含むと、凄じい音を立てて歯茎を洗いはじめた。順庵は漁雲を観る老漁夫のように、危惧と畏怖を以て治貞の表情を見戌っていた。
こんどはしみなかった。芳香がくされた歯茎にこころよく浸透して、鼻について寸時も離れぬ異臭が、煙のように消えてしまった。治貞はがーと薬を痰壺の中へ吐きすてると、大きくうなずいて、
「うん、宜い、宜いぞ」
「は」
「此調法忘れずに居れ」
「は、面目にござりまする」
「退って宜ろし」
順庵は平伏して退った。
金碗一杯で口を漱ぎ終ると、治貞は机に向って紙をのべ、筆を執った。
大名も下侍も同じ人、自分身の廻りの始末は自分でする、と云うのが治貞の持論だ。武家諸藩の内政苦境を処理するには、藩主先ず生活法外の無駄を節し、格式は格式として日常の挙措は出来るだけ質素単簡を尊ぶ可し、とも云った。それで治貞は公式の外小姓を使わず、書簡も多くは自分で認めた。
治貞は、自分を遠謀深慮の士と信じていた。幕府の頽勢を挽回するには、先ず己れ治貞が起たねばならぬと信じていた。幕府の頽勢(崩れ衰える有様)――これ位不可思議な事があろうか。神君以来、源氏の頭株として兵馬の権威に居り、天下の事を掌握して、万の法制一に幕府より出る筈、何が故に財政の逼迫を来し、何が故に民心の憎悪を買うか。他なし、成上り者田沼意次の執政宜敷(よろしく)を得ぬに因る。
治貞は斯う考えていた。
数年来、幕府の執って来た課税政策、これこそ悪法の悪とも云う可きものだ。意次はあらゆる産業商品に税を課した。物に依っては幕府自ら産業に参加しつつある、下剋上の風は所以するところ有だ、意次は幕府を、今や全くの商人会所にしようとしている。神君以来の威令を失墜したばかりか、その上に幕府を商算の府に変じようとしているのだ。
意次を斃せ、幕府の神聖を挽回せよ!
これが、治貞を主にした、反田沼派の主張であった。
治貞は書面を二通書終ると、
「これ!」
と呼ぶ。
近侍の士が来ると一通を渡して、
「是を大目付松本対馬へ持って行け」
「は」
「それから是を」
ともう一通を出して、
「清水殿へ届けて」
「は」
「宮内卿からは、御返しを頂いて参るのだ」
「は――」
近侍が去ると、立って奥へ通ずる襖を明けた。侍女が二人、はっと平伏するのへ、
「湯を浴びるぞ」
と云う。
「は」
と二人が立つ、小走りに行く後から、治貞は大股に続いた。治貞の大きい眸子は、右側にいる侍女の、豊かな臀肉が、むりむり動くのを、飽かずに見戊っていた。
しっと
一
新太郎の血が躍った。
家へ戻ってからも、幾度か取出しては、うす墨の文字のあとを貪るように読みかえすのであった。
明夜四つ(午後十時ころ)奥庭の築地の裏にて――
千
と書いた文だ。
墨の匂い、手蹟の美しさ、それに早咲きの山茶花を一輪手筺の中に封じ籠めて――。
――御方様より、是を。
と奥勤女の佐賀から渡された時、
何を、此奴!
と思ったが、最早それどころではない。佐賀を不審の女と看ていた新太郎も、手筺の主を疑う気にはなれなかった。
二十八歳にして初めて知った恋。無明暗夜の心に慈光を點(てん)じてくれた、かの人から直々の文だ。当の人の身分も、自分の境涯も、何ものも忘れさせる恋の血が、安芸新太郎五尺七寸の全身に脈々と燃えた。
「お帰りですか」
新太郎を追うようにして来た、『よし田』のお園が、門口からこう声をかけた。
「御飯は?」
「いらぬ!」
不愛想な答えだ。
「まあ御挨拶ですねえ」
とお園は構わず格子障子を明けて、
「まさか飢え死ぬお覚悟でもござんすまい」
「よう――」
新太郎が振返って、
「化粧(めか)したな」
「悪うござんしたね」
「悪うはない――が、また辰公めにいためられようかと思ってな」「あい、御親切」
お園は白粉を刷いた頬を抑えながら、ついとあがった。
「あら」
驚いたと云う表情で、
「珍しいこと」
「何だ」
「それ――山茶花じゃござんせんの?」
「う」
と新太郎、慌てて小机の上に手をやる、よりも早くお園が、
「まあ綺麗だこと」
と、素早く横から奪って鼻へ、
「誰から――?」
じろっと艶な眼だ。
「ばかを、申せ」
「なあぜ?」
いたずららしく、くるっと眼を瞠ってみせたが、そう見せるにしては、内心の焔の方が幾らか強かった。
「なぜ、ばか――です?」
「つまらぬ、いま戻る道で、みかけた故、何の気もなく摘み取って来たのよ」
「へえ――この辺にもそんな、風流なお邸がござんすかしら」
「あるとも、な、無くって」
新太郎むきになる。
「何所?」
「そ、そこ――つい愛宕下の隠岐様のな」
「隠岐様の」
「裏の、小造りな家でな」
お園がつんとして、
「坂があって、お邸の前には赤松が十五六本、黒塀を取廻した――」
「これ!」
新太郎が驚いて制した。
「何を、愚かな」
「私が愚かな女でも、もうこれでふた月、思う男の行先をつき止める位の知恵はございますのさ、はい失礼」
お園、いくらか酔っているらしい。
二
思う男――と、はっきり云ったお園、酔ってはいるが、流石にいくらか衒れたらしく、持っていた山茶花の花を、
「焦れったいねえ」
と云いながらつかみつぶそうとする、手を、
「これ」
新太郎が逆に取って、
「何をする」
と云いさま、関節を緊めて置いて、しずかに、花の損せぬように山茶花を取上げた。
「ほほほ」
お園は短く笑った。
「業平浪人が、花を持って、ほほほ、これやとんだ判じ物だね」
「貴様、酔っているな」
「おやおや、急に貴様とお見限りですね、先生!」
お園はぐいと片膝を立てた。それでなくても崩れていた常前が、ぱっとはだかって、白いものがぞっきり剥いたように、緋色を割って露わになった。
「薄情男と夕立は東自慢だと云うが、貴方っくらい薄情も珍しいよ、まあー考えてもごらんなさい三年、三年ですよ」
お園は手で三度、膝を打って、
「お故郷の越後はどうかしらず、江戸じゃあ石の上にも三年と云ってね、辛棒もそれが年限になっています、あたしゃしがない料理茶屋の女、女房にして呉れの、奥方にして頂き度いのため、最初からこれっぱっちも云ったこたあ有りません。けれどね――先生」
新太郎は眼を閉じていた。
「けれどねえ、三年も朝晩貢ぐにゃあ、欲得や見栄じゃ出来ませんよ。濯ぎ洗い、御酒の面倒まで見たたあ云いません。見させて頂きました。ええ立派に、嬉しく見させて頂きましたさ。けれどねえ、白痴が狐に憑かれやあしまいし、いくらあたしが後生楽だって、心に思いもしない男に、のんべんだらりと三年も、何で御奉公しますものか――」
お園はぐたりと右手を畳へ下ろした。
「こうもしたら、偶には、優しい言葉の一つもかけて呉れるか、いまに此の気持を察して貰えるかと精精がそんな空頼み――不実にされても怒るせきはありません。いいえさ、厭ならこれっ限りと、遠くへでも行かれたら、却って歎きの種と思って、これでも随分、胸を抑えて暮らして来ました。それなのに、それなのに貴方という人は」
ずっと片膝にじり寄って、
「あたしの気も察せぬ風で、ぬけぬけと葵坂あたりへ女を――」
「これ」
新太郎が強く制した。
「これ! 何がこれです?」
お園はもうひと膝、
「女と云ったが悪うござんすか。へん、大きに憚りさま。どこの何様の御姫様か知らないが、扶持米一粒頂いている訳じゃなし、女を女と云うに不思議はござんすまい。それとも可愛いい者を、こんな茶屋女風情にさげすまれては一分が立たないとでも仰有いますか――先生」
「もう分った。宜い加減にしろ」
「宜かあ有りません。三年も黙っていたあたしだ。おなかあ云い度いこって一杯になっている。口を裂かれたって、云う丈の事あ云ってみせます」
「少々うるさいぞ」
新太郎が向うを向く、肩へ、お園がぐっと手をかけた、
「先生――」
と曳く、酔っているのに無理な姿勢、新太郎がちょっと肩を外すと、いくじなくも女はそこへ仰向きさまに、裾を乱して倒れた。
「よう――色模様だの」
表で、風来山人の声がした。
三
「あら!」
お園は流石に狼狽して、
「まあ失礼」
裾前を庇いながら慌てて起き直る。風来山人にやにや笑って、
「いや、そのままそのまま」
と上へあがる、
「緋雲乱るる中に白蛇纏綿(はくじゃてんめん)す、薫匂婀娜として宵情頓に悩殺――かのう」
「もうもう降参」
お園は手を振って、
「御勘弁、ごかんべん――」
「はははは」
風来は機嫌だ。
「業平浪人なかなか隅へ置けぬのう」
「さも、ござろうか」
新太郎は座を譲りながら、
「お園どのが、今宵はたいそう酔って、何やら小生先刻よりひどく苛められて居りました、山人御帰館で命拾いを仕ったよ、ははは」「浮気をなさるから――よ」
といったが、お園、もう半分酔いが醒めかけている、はっと気がついて袖口を唇へ当てると、面を染めながら土間へ下りた、
「浮気――ほほう、業平浪人が浮気をしたか」
「ちと叱って――」
お園の声はもう尋常だった、
「ねえ平賀先生」
「うん、心得た、みっちり意見をいたそう」
「先生!」
新太郎に、
「今夜のところは、どうぞお赦しを――」
「知らぬぞ」
眼では笑って、
「のう、平賀先生」
「そう両方から加勢を求められては困る、風来はもとより痴話喧嘩の仲裁は不馴れでな」
「おお恥かし」
袖屏風をして、
「御免下さいまし」
とお園は出て行った。
「是だな」
風来は膝を崩しながら、そこに落ちている山茶花を取上げた。
「諍いのもとは、そうであろう」
「戯れでござるよ、あの女、ふだんは至極おとなしくて、冗談にからかわれても、あかくなってにげる位、されば性悪の酒客などもお園ばかりは手が出せぬと評判でござる。なんとしたか今宵はひどく酔って――」
「や、しかし左様な者こそ、酔わねばいえぬこともござろうでな」 そういって風来山人、にやり笑ったが、ふと調子を変えて、
「話は違うが――」
「――」
「先刻、外にてちらと洩れ聞くところ、葵坂という言葉が出たようだが」
新太郎はっとした。
「其許、彼所(あそこ)へお出入なさるか」
「と――申されると?」
「いや、精しくは承知せぬが、たしか彼所には折々主殿頭がみえる筈」
「は」
「御入魂か」
「――」
「御入魂ならば、御伝言願うことがある」
「なんと、申して?」
新太郎は躊躇いながら、
「いや大した事でござらん、源内この家にありとお伝え下されえ」「相良侯は、先生を御存知でござるか」
「と――思うがの」
風来は笑って、
「或いは、知らんというかもしれぬが、まあ伝言だけ頼む」
「承知仕った」
四
「ところで」
風来が話を変えようとした時、
「今晩は」
と声がして『よし田」の小女が岡持と酒徳利を持って入って来た。
「遅くなりまして」
「よう、馳走だな、是は有難い」
風来が手を伸ばして受取る、
「や、燗も出来ているな」
「よろしく」
と小女は去る。
「鱧に、塩焼に、小鉢が甘煮か、吸物は――鴨か」
「先ず一盞」
新太郎が徳利を取った。
「のう、安芸氏」
「はあ」
「其許、この世相を何と観る」
「と、仰せられますと」
「たとえば、其許は何をめあてに生きている、何か生命を打込んでやろうと云う目的を持って居らるるか」
「――」
「それとも、便々と生をたのしんで、徒食に定命を全うせば能事足ると思って居るか」
「大分、むずかしゅうござるな」
「むずかしくはない、わしが訊き度いのは、一生をうち込むに足るようなものを、持って居らるるかと云うことだ」
「――」
「有るかな――、否、有るまい」
風来は酒を仰る、
「有れば好んで晒巷(ろうこう)に無頼の暮しをせんでも足りよう、葵坂あたりの用心棒にならんでも済もう、が――生きる目標がない、何をめあてに一生を送るべきか、その方途が無い!」
「なる程」
新太郎は微笑する。
「世相最も著しき弊は是だ」
風来は自らうなずいて続ける、
「上は六十余州諸侯から、下は駕籠舁き人足に至るまで、一心以て帰依するものがない、これは何が故か――」
「さて」
「人世界を築く諸般の道徳が違って来たのじゃよ、たとえて申せば神社の境内を犯してはならぬ、敢て犯せば神罰たちどころ――と云われて居った。所が時勢の変遷は、神境を犯しても神罰などと云う愚かなものの存ぜぬことを人に教えた。また、高貴の通過に際しては門前に土下座して迎える可し、重代の家恩我に限り無しと申して、将軍、藩侯の行列に対しては寧ろ崇敬思慕の情から、争って戸外に土下座して送迎した者も、時勢の鏡にかけてその機関を知ると、藩侯将軍の恩は寧ろ一個の欠鍬に如かずといって、行列に当っても戸を閉じ、内にふん反って知らぬ顔をする始末だ――。分るか、武将は権と力とを以て世に臨んだ、山野の財、海川の宝は居ながらにして掌握することが出来た、しかし――時勢は権と力との外に、新しく利と申すものを生み出した。算盤算数――だ」
「ほほう」
「六十余州の諸侯、中には異例もあるであろうが、四分三は財政逼迫手も足も出ぬ、曽て権と力とで簒奪した国土、生殺与奪の権を握って居る国土を有ちながら、借財を借財に換えねば立ち行かぬ――何故だ、新しい道徳が出て来たからだ、新しい道徳」
風来山人、つと盃を挙げて大きく云った。
「商法――だ」
「なる程」
新太郎は相変らず、にやりにやり微笑しているばかり。
「領主の力を以てしても、将軍の権を以てしても犯すことの出来ぬ新しい力、算盤の活動が始まったからだ」
五
「人は斬れる、が、算盤は斬れぬ、利殖と申す眼に見えぬ毛物、先ずこれが新しい時勢の梶取でござろう、執権その権を喪い、神仏衆の帰依を喪い、庶民その食を失う――これが此の世相でござる」
「ふ――む」
新太郎尤もらしくうなずいて、
「すると、我ら方途を失って、市井無頼になり下った者などは」
「左様、当分はこの儘」
「ははあ」
「よき酒と、美しき女と美味き肴と――これが当分は我らの仏如来、世の中がひっくりかえって、活溌発たる新しい世界が現われるまでは放浪三昧を法楽浄土とする外はどざるまい」
「ご――ござるかの?」
新太郎は酒を啜って、
「が――先生」
と微笑を向ける、
「果して、新しき世界などが現われましょうかな」
「うん?」
「生来無学、世史(よのふみ)のことなど詳かにしませぬが、執権その権を専らにし、庶民飢えざる世、果して我らに望めましょうか。我ら五十年の生涯を是にこそと打込む、明かな希望のもてる世界、果して現出いたしましょうか」
「されば――」
「ま、暫く」
新太郎が肩をあげる、
「私は斯様に思案仕ります、人性命あり、世流に媚ず、権に制せられず、行住座臥欲するが儘にあれば、酒無くば無くて宜く、美女無くば――」
「無くも――宜きか?」
「――」
「ははははは」
風来が高らかに笑う、
「さらば山茶花の一枝、ことさらに諍いの種ともなるまいが」
「それは、それ」
「否、一事は万事じゃ。いま其許の申された行住座臥欲するが儘にあればと云う言葉、それじゃよ、儂の申そうとする所は。のう、斯様に巷に飢ゆる者が満つる時、其許一人欲するがままにあればとて、それで満足することが出来るかな――。如何にも、世史は法権の順還を証し、飢餓の順還を証している、併し人性命ありとして酒無くば無くとも宜しと云い去る前に、人性命あり、酒をして何人にもあらしめよと云う事を考えられぬか」
「考えられませぬな、否、考えようとは存じませぬな」
新太郎は笑う、
「佳き酒、美しい女は、手に入り難ければこそ味わいもまた一入。何人にもあるとなれば、美酒も珍ならず、佳人も興なく存ずるよ、水飯をくえばこそ、あつもののたまさかなるに舌鼓もうつべく、濁酒三旬にして灘の生一本に天上の味楽を恣(ほしいまま)にする娯み、ははは、新太郎のつらねは斯様にござる、御笑殺」
「人さまざま」
風来山人も頬笑んで、
「ま、一盞参ろう」
徳利を取上げた時、裏で、
「ものもう――」
と胴間声をあげる奴があった、
「誰だ」
新太郎が居ながらに、
「こ、こ、この、や、此の家に――か、か、か、かかか、う――ん」
「誰か知らんが、その辺へ炎を吐き散らしてはいかんぞ」
「た、た、たん、痰、じゃ、痰じゃあ、ございま、ご、ご、ござらん」
がらり裏を明ける、
「と、と、東、天、紅」
「あ、鶏か」
と新太郎。山人は腹をゆすって笑った。
六
明るい夜だ。
定めの刻限に葵坂の邸へ詰めた新太郎、四つ(午後十時頃) 少し前に座を立つと、見廻りを装って、裏庭の方へ出て行った。
寒い夜で、月のない空に、磨き出したような星が冴えわたっていた。数寄屋を廻って、池を右に、暗い亭をぬけて、足音を忍ばせるように築地へ来たが、まだ刻が早いかして、文の主は見えなかった。
軽い失望と、ふしぎな安堵とにほっとした新太郎、夜空の星を仰ぎながら、
「しかし」
と低く、
「お逢い申して、どうしようというのだ」
低くつぶやいた。
「二十八歳にして初めての恋、想う人にことを欠いて、当上様の姫君に心奪われるなんど、新太郎よくよくの不運よのう」
悲しげな微笑が、唇を僅かに歪める。
「いっそ謁を受けず、お言葉も賜わらねば、あきらめの法もあったろうに、かりそめの御情が今は恨めしゅう思われる」
星が飛んだ。
と――新太郎はきっと耳を澄ました、人の気配がする、亭の裏手から、忍び足で来る、
「御方か――」
と思って築地の植込みを出ようとすると、亭の暗がりを出て来た人影、男だ――。
「や!」
とつぶやいて植込みの中に退く。
見ると相手は、黒い頭巾で面を隠している、身拵えから見ると討入りの者でもないらしい、といって今時分、此の裏庭へ、面をつつんで忍び入る男が尋常であろうか。
相手の男は、暫く四辺を窺っていたが、やがて静かに築地の方へやって来た。新太郎、黙って二三歩やり過しておいて、
「待て!」
と声をかけた。
「――!」
相手は一瞬そこへ立ちすくんだが、
「誰だ」
と新太郎が声をかけた刹那。右足を半歩ひいて、さっと身を沈めざま、
「――!」
陰の気合、いきなり新太郎に斬りつけた。鋭い切尖、危うくかわして、
「うぬ!」
と新太郎、
「斬るぞ」
叫ぶのと、抜くのと同時だ、曲者の面上へ電光の如く浴びせると見せてきらりかえす、刹那! 逆をとって曲者の剣が真一文字に新太郎の胸を狙った。
「とう!」
危くひっ外して、
「うまい!」
いいながら新太郎一歩さがった。
「出来るな、察するところ念流、それも相当に苦労した腕だ、名乗れ!」
「――」
「今までは瀬踏み、こんどの太刀は必ず斬るぞ、名乗れ!」
「――」
曲者は飽くまで無言だ。
「ほう、殺気、凄じい殺気――貴様、このおれを斬る気になったな、面白い、江戸市中剣客多くとも、安芸新太郎を向うに廻して、必殺の剣舞をやる奴はそう沢山はいないぞ、来い! だが、今度の打込みは間違いなく死出の門出だぞ、念仏を忘れるなよ!」
「心得た!」
曲者はじめて声をだした。
「あ、その声」
新太郎は思わず叫ぶ。
曲者は鋩子先を下げ気味に、じりっと右へ廻った。――また星が飛んだ。
七
「待て!」
新太郎が叫ぶ。
「その声に覚えある、その構えに覚えある、誰だ、貴公誰だ?」
「――」
「名乗れ、勝負はいずれにもあれ、拙者を安芸新太
郎と知って斬る気になった貴公、名を聞こう――」
曲者は答えぬ、鋩子さがりの剣に、ゆらり波をうたせると見るや、
「えいっ!」
はねあげるように突いて来た、
「おっ!」
払って、退く安芸、
「名乗らぬか、よし、聞くまい」
そういって、ばっと草履を脱いだ。
「それじゃあ――斬るぞ」
「――」
新太郎、むらむらと殺意を生じた。今日が日まで幾十度となく真剣の勝負を経て来たが、これだけの相手には初めて、相手も充分の殺気だし、自分にもはち切れそうな殺意が出た、これなら斬り甲斐があるぞ。
「えい!」
「――」
「えい、おっ!」
半歩出る安芸、足袋の裏にうす霜の冷たさが快くしみる。
「やあっ!」
つつと詰める。相手は僅かに右へ廻る。微塵も隙のない呼吸、胆力の太さだ。
築山の上に、ぽっ――と雪洞の灯が現れた。女が一人凝乎と死闘の両名を見まもっている、佐賀という、例の奥勤女だ。
新太郎も、相手も、この雪洞の灯をちらと認めた。
「あ、御方!」
と新太郎が思う、利那!
「か――っ!」
わめいて相手が、例の鋩子さがりから、なみを打ってはねあげて来る突き。
「――」
無言で上体を捻る安芸、左足をぐいと折って猛然と横っさまに払う、刹那! 相手は突きの剣をそのまま上から、断鉄の勢いで打下ろした。払うのと斬り下すのと殆ど同時だ。
「あ!」
佐賀が低く叫んで雪洞をあげた時、
「う――む」
低く不気味にうめきながら、名乗らぬ曲者が脇腹を抑えて、地上に這っていた。
新太郎は二三歩さがって、素早く左肩へ手をやった。衣服が二寸ばかり裂けている、指を入れると温いものが流れていた。
「危かった」
思わずつぶやいて、傷口をさぐると、僅かに筋肉をかすったばかり。
「おお」
気付いて振返ると、植込みの蔭に、ぽっーと雪洞の明りが見える、新太郎は手早く刀に拭いをかけて鞘へ、つつーと築山の方へ近寄った。
正しく、御方が。
と思っていたが、そこには人の影もなく、燈のともった雪洞がひとつ、ほつんと地の上に置いてあるばかり。
「や――」
と思って見ると、雪洞に近く、さあこれを――といわんばかりに、一通の封書が置かれてあった。取上げてみると、裏には見覚えのある御方の筆蹟で、
竜 様 まいる
裏には一字「千」と書いてあった。
「竜――竜様?」
新太郎は呆然とつぶやいたが、
「あっ」
といって立上った。
八
封書を片手に、雪洞を持って、倒れている曲者の傍へ戻った新太郎。
雪洞を其処へ置くと、呻いている男の頸へ手をかけてぐっと引起し、覆面を脱いだ。
「や、矢張り貴殿!」
と新太郎が驚きの声だ。
「諏訪竜次郎氏か」
諏訪竜次郎、薩摩侯重豪(しげひで)の愛臣、曽つて太伯一味の士を庭前で斬った、あの若者である。
「諏訪氏! 諏訪氏!」
耳に口を寄せて叫ぶと、歯をくいしばっていた竜次郎、辛うじて半眼をひらいた。
「気を、気をたしかにもたれい」
「――」
「何故の、何故の――」
云いかけたが、
「否、訊くまい、拙者も何も申さぬ、しかし、貴公何か申される事があるか」
「――」
竜次郎は静かに頭を振った。
「深傷だ、とても助命覚束ない、申される事あらば、聞こう――」「た、ただ」
「うん」
「無念だ、姫君に、姫君に――」
云いかけて、きっと新太郎を見たが、生力を失った両のひとみは、一瞬、燐のようにきらきらと光った。それは――嫉妬の色だった。
「申されい」
新太郎は片手の文を、竜次郎の眼前に差し出しながら、
「これは、姫君より貴公への御文だ」
「――」
「これを姫君と思って、何なりとも申されい」
「うーむ」
竜次郎はふるえる手で、新太郎の持つ文を取ろうと、指を空に泳がせた。新太郎がその手に文をつかませると、凄じい執念で、むずと文を掴みしめた。
「諏訪氏!」
と叫ぶと、
「む、無念だ」
歯をがちがち噛み鳴らせながら死の憎悪を籠めて、凝乎と新太郎を睨みながら、竜次郎は前へ、のめり斃れた。
「――」
新太郎は呆然と、諏訪竜次郎の姿を見下ろしていたが、やがて何思ったか、竜次郎の手から、御方の文を奪い取って立上った。そして覆面を竜次郎の顔へうちかけ、雪洞を築地の向うへ投げやり、裾の塵を払って数寄屋の方へ戻って来た。
付人の役人へ、
「唯今奥庭見廻りの折、曲者が忍び入りましたので、斬り捨てて参りました」
と届け出ると、自分は手傷の手当をすべく、御医師の部屋へ行くとみせて、邸を脱け出た。
相手は薩摩侯の愛臣、表沙汰になると面倒だ、一時身を外ずすより他に方法なし、と思ったから、お邸を出るとそのまま、星空の下を虎ノ御門へぬけ河岸伝いに鍛冶橋へ、足にまかせて来た。
田沼邸に参って、意次に次第を語り、善後の処置を取る考えである。
しかし、意次は、将軍家微恙(びよう)ということで、城中に詰めたまま帰っていなかった、ぐずぐずしていて薩摩の追手にでもかかっては不面目と、早々に田沼邸を辞して道を裏へ裏へと取りながら、新銭座の家へ帰ったのは、既にその夜九つ(午後十二時)を廻った頃であった。
「よう」
風来山人は机に向って筆を走らせていたが、
「どうした、大層顔が蒼いぞ」
と云う。新太郎は刀を脱りながら、
「先生とも、お別れをせねばならぬ仕儀と相成ったよ」
と答えて、さびしく笑った。
家治病む
一
家治は床の上に身を起し、脇息に売れながら、しずかに香をきいていた。
秋ぐちからの風邪が、いつまでもぬけきらぬで居ると思ったら、師走に入って軽い胸痛を訴えはじめ、四五日前から僅かながら喀痰(かくたん)に血を交えはじめたのである。
奥医師たちは喉頭の風傷だと診たが、田沼意次は御目見得医師として滝鶴台に更診させて、肺気傷という診候を得た。
家治は読書を禁ぜられ、晒風を禁ぜられ、聴政を禁ぜられ、御養生所にひき籠って専ら静養さるべきことをすすめられた。
御台所の嫉みで、愛妾於知保の方も近づくこと少く、身のまわりは側衆と小姓と――、医師と、時折
奥から於品の方が、御台所の意を含んで介抱に参るくらい、極めて寂莫としたものであった。
襖の向うで、低く、
「主殿頭伺候仕りました」
と声がした。
「これへ」
家治は香炉を押しやって眼をあげた。
襖を明けて入ると、田沼意次は静かに進みよって平伏した。
「如何にござりますか」
「今日は、朝から具合がよい、痰を三度ばかり吐いたが、血は見えぬそうだ」
「御胸痛は――」
「少し、重苦しいと思ったが、香をきいて居ったら大分軽くなった」
「それは」
意次は些か眉をひらいて、
「重畳に存じまする」
といって、かすかに頬笑みながら、
「実は――」
「――」
「吉報を持って――」
「ほう」
家治が脇息を抱えるように、
「まさか」
「御意」
「――本当か」
意次は真面目に、
「御微恙(びよう)御見舞として」
「いつ?」
「今日」
「――本当か」
と、もう一度。意次は叩頭して、
「間もなく、御伺候なされまする筈」
家治は眼を閉じて、暫く心を鎮めようとするように、そのまま黙っていたが、
「相良侯」
という。
「はあ」
「ふたりだけで、暫く話すことは出来まいか」
「左様に御計らい申上ぐるよう、仕りましょう」
「儂は――」
家治は眼を明けて、
「この四五日、考えていたのだが、姫を」
「は」
「姫を、江戸に置き度うない」
「と、仰せられますると」
「儂はこの通り、不治の病であるて」
「不治と申すこと」
「ま聴け」
家治は意次を制して、
「茨の莚にも等しい江戸に置いたとて、姫の身の行末に幸福があろうとは思われぬ、就ては――彼の人に頼んで」
「は」
「京へ伴って貰い、折をみて尼になと――」
意次がはっと顔をあげた。家治は静かに意次を見下しながら、
「儂も、相良侯も、世を失うこと遠い身ではなし――その後の姫のことを考うると――のう」
意次は頭を垂れた。
二
家治は軽く咳きだしたが、啖を吐き出すと共に、暫く眼を閉じて気息を調えた。
「儂も幼少からの病弱、最早五年の生命は覚束なく考える――、相良侯とても同様、儂が病に起たずと定れば、四面の楚歌一時に起って、必ず貶黜(へんちゅつ。官位を下げて、しりぞけること。 貶斥)されるであろう」
「其儀なれば」
と意次が低く答える。
「御起用を添う致しました折より疾く覚悟任ってござりまする」
家治は頷いて、
「盛衰の律は、人の力に及ばぬことだ。さればこそ今のうちに――」
「は――」
家治は少しの間、また眼を閉じて何か考えているようだったが、「彼の人はたしか、近く落飾さるるよう聞いたと思ったが――」
「私も左様に伺い居りまする」
「北家は、勧修寺であったのう」
「さ、その儀は」
家治うなずいて、
「たしかにそう覚えて居った、勧修寺とあれば、洛外――四季のながめも近く、庵をむすんで姫の、行いすます姿を偲ぶにも相応わしい。だが――姫が厭などと申したら」
「――」
意次には答えが出来なかった。
「相良侯」
「は」
「わしの口からは、さすがいたましゅうて云えぬ、彼の人が承知されたら、姫へは相良侯から話して貰えぬか」
「は!」
「初めに尼などと申したら、乙女心に、傷をつけるかも知れぬ、ただ彼の人と共に、暫く京住い――と、のう」
「は――」
意次は平伏した。
その前夜、意次は葵坂邸内の事件を知らされていた。何故か知らぬ、安芸新太郎が、奥庭の築地際で、薩摩藩からの付人――と云ってもその夜は非番に当っていたが――諏訪竜次郎を斬って立退いた。然もその上に悪いことは、築地の向うに、奥用の雪洞が落ちていたし。新太郎が斬った時、たしかに竜次郎は覆面していたのを、詰合の役人が検死した時には覆面がなくなっていたので、薩藩では――、
「安芸とか申す奴、善男という噂であったが、奥勤女とでも密会して居るところを、何かの用向きで来合せた諏訪に発見され、不意討に斬って逃げたものに違いない!」
と云い張った。そして今朝早く諏訪竜次郎の兄という、豪太郎と名乗るのが意次を訪ねて来て、
「逆縁ながら弟の仇を討ち度いから、安芸新太郎の居所を御教示願い度い――」
と厳重に談じ込んで来た。勿論――愛臣を失った重豪(しげひで)が、どんな気持でいるか察せられぬことは無い。
「姫君の身いよいよ危し!」
と思っていた意次だった。
「憚りながら」
と意次は平伏して、
「御胸中、何とも申上ようござりませぬ、唯々、おいたわしけれど、仰せのように仕るが、姫君御為にも、至極の手段かと存ぜられまする」
「うん」
家治は力無くうなずいた。
「それでは、これより――」
意次は座をすべって、
「彼の御方を、御案内申上げまする」
「このままで宜いか」
「御意」
と答えて、意次はすべり出た。
三
間もなく――。
意次は、一人の美しい上臈を導いて、家治の病間へ参入した。
上臈というはその時、年齢二十七、京の藤原一門で、北家の姫、将軍の御台所と従姉妹にあたる人である。葛の花によせて、家治の恋歌(こいか)に返しを送って来たのはこの人だ。
この時まで、家治とこの姫――媜子姫、とは一面の識もなかった。御台所の従姉妹というので、これまでに二度程大奥へ滞られたが、いつも顔を合わさずにわかれた。それがこの春、堂上の歌垣に名歌の誉を得て、北家の媜子と名が高くなってから、家治の心は、歌を通じて熱く媜子姫に傾いて行った。
「――」
家治は襖の明くと共に、眼をあげて入り来る人を見衛った。高い額と、におう眉と、朱のようにあかい唇とが先ず眼に入った。
媜子姫が座につくと、意次は低く家治にひきあわせの挨拶をして座をすべり出た。
家治も、媜子姫も、黙って暫くそのまま、互いの眼をみつめていた。
「おらくに」
と家治がいう。
「はあ」
媜子姫は眼を伏せた。
「東の冬は厳しゅうござろうに、恙なくいらせられて重畳に存ずる」
そういって、家治は暫く口を閉じていたが、
「過日は、めずらしき花を――」
と媜子姫を見て、
「何よりの賜物。嬉しくて――」
「はあ」
姫が面をあげた。
「それでも、花の美しかったは、私の手柄ではござりますまい、上様御仁政の世を寿ぐ」
「いやいや」
家治は苦笑しながら、
「姫の手ずからこそ美しく、姫の心添えこそうれしくて――」
「――」
姫はじっと家治を見た。家治もじっと姫を見衛った。ほんの一瞬、姫のひとみはあやしく光をましたが、直ぐに、眼を伏せてしまった。
「姫は」
と家治が、
「京へ戻られると、近く――仏門に入られるかに聞き及んだが」
「はあ、知恩院に入って」
「知恩院?」
「本来なれば勧修寺でありますけれど、憚ることがございまして」「ほう」
うなずきつつ、
「して、御安住はいずれに」
「洛北の真如院とほぼ、定まって居る様子に思われまするが」
家治はいたましげにうなずき、うなずいたが、
「実は――」
と低い声で、
「姫にお願いいたすことが、あるのだが」
「はあ」
「私の娘のこと」
「姫様」
「公の披露を憚って、今に日陰の身上、それに不幸なことは、将軍職を中心に、叔伯(しゅくはく)相食む事情。私に嫡子なくて、御承知の如く田安より養子を仕った。子と申せばただ今の嬢一人――、これをこのままにして置いてはと――いう単純ならぬ理由も外にござる」
「はあ」
媜子姫がうなずく、
「御台様の、御潔癖で、ありましょう?」
「御賢察じゃ」
家治はさびし気に笑った。
四
「それで――」
家治は面をあげて、
「お願い申すというは、その嬢――千代というもの、姫が京へ戻られる折、共に連れて行って頂きたいのだ」
「京へ――?」
「その上で良き時を選び、姫の御弟子としてでも、仏門へ入らせて下さらば」
「まあ――」
媜子姫は眼を大きくみはった。
「私の命数も、一年か、精々一年半であろう。いま申した如く、江戸に在るうちは、千代の存命を忌む者の眼が余りに多く、家治死すとなれば、千代の身の危きは掌を指す如く明かでござる」
「――」
「京へのぼして、尼にでもすれば、むざと害を加えもいたすまいと」
「はあ」
媜子姫は、袖をつと、眼頭へあてた。そして低く頭を下げながら、
「――おいたわしゅう、存じあげまする」
「御承引くださるまいか」
「面目に思いまする」
「忝い――お礼を申す」
「生涯に一度の、お目見得、上様にも御病身、私は間もなく出家、この世にあるうちは再び、御機嫌をお伺い申すことも出来ませぬが」
「――」
「お預かりいたしました姫様は、私が――上様とも、存じあげて、必ず」
「――」
「御行末を、御安泰に、お護り申上げます」
「――」
家治は無言で、つと片手を下ろした。が、直ぐに安堵の微笑と共に去った。
「草双紙などは、姫のお眼には触れまいが。西塔の荒法師が一生に一度の恋、娘を儲けて云々の小説がある、それと事は違えど」
「――」
媜子姫が家治の眼を見た、艶やかな姫の眼が、僅かに媚びて――家治の言葉をそのままうけた。
「武蔵野の葛の花、かりそめの恋に」
「や」
と家治。姫は続ける、
「千代姫となん申す、いみじき姫を儲けて」
「――」
「吾妻の人の俤を、京にうつす。私の明け暮れは、末ながくたのしゅうありましょう」
「姫」
家治の声はふるえていた。
襖が明いて、意次が、
「御奥より、御迎えの者にござります」
と報じた。
「――」
媜子姫は家治を見た。
「それでは」
家治は眼を閉じていう。
「これで、お別れ申そう、仰せられる如く、生涯再び、対面もなるまいが――御志あらば折々、御歌を――」
「はい」
姫は低く答えた、
「私が、これから詠みます歌は、みな――上様にお贈り申上ぐる心。そう思召して」
「添い――」
「――御健固に」
「姫にも――」
媜子姫は、もう一度家治を見上げたが。家治は矢張り眼を閉じたままだった。
一生に一度の逢瀬、男は死病の床にあって、女は仏門に入らんとする。娘をする家治の心も、預かる媜子の思いも、ともに、ともに心の臓を掻き破らるる悲痛なものだ。
意次は、面も挙げ得ず、じっとそこに平伏したきりだった。
安永一代男 中編ここから
ちまたの人
■ 一
よし田の軒行燈、もう油べりのした精のない燈に、血相の変った横っ面をぶっつけて、目貫の辰が、
「ごめんよ」
と入った。
「おや、お帰んなさい」
お園が慌てて立つ、
「どう辰さん、みつかったかい」
「だめだ」
辰はどっかり腰をかける、
「何所にも見当らねえ。業平浪人、地へもぐったか天へはしったか、影もねえ」
「気取んなさんな」
お園も煙管を置いて、
「葵坂にいらっしゃらないのは慥かかい」
「それだ!」
ぽんと膝を叩いて、
「間違えのもとは葵坂なんだ」
「何かあったのかい」
「業平浪人が、ばっさり殺ったんだ」
「誰を――」
「なんでも薩摩様の御寵臣で、それ――何とか云ったっけ、神田じゃあなし――」
辰が頭を叩いて、
「ええと、春日でもなし、よ」
「何を云ってるのさ」
「なんでも明神様みてえな名なんだ――」
「誰がさ」
「相手の待さ、焦れってえ」
「聞いてる方が余っぼど焦れったいよ」
「この明神、あ! 思出した、諏訪ってえんだ、お諏訪様、諏訪明神、ざまあみやがれ」
「見るから後をお話しよ」
「合点だ」
辰は拳でぐいと鼻をこいで、
「業平浪人がその諏訪ってえ侍を葵坂の奥で斬っちまったんだ、相手は即死、先生はその場から邸を脱けてしまいなすった、とにかく諏訪ってえ侍は剣術の名人で、薩摩様がひどくお気に入りだ相だから、早速詮議をしてみたが死人に口は無え、当の相手の業平浪人は行方不明、とにかく其奴を捉めえいってんで、町奉行なんぞへも手をまわしたらしい」
「じゃあ、一昨日おんなすった時は、そんな事のあとだったのね」「おらあ居なかったから知らねえが、多分そうだろうぜ」
「全体どうしてそんな――」
「ちらと聞いたんだが、どうも女出入りがもとらしいんだ」
「本当かい」
お園の眼が大きくなる、
「なんでも現場に、奥用の雪洞が落ちていたそうだ。下郎のとり沙汰だから嘘か本当か分らねえが、業平浪人が奥動めの女とでも逢引をしていたところを、その諏訪ってえ侍にみつけられて、うぬ――てんで殺っちまったんだろうという話だが」
「まあ――」
「どうも己らあそうは思わねえ」
「どうしてさ」
「業平浪人ともある者が、女中風情と良い仲になるなんか信用できねえ。先ずそうとしたところがよ、逢引の現場をみつけられて相手を斬る位えなら、女を連れて逃げる筈じゃあねえか」
「そうかしら」
「何かいわくがあるぜ」
辰は腕を組んだ。
「こいつにゃあ、何か余っほど入組んだ訳があるぜ姐さん。第一ねえ、あの葵坂の邸ってえのがくせものだ、己らあ二日見張をしたっきりだが、あの邸は大変なものだぜ」
「どう大変なのさ」
「おめえ――」
云いかけた時、ずいと入って来た二名の武士があった。
■ 二
入って来た武士。
「よし田と申すは此の家だな」
と云う。
「はい」
お園がちらと、辰にめくばせ。
「左様でございます」
「ちと物を訊ねるが、此の辺に業平浪人とかいう者が居る筈、いずれが住居か知りたい、教えてくれぬか」
お園が立って来て、
「はい、あのよくは存じませぬがたしかその横丁の荒屋、五軒めか六軒めに、そんな噂のお方がお住いでございました――が」
「――?」
「二三日前」
と辰に振返って、
「ねえ辰さん、たしか二三日前だったねえ」
「へえ――」
「二三日前にどうした」
別の武士が急きこんで訊く、
「夜更になってからお帰りで、それっきり何所かへ」
「行方知れずと申すか」
「はい」
武士はじろじろお園と辰の顔を見戌っていたが、やがて新太郎の住居を精しく訊ねて出て行った。
「業平浪人いよいよ危ねえぞ」
「何だろう、今の」
「一人は知らねえ、先に入って来た奴は町与力の斎藤庄吉という腕っこきだ、あとの一人は多分薩摩様の家来だろうぜ」
「ええ気が揉める、先生はいったいどうしているんだろう」
「しっ!」
辰が制した。
横丁で何か大声に罵るのが聞える。
「まさか、帰ってるんじゃあるめえな」
「ちょっと見て来ておくれな」
「合点だ」
辰はすっと出て、暗がりを横丁へ、直ぐに新太郎の家が見える。家の中からさす明りで、今の侍が二人、戸口に立って、一人が何か罵っている。
軒下を伝わって近寄る辰、
「あ、風来山人」
なる程、二人の武士に対して、上框に端座しているのは、平賀源内と弟子の東天紅。
「つべこべと」
武士の一人が叫ぶ、
「余計な世話を申すな、安芸新太郎いずれに居るかと訊くのだ、知って居たら申せ、知らねば知らぬで結構だ、強かろうと弱かろうと貴様らの知った事ではない!」
「怒るなよ」
源内はにやにやしながら、
「人間でも豚でもなあ、怒ると唾の中に毒素が生じて、五臓を害し六腑を損ねる、癇癪持の長生をした例はないぞ、怒るな、怒るな」「ええ黙れ」
怒鳴って出る、
「貴様――怪しい奴、安芸新太郎の一味だな、うぬ名乗れ」
「他人の姓名が知りたくば、己れから先に名乗るが宜い」
「薩摩の家臣諏訪」
「待て!」
と源内が制した。
「諏訪――なる程、それ丈で結構、太郎か三郎か知らぬが、竜次郎と申す者の兄弟、新太郎を仇と狙って来たのであろう」
「無論だ!」
「だが、それやあ駄目だろう」
「なに駄目?」
源内はうなずいて云う。
「新太郎はもう江戸には居らぬ」
辰が驚いた。
■ 三
「江戸におらぬ?」
諏訪というのが一歩前へ出た。
「し、してどこへ参った」
「知らぬよ」
山人はにやりとして、
「江戸におらぬことはたしかだ、わしがそう忠告して立退かせたのじゃからなあ」
「ええ知らぬ筈はあるまい」
諏訪は威丈高に、
「江戸を立退けと唆した貴公が行先を存ぜぬとて筋は通らぬぞ、申されい」
「はてくどいな」
源内は眉をひそめて、
「籠の戸を明けたからとて、飛去った鳥の行先を、知らねばならぬという道理はあるまい、ま、いってみれば業平浪人は飛去った鳥だ、西か東か、北か南か――」
「黙れ!」
と詰寄る諏訪を、
「まあ」
伴の武士が制した、辰謂うところの町与力斎藤庄吉だ。ずいと進み出ると、
「平賀先生」
といった。
「誰だ、貴公?」
「先生は御存知ではござるまいが、拙者の方では存じ申しておる者」
「気味の悪い奴だな」
「町与力、斎藤庄吉と申す、以後何分宜敷く――」
「まあ辞退しようか」
源内は冷然と、
「町与力などの近づきは有難くないよ」
「先生の方では、有難くござるまいが、拙者の方ではそう許りもいえませぬて」
「ふふ、何かその内にあるか」
「案外早く――」
「――」
源内の眼が光った。
「ところで」
庄吉は慇懃に、
「安芸新太郎と申す者の行方、御存知なればお明し下さりませぬか、先生のお言葉では稀代の剣士、三人五人の討手は物の数でないといわれる者が、逃げ隠れする必要もござりますまい」
「知らぬ、知らぬよ」
源内は語気強く、
「が――唯一つだけは教えて進ぜよう、安芸新太郎は越後の小藩某とか申す家の浪人だ、国元には縁辺の者ありと聞いたから、ことによると――」
「越後の、何と申す藩でござる」
「知らぬ、是以上は知らぬ」
「かたじけのうござった」
斉藤庄吉があっさり一揖して、諏訪の方へ振返った、
「是だけ分ればあとは何とかなりましょう、真に越後へ脱けたと定まれば、たかが二日の差、間道伝いに追いぬいて上野の白井か、先へ行っても三国峠、この二ヶ所で待受けて」
「よし、お任せ申そう」
諏訪はうなずいた。
「お邪魔を仕った、いずれ後日お礼に――」
斎藤が叩頭するのを、じろりと見た平賀源内、冷笑一番答える、「貴様、己を縛る気だな!」
「はははは」
庄吉も笑う、
「先生お作の源内節や、俗正統記がだいぶやかましい事になり相でござるからな」
源内は闊然と胸をひらいて、
「では、精々旨い酒など、呑み溜めて置くとしようか」
「御免」
斎藤は、諏訪を促して去った。
見えがくれに、二人をやり過ごした辰公、
「姐さん、大変な事になったぜ」
とよし田へとび込んだ。
■ 四
お園の顔色が変った、
「どうしたっての」
「業平浪人、江戸にゃあいねえぜ」
「え」
「風来坊めが江戸を落してやったんだそうだ、それや宜い、それや宜いがね――まあ、落着いて聞きねえよ」
「あたしゃ落着いてるよ」
「御挨拶にや及ばねえ」
辰、ぐいと食指で空をはねて、
「いまの奴ら、片っ方は町与力と教えたろう、もう一方の野郎、あいつがね、さっき話の葵坂で、業平浪人が斬った諏訪ってえ侍の兄弟で、仇と狙って乗込んで来たんだ」
「それで」
「それを――あの風来坊め、ぬけぬけと彼奴らに業平浪人の落行く先というのを教えちめえやがったんだ」
「行く先とは――」
「何でも国元が越後とかでね」
「越後の?」
「それから先や風来坊にも分らねえらしい、幾ら訊かれてもいわなかったよ、だがあの与力の野郎は、よしそんなら上州白井か、遠くとも三国峠で待伏せをかけようって相談していたぜ」
「上州白井か――三国峠」
お園は上ずった眼で空を睨んだが、
「それで」
と振返る、
「先生はその諏訪というお侍が、仇と狙っていることは御存じないんだね」
「話の様子じゃあそうらしい」
「そうかい」
お園はぐっと片膝を立てた、
「辰さん」
「おい」
「お前さんに頼みがあるんだが、きいておくれかえ」
「水臭えことをいいなさんな、己らも目貫の辰といわれる男だ、頼まれて二の足をふむようなどじじゃねえ、何なりといってくんねえ」
「有難う」
お園は手をついて、
「恩に着るよ」
「とっと、気障なことはいいっこなし、手っ取早いとこその頼みというのを訊こうじゃ、ありませんか」
「実はね、あたしと一緒に、旅へ出て貰い度いのさ」
「旅?」
辰が眼を瞠った。
「草鞋をはくのかい」
「このまま、先生の顔も見ずに、一生の別れをして了うのも辛いし――」
「あ、痛!」
「まあお聞きよ、ふたつには、今の諏訪とかいうお侍が、仇と狙って三国峠に待伏せをかけているということも、お知らせし度いし」
「分った!」
辰がぽんと膝を叩いた、
「二度と仰有るな、これから引返して行ってね、おいらあ風来坊に膝詰で、本当のところを訊いて来るから、若し越後へ落ちたこと疑いなしと定まったら、二人旅と出掛ましょう」
「行っておくれかえ」
「訊くまでもねえさ、先生に危急をお知らせ申すなら、かってえ坊とだって旅をするんだ、姐さんのような――」
「おっとあとは無駄だよ」
「しまった」
と辰が立上る、
「じゃあ、ちょっと風来坊を叩いて来るからね!」
「頼んだよ」
辰は外へ――。
■ 五
越後村松に存命の、父に今生のわかれをして、江戸にまかり帰る時は、再び昔の業平やくざ、思う存分あばれ廻って、飽酒恣色に世を送ろう! そういって安芸新太郎、道を北に上野へ出て、安積越に上田へ向ったと、平賀源内の話だ。
その夜のうちにお園は店を仕舞い、あとは店主と小女に頼んで身軽な旅仕度、目貫の辰を供にしたて、新発田(しばた)に遠縁のあるを幸い、急病見舞いとこしらえて切手を貰い、明る日早く江戸を出立、一路新太郎の後を追った、
しかし、新太郎のあとを追う者は、諏訪豪太郎と、お園、辰公の外にもうひと組あった。いうまでもあるまいが、吉川太伯と門弟三名、菊地丙午、由沢珂軒(かけん)、田原逸平という選抜の剣士だ。忍びを入れて新太郎越後落ちと探知するより、諏訪豪太郎の討つ前に討ってとれと、蒼惶これも江戸を立った。
二日――三日。
新太郎は上野へ入って、平井の宿で一夜を過ごし、明る日早く出立した。
からりと晴れた、よい小春日だ。
赤城の山は東に、青く、西には遠くこれと榛名も見える、すくすくと伸びた畑の麦に、微風が戯れて、低く空を切って飛ぶ鴉の声も旅情を慰めて豊かだった。
神流川を越した新太郎、川水の美しさに誘われて、咽喉をうるおそうと河原へ下りた、鶺鴒の影がさっとかすめると、岩間の雑魚が陽だまりから物蔭へ走るさままで透とおってみえる淀み、碧色を解いて流したような水を、手に掬って二口、三口、歯にしみる冷たさが、
「――うまい」
といって立上ると、
「憚りながら御意を得ます」
という声。
「――」
振返ると、所の役人らしいのが三人、堤の上に立っている。
「拙者でござるか」
新太郎、手を拭く。役人の頭らしいのが、堤を下りて来た、が――傍までは来ずに、七、八間先で、
「拙者は高崎藩の見廻り役でござるが。貴殿、いずれからいずれへお立越えなさるか、またいずれの御藩中にて御姓名は何んと仰せらるるか、承りたい」
「ほほう」
新太郎は微笑した、
「何ぞ、拙者に不審の廉でもござるかな」
「いや貴殿御一人に不審を申すのではござらん、江戸表よりの達しによって、ちと検め申さねばならぬ筋でござる」
「それは御苦労」
そういって新太郎は二、三歩相手の方へ歩み寄った。
「拙者は――」
「――」
「越後、三日市、柳沢藩の――」
「――」
「秋本、数馬、と申す者」
「ははあ」
見廻り役はとぼけた顔で、
「して、御出府でござるか、御帰藩でござるか――?」
「帰藩、左様――帰藩の途中でござる」
「いや、よく相分った、甚だ慮外でござるが、藩符を拝見が願いたい」
「藩符?」
「左様、旅中切手でござる」
「心得た」
新太郎も人を喰ったもので、片手をふところへ入れて、しばらく掻き探っていたが、
「はてな――」
などと小首をかしげる、
「如何めされた」
見廻り役がちらと、堤の上にいる手下の方へ眼配せをくれた。
■ 六
「姐さん」
「――」
「姐さん、姐さん」
目貫の辰が、声を殺して、暗の中を、手探りにお園の寝床の方へ這い寄った。
「ちょっ、仕様がねえ、幾ら急ぎの旅で疲れが出たからったって、十七八の娘っ子じゃああるめえし、これじゃあ寝首を掻かれたって知れねえや、もし――姐さん」
辰の手が夜着の衿に当った、とたんお園がつと身をすべらして、
「誰だい!」
「あっしです」
「辰さんかい」
「へえ」
「おふざけでないよ」
「え」
「なんだね、夜る夜中、ふざけると承知しないよ」
「しっ、しっ」
辰が、暗の中で手を振る、
「静かに、静かに」
「何が静かにさ、冗談じゃあない、お前さんも飛んだ狼だね」
「ち、違う、違うんだってば」
「白をきんなさんな」
「癪だなあ、違うんだ。もっと大切、大事、大変、大騒動なんだ」
「兎に角灯をつけておくれな」
「落着いてちゃいけねえ、ま、落着いて聞いてくんねえ」
お園がふきだして、
「どうすんのさ、落着いてちゃいけないってったり、落着けったり、お前さん夢でも見てるんじゃないかい」
「ちぇっ!」
辰公がうなった。
「そう半畳が多くっちゃ、肝心な話が出来ねえ、先へ一本槍をつけるぜ、性根を据えてお聞きなせえよ、実はね―――業平浪人に追いついたんだ」
「え! 新さん」
「とっととと先ず落着いて」
「辰さん」
「まあさ、姐さん」
「辰さん、お前さん、それや本当かい」
「さ、先があるんだ、話の先を聞いてからにしておくんなさい」
「聞くよ、聞くから早くお聞かせな」
お園は枕元の衣装を片手に掴み寄せながら、
「焦れったいねえ」
といざり出た。
辰の話はこうだ。
此所――林田の宿に草鞋をぬいで、辰公――風呂のあとで夕飯につけた酒が、三本――五本となった。
ふと眼が覚めると、ひどい渇きだ、同じ部屋だがぐっと離れて、部屋の隅と隅に床を敷いて寝ているお園、眼をさましては悪いと、足音を忍ばせて廊下へ出た。
後架を出て、水口へ来る、筧からひいてあるやつが、とっとっと景気よく迷っているのへ、いきなり口を持って行って、やけつくような喉へ、ごくりごくりと流しこんだ。歯にヒビの入りそうな冷たさ、喉も、胃袋も、きゅうっと縮みあがってゆく冷たさだ。
――酔醒めの水に値をつけやあがったね。へっ! 千両たあ、よく踏んだぜ、畜生。
つぶやきながら、部屋へ帰ろうとすると、隣の風呂場で大声に話す言葉、
――安芸新太郎。
というのがふっと耳へ入った。はっと思ったから立寄って聞くと、仕舞風呂につかっている宿の若い者の世間話だった。
「なにしろお前、仇討ちだというんだ」
一人が饒舌っている。
河原
■ 一
辰は全身を耳にして聞いた。
「下の鳴戸屋へお泊んなさったのが、なんでも江戸のお侍で、これに又何とやらいう探索衆が二人、お伴れが三人の同勢だ、そこでその今云った安芸新太郎というのがそのお侍の弟御の仇敵ちだそうで、お江戸の探索衆からのお差図、この宿へお着きになると直ぐ御藩中のお見廻りが上下二宿へ手を廻して探ったところが、平井の小花屋というのへ泊った侍がその安芸という者に相違なしと分った」「へへえ――」
と聞き手の声。
「それってんで同勢六人、急に出立して行ったのが、今の騒ぎよ」
「するともう斬り合いをやってる時分だね」
「なんでも足場の都合で先廻りをして、神流川の向う、関の松原に待伏せをかけるという話だったから、どうせ早くっても始まるのは五つか、五つ半だろう」
それだけ聞けば沢山と、転げるように駈け戻って来た辰公だ。
聞き終る時分には、もうお園はきりりと身仕度を了えていた。
「辰さん、急どう」
「合点だ!」
「あたしゃ下で、待ってるよ」
「え? 仕度は」
「草履をはくばっかりさ」
「やられたあ」
お園は下へおりて、急立の言い訳もそこそこに勘定を済ます、辰も仕度をして下りて来た。刻を訊くと七つだ。
駕籠を二挺。
「酒手は心得た、神流川まで、風のように飛んでくれ」
と辰、威勢が宜い。
話は元へ戻って、神流川の河原で、新太郎はふところを探っている。
「藩符、如何めされた」
見廻り役はそ知らぬ顔だ。
「はて不思議」
「何でござる」
「今朝、宿を立つ時には、たしかにこの懐中へ納めたものと存じたが、見当らぬというは心得がたい」
「それは怪しからん」
相手も人を喰った奴で、
「当藩内で旅中切手紛失とあっては拙者共役目としても大事、お宿はいずれでござったかな」
「左様、たしか小花屋とか申したように存ずるが」
「小花屋、ははあ」
と見廻り役はうなずいて、
「よく相分った、然らば拙者これより直ちに立戻って、小花屋を詮議仕る」
「で――拙者は」
と新太郎。
「いや、御身分御姓名お明し下さる上は、最早不審はござらぬ、御随意に」
「しかし――」
「いや、若し小花屋に藩符がござったら、使者を以てお後を追わせまする、御心配なくお立ち下さい」
「左様か、添けない」
「御免!」
と云って見廻り役は土堤の方へ戻った。
「ふふふふ」
新太郎は低く笑いながら見送ると、見廻り役はふたつに別れ、今の男は一人をつれて宿の方へ川を越え、いまひと組は元来た方へと立去った。
「なあんだ、人騒がせな」
新太郎は力ぬけのした気持で、静かに堤へあがると、橋の袂を和田の方へ歩き出した。
しかし十歩と行かぬうち、
「お――い、先生」
と呼ぶ声だった。
■ 二
足を停めて新太郎が振返ると、宙を飛ぶように走って来る二挺の駕籠、その先のやつから半身を乗出しているのが、
「や、辰――」
まさに辰公である。
「待った待った!」
新太郎の立止まったのを見ると、辰はいっそう乗出して吸鳴る、
「そこから一歩も動いちゃあいけませんぜ」
「――」
新太郎苦笑しながら立止っている。
二挺の駕籠が着いた。
「どうした辰!」
という新太郎の前へ、後の駕籠からのめり出た――
「や、そなたお園」
「逢いとうござんした」
と袂を眼へ、
「あ、いけねえ」
辰が慌てて、
「此所で愁嘆場を明けちゃ駄目だ」
新太郎が訝しげに、
「辰」
「へい」
「是はどうした訳だ」
「どうした訳だって、なにしろ貴方」
指が空をはねる、
「仕方はやめて、話だけしろ」
「兎に角その」
「あたしが話すよ、お前さんは口数ばかり多くって、肝心な用は足りやあしない」
お園は袂から顔をだして、
「この向うの松原に、先生を待伏せしている奴らがいるんです」
「拙者を待伏せ?」
「貴方を兄弟の仇とかいって、六人づれの侍が、江戸から後を追うのを知ったから、あたしも辰さんを頼んで、それをお知らせ申そうと急いで来たのです」
「何しろねえ」
辰がまた指で空をはねるのを、お園は睨みつけながら、
「宿々で先生らしい方を探し探し、昨夜の泊りが林田宿、夜更に辰さんが風呂場で若い衆の噂話を聞いて来たには」
手短に次第を語った。
「そうか!」
新太郎は頷いて、
「遠路のところよく追いついてくれた、忝い。辰にも礼をいうぞ」
「へ! 水臭えととあいいっこなしにしましょうぜ、なんしろあっしゃあね――」
「また無駄口だよ」
お園が、
「兎に角こんな街道のまん中は、見通し、どこかへ早く道を変えて、ねえ先生」
「ちぇっ」
辰は舌打をして、
「急に浮きうきした声だぜ」
「何とでもおいい、あたしゃ一生に一度と願っていたが、今日こそ先生から優しい言葉をかけて頂いた、もう本望なんだ、辰さんの毒口ぐらいじゃあ、今日のあたしゃあへこまないよ」
「おっ、是は凄えや」
「道を変えて、ねえ先生」
お園が新太郎に甘えかかった時、新太郎は橋の彼方を見やりながら左手でぐいと刀を掴んでいた。
「ど、どうなせえました」
と辰。
「来おったよ」
新太郎が答えた。
「己を仇と狙う奴らの外に、もう一組、新太郎の首を欲しがる奴らがやって来る」
「え――!」
お園は仰天して新太郎の腕へすがる。
橋の上を、吉川太伯、由沢珂軒、田原逸平、菊地丙午の四名が近づいて来た。
■ 三
「辰!」
新太郎は強く呼ぶ、
「へい」
「貴様己のこの包と、羽織を持って、向うの松林の中に隠れていろ、若し己が逃げたら、其方へついて来い!」
「先生」
お園が顕え声で、
「このまま逃げて――」
「宜しい」
新太郎は大きく頷いた。
「一度父上と今生のお別れを申そうと存じて此所まで来たが、そなたと辰の情が身にしみた、帰国は思い止まって、此処から江戸へ立戻る決心」
「おお嬉しい」
「辰と一緒に、彼方で見て居られい、直ぐに片付く」
「でも何だか気懸りな」
四人の姿は益々近づく、新太郎は袴の股立を取り、襷をかけると、
「さ、早く」
と云って草鞋の緊緒を試みた。
「辰、お園殿をつれて」
「合点です、さ、姐さん」
お園はおろおろと、辰にひかれて、堤外の松林へあがって行った。
吉川太伯は十二三間先で足を止めると、
「安芸氏!」
と声をかけた。
「問答無益」
新太郎は冷然と、
「用向は分っている、抜け!」
「待たれい」
太伯は手をあげて、
「察しの通り、拙者貴公の首を貰いに追って来た、が――云って置き度いのは、拙者は最早あの折の吉川ではない」
「――」
「あの折は紀伊家よりの御命にて、貴公に誘い討ちをかけた。併しあれ以来拙者は紀伊家からの扶持を辞した天下の浪人だ」
「早くしろ」
「あの夜木挽町の原で、吉川太伯の面目、扶持米と共に、拙者は左手を失った。此処にいる拙者は、左手もなく、姓名もない素浪人だ、お分りか」
「早く、早く」
「貴公を斬って吉川太伯の面目を取戻すか、斬られて無名の屍を晒すか、拙者の道は唯二つだ、恨みでなし、敵でなし、取られたものを取返しに来た拙者だ」
「分った」
新太郎が一歩さがる、
「借財は数えきれぬ安芸新太郎、早いが勝ちだ、取るなら取られい!」
「では頂戴するか」
「心得た」
つと横へ、堤を下ると、石塊のどろどろした足場の悪い河原、そのまん中へ、ばらばらと新太郎は走り出た。
相手は四人、うかうかしている内に諏訪の奴らもやって来るだろう、そこで却って足場の悪いが此方の利分と、河原を選んだのである。
「それ!」
と云うと吉川をはじめ、三名の門弟、堤の上で手早く身拵えをして、手に手に一刀を抜きつれ、河原へ下りて来た。
吉川太伯は二の腕から切断した左手を、固く胴へ縛りつけて、右手に例の無双の強刀を提げ、中央に立って進み寄った。
「ほほう」
新太郎も静かに一刀を抜きながら、じろり左右の三名を見やって、
「あの夜と違って、いずれもなかなかやりそうだな、こいつ面白い勝負ができそうだぞ」
水の上を低く、鶴鶴が飛んだ。
■ 四
新太郎は青眼の剣。
吉川は片手青眼、由沢、田原、菊地の三名いずれも青眼だ。
見合ったまま無言。
鶴鶴が、ま近をびびびと鳴きながら飛び去った。とたん、右端にいた由沢珂軒が、
「えいっ!」
叫んで空討ちを入れた。
「――!」
新太郎の剣は微動もせぬ。左端の田原逸平が虚をつかんで、
「やっ、えいっ!」
と是また空討ちを入れる、刹那!
「――!」
新太郎の剣が田原の面上へ伸びた。逸平は跳び退こうとしたが、足が丸い石塊を踏んで滑ったから、額を割られてだだだだと後へ倒れた。
吉川の顔面がきっと緊った。
新太郎は依然として青眼、由沢は二歩ほどさがり、菊地丙午が詰め寄っていた。
うーむ。
河原へ倒れたまま、田原逸平が立上ろうともがいている。あたりの白い石塊は、見る見るうちに赤く染みひろがって行った。
菊地丙午の青眼、籠手が少しずつ上る、と見た新太郎、
「突きか!」
と叫んだ。
「!」
先を制せられて、思わず菊地の剣尖が眼線をぬいた刹那!
「えい!」
新太郎の剣が電光のように飛んで菊地の籠手へ入った、骨を断つ刹那!
「とうっ!」
吉川太伯の片手討ち、水平のまんま、必殺必死の突きだ。
「くそっ!」
とひっ外して右へ、身を転じながら殴るように払う、届かぬ、ぱっと跳んで、逆に、新太郎は堤を背に立った。
菊地丙午は四五間退って、ぶらぶらんになった右の手首を、巻木綿できりきり巻いている。顔面に血の気を失って、両方の膝ががくがく見えるほどふるえていた。
田原逸平はもう動かなくなっていた。
「えいっ!」
由沢がつつと寄った。
「――!」
新太郎は動かぬ。由沢は直ぐに退った。
吉川太伯は右へ右へと廻る、新太郎は依然として動かない、しかし――早く勝負を決せぬと、二人の血を吸った奴に血が凝って刄鈍りがくる、それが危険だとは思っていた。
吉川の剣がゆったりと波をうった。
「や!」
新太郎はふっと眼をみはった。波をうつ剣、
「おお、あれだ」
と思った。
諏訪竜次郎、あの執念深い剣がこれだった、手元から切尖へかけて蛇のように、うねうねと波をうって来る突き。あの時、
「苦手だ」
と思った事が、はっきり今胸へ思い出されて来た。
「よいよい」
太伯が不意に叫んだ。
「そこで見物なされい、手負いに働かしたとあっては恥辱だ、休んで居られい」
右手を肩から釣った菊地丙午が、左手に刀を提げて近寄ってくるところなのだ。
「見て居るがよい」
由沢も叫んだ、が――丙午は土色をして唇を固く喰いしばりながら、幽鬼のように歩み寄って来た。
■ 五
関の松原では、諏訪豪太郎、斎藤庄吉をはじめ、薩摩の士四名がさっきからしびれを切らして待っていた。
見廻り役の男は、松原と街道とを出たり入ったりしながら、
「おかしいな、もう来る頃だが」
ぶつぶつ口の中で呟いている。河原でそれと慥かめて来てから、かれこれもう半刻になる。
「誰か行って見届けて来い」
たまりかねて豪太郎が吸鳴った。見廻りの下役は弾かれたように立上って、街道を神流川の方へ走り去った。
「ぬけ道などござるかな」
斎藤が訊く、
「いや」
見廻り役は、相手が、江戸町奉行直轄の与力と知っているから、一目も二目もおいて口を利く。
「平井から和田迄は一本道、脇へぬけるには田畝道もござるが、いずれは此街道へ出る外ござりませぬ」
「――」
斎藤は軽く頷いたのみだ。
「奴、感づいたのだ」
豪太郎は苛々と、
「それで引返したに相違ない」
「いや」
見廻り役が遮った、
「宿の入口に下役を張らしてござる、万一にも立戻った節は、直ぐに此方へ注進に参る手筈!」
「ちぇっ、田舎の平役人が、何をして居るやら!」
豪太郎は聞えよがしに罵った。
見廻り役も流石にむっとしたが、公儀与力、公儀与力と三遍唱えて忍耐した。辛いところである。
「た、大変出来にござります」
そう喚きながら、見届けに行った下役が帰って来た。
「どうした」
「逃げたか」
口々に訊く、下役はむしょうに後を指しながら、
「河原に、河原に」
「河原で何とした、何だ?」
「死んで居ります、二人、河原に二人、たしかに斬られて――」
「来い!」
豪太郎は叫ぶと、ぱっと川の方へ走りだした、見廻り役も、同藩の士四名も続いた。
河原へ来てみると、
「やっ!」
と云って豪太郎が、口惜しそうな叫び、
「やったか!」
駈け下りて倒れている一人を抱起したが、こと切れている。いま一人を検めたが、手首からのひどい失血で絶命だ。
「この中に先刻の者は居るか」
豪太郎は近寄って来た見廻り役に振返った。見廻り役は二人を見るなり、
「否、二人とも違います」
と答えた。
豪太郎は同藩の士の方へ振向いて訊く、
「上村氏は安芸新太郎を御覧なされたとか聞くが、お覚えござらんか」
「左様」
上村というのが覗きこんだが、
「夜眼のことで確かとは記憶せぬが、新太郎は聞えた善男、此両名でない事丈は断言仕る」
「有難い!」
豪太郎は立上って、
「生きてあれば結構、延びたところで一日か二日、此処まで追詰めれば袋の鼠同様だ」
そう云って高く笑った。
さっき辰公とお園の隠れていた堤の上の松林で、吉川太伯と由沢珂軒とが、薄手の手当をしているのには、誰一人気がつかなかったらしい。
ちまたの声
■ 一
芝虎ノ御門外、金刀比羅宮の納め祭。
宵宮の晩で、巴町あたりまで、町の両側には物売店が並び、空地には例によって見世物の小舎から辻講釈までが出ていた。
その空地の一番はずれに、まっ黒な人集まりがあって、さっきから頻りにやんやの喝采を博しているのは、わが風来山人の講筵だ。「そこで訊くが――」
山人は髯をしごいて、
「この中に、鎖国という言葉の意味を知っている者があるか」
「――」
「鎖国だ――無いか、なければ教えてやる、これとれ後の方の者共、もそっと静かに致せ、今までは前講釈、これから本編に入る、ちとむずかしいが辛棒して聴け、いいか」
「狸穴の鉄が控えてらあ、しっかり頼むぜ」
誰かうしろの方で声援する者があった。
「鎖国とは、国を鎖すと書く」
「ようよう」
「だ、だ、黙れ!」
東天紅があかくなって叫んだ。
「国を鎖すとは何か。それは斯様だ、元来われらの立っている地面というやつは大きな球のかたちをしているものだ、いいか、その球の表面は海と陸地とにわかれていて、陸地にはいろいろな国があり、いろいろな人間が棲んでいる」
「おっと承知だ」
また半畳が入った、が今度は誰も笑わなかった。風来山人はつづける。
「われわれの住んでいるこの日本は神州といわれる位で実に有難い国柄であるが、外にも国がない訳ではない、先ず北にはロシヤ、西には支那、西域から、遠くはイギリス、オランダ、フランスなどという国々がある」
「それからスウピイ・デリケン」
この半畳は利いて、
「わあっ」
と見物がさわいだ。源内は笑声の鎮まるのをまってつづける、
「これらの国々は、いずれも文化開けて、化学機械というものをどしどし発明し、理を究めて社会の進展に努力している」
「――」
「たとえば時計じゃ、たとえば鉄砲じゃ、たとえばギヤマン製法じゃ、船を造れば三十、五十の縦横走帆を考えて、風の力を無駄のないように利用し、千海里、万海里を越えて航海する。天に雷が鳴れば、雷神が太鼓を叩くなどと、お前がたは今でも思っているであろうが、あれは空中にある電気というものの作用でしかないと発見したのも外国人じゃ」
「――」
「そこで――こんな国々と交際をすれば、有無通じて互いに便利調法であるとは思わぬか、どうじゃ――。わしが干魚を一枚持っている、隣の奴は酒を一升持っている、と――あれば二人が集まって酒と肴を出し合い、楽しく酒盛をするのが便利ではないか」
皆ごくりと唾を呑込んだ。東天紅も、右手の掌でそっと口尻を押拭った。
「鎖国とは、この酒と肴を一緒にさせない法文だ。新しい鉄砲もいらん、万国海図もいらん、ギヤマンもいらん、電気機械もいらん、お前らは絶対に日本へ足を踏入れてはならん、これが鎖国だ!」
「――」
「それもよし、古い鉄砲、槍刀。日本だけがそれで威張っておらるればよろしいが、若し北方ロシヤ、西支那、イギリス、オランダの国々が、新しい鉄砲、新しい船、新しい機械で攻め寄せて来たら何んとする!」
その時、集まっていた群集の後がにわかにがやがやと動揺しはじめた。
■ 二
「退け、退け!」
乱暴に喚きながら、群衆を掻き分けてそれへ出て来た男三人。先に立つのが、
「おい、辻講釈!」
と源内に向って、
「ちょいとお検めの筋があるから、己と一緒にそこまで歩びな」
「何だ、貴公」
「己か、己あ神明の米造という目明しだ」
「目明し――?」
風来山人は冷笑して、
「目明しがわしに何の用だ」
「何の用かは番所へ行けあ分るとった、さあ歩びねえという事」
「貴様、儂が誰か知っているか」
「己も知っているが、もっとようく御存じのお方が、しょ曳いて来いと仰有るんだ、ぐずぐずぬかすと縄をうつぜ」
源内は黙した。
「何だその野郎は」
群衆の中から或る声が叫んだ、すると直ぐ続いて彼方から、
「負けるな風来山人」
「しっかりやれ」
「目明しなんざあ屁でふっ飛ばせ」
「狸穴の鉄が控えてるぞ」
「わあっ」
騒然となった。
「やれやれ!」
「其奴をぶち殺せ!」
そういう声がしたと思うと、目明し米造をめがけて、飛礫(つぶて)がばらばらと飛んで来た。
「やめろ! 鎮まれ!」
源内が必死に制したが、その時遅く、かねて企らんであったらしく、二三十名の手先が、群衆の中から不意に現われて、源内を取巻いた。
「愚民を煽動して上役人に危害を加える奴、召捕れ!」
「わっ」
と詰寄った。
「ま、まま待て、待て!」
東天紅が、顔をまっ級にしてそこへ出た、源内を背に庇いながら、
「せせせ先、先生は、愚民煽動など、な、な、なさりは、なな、」
「面倒だ此奴も一緒にひっ括れ」
言下に一人が、ぱっと平手打で東天紅の横面をはった。
「な、なにをする!」
嚇となった天紅書生、
「うぬ、下種役人」
というと、其奴の手を逆にとって、肩へかつぐと見るや、
「や!」
といって投げつけた。
「ぐわっ!」
異様に呻いてへたばったまま動かなくなった。それとみるより手先の面々、
「捕れ、捕れ!」
と詰寄った。
「手向うな、天紅!」
源内は目明し米造に右手を捻上げられながら、大声をあげて叫んでいた。
「も、も、も、が、我慢ならねえ、どうしても我慢が、なな、ならねえ」
天紅は怒り狂って、縦横無尽に暴れていたが、ふと見ると、平賀源内に縄がかけられようとしている。
「畜生、やるか!」
呻くと、左右の奴を投げとばして走り寄る、今にも細(ほそ)で源内を括りあげようとしている米造の顎へぐわん! と一撃。
「くたばれ」
と拳骨をくれる、あっとひるむところを、源内の腕を掴んで、ばらばらと、群れわく人波の中へおどりこんだ。
■ 三
群衆は渦潮のように混乱した。
「わあっ」
「喧嘩だあ――」
「仇討だ」
「盗賊だ」
虎ノ御門通りは、両側の物売店にせばめられて、それでなくともぎしぎしの混雑、それが右往左往に騒然とわきたった。手先は気違いのように、もみかえす人波を掻き分けながら、風来山人と東天紅を追いまわした。
天紅は縄つきの山人を、引きずるように、わざと人混みを縫って、一度金刀比羅宮の境内へ入り、門へぬけて、右へ暗がりの社務所横を逆に裏門に出る。
「裏だ裏だ」
「裏門から相模様の方へ行った」
「溜池の方だ――」
口々に叫び交わす群衆。
天紅は通りを横切って琴平町の町家の横へ入ると、小暗い家の蔭へ入って手早く山人の縄を解いた。
「お、お、おいた、お痛みは」
「大丈夫じゃ」
「危い、危いところ、ところで、ございました、が、が、ももももう」
「同じ事よ」
源内は憮然として、
「大目付松平対馬めが指図だ、鎖国反対で大分以前からめをつけられていたのだ。田沼主殿の庇護で今日まで無事だったが、対馬が急に斯う強硬になった所をみると、主殿頭もながくないとみえる――」
「ととと兎に角、此所を逃げて」
「逃げる?――逃げて何所へ行く、新銭座の店へも、最早手配がしてあるに相違ない、逃げたところで、しょせん五日か十日だ」
「と、も、申して――」
「お前行け、わしの傍にいると、お前も必ず巻添えをくう、今のうちに何所へでも逃げろ」
「いいいやです。そそそそんな」
「しっ、誰か来たぞ!」
東天紅はあわてて口を抑え、羽目板へぴったり身を寄せた。
暗がりへ入って来たのは二人。
「常さん」
という女の声だ。
「何の用かしらぬが、こんな宵の口、人眼の多い時に呼び出しをよこすなんて、お前もよっ程の苦労知らずだね、お小夜さん」
男の調子は邪険だった。
羽目板へへばり付いた内と天紅、とんだ者に袋の口を押えられて苦笑するばかりだ。
「あのころは常さんも、そんな冷たい口は利かなかったのに。男って薄情だねえ」
「こんな所で、口説をされては迷惑、もしお店へ知れでもしたら、お互い身の詰りじゃあないか、用があるならさっさとお話しょ」
「私は知れてもいいよ」
女はすねた声。
「なにも江戸屋ばかりに日が照りはしまいし、お前と一緒ならどんな苦労だって――」
「それが女の浅知恵というものだよ、どんな苦労だって厭わないと口ではいうが、苦労に負けるのはも女が先さ」
「私はそんな女じゃありません」
「そうかも知れないねえ、だがどうせ二人で暮らすなら、苦労するより安楽な方がよいじゃないか」
「――」
「なにも私だって、お前に苦労をさせて良い気なら、こんなに心配はしやあしない」
「口だけはうまいこと、このごろでは私なんか見向きもしないで、お嬢さんにばかりちやほやして、いえ知っていますよ」
「まあお聞きといったら」
「いいのよ、いいのよ、どうせ私はお多福だから、嫌われるのも尤さ」
女はくるり外向いたらしい。
■ 四
男はぐっと声をおとして、
「そんなにお前が疑うなら、大事なことだが教えてあげよう」
「また私を騙そうと思って」
「お聞きと云ったら」
男は秘密を明すように、
「実はね、いま江戸屋は大きな山を張っているんだよ、大旦那はそれで、紀州様や尾州様をはじめ、清水、一橋のお屋形様に大変な運動している最中なんだ」
「そんな事を聞いたって、私にゃあ何だか分りゃあしません」
「だから分るように話してあげようと云うのさ、宜いかい」
男は更に声をひそめる、平賀源内も、じっと耳を澄ませた。
「紀州様はじめ、今云った御連枝がたは、当将軍様や、田沼様にひどい反対でいらっしゃる、そこでね、江戸屋は紀州様御一派の後押をして、今の幕府の政治をぶち壊す陰謀を企んでいるのだよ。つい此の間も秩父の方で織元の騒動があったろう、手賀沼や印旛沼の埋立も、農夫が一揆を起して中止になった、あれはみんな江戸屋の金で企まれた事なのだ」
「まあ――」
と女は唾をのんだ、
「そんな恐ろしい事をして、いやだねえ」
男は幾分得意らしく、
「そればかりじゃない、今にもっとどえらい事が持上るんだ。もう少しすると江戸市中にも暴動を起す、うち壊しや、放火や、米の暴落を謀って、何も彼もひっくりかえすんだ」
「まあ――」
女はふるえたらしい。
「そんな事が、出来るのかねえ」
「金さえあれば、出来ぬことなんかありゃあしないよ、おまけに御連枝が承知なんだ、こんな楽な仕事はないさ」
「だけど常さん、そんな虐いことをして、どうしようと云うの」
「そうやって田沼様一派を潰して、めでたく紀州様がたに天下が廻れば、江戸屋は長崎の唐船物売買の大きな権利が握れるのさ」
「それで――?」
「そうなれば長崎に支店を造る、支配人はこの常吉と、大旦那のお考えは定まっているんだ、だから今暫くの辛棒、逢う瀬の三度や五度は我慢しても、今に長崎支配となれば、大旦那に話してお前を嫁に貰って――」
「本当かえ」
「嘘にこんな大事が話せるものかね」
「でも――長崎支配のお内儀さんなんて、あたしゃ何だか、怖いようだねえ」
「私というものが付いているじゃないか、怖いも怖くないも無い、そうなればお前も絹物づくめ、食い度い物を食べて、し度い参昧が出来るんだ」
「何だか夢のようだこと」
女が男に寄添った。
「常さん」
と熱い息だ。男はぐいと抱き寄せたらしい。
源内は、低く、
「えへん!」
と咳払いをした。突然だ!
「あれ」
女が男からとび離れる、
「誰かいるよ」
「お逃げ」
と男は、いなごのように表へ跳出した。女も続いて出たが、男とは反対の方へ、ばたばたと走り去った。
「天紅!」
「わしは、鍛冶橋へ行く」
「は」
「主殿に会って、その上で兎に角もしよう、お前は此処から、何処へでも身を隠せ」
そう云って源内は暗がりを外へ。
■ 五
源内と別れて。
東天紅は、兎も角新銭座の様子を見ようと、露地露地を抜けながら、増上寺内へ出て、門前から金杉へ切れ、引返して戸田丹後の河岸を、堀にそって新銭座へやって来た。
よし田の角、数日前から女将が旅に出て、店を休んでいるから、軒行燈もなくひっそりとしている。
ところが、よし田の角を曲ろうとするとたん、つっ――と後へ走寄った、職人体の男、
「御用だ!」
どしんと激しく体当りをくれる、
「あ!」
だだだとのめる天紅。
「神妙にしろ」
とびかかるやつ、身をひねってをとる、逆にけ 上げてくる足、天紅得たりと、
「うん!」
と叫ぶや、腰を入れて、強かにそこへ投げつけた。逃げようとすると、いつかけられたか手首の細だ。
「しまった」
と思う、虚。
「神妙にしろ」
ぐぐぐと緊めながら、はね起きて来る手先、天紅は腰にさした一本刀、小さいのの柄へ手をかけた。
「神妙にしろ、神妙にしろ」
手先は縄の張を緩めながら右へる。天紅はつつ――と走る、縄を張ろうとするが、手先も素早く間隔を縮める。手首をぬこうとすれば、ぴんと張って緊める。
「うぬ!」
天紅はぎらり抜いた。
手先は蒼白な顔を痙攣させながら、腰を落して縄さばきの際を狙っている。
「――!」
突然、天紅は逆襲に出た。
「御用だ!」
必死に叫ぶのへ、走り寄る、手先は慌てて逃げようとしたが、足を取られて、片膝をついた。刹那!
「どうだ」
天紅が斬りつける、身を躱されたから、刀は手先の着物を裂く。
「やっ」
と右へとび退こうとすると、きりきり、細は刀へ蔓草のように巻きついて来た。
「しまった」
「神妙にしろ」
ぐぐぐと引く縄、
「うん」
引かれながら、天紅は小刀の切先を、手先の胸へ擬してぱっと寄った。ずぶ! という不気味な手応え、
「わっ!」
と云って身をひいた手先、
「ち、畜生」
呻きながら、そこへ尻をおとした。天紅は刀をかえして手首の縄を切ろうとしたが、堅く緊まってなかなか切れぬ。
「だ、誰か、来てくれ」
手先は、片手で腹を押え、片手を地へ突いたまま、悩乱した声で叫んだ。
「誰か――人殺しだあ――」
漸く手首のを切って、刀にからんだものを引放して、逃げようとすると、さっきからそこらの軒下、家の陰にかくれて、怖るおそる見物していた、町の人達が、
「そいつを捉えろ」
「人殺しだ」
「泥棒だあっ」
と喚きだした。度を失った天紅が、表通へ出ようとすると、十二三人の捕手が、ばらばらと行手を塞いで立った。海へ突き当る一方口。
「だめだ」
と天紅は刀を投げ出した。
■ 六
源内は田沼邸にあった。
離れのひと間で、暫く待つ、直ぐに意次が出て来た。
「ようこそ見えられた」
意次が席に就く。
「いや余りよくは来ぬ、主殿どの」
「――」
「かねてお頼みのあった仕事、まだ残って居るなら仕ろう」
「金鉱試析の事か」
「うん」
「それは有難い、新太郎と申す者より貴公の住居を知らされたので、折あらば再び使者を立てようと存じて居ったところだ」
「わしもその前に、いま少しそれに関する蘭書を読んで置き度く思ったが、余儀ない事情で先を急がねばならなくなった」
「先を急ぐ――?」
意次が訝しげに見る。
「何処かへお立ちか」
「是だ」
源内は平手で首を叩いた。
「なに?」
「松平対馬の手が伸びて来た。僕の運もどうやら之までらしい」
「しかし、何を理由に」
「理窟はなんとでもつく、今宵虎ノ御門の金刀比羅が納めの祭礼で、わしは例の辻講釈、いつもはためて出さぬ終世論、つい時のはずみで鎖国罵倒をはじめた――」
手短に、始末を語って、
「その折、どうも書生の天紅と申す奴が、下役人を二三傷つけた様子、これだけでも対馬の手に乗る結果だ」
「貴公にも似合わぬ」
意次は暗然とし声をのむ。
「わしは心得て居ったのだ、黙って曳かれて参れば後は何か、田沼様が取捌いてくれるだろうと思ったのだが、天紅めすっかり逆上して――」
「してその男は?」
「其の場で別れて参った。と云うのが、取急いで主殿どのに申上ぐる事があったし、今日までの御恩顧に酬い度く、金鉱試析も充分にやった上で兎も角もと存じて」
意次はうなずいて、
「それは恐れ入る」
「取急いでお聞かせ申す事は――最早御存じであるかしれぬが、紀伊侯一派の策動」
「ほう」
「江戸屋八左衛門めが、其の策源となって、過日の秩父織元の暴動」
「うん」
「手賀沼、印旛沼の一揆――これらみな江戸屋の資金という事」
意次は首を傾けて、
「江戸屋――江戸屋――」
とつぶやく。
源内は、江戸屋の者の話した事を委しく語った上、まさに彼らの手が江戸市中へも伸びつつある事を付加えた。
意次は不審げに、
「江戸屋が左様な策動を致そうとは意外、しかし早速に探索させるとしよう」
「将軍家の御加減は」
「急変もあるまいが、なにしろ弱って居らるるでのう」
源内はうなずいて、
「田沼侯も最早、余り長くはないの」
「先ず二年か、二年半」
「その間に――?」
「蝦夷地の開発、ロシヤに対する北辺の開港、このふたつをものにする積りだ」
「成算がござるか」
「死命を堵してやる覚悟!」
源内は微笑しながら、大きく何度もうなずいた。
安永一代男 後編ここから
痩身
一
「先生――」
「黙っていろ」
「それだって、寒うござんすぜ」
「饒舌っても温うはならぬ」
「ならなくったって、気が紛れる丈めっけものでさあ」
新太郎は足を早めた、
「先生」
「黙って来いというに」
「行きますよ、行きますとも、だからこうやって水洟を啜りながらてくってるんで、冗談じゃねえ――行かねえ者が」
「うるさいぞ」
「で――げすかね」
辰は首をすくめた。
新銭座を出たのが八つ半(午後三時頃)を過ぎていた。真直に来て浅草寺、山の宿へぬけて一度田圃へ出てから又引返し、浅草寺の前を素通りして誓願寺の手前を右へ、さっきの田圃を北へ出て、ここで又暫く何か案じている新太郎だ。
曇り日の日暮れ近く、田圃面を来る北風の吹きっ晒しで、辰もういい加減しなびて了った。
「先生――」
「――」
「そう云っても寒うござんすぜ」
「分って居る」
「全体どこへいらっしゃるんで」
「もう来た」
「へえ――?」
「此所だ」
「此所って、この吹きっ晒しですか、こいつあ少し洒落がきつ過ぎますぜ」
「洒落じゃあない」
「に、してもさ、向うに廓をおあずけの、北風に野晒じゃあ、幾ら辰が後生楽でもこいつあ合点がならねえ図だ」
浅草寺の七つ半が鳴った。
「おお寒い」
辰が身ぶるいする。新太郎は足を止めて、道の上下を見計りながら、
「此所で――彼所で」
と何かつぶやいている。
「先生」
「うん?」
「全体、どう云う趣向です」
「今に分る」
「今に分る今に分るで、到頭ここまで誘き出されて来たが、私にゃさっぱり分らねえ」
「いまの鐘は?」
「へい七つ半で――」
「もう宜かろう――辰」
「へえ」
「貴様山の宿へ行って駕籠を一挺拾って来い」
「へえ、一挺?」
辰うんざりして、
「冗談じゃ無え、その一挺へ誰が乗るんで」
「貴様でない事だけは確かだ」
「あやまるよもう」
辰手をあげる、
「この上先生は駕籠でとばしの、私一人田圃へ置きっ去りは、なんぼ何でも殺生ですぜ」
「大丈夫だ」
「二挺でござんしょう?」
「一挺だ、早くしろ」
「だって」
「あとで分る、心配するな」
「そうでござんすかねえ」
「なる可く達者な駕籠が宜いぞ、ことによると五六里とばしするかも知れんから」
「いよいよ分らねえ」
「ぐずぐず云うな、酒手は心得たと云っているではないか」
「へえ、行って参りやす」
辰は北風に横面を叩かれながら、山の宿の方へ走って行った。
二
辰が、足達者そうな駕籠を後に帰って来た。
「御苦労!」
「へい、お待たせ申しやした」
駕籠屋が額の汗を拭く。
「済まんがの」
新太郎、紙入を取出して、小粒で一両。
「酒手だ」
「へい?」
駕籠屋が吃驚して、
「な、何で、ございますね」
「一両ばかりの酒手に尻込みをする場所柄でもあるまい、取って置け」
「へい、そりゃあ」
受取って、
「棒組、旦那だ」
「へい、御多分に――」
後棒が出て、
「で――行先は?」
「ちと遠い」
「と仰有いますと――」
「実はな」
新太郎が道の上を見やって、
「御手当筋だ」
「――?」
「浅草溜へ送られる人を助ける」
「すると」
「駕籠を破るのだ」
駕籠屋が顔を見合せた。新太郎は左手でぐいと柄際を摘んで、
「貴様らも多分御姓名位は聞いているだろう、風来山人平賀源内先生」
「へい」
「つまらぬ冤罪で小伝馬町に入って居られたが、病を得られたので今日、浅草の病牢へ送りになるのだ」
「へい」
「拙者縁あって先生に師事する者、お救い申して安全の地へかくまうつもりだ、駕籠を破ってお出し申すから、貴様ら直ぐにお乗せして、松崎の渡か橋場で船を雇い、御殿跡から綾瀬川へ入っていてくれ」
「――」
「渋江から水戸街道へ出て、あとは二里毎に一両ずつ、行けるところまで頼む」
「こ、こりゃいけねえ」
先棒が手を振った。
「駕籠脱けの手伝いなんぞした日にゃあ、二度と江戸の土ゃあ踏めなくなる、十両が五十両でも、こいつばかりはお断りだ」
「棒組の申上る通り、旦那、こいつあ御免蒙るといたしやす」
「厭か」
新太郎にやりとした、
「へい、どうも外の事と違って」
「よし、厭なら止せ」
ぐいと鯉口を切った。
「しかし、法度を犯す始末、すっかり聞かした上は、古風な文句だが生かしては返さぬぞ、死骸だけ痩宿へ送ってやる、宿をいって置け」
「ととと」
驚いて両手を前へ、
「ま、待っておくんねえ」
一人がぱっと踵をかえす、刹那、
「えい!」
ぱちんと鍔鳴り。
「だはっ!」
足が竦んでそこへ、ぺたりと坐ってしまった。新太郎にやりと笑って、
「どうだ、まだ厭か」
「や、や、やります、やります」
後棒が音をあげた、
「手当は充分にやるぞ。江戸から二三年足をぬいて、湯治場稼ぎなどをやってみるも面白いではないか、のう」
「へ、へい、左様で」
辰、傍でのほんと反っている。
三
やがて――。
浅草裏の道を、黙々とやって来る一団の人影が見えた。同心が先に立って、前後を六人の手先で固めている。駕籠には網がかかっているが、流石に平賀源内を送るだけあって、ほんの形式だけだ。
兵庫邸を立端れて右へ曲る、あとは一本道――新太郎は駕籠屋に合図をして、
「辰、ぬかるな」
「合点です」
駕籠を中に、先へ新太郎、あとに辰、そ知らぬ顔で行く。
同心がうさん臭そうに新太郎を見ながら近づいて来る、新太郎は送りの列を避けるように、道の隅へ立止った。
同心が通り過ぎようとする、とたんに新太郎が、つつ――と寄って、
「暫く!」
と声をかけた。
同心が是を止めて振返る、すわ!と前後の手先が詰寄った。新太郎小腰をかがめて、
「乗物の内は平賀先生にござりましょうな」
「貴公何だ!」
同心が腰へ手をやった、
「拙者、先生の門人にござるが、お暇乞いにこれまで推参仕った、ひと眼お会わせ下さるまいか――?」
「ならぬ」
同心が頭を振った、
「順序を踏んで願い出られい、途上の強請は罪科に問われますぞ」
「しかしひと眼だけ」
といいながら、ぐっと寄る。
「狼藉するか!」
同心が叫ぶ、
「狼藉は仕らぬ、師弟の情をお掬みあって、御一存にお縋り申すのだ」
「ならぬならぬ」
「そこを何とか」
「ならぬと云うに――、それ」
駕籠をやれという合図、新太郎が一歩さがって柄へ手をかける、刹那。
「待て!」
と駕籠の中から、
「無駄な事だ、やめやめ、安芸氏」
源内の声である。
「先生」
「時世じゃ、風来は己れの天命を知って居る、囚獄の檻をのがれたところで、天命をのがれることは出来ぬ」
「しかし――」
「もう宜い、貴公の心尽しは分った、これでわしも本望じゃ、行かれい」
新太郎は頷いた。
「さらば、仰せのままに致しましょう、何ぞ拙者で足りる事などござらば」
「何もない、が――」
山人の声が曇った。
「あ。よし田の女将お園、可哀相なやつじゃ、貴公――嫁にしてやれ」
「は!」
「嫁で厭なら情人(いろ)でも宜かろ。ではさらばじゃ、もう会えぬぞ」
「先生」
「日向守光秀の辞世の詩を聞かせてやろうか、お役人衆、乗物をおあげ下されい」
同心ははっと気付いて、
「急げ!」
と喚いた。駕籠があがると、
「新太郎、こうじゃ」
と源内が吟じ初めた。
「順逆二門無し、即身大道に徹す、五十五年の夢、醒め来って一元に帰す」
最後の句は、遠くなって、かすれて、殆ど幽界の声のように、新太郎の胸へしみ入って来た。
辰が、拳で、涙を押拭っていた。
四
「行こうか」
やがて新太郎が振返った、
「泣くな、辰」
「泣きゃあしませんやね」
辰が眼の廻りを濃くして外向いた。少し離れていた駕籠屋が、
「へい、旦那」
と声をかけた。
「駕籠屋か、まだいたのか」
「へい、どう云うことに――」
「もう用は済んだ、帰れ」
「へい、帰れは宜しゅうござんすが、頂戴の駄賃はどう云うことに――」
「山の宿あたりで稼いでいる者が、一両ばかりの端た金でへいこらするな、遣った物を取るような浅黄裏じゃあないぞ、持ってけ持ってけ」
「へへへ左様でござんすか」
ぺこりと頭を下げる傍から、
「おう棒組」
と後棒が、
「おめえ、その金を貰う気か」
「何よう」
「べらぼうめえ、駕籠へ乗せればこそ駄賃も貰うが、乞食じゃあ有るめえし、いわれの無え金を銀一文だって貰えるけえ、返しちまいねえ!」
「ははは」
新太郎が笑った、
「後棒、急に強くなったな、宜し宜し、そんなら並木あたりまで乗せて貰うぞ」
「ちえっ」
辰が――、
「多分そんなこったろうと思ったよ」
「何をぼやく」
新太郎は駕籠へ。
「ねえ、向うに見えるんですぜ、田圃のつきあたりにねえ――ちょっ、灯が入りゃあがった」
「ほいっ!」
駕籠があがった。
辰、ぶつぶつ口のうちで不平をこぽしながら、ゆっくり行く駕籠について走った。
並木で駕籠を下りると、
「辰!」
「へえ」
「冷える――」
「飲(や)りますか」
「何処かあるか」
「へ! かと仰有いましたね」
辰が先に立って、横に外れたところの、小柳という鰻屋へあがった。
「あらいところを割いて呉れ、酒だ」
酒が来る。
「先ずやれ」
「私(あっし)ですか」
酒を注いでやって、
「辰!」
「へえ」
「悪く思うなよ」
「なんで」
「田圃を越える法も、知らぬ己ではないが、のう――平賀先生を追いぬいて、妓の匂いを嗅ぐのは辛過ぎる」
「知ってます」
手を振って、
「知ってますよ先生、私だって、だから私だって心漫にも無えことを」
指で空をはねる、
「そうじゃ有りませんか、目貫の辰ですぜ、幾日女にかつえてやあしめえし、本気でねえ位のこたあ知っておいでなさると思って云ったことなんですぜ」
「飲もう」
新太郎が盃を取った、
「今夜こそ飲むぞ、江戸中の酒倉を干すまで飲むぞ」
五
新太郎は酔った。
「辰―」
「へえ」
「己は、安芸新太郎だ」
「業平浪人、正真正銘でさあ」
「己は、又やくざにかえるぞ、辰! しょせん無頼の水にしみた肌、つまらぬ煩悩に眼の眩んだのが馬鹿であったよ」
「葵坂ですかい」
「そうだ」
さっきから持変えている、盃洗の酒、くくと仰って、
「貴様、初恋ということを知って居るか」
「存じませんや」
「しあわせだなあ」
「そうで、ござんすか」
辰もずぶ六に酔っている、
「槍襖、刃の屏風に囲まれても、退いたことの無い己だが――眼を閉ずると見えるあの、夢に訪れるあの声、苦手だ」
「へえ――」
「痩せる、新太郎は痩せたぞ」
「御馳走さまで」
「何をぬかす、知りもせんで」
「へ、御挨拶ですね」
辰が、がくんと首を垂れて、
「先生」
「なんだ」
「貴方あ――ねえ、そうやって、御自分の色事に痩せると仰有る、ねえ」
「色事――? ばかを申せ」
「まあ聞いてお呉んなさい」
辰が肩をおとして、
「だが、他人の事あ、何一つお分りにゃあなっていねえ、そうでしょう」
「聞いて居る」
「あっしゃねえ、御覧の通りのすかんぴん、世間の裏道を歩くやくざの中のやくざですが、これでも血は温こうござんすぜ、一人や半分、命にかけた女もありまさあね」
「ほほう、出たな」
新太郎が盃洗を仰って、
「ま、やれ」
とさす。
「くすり店のお松とか――」
「ぶるるる」
頭を振って、
「あんななあ、と云っちゃあ済まねえ、すべただが、あいつあ血の出るような金を貢いで呉れる、気の毒な女です、私ゃ是っぽっちも惚れちゃあいねえが、はっきりそう云うのが可哀相で、つい云いなりになっている女だ。あいつあ違います」
「外にあるか」
「お聞かせ致しやしょうか」
「聞こう」
「驚いちゃあいけませんぜ――よし田の、お園さんですよ」
「はははは」
新太郎が思わず声をあげた。辰はちらとそれを窃み見たが、急に膝を崩して、
「へっへへへへ」
と卑しく笑いを含ませた。
「貴様、ひとを、騙して」
新太郎が、
「真面目に聞いて居れば。よしよし、帰ったら云いつけてやるからの」
「平に、平に」
辰公は叩頭して、
「唯今のは失言、時のはずみ、こんな冗談が分ったら、辰明日からお出入差止です、平に御勘弁」
「はははは、はははは」
新太郎は笑いながら仰反に倒れた。
笑いすぎたのであろうか、新太郎の眼尻を、温かいものが溢れ落ちて来た。
辰は知らぬ――。
六
「辰!」
「あ、危のうござんす」
「辰!」
「そ、其方へ行っちゃドブだ」
「これ、辰と申すに」
「へい」
「此所はどの辺だ」
「私にもよく知れねえが、どうやら天王閻魔の近くですぜ」
「池田滋賀の邸は近いか」
「直ぐ向うでしょう――どうなさるんで」
「来い!」
新太郎は右へ切れた。
「どうなさるんです全体」
「ひと荒やらかすんだ」
「えー?」
「滋賀の長屋は定開帳同様だ、賭場を荒してやるのさ」
「冗、冗談じゃあ有りませんぜ、先生」
辰は新太郎に縋りついて、
「池田の閻魔邸といわれるくれえ荒っぽい場ですぜ、閻魔邸ったって、天王閻魔の傍だからいうんじゃありません、おっ恐しく腕っ節の利くのが十と二十揃っていて、賭場荒しなんぞが来ようものなら、草加の煎餅じゃあねえが、ぺしゃんこに潰して天日に千そうてえところなんだ、あそこは止しましょう」
「宜いから放せよ、業平浪人ともいわれる男が、そう聞いて後へ退けるか、放せ」
「止してお呉んなせえというのに、先生」
争っていると、
「何をして居る――?」
向うから来たのが声をかけた、同心二名を連れた町与力、臨時廻りとみえて提灯を持っていない。
「へい、なに――」
辰が吃驚して、
「少々悪酔いを致しましたので」
「何だ何だ」
新太郎が寄って来た、
「何か用か――?」
「手前は町与力だが――」
「与力――ほう」
「先生!」
止めるのを振払って、
「与力が、拙者に、用でもあるというのか」
「貴公、藩士か直参か」
「天下の浪人だ」
「旧藩は」
「越後――あとは忘れた」
「御姓名は」
「安芸新太郎」
「ほう」
与力は同心の方へ振返って、
「駕籠を二挺呼んで参れ」
「は」
同心の一人が浅草橋の方へ走りだした。
「もう訊問は終りかな」
「失礼仕った、実は」
与力が微笑して、
「さる方より、貴殿をお捜し申して、お同道を願えと申しつかりました故、この両三日来市中をお尋ね仕って――」
「己を――ふふん」
新太郎は冷笑した、
「又か」
「は――?」
「又か、と申したのだ、その頼んだという奴、又薩摩のへろへろであろうと申すのだ」
「薩摩侯かいずれか知らぬが、手前が申しつかったは鍛冶橋でござるよ」
「え――?」
「誰にも内密にて、ひそかに会い度いと申されてのう」
「田沼侯――まことか」
新太郎、頭がくらくらとなった、駕籠が二挺、勢いよく向うからとんで来る。
七
どうしてそこまで運ばれて来たか、覚えていない。
兎に角、気がつくと、眼の前に意次が坐っていた。ひどく咽喉が渇いて、胸が爆けるような気持である――、
「ひやはそこにあるぞ」
「は」
見ると右手に、茶碗と水差があった。注ぐ間もどかしく、ごくごくと仰る、二杯、三杯――だ。
「気がついたか」
「意外な、無礼――平に」
「宜い宜い」
意次は労わるように、
「気分が直ったら、頼みがあるで――」
「は――何か」
「大丈夫かのう」
「最早、すっかり醒めて居ります」
意次はつくづく見て、
「そち、痩せたのう」
「――」
「案じて居ったぞ、俺ばかりではない――」
「ああ」
新太郎は遮って、
「憚りながら、御用向を――」
「――」
意次は、頓に蒼白めた新太郎の顔を、じっと見まもっていたが、
「実は、葵坂御方の御身上じゃ」
「は」
「近々に上洛なさる」
「――京へ?」
「うん、お痛わしいことに、御上洛のうえ、御出家遊ばすと定った」
「――」
きゅっと、新太郎の胸が痛んだ、何か大声に叫ぶか、思いきって泣かずにはいられないものが、むらむらとこみあげの来る。
「それについて、途中のことじゃ――、そちも知って居る通り、御台様御一派の手が、いつ御旅先の妨げとなるか知れぬ。京までの御警護を、其方に頼み度いのだ」
新太郎は、頭も胸も乱れて、狂って、何を考えることも出来ず、何を見ることも出来ぬ気持だった。
千代姫が京へ上って尼に――。
「ああ」
というと、思わず両の手が面をおおった。
「新太郎!」
「――」
「見苦しいぞ」
「はい」
「其方の心、俺はよく知っている、また、姫君の御心も、知って居る、しかし」
意次は低いが、強く、
「世には、世の掟というものがある、越すことの出来ぬ垣がある、左程のこと知らぬそちでもあるまいが!」
「――」
新太郎は両手を下した。畳の上へ、音をたてて滴るものがあった。
「御出家遊ばす御旅の、警護についてくれというは、さぞ慈悲を知らぬ老人と思うであろうが――のう其方を措いて此役を頼める者は無いし。ひとつには」
意次は暗然として、
「途中の泊り泊り、折もあらば今生の、お別れを申上ることも出来ようかと」
「は――」
新太郎は頭を垂れるばかり、
「頼まれてくれるか」
「か、かたじけのう――」
「うん」
意次は外向いた、
「可哀相な奴よ、のう――そちも」
「――」
新太郎はそこへうち伏した。
罠
一
二十日正月の日。
千代姫は意次の計いで城中へ上り、ひそかに家治と別れの対面をした。家治はやや病怠っていたので、小半日も話し過ごし、日暮れがたになってから、形見の品を取交わして下城した。
会っている時はさほどに別れの悲しさを覚えなかったが、葵坂の邸へ戻って、灯の入った居間に坐ったら、胸苦しいまでに淋しく、悲しくなって来た。
――もうこれで、父上のお顔も再び見ることは出来まい。
そう思うと、幼い時から日陰に育って、唯の一度も父らしく娘らしく話をしたことのないのが思い返されて、辛かった。
――何故今日、ひと言父上とお呼びしなかったのだろう。
とも思い、
――父上もまた、どうして千代と呼んでは下さらなかったろう、 とも思った。
――不運、不幸、こんなにも悲しい身上が外にあるだろうか。
そう思うと、泣けて泣けて、身も世もなく涙にひたっていた。
夕餉もとらずに――。
六つ半 (午後七時頃)の時計が鳴ってから間もなく、泣き疲れた千代姫が、家治から形見に貰ったみごとな香炉を、ぼんやり眺めている、襖の外で軽く咳く者があった。
「誰かいるのかえ」
「はい」
「用は無い」
「はい」
答えたが、同時に襖がすっと明いた。
「お姫さま」
と云う。佐賀である。
「佐賀ではないか」
「はい――」
佐賀は神妙に平伏している。
「何だえ」
「あの、差出がましいとお叱りを頂くかは存じませぬが」
「――」
「実は――」
と姫を見上げて、
「何だというに」
「是を、御覧下さいませ」
一封の書面だ。千代姫は前るように、書面と佐賀の顔を見比べていたが、
「文ではないか」
「はい」
「誰からじゃ」
佐賀は黙って書面をすすめた。赦されぬ僭越だ、が――何か心を惹かれて、千代姫はつと取り上げた。裏に一字、新。
「あ――」
どきんと大きく、血が胸をうった、くらくらと、眼が舞うようで手がふるえた。
「佐賀――」
「お叱りは覚悟の上、余りにおいたわしく、僭上ながらお咎めを承知で――」
「――」
姫の頬に血がさした。
「叱りはせぬ、叱って、よいものか、私は、私は――」
「有難う存じます」
佐賀が袖口を眼へ、
「礼を云うのは、私だよ」
姫の声もうるんでいた。封を切って読む。
――恐れながら、今生の望み、いま一度御かんばせを拝みたく、其の場で死ぬる覚悟にて待入候。佐賀女に御頼み呉々も――新太郎。
「おまえ」
と顔を外向けて、
「この文の者――、居るところを知っておいでか」
「はい」
佐賀はすり寄った。
二
その夜五つ半(午後九時ごろ)。
葵坂の邸の裏門から、端下女姿の女が二人、忍びやかに外へ出て行った。
「乗物では人眼につきやすうござります故、おそれながらおひろいで」
「ああよいよ」
低くささやき合うと、坂を下りて、溜池へ出る。ふたりが邸をぬけたとき、松林の中からついと人影が出たが、それから一丁余の距離で、ずっと二人をつけはじめた。
女二人は溜池を西へ、榎坂を左へ曲り、安藤坂を登りはじめた。 と――暗の中から、不意に六名の覆面の武士が現れて、女二人を取囲んだ。
「あれ――」
叫んだのは千代姫の声だ。
「何をなされます」
佐賀が千代姫を後に庇った時、背後から迫ったのが、ぐっと姫の頸へ腕をかけた。
「――!」
懐剣へやる姫の手、
「騒ぐな」
耳元で、圧えつけるようにいいながら、強く姫の肱をつかんだ。姫はつかまれたまま肱で、ぐいと相手の水落を突く。
「う!」
と思わずゆるむ頸の腕。すりぬけて、
「佐賀――」
片手に懐剣を抜くや、坂を下へ姫は懸命に走り下りた。
「やるな!」
喚くと、二、三人が、疾風のように追う、佐賀を押えていたのも放して、後を走った。佐賀は道傍に、冷笑しながら立っている。
「待て!」
「斬るぞ!」
追い抜いた一人が、振返りざま叫ぶのと、そいつが、背後から峰打ちを喰って、
「あっ」
横へとぶのと同時だった。
「何をする」
と現れた男――さっきから、二人をつけていた武士、安芸新太郎だった。思わず退る一同、千代姫はそれとは知らず、助けの人と見てそのうしろへ、
「お助け下さりませ」
とかくれた。
「御安堵なされい」
と新太郎が、相手へ剣をつけながら、
「いま一人は、どうなされた」
「坂の中途に――」
「よろしい」
うなずく。声――身体つき、姫は、はっとしたが、身も心も顛倒して、
「おまえは、新太郎」
と叫ぶ。
「や!」
新太郎も仰天、
「貴女さまは――!」
剣尖がさがる。刹那!
「斬れ……」
わめくと同時に、右の端のが、棄て身で、
「かつ!」
と突いて来た。左右をひいてかわす、
「えいっ!」
腰へ一刀。斬りつけるのと、かえして、正面にいる奴の剣をはね上げ、避けようとする右隣の足を払うのとが、殆ど一瞬だった。
腰をやられたのは、左側にある松平右近の土塀際へ倒れてうなっているし、足を斬払われたのは右側の松平大和の石垣の下に坐り込んであえいでいる、
最初に峰打ちを喰らったのと、刀をはねあげられた二人は、もう気疲れがして、二、三間さがって構えているばかり。だから、新太郎に正面からいどんでいるのはたった二人ということになる。
「さあ、来ぬか!」
と新太郎が声をかけた。
三
正面の一人が、
「えいっ!」
空打ちを入れる。刹那、もう一人が横から鋭く払って来た。新太郎は体を捻って避けると、峰をかえして、払い余った剣を叩き落す、隙! 空打ちを入れた奴が、
「とう!」
と正面へ、必死の打ちを入れようと体の伸びる、刹那、身を沈めた新太郎がさっと胴へ一刀入れた。同時に相手の剣が頭上へ来る、鍔元で止めてひっ外すと、
「が――」
横へつんのめってそれなりだ。
刀を叩き落されたのは、さっきの二人と同じく退って慄えている。
新太郎は姫へ、
「いま一人は、お腰元でござるか」
と訊く。
「召使の者」
「心得ました」
頷くと、
「姫君――私のあとについて」
云って、つつ――二三歩出た。相手三人がさがる、同時にその三人のうしろから、
びゅっ!
と何か飛んで来た。
「はっ!」
払うと、奴に当って、ち――んと鳴って落ちた白い物、銀平打の簪だ。
「あ!」
新太郎が低く叫んだ。闇時雨を冒して、新銭座の浪宅へ斬込みをかけた一党の中に、男装の女が一人、銀平打の箸を落して遁れ去ったが――いよいよまた出たぞ。
――今度こそ、遁さぬ!
思うや。突然、
「えいっ!」
つつと二三歩出る。慌てて退ろうとする三人の、左端にいるのへばっとあびせる、
「わっ」
柄で面を庇いながらそいつが身を疎めた時、中のやつは踵をかえして逃げようとする右足を膝のつけ根から斬り落されていた。
残ったのが夢中で坂を駈登る、反対に、此方へ下りて来る女がある、佐賀だ。
「おお佐賀!」
千代姫が呼ぶと、
「御無事で、御無事で――」
顧えながら走り寄ろうとする佐賀、新太郎は左足を開くと、突然佐賀の右手をつかんで捻じあげた。
「新太郎!」
と姫が驚く。とたんに、
「あっ」
苦痛の呻きをあげる佐賀の、捻じあげられた右手から、からりと懐剣が落ちた。
「新太郎、それは私の――」
「いや!」
新太郎は強く、
「此奴、諜者でござります」
「え――?」
「お邸に入込んで、御不為を計る奴、廻し者でござります」
「放して」
佐賀が苦しそうに、
「お姫さま」
「新太郎、それは何かの思違いでしょう、現に今宵もおまえの文を――」
「私の文?」
「ええ――」
「私の文とは、何の事でござります」
「あれ、おまえが」
と云った時、佐賀が、
「む――」
と呻きだした。
「どうした?」
振返ると、佐賀の口から血まみれの舌が、だらりと半分垂れていた。
四
新太郎は、
「しまった」
というと、倒れかかる佐賀を、かがんで膝の上に仰向けにした。
佐賀は、燃えるような眼で、千代姫を――新太郎を、じっと見比べていたが、やがて眼を閉じた。
「人が――」
と姫がいう。
新太郎は急いで、佐賀の懐中を掻探り、袖をかえし、一通の封書を探りあてると、膝の上から佐賀を押落して立っ、
「此方へ!」
といって姫を促して坂を右へ、西ノ久保の町家の方へと足早に去った。
新下谷の帳場で駕籠を一挺、それへ姫を乗せて、大廻りに葵坂の邸へ戻ったのは、それから半刻あまり後だった。
直に意次へ使者を立てて置いて、血で汚れた衣服を、小侍の一人に借りて更えていると、
「直に会い度いから」
と姫から招きが来た。暫く考えていたが、
「主殿頭様の来るまで」
とことわる。
控えの部屋で、さっき佐賀の懐中にあった封書を取出して改めにかかった。封の表は無名、裏に「新」と一字。封を切ってみる。
――喫急の事情にて、御会い申上る場所に支障出来、佐賀女承知に候えば、直に次の場所へ御乗與(じょうよ)の程待入候。新太郎。
とある――。
「計ったな」
と呟く新太郎。
「己を囮にして姫を誘い出し、手もなく掠う計策だ」
そう分ると同時に、新太郎は旧冬邸の奥庭で諏訪を斬った時の事を思い出した。
「あの時、己に、姫からの文を渡したのは佐賀――。前後を忘れて奥庭へ参ると、諏訪が来てあの始末。恐らく竜次郎も姫からの招きで来たに違いあるまい。諏訪を斬った後で、築山の上に置忘れてあった姫から諏訪竜次郎への文を見た己は愚かや一時の嫉妬に心眩んで、恨みと恋とに居耐らず、再び江戸の土を踏むまで――と、故郷へ向ったのだが。今こそ明らかとなった。己への文も、諏訪への文も、みんな佐賀めが企みだったのだ、みんな罠だったのだ」
新太郎は頷いた。
自分を文で呼びながら、同時に諏訪竜次郎へも文をやっている姫――。あの時は一図にそうと信じて余りのことと怨みさえしたのだが、怨みより強い恋慕をどうしようもなく、一度立退いた江戸へ、再び帰って来た新太郎である。
「如何にものを知らぬとはいえ、一人の女の悪知恵に、斯程まで弄ばれるとは己も、よくよく眼が眩んでいたに違いない」
今は解けた。
何も彼も釈然とした。今宵姫がたった一本の自分の――偽の書面を疑いもせずに、夜陰に邸をぬけ出られた、というそれ丈で、姫の気持は分り過ぎる程分った。
「もう是で本望だ」
新太郎は晴れ晴れと呟いた、
「主殿頭様、御来邸にござる」
小侍が知らせて来た。
急いで詰間へ行くと、意次は座へつくところだった。
「どうしたという――」
「は、実に危いところにて」
新太郎は手短に始終を語った。
「よかった、よかった」
意次は何度も頷いて、
「礼をいうぞ安芸、よく見張りをやっていてくれた、天運じゃ――天運じゃ」
五
意次は直に座を立って、
「儂はこれから御前へ伺うが、其方も一緒に参れ」
という
「いや、私は」
新太郎は微笑して、
「このままおいとまを頂きます」
「まあ宜い」
意次は制して、
「兎に角一度、御挨拶をして」
「は、併し――」
安芸はきっぱりと、
「私、少々決することがござりまする故、再び姫君には、お会い申上げぬ所存」
「何故だ」
「それはお訊ね下さりまするな」
新太郎は微笑して
「二度とおめにかからぬでも、最早心残りなき事がござりました」
「ほう」
意次は膝をおろした、
「先夜のわしの意見、あれが――」
「否や!」
新太郎は遮って、
「違いまする、今宵という今宵、姫君の御心がはっきりと知れました、それだけで何よりの満足、これ以上に何も望むところはござりませぬ――御賢察を」
「そうか、宜かろう」
意次は頷いて、
「実はのう、姫君の御上洛に就て、儂は今宵一案を練ったのじゃ」
「は」
「奥勤女の中にまで廻し者が入込むようでは、此上ながくこの邸の御安態は望まれぬし、薩摩侯の掩護も覚束なくなった以上、一日も早く御上洛をお計り申す外あるまいと――。そこで、のう、――松本豆州とも相談して、表向は飽くまでさだ子姫と御同列にて御発輿(ごはつよ)と拵え、姫君はそれより先に道を変えて、秘かに京へ御送り申そうと存ずるのだ」
「して、私は――」
「其方は」
と意次が声を低める、
「勿論、御台様御一派に眼をつけられている体、はじめより御警護に付いては直に感ずかれる故、江戸をぬけて途中に御待ち受け申上るか、又は道を変えて途中に落合うか、いずれこの二つの外に方法はあるまい」
新太郎は頷いて、
「して、御道筋は」
「矢張り、甲州路を信濃へぬけ、木曽から美濃へ出る順路、是であろうな」
「では――」
と新太郎が手を下した。
「うん」
意次は立つ、
「それではいずれ又、精しいことを打合せると致して」
「は」
「気付かれるといかぬ故、当分は邸の見張もやめているが宜い」
「では。姫君には、殿より」
「心得た、さらばじゃ」
意次は行こうとして、
「おう、忘れていたが」
と立止って、
「其方、平賀源内と知己であったのう」
「は、些かばかり」
「源内は昨日、死んだぞ」
「え!」
「浅草の病牢で。夕傾のことだそうな」
新太郎は暗然と眼を閉じた。
「弔ってやるがよい」
「――」
意次は去った。
寒雷
一
「まあ――」
お園がびっくりして、
「どうなさいました」
「どうだ!」
新太郎、にやにやしながら店へ入ると、熨斗目麻裃の袖をひいて、
「立派であろうが」
と云う。
「立派ですこと、まるで七三郎の判官」
「と、申す程でもあるまいがの」
「いいえ本当ですよ、矢張り先生は、何を着せても板につきますねえ」
「似合うか」
「ふるい付きたいくらい」
と云ったが、ふと不安そうに、
「でも、それは全体どういう訳なんです」
「是か」
新太郎はずいとあがって、
「ま、一本つけて貰おうか」
「先に聞かせて」
と向直る。
風呂から出たばかり、鏡に向って髪を直していたお園が、髪がさらりと落ちてくるのをうるさそうに掻き上げながら、
「ねえ」
「聞かそうか、が、まあ一盞先にしよう」
「なあぜ」
「聞いた後で飲ませぬなどと云われては困る、大事な祝儀だからのう」
「そんなに焦らさずに、ねえ」
「ははは」
新太郎はきちんと坐った膝へ手を正して、
「ではもうそうか」
「ええ」
「新太郎、仕官したのだ」
「仕官――?」
「長の浪人暮らしも飽きた故、かねて手蔓を求めて置いたのが、ばたばたと運んでのう、主家は信州高島藩、食禄は百五十石、ちと不足だが時世だ、我慢して仕官と定めたよ」
「まあ――」
「今日お目見得での」
新太郎は、お園の表情には眼もくれずに、
「御用人というに会って来たが、国詰でその場で定って、二三日内には信州へ立たねばならぬことになった」
「信州へ――お立ちになる?」
お園は気もそぞろに、
「本当に信州へ行って了うんですか」
「嘘を言ってどうなる、今時百五十石と言えば高禄だ、蝦夷であろうと、佐渡であろうと行くさ」
「でも――」
お園は、やっとのことで笑いながら、冗談なら早く冗談にする気だった。
「嘘でしょう」
「どうして――?」
「私を騙そうと思って、知ってますよ」
「知っているとは、何を」
「この間辰さんから聞きましたよ、こん度こそ本性からの業平やくざだって、現にその晩も閻魔邸へ、賭場荒しに入ろうとなすったそうじゃありませんか」
「そんな事も云ったかのう」
新太郎苦笑して、
「ひどく酔って居ったよ、あの時は――が、考えてもみるがよい、浪人も五年となると、そろそろ飽きてくるぞ。ま、よい、兎に角仕官の祝じゃ、早速一盞頼む」
「では、どうしても本当なんですね。信州へいらっしゃるのも――」
「何度申しても同じことよ」
「それは――」
と云ったが声が詰った、
「おめでとう、ござんすこと」
顔を外向けて、立った。
二
「はい、つきました」
小女の手もかりずに、独りで仕度した酒と肴、奥の間へ仕度をする。新太郎は遠慮なく盃を取って、
「では貰うぞ」
「御出世を――」
と注ぐ。
「長い世話であったのう」
「――」
「忘れぬぞ」
お園は外向いた。新太郎は盃をほして、
「受けぬか」
と出す。
「祝じゃ、一盞あけて呉れ」
「あい」
お園が盃を受けた。きりきりと糸切歯で、唇尻を噛んで、眼を伏せて――盃を持つ手がかすかにふるえる。新太郎の注いだ酒、じっとみつめていたが、眼をつむってくっとあおる。
「みごとだ」
「――」
盃を返す。
「どうした――」
「いいえ、何も」
お園は仰向いたが、我慢できずに、袂を顔へ当ててそこへ、泣き伏して了った。
新太郎は、手酌で四五杯、たて続けにあおると、暫く眼を閉じて、お園の忍び泣く音に聞入っていたが、やがて静かに、
「お園――」
と云う。
「あ、あい」
「そなたの心、よく分る――、よく分るが、それは新太郎にはどうにもならぬ事だ」
「――」
「人の世はふしぎだ。想う者は想われず、想い合う者には犯せぬ掟が邪魔をする。あしかけ四年の間、心をこめたそなたの親切、それは世に代え難く嬉しいが、――その嬉しさは恋とはならぬ」
お園はむせんだ。
「なまじ近くに居ればこそ拙者も心苦しく、そなたも余計に辛いから、しょせん一つになる折の無い心二つ、思切って離るるがましとは考えぬか」
「あ、あい――」
「いつかそなたの云った、葵坂の御方。打開けて申すが彼の人は、当上様御血統だ」
お園は驚いて涙の面をあげた、
「そなたが云う通り、新太郎一度はたしかに彼の人に――想いをかけた」
「ええ」
「だが、素浪人と、日陰ながら将軍家の御血筋だ、考えるまでもあるまい、諦めた」
「――」
「諦めたが、それと一緒に、生涯女を近づけぬ決心もした」
お園は涙を拭う。
「自慢にはならぬが、生来二十五年、曽て一度も女の肌に触れぬ新太郎、命に賭けて思い込んだ女に、男一代の操を守り通す決心、分って呉れるであろうな」
「あい」
「そなたの情も、生涯心に刻んで忘れぬぞ、新太郎は明日から有髪の道心、酒も今宵限りで断つ積りだ」
お園は膝を正して、
「よく分りました」
とふるえる声で云う、
「あたしも、元々、先生の奥様になろうの、お心を盗もうのと、そんな考えがあって御面倒をみたのではありません」
「分って居る」
「身分の違い、末のことまで、ちゃんと知ってはいたのですが――卑しい身の迷いで、どうにも諦めることが出来ず――」
声がつまる――。
三
新太郎は盃をとって、
「もうよい」
「あい」
「何を申さぬでも、そなたの気持は分っている、斯様な話は最早よしとして、さあもう一ぱいうけてくれ」
「いいえもう」
「まあよい、新太郎が最後の酒だ、この一ぱいの後で頼みがある」
「あたしに――?」
と盃をとった。飲んで返すと、ようやく眉をひらいて、
「何でしょう、お頼みって」
「辰だ――」
「辰さん――?」
うなずいて、
「怒ってはいかんぞ、怒らずに終いまで聞いてくれ」
「なんで、怒りなんか」
「頼みというのは、辰と――一緒になってくれぬか、ということだ」
「――」
「やくざではあるが、辰は性根の据わったところがある、情もある、おくべきところへおけば、人並以上に働ける奴だ」
「ええ――」
「そのうえに、のう」
新太郎は低く、
「辰は、そなたに、うちこんでいる。それも浮気根性からでなく、心の底からだ」
お園は眼をみはって、
「どうして、そんなことが――」
「隠していたのだ、可愛いい奴よ、心の中では死ぬ程こがれていながら、表に洒落をきめこんで、自分の心を見透されまいと、ひた隠しに隠していた」
お園は信じかねた色だ。
「流石に新太郎も、こればかりは気がつかなかったが、先夜酒に酔って、前後不覚となった時それが出た」
「なんて――?」
「言葉ではない、言葉などはどうにもなるが、外に隠せぬものがある、思わずもらした言葉を、あわててまぎらかしたが、ひとみは泣いていた――泣いていたぞ」
お園は俯向いた。
「拙者と違ってそなたは、生涯独り身と申す訳もいかぬ、直ぐにとはいわぬから、折をみて辰と一緒になってくれ」
「――――」
「夫婦は後の恋とか申して、いつかは情のうつるものと聞いた、信州へ去ればまたいつ会えるか知れぬ拙者、せめてそなたの身のかたまるを見て安心したい」
「――――」
「どうだ、きいてくれぬか」
「よく――考えて」
新太郎はうなずいて、
「よし、これでこの話も了いだ」
お園は吐息をして、
「先生が江戸をお立ちなすったら、新銭座もさびしくなりますねえ」
「名跡は辰に譲ろうさ」
「茶屋町でも、神明でも、泣く娘が沢山ござんしょう」
「その代りには――」
と笑って、
「信州娘を、ずんとよろこばしてのう――」
「憎いこと」
「それ笑った」
と盃を出して、
「いずれ辰と祝言をしたなら、つれだって木曽詣でになと参るがよい、若し――、若し在国なれば案内をするぞ」
「あい」
「その時分には、新太郎もすっかり国侍になって、そなた達に笑われることであろうよ、ははは」
四
「た、大変だ!」
喚いて表から、松かさの三吉が、
「先生はいねえか」
と跳込んで来た。
「何だ」
新太郎がおっ取刀で出る、
「辰が、辰が――」
「辰がどうした」
「神尾邸の角で、やられてます」
「喧嘩か」
「そうじゃあねえ、相手は浪人者らしい、何でも五六人いるんで」
「よし案内しろ」
裃の肩をはねると、
「行って来るぞ」
とお園に云って、草履をつっかけると表へ、三吉のあとから走った。
新銭座の横丁を通へ出て左へ、堀止を更に左へ曲ると、神尾主膳の下邸、その築地の蔭の所に、五六人の姿。
「あれです!」
と三吉が。
新太郎は二三十歩手前から、
「辰! ぬかるな」
と叫んだ。振返って、さっと左右へひらく浪人態の者、六人。手に手に抜いていたが、新太郎を見るとぱっと逃げだした。
あとには辰が、仰反に倒れている。はだかった脚に血を見たから、
「三吉、辰を頼むぞ」
と云うと、
「待て、うぬ」
逃げてゆくのを追った。と――辰が、むっくり半身を起して、
「いけねえ、先生!」
と叫ぶ、
「誘いだ、行っちゃあいけねえ、先生!」
「なに?」
足を止めると、
「奴らあ、先生を誘き出しに来たんだ、危ねえからやめてお呉んなさい」
「だが、この儘で」
「宜いんですったら」
辰は、三吉の肩につかまって、立とうとあせりながら、頻りに手を振った。
「私の傷なんざあ知れたもんだ。早く此処から帰って下さい」
逃げた六人は、越中邸の向う角で、此方を見ながら立っている。新太郎は、自分の身の大事であることに気付いた。
「よし、見逃した」
新太郎は立戻って、
「どこをやられた――」
「なあに、腿ったぶを、ちょいと撫でられた許りで――」
「ひどい血だぞ」
「この位、ノミが喰ったって、出まさあね」
「三吉!」
新太郎が、
「辰は己が背負って行く、先へ帰って医者を呼んで置け」
「合点です!」
三吉が走り去る。傷は高腿を三寸余斬っている。出血も相当にひどい。新太郎は辰のふところから手拭を取出して、傷の上を力任せに縛った。
「辰、確りしろ」
「だ、大丈夫ですよ」
「さ、負され」
「歩けます、歩けます」
立とうとすると、腰がすくんで、くらくらと白眼になった。
「辰! 意気地無しめ」
新太郎が叫ぶ、
「人が見ているぞ、それでも貴様江戸っ児か!」
「だ、大丈夫でさあ」
辰は細く、眼を明けた。
五
医者は傷を検めて、
「大丈夫、骨はたしかじゃ」
とうけあった。
手当をして、医者が帰るのを、三吉とお園が送って出た、隙。
「辰!」
と低い声で、
「へえ」
「お園を口説け」
「え――?」
「男は度胸だ、やってみろ」
「――」
「下地は己が拵えて置いた、これで出来なきゃ目貫と云われた名がすたるぞ」
「――」
「宜いか」
「へえ」
「そして、やくざの足を洗うんだ、二度とは云わぬから確り覚えて置けよ」
「へえ」
そこへお園が戻って来た。三吉もあとから来て、隅の方へ坐りながら、
「何しろ、いきなり六人出たんでねえ、あっと云う間もねえ」
「どうしたのさ、全体」
「どうしたも斯うしたもありゃしねえ、梅の湯へ行こうと思って堀止のところまで来ると、挨拶なしに取巻かれて、業平浪人の身内だ、殺っちまえっ! てえ始末さ」
「――」
辰が、指をあげて、
「その中に、居たんですよ」
「居たとは?」
「関宿の泊で、先生を探していた奴、あの斎藤てえ与力と一緒の侍です」
「ほう」
「三公が駈戻ってくと、そいつ――あっしが斬られて気を失ってるとでも思ったか、きっと来るから向うの用意をして置け、って傍らのに云いつけていやあがる、こいつあ誘き出しだなと思ったから――」
「そうか!」
頷いて、
「卑怯な奴らめ、だが辰、いまにきっと仇はとってやるぞ、気をくさらせるな」
「そんな事あ大丈夫でさあ」
と笑ってみせたが、
「だが、先生――、その装束は、どうした訳ですね」
「是か、ははは」
大きく笑って、
「拙者はな、今日から百五十石の主持になったのだ、偉かろう」
「百五十石――?」
「千石出しても、当今なかなか、安芸新太郎ほどの男はあるまい。が――伯楽無ければ名馬も空しで、まあ百五十石と落着いたところよ」
「つまらねえ」
辰が不服そうに、
「業平浪人が、主取をするなんざあ、もう世も末ですね」
「不服か」
「似合いませんよ、そんな熨斗目なんぞ、業平浪人は矢張着流しで、ずぶろくで、喧嘩をやらなくっちゃあねえ」
「その喧嘩を、いま貴様とめたではないか」
「へっ!」
辰は唇を歪めて、
「熨斗目の喧嘩なんざあ有難くねえ」
「大きく出たな」
「それで――」
と辰は向うを向いたなり、
「何所へいらっしゃるんで――」
「信濃だ」
「いつ帰っていらっしゃいます」
「もう帰らぬ積だ」
辰はそれなり黙って了った。
狙う人達
一
吉川太伯は草鞋の緒をしめさせながら、
「で――」
と振返った。
林壮三郎、栗本要助、北村勇造、いずれもせっせと旅装をととのえながら、聞いている。
「安芸の剣は、空打ちのかえしを、 必ず入れて来る、得意は払いだ、胴か、足、必ず一度は払って来る、是を見分けるのが第一」
「それから――」
式台の上に、隻脚をなげ出して由沢珂軒が云った。
「右へ来る剣が鋭い、打ちを入れると直に右を狙う。三面した時に左へ入れる打ちは、どんなに気合が籠っていても空打ちだ、必ず変化して右を狙う、是を見分けねばならぬ」
三人は頷いて、いちいち記憶するように、眼を宙へやった。
仕度が出来た。
「由沢、後を頼むぞ」
太伯が草鞋を踏み試みながら、珂軒に振返って云った。
「御武運を祈りまする、私も両足満足なれば、是非いま一度安芸と立合ってみたいのですが、この身体では――」
「なに、今度こそは仕止めて帰る」
太伯は脇腹へそっと手をやった、旧冬、足立郡本木で、新太郎に斬られた傷が、まだ直りきっていないのだ。
「では行って参る」
「一日も早く、御帰邸を――」
太伯を先に、三名の者は道場を出た。
新太郎が信州高島藩に仕官して、唯一人甲州路を西行すると探知するより、太伯は三度、これを途中に斬らんとして立った。
今度は陣容を改めて、投げ突きの達者林壮三郎。離想流の槍を使う北村勇造。それに神谷源心道場で麒麟と呼ばれた栗本要助、これこそ最後の攻手、必殺の陣だ。
新宿で甲州路へ入って、府中へ着いたのが日暮れがた、ここに新太郎を跟けて先行した門弟、横川順介が待っていて、
「安芸新太郎たしかに府中を通過、恐らく今宵は八王子あたりの泊り」
と報告した。
「急げば半日で追いつける」
頷いた太伯、その日は府中で宿をとった。ところが、その夜――宿の廊下で意外な人物に出会ったのである。曾て足立郡本木で、新太郎を中に先を争った相手、町与力斎藤庄吉その人である。
「や、これは――」
斎藤が先に声をかけた。悪い奴にみつかった、勿論これも新太郎を追うのであろう、と思ったが、声をかけられて知らぬ顔も出来ぬ、しかたなしに足を止めて、
「これは珍しい」
という。
「その節は、いろいろと」
「いや手前こそ」
「なにしろ、あの折は、あの始末で」
「左様、兎に角、のう」
話のばつがどうも合わぬ、二人とも余り自慢にならぬ図を見られている。暫く気まずいやりとりをしていたが、
「ときに――」
と斎藤庄吉が、
「その節のお詫かたがた、一盞献じ度いと存ずるが、手前部屋へおいで下さらぬか」
「忝のうござるが――」
「お手間はとらせぬ、ほんの一盞だけ――」
「併し、明朝は早立ち故」
「それに就ても、御相談申し度い、お引合せ仕る者も居るし、是非」
それに就ての御相談と云えば、要するに新太郎に関した事に違いない、太伯はちょっと考えたが決心して、
「ではお邪魔致そう」
と答えた。
二
斎藤庄吉の部屋には、四人の武士と、武家育ちらしい、十七八のきりりとした顔立の娘とがいた。
薩藩の士、大村三九馬、原弥太七、塩見平兵衛、日野左門。娘は弓江といって、これは諏訪兄弟肉身の妹であった。弓江は勿論兄二人の仇を討つため、四人は介添、助太刀としての付人、斎藤庄吉は所の役人に便宜を得るためと、新太郎を見知る案内役である。
入って来た太伯を見ると、
「おお、吉川先生」
と悦ばしげに、日野左門が声をあげた。この男曽て太伯の道場へ半年ばかり通ったことがある、口達者で技が下手くそで、みんなが構いつけなかったら、間もなく来なくなった、甚だ心許ない男である。
太伯は軽く目礼しただけで、すすめられる席へ就いた。
「日野氏は御存じか」
斎藤が訊くと、左門はしたり顔に一座を見廻して、
「麹町の吉川太伯先生です」
と披露した。
八荒不破の太伯といえば、顔を知らぬまでも剣では相当に聞えた名だ。一座はにわかに活気を呈して来た。
簡単に名乗り合っていると酒が来た。
「先ず――」
と太伯に盃をさす。
酒が二三周すると、斎藤庄吉が改めて一同を見やりながら口を切った、
「さて、各々に申上るが、吉川先生も、実はわれらと同じく安芸新太郎を討とうとして居られるのだ」
「ははあ」
左門がうなずく、
「われわれは、弓江殿の仇討に介添をするため、斯うして出て来たのでござるが、前以て申上げた通り、安芸と申す奴なかなか剣をよく使う故、万一にも再び取逃すようなことに相成った場合は、面目を失う道理でござる」
「如何にも」
また左門だ。
弓江はじっと膝をみつめている。
「そこで、失礼ながら、吉川先生に後見役をお願い申したいと思うが」
「結構でござるな」
左門が言下に賛成した。
「御異存はござるまいか――」
「異存があります」
腕組をしていた原弥太七が答えた。斎藤庄吉は眉をひそめて、
「御異存とは――?」
「左様」
弥太七は濃い眉をぴくぴく神経質にふるわせながら、ぶっきら棒な口調で、
「われらは藩侯の仰せにより、弓江殿の介添として参ったのでござる。介添四名が全部斬死をした後なら知らず、まだ当の敵と一太刀も合せぬ先から、知己でもなき方に後見をお願い申すなどとは、薩藩の武士として承服できかねまする、いずれも如何?」
と振返る、
「勿論だ」
「いうまでもない」
大村も、塩見も、昂然と答えた。
太伯は微笑しながら見ていた。弥太七という奴、肚のありそうなことをいうが、弓江に野心たっぷりらしい。他人の手をからず、みごとに助太刀して、娘の気に入ろうという考えだ。他の三人とも、いずれは同じ胸算用。
――みんな斬られる。
そう思うと、不憫というより滑稽で、太伯は危く笑い出しそうになった。
「そうだ、それはそうだ」
思出したように、左門が大きく叫んだ。
三
明る朝、太伯らが起出た時、既に薩藩の一行は出立したあとだった。
「どうせ討てる気遣いはなし、まあ先にやるもよかろう」
そういって、ゆっくり朝食をすませた後、宿を出た。
杉屋の宿で先行の横川と会う。
「新太郎、昨日八王子泊りに相違なし」
という報告だ。
八王子へ着いたのが七つ。その夜はそこに宿を取ったが、ここでまた薩藩の連中と同宿になった。
斎藤庄吉はその夜、夕食のあとで一同を前にして、もう一度昨夜の話を持出していた。
「各々は安芸の腕を御存じない故、昨夜のように仰せらるるが、吉川太伯の片腕――左手の無いのを何と思われる」
「そういえば」
左門がしゃしゃり出て、
「拙者が入門しておった頃、たしかに両腕揃って居られた筈」
「その腕を――?」
三九馬が、何を云うか――と、いい度げに訊きかえした。
「あれは安芸の為に斬られたのでござるぞ」
「ほう」
「それ許りではない、豪太郎殿不運となられた折も、たしか脾腹を斬られている筈、血まみれになって倒れて居るを拙者たしかに見ました」
「そういえば」
左門が、
「少々体つきが妙だ」
「諏訪氏御兄弟は、各々を前にして失礼だが、薩藩でも五本の指に折らるる武芸者と承わって居る、その御兄弟ですら――」
「だが――」
原弥太七が皮肉な調子で、
「当の相手に、腕をもがれ、脾腹を割られたような仁を、わざわざ後見に頼んでみたところで致し方あるまいが」
庄吉ははたと詰った、自分が掘った穴へ足を踏込んだのである。
「それはそうだ」
左門が頷いた。斎藤庄吉も諦めて、再びその話は持出さなかった。
弓江は黙々として語らない。
弓江には、四人の介添の気持が分っていたのだ。話す声、見る眼、誰も彼も自分をわが物にしようと焦っている。最初に仇討の許しが出た時、介添はきっぱり断ったのだが、重豪(しげひで)が娘故に案じてか、
――助太刀ではない介添だ、是非同道せよ。
といってきかなかったのだ。
どうせ討つなら一人と一人、討取ることが出来ても、返り討ちになっても、助太刀があったのでは世間の聞えが恥かしい。
「いつかはこの人達から逃れて」
それが弓江の本心だった。
明る朝――。まだみんな寝ている暗いうちに、宿の女中が一封の書面を持って、
「ちょっとお起き下さいませ!」
とやって来た。
「何だ」
斎藤が寝呆け眼で身を起す前へ書面を差出した女中が、
「お隣のお部屋へ、唯今お火を入れに参じますと、お連れのお嬢様のお姿が見えず、こんな手紙が――」
「手紙?」
弥太七がむっくり起上って、
「見せろ」
とひったくったが、封を切って読むうちにさっと顔色が変った。
「おい皆、弓江殿が――」
「どうした、何事だ」
「江戸へ戻ると、書置だ」
四人は唖然とした。
四
「どれ見せろ」
塩見平兵衛が手紙を取って読む、
――少々思案がございます故、慮外ながら私一人、一度江戸へ立戻らせて頂きます、皆々様御帰邸を待って万縷(ばんる)。弓江。
とある。
「う――む、合点がゆかぬ」
左門がうろうろして、
「これ女中、弓江殿はいつごろ立たれたのだ」
「さあ、誰もお見かけ申しませぬので」
「見かけなかった?」
三九馬が、
「荷物なども無いか」
「はい、綺麗に片付いて居ります、街道の馬子か籠屋にでも、訊いたら、何か分るかも知れませんが――」
「では急いでそうしてくれ」
女中が去ると、皆慌てて衣服を着換え、洗面にも立たず座を寄せた。
「何か消息があっての上だが、若し本当に江戸へ戻られたとしたらどうする」
三九馬が皆の顔を見た、
「江戸へ帰る外あるまい」
左門がいう、言下に、
「ばかな」
弥太七が強く、
「われらの役は、表向は弓江殿の介添だが、殿は、必ず安芸新太郎を討って戻れと仰せられた筈だ、このまま江戸へ帰れるものか」
「しかし、仇討をする当の弓江殿を措いて、われら丈で討取ることもどうかと思われるが」
平兵衛がいう。
「兎に角弓江殿の行先をたしかめてからのことにする外はあるまい」
斎藤庄吉の言葉に、皆は賛成して、兎も角手分けをして弓江の行衛を探ることになった。
薩藩の一行がそんなことでごたごたしている内、吉川太伯達は宿を出て西行を続けた、阿佐川を過ぎて山路に入る、本郷で茶をつかって、与瀬へかかると、先行していた順介が戻って来るのに出会った。
「新太郎の姿が見えぬ――」
というのである。
「どうしたということだ」
太伯がなじるように訊く。
八王子を立って西へ向ったことは確実だが、阿佐川の宿で踪跡(そうせき)を消した、本郷、田川、与瀬と急行してみたが、新太郎の通過した形跡が無い、驚いてなおも精細に探査しながら逆行して来たのだが、阿佐川以西に新太郎の通過した様子が無いというのである。
「感付いたな」
太伯は舌打をしたが、
「しかし、いずれは高島藩へ行くに違いないのだ、若し本街道を避けたとすれば、裏街道を武州御嶽へぬけ、多摩の上流を遡行(そこう)して甲斐へ入るに相違ない、と――すれば」
しばらく案じた後。
「よし、では二手にわかれよう、一手は今申した順路を行け、一手は本街道をこのまま進む、落合う先は甲斐勝沼だ」
そういって、太伯と林壮三郎の二人は本街道を、栗本要助、北村勇造、横川順介の三人は裏道を行くことに決定した。
「若し新太郎を発見しても、勝沼まではそのまま跟けること、討取る場所は勝沼で合体した時に太伯が定めること」
打合せをして一行は二手にわかれた。
この相談を、街道の上から見ていた者がある、我が安芸新太郎だ。
「ははは」
太伯達が左右にわかれて、街道の上と下へ見えなくなると、新太郎は青空に向って大きな笑いをなげかけた。そして暫く休んだ後に街道へ下りて来ると、阿佐川の方へと逆行した。
早春
一
千代姫の発輿は二月五日。同八日夕刻八王子本陣木曽屋着。
それが新太郎の受取った通告だ。
京までの警護、それは無論蔭の役で、千代姫は京松園寺家の姫、帰洛の途中木曽へ参詣という触込みである。供は老女一、女房三、青侍二、という至って目立たぬ人数、併しこの青侍二人は相当に心得のある者を化けさしたこと無論である。
八日といえばまだ五日の間があった。
信濃高島藩へ仕官と偽わったのは、江戸を立つことを疑われぬ為と、再び江戸へ帰らぬ決心との二つから来たことだ。
「姫在すところで、例え塩を嘗めてでも一生を過ごし度い」
それが新太郎の気持だった。
江戸を立った時は勿論、さっき与瀬の街道上から太伯一党をみつける迄、新太郎は自分を狙う追手のあることを知らなかった。
「太伯が来ているようでは、御台様一派の手も伸びているか知れぬぞ」
そう思ったから、街道を戻って裏へ外れ、青梅道へと向った。
そこで二三日ひそむ積りである。
梅の咲く村をふたつみつ通り過ぎて、道は権現山というのへかかった。南向きの畑には菜種が黄の花をつけていた。椿の濃い葉がくれや、芽の色づきはじめた灌木の林の中では、鶯も鳴いていた。
「長閑だなあ。斯うした静かな自然の中に、濁りきった世を捨てて、何の悩みもなく一生を終る人達もある」
久し振りに故郷のことなどを想いながら、権現堂の下まで来ると、道の傍に武家の娘らしい女が一人、石に腰かけて頻りに足を揉んでいた。
娘は新太郎を見ると、ちょっと躊躇っていたが、通り過ぎようとした時、
「あのう、卒爾ながら――」
と声をかけた。
「は」
新太郎が足を止めて振返ると、
「甲州街道へは、どう参りましたら宜しゅうございましょう」
と訊く。
「それは此の道を真直に行けば宜しい」
「はあ、そうでございますか――」
きっとした様子だが、どこかひどく頼り無げで、息疲れが眼に見える。
「失礼だがお一人の旅でござるか」
「はい――」
「遠方へ――?」
「はい、あのう――」
何と答えて宜いか迷っている様子だ、何か事情があるらしい、まだ頻りに足を揉んでいるから、ふっと見ると白い足袋の爪先に血が滲んでいる。
「足をどうかなされたか」
「はあ」
娘は不安げに、ちらと新太郎の顔を見上げたが、新太郎の澄んだ眸子に出会うとぽっと頬を染めて、
「実は、この先で悪者に追われまして、逃げるのに道を失い、此の様に爪を――」
「生爪を剥がされたな」
「はあ、足袋を脱いで手当を致そうにも、道も知れぬ山の中故、心許なくて」
新太郎は頷いて、
「失礼ながら、拙者がお手当をして進ぜよう、幸い傷薬を用意して居ります」
とかがむ。娘は羞いながら、
「否え、それでは余り」
「遠慮は御無用、血が固まっては悪うござる、さあ――」
と手を添えた。
娘は耳まで染めながら、結付草履の紐を解きはじめた。二人の頭の直ぐ上で、ふいに鶯が囀りはじめた。
二
手当を終って立上ると、
「いろいろと、御迷惑をかけまして」
と娘は礼を云う。
「痛みは間もなく止りましょう」
新太郎は巻木綿や瘡薬(きずぐすり)を納いながら、改めて、
「無礼とお咎め下さるな。何か由ありげな旅のように存ぜられるが、お困りの事どもあったらお話しなされぬか?」
「はい」
娘はちらと新太郎を見て、
「実は――」
云いかけたが、
「失礼ではござりますが、貴方様はお江戸でござりますか」
「江戸でもあり――でも無し。唯今は浪々の身上でござる」
「これから何方(いずかた)へおいで遊ばします」
「青梅へ参って二三日滞在する心組でござるが――それが何か」
「はあ、実は私」
娘は思い切った様子で、
「兄の仇を討ちに出たのでござります」
「ほう――仇討ち」
新太郎は何の気もつかず、
「して相手はどのような」
「越後の浪人で、安芸新太郎と申す者」
「――」
新太郎ぎくっとした。
「薩摩の藩士、諏訪豪太郎、竜次郎と申しますのが私の二人の兄、その二人が新太郎のために討たれましたので――」
「して――」
新太郎は低く、
「其許御一人、仇討ちに向われるのでござるか」
「はい、殿の思召しで四人の介添が居りましたけれど、私としては唯一人討ち度く、今朝早朝八王子の宿にて、四人の介添の者を置いて脱け出たのでござります」
「みごとお討ちなさる御覚悟か」
「はい――」
「名は何と申される」
「弓江と申します」
「弓江殿美しい響よのう」
新太郎はふと上を見上げた。梢を渡る鶯が鳴く。
暫く鶯の音に聞き惚れていたが、やがて新太郎は娘の方へ振返った。
「弓江殿」
「はい」
「その仇討ちは、かないませんぞ」
「え?――」
「其許の兄上二人、斬った新太郎にも斬る丈の理由があったのだ、討たれるべき仇なれば討たれもしようが、理非を論ぜぬ仇討ちには承服が出来難い!」
「あ、貴方様は?」
娘は眼を瞠った、
「其許の尋ねらるる、安芸新太郎でござる」
「――!」
弓江はあっ! と叫んだ。
「江戸へお戻りなされい」
「――」
「そうなされい。のう」
弓江はそこへ、放心したように腰をおとした。
「豪太郎殿は兎も角、竜殿を斬ったはほんの行掛り、それも竜殿から仕掛けて来た勝負、闇の中とて誰とも知らず、斬ってから気づいて竜殿と分った、種々と申せばはっきり理由も知れるが、死者への礼、それは申さぬ、ただ新太郎においては些かもやましきところ無く、したがって仇と呼ばるる覚えもござらぬ。――これだけ申しても拙者を討つと仰せあらば好きになされい、お相手はいつにても仕る」
新太郎は会釈をした。
「さらば――」
三
八日の夕刻、千代姫は八王子へ着いた。
新太郎はかげながら到着を知ると、新しくとった宿の二階から、御台様一派の追手が有るか無いかと見張っていた。勿論それまでも絶えず街道の往来に注意していたが、遂にそれらしいものを見なかったのだ。
「大丈夫だ」
九つ(午後十二時頃)まで見張ってから、そううなずいて寝に就く。
翌日五つ(午前九時頃)の出発、新太郎は編笠を冠って、行列のあとから一丁余も後れて八王子を立った。
その日は原で泊る。
一度宿に入ってから、着流しで外へ出た新太郎、編笠を冠り釣の道具を借りて、宿の下へ出かけて行った。勿論追手の有無を見張るためである。
宿の下五六丁離れて、相模川へ落ちる小さな流れがある。さっきそこに一人、釣糸を垂れているのを見ての思いつきだ。街道はまる見えだし、見張りにはもってこいである。
餌もなにもつけない、糸を垂れて待つこと一刻あまり、高原であるがさすがに暮れて来た。それらしい者も見えぬから、糸を巻いてそろそろ引揚げようとした時、街道をやって来る四五人連れの侍、先頭にいるのをひと眼見るなり、
「おやおや」
と新太郎がつぶやいた。
斎藤庄吉である、続く四名は例の大村、原、塩見、日野らだ。
「又殖えたぞ」
疑うまでもなく、弓江の介添として来た連中に違いない。
「まてよ、吉川太伯らが先に待っている、またここで此奴らを遣っては、御旅先の警護が面倒になるぞ」
彼らの後を見たが娘の姿はない、
「よし、片をつけてやろう」
うなずいた新太郎、釣竿を持って、つかつかと街道へ出ていった。
斎藤庄吉を先に、道を急いで来る五名。
八王子の宿で弓江にぬけられてから、一度江戸まで引返したが、果して弓江は帰っていない。そこで、弓江が居らずとも朋友の仇として、新太郎を討ってよろしという許可を得た。それ! というので昼夜兼行、ここまでやって来たのである
「や!」
斎藤庄吉は、どやしつけられたようにそこへ立停った。
「どうなさった」
続く三九馬が声をかける。
「き、来た」
「え?」
「あれが、安芸新太郎」
いずれもぎくっとして立停る。向うから、新太郎がにやにやしながら近づいて来た。
「彼奴か!」
原弥太七が前へ進み出る
「よう――」
二三間まで近づくと、新太郎は編笠の前をあげて、
「貴公ら、安芸新太郎を捜しておいでではないか?」
という。
「如何にも!」
原が、もう蒼白になった顔で、睨みつけながら答える。
「矢張りそうか。で――? 矢張り諏訪兄弟の遺恨を晴らしにやって来たのだろうな」
「も、勿論だ!」
日野左門は、うしろを振返った、誰か頼りになりそうな人物は来ないものかと、無意識にそう思ったからだ。
「拙者がその新太郎、証人はそこに居る斎藤どのが御存じの筈、のう――」
新太郎はにやりとする。
四
斎藤庄吉は頷いた。紀州侯の仰付けでこんな役廻りを引受けたが、こいつはどうも苦手なのだ――。
新太郎は静かに、
「御覧の通りじゃ、斎藤どのは新太郎に相違ないと申される。そこで」
と皆を見廻して、
「勝負は直ちに始めるかな」
「抜け!」
原弥太七が痙攣るように喚く、
「朋友の仇だ、勝負しろ!」
「貴公一人、大層元気だのう、宜しい、やろう、併し此処では場所が悪い、向うに草原があるが、彼処(あそこ)ではどうだ」
「逃げるか!」
「逃げはせぬよ。まあそう苛立たずに聞け、真剣勝負というやつはのう、先ず胆を据えるが第一、焦ると必ず負をとるから、丹田に力を入れて――」
「雑言無用、早くせい!」
これも弥太七だ。
新太郎は先に立って、街道をそれる、山手へ一丁ばかり、小高くなった草原へやって来た。
新太郎は編笠を脱り、釣道具を置くと、羽織をぬぎ襷をかけ、裾を強く端折った。どんな相手にも用意を怠らぬのが、新太郎の心得である。
四名の者も手早く仕度にかかったが、日野左門だけはいつまでも襷がかからなかったり、袴の紐を結び直したり、ぐずぐずと暇取っている。
――なにも己を待っていなくとも、早く始めて早く片をつけたらよさそうなものだ。
胸の中で思っている。
「仕度が宜かったら、始めよう」
「――」
大村三九馬が先ず抜いた。
原も塩見も抜いたが、これは七八歩さがって構えていた。
「一人一人か」
新太郎が微笑して、
「拙者は構わぬから、皆一緒に掛ったらどうだ――?」
「ばかを」
三九馬が冷ややかに、
「薩摩の武士は作法くらい心得て居るぞ!」
「ほう、偉いな」
新太郎は抜いて、右手に柄を持つと、真直に刃を立てて、ぐっと右足を前に出した。
「来い!」
「えいっ!」
三九馬は上手青眼に構えた。
山国は晩く明けて、早く暮れる。だが、日没のあとの黄昏がながい、山の上に垂れている雲を染めた夕日が、さっとこの草原を明るくした。
重畳した山壁や、雲からの反射光線だから、その明るさは妙に白々したもので、殊にその光の中では影がうつらぬ。ふしぎな――一種鬼気のある時刻だ。
「やっ!」
三九馬が喚く。とたんに新太郎の剣光がきらりと三九馬の面上へ直線を描いた、
「はっ」
躱す刹那
「――!」
かえした新太郎の剣が高腿を断った。
「あ――」
叫んだのは日野左門。同時に三九馬は、だだだ、と横へ倒れた。
「斎藤どの――」
新太郎が声をかける、
「手負いの介抱は貴殿の役だぞ」
と云ってから、
「次!」
と大きく叫んだ。
五
塩見平兵衛が出た。ひどく長い――二尺八九寸もあろうという刀を持っている。
「貴公はどこを斬ろう」
新太郎がいった。
平兵衛は無精髭の伸びかかった頬を、ぴくぴくとふるわせながら、青眼正しく取って進んだ。
「貴公、諏訪兄弟とは親しかったのか」
「――」
「気の毒にのう、邸勤めをすればこそ、したくもない真剣勝負。いずれもお若い人達だ、片輪になるも本意であるまい、――それでは腕を少々、痛めるとしようか」
「やっ……」
「胴があいたぞ…」
平兵衛の剣尖がぴりりとふるえる、
「――と!」
ばっと新太郎の右足が地をはねた、面へくる! と感じたから籠手があがる、きらりと新太郎の剣が逆にとんで、平兵衛の右の二の腕を峰打にとった。
「う!」
ぽろりと剣を落して、苦痛を耐えながら平兵衛はさがる。
「峰打ちの痕は三年病むというが、加減して置いたから半年もすれば竹刀位は持てるようになろうぞ」
原弥太七が、
「日野、出ろ!」
といった。
「い、いや、拙者は!」
左門、眼を剥いて尻込する、
「なに、何のために討手に加わったのだ、出ろ、勝負をするんだ」
「せ、拙者は、あ、後で」
「卑怯者!」
弥太七は罵ると、抜刀で二三度空を試みてから、つかつかと迫った、
「元気な御仁、いよいよ貴公か」
新太郎は笑って、
「貴公はどこを斬ろう」
「斬るなら思う存分に斬れ」
弥太七は叫ぶ、
「命など助かっても、おめおめ藩へ帰れると思うか、死ぬ覚悟で来た以上、拙者は貴公を殺すか、自分が死ぬかの勝負が望みだ、他の者とは少々違うぞ」
「ほう――」
新太郎は相手の手足に眼をやって、
「なる程、貴公は少しやるな」
「無駄言は聞きあきた、来い!」
「よし」
新太郎は立直って、
「それなら思う存分に斬るぞ」
「望むところだ」
弥太七は上段につけた、新太郎ほどの相手に、さりとは大胆というべきである。
「えい!」
新太郎は高青眼、剣尖を相手の左拳につけて待った。
出来る、自分でいった通り、たしかに今までの二人とは格段の差だ。然もこの上段、捨身必殺の構えだ。新太郎の全神経は、初めて濶然(かつぜん)と醒めて来た。
と――突然、弥太七は、上段の剣をすっとさげた。や、と思う、刹那! さげると見た剣が再び上段にあがるのと、
「か――っ!」
叫んで打下すのと同時だった、
「おっ!」
剣尖一髪を容れぬ危さで左へ避けた新太郎、避けながら籠手を払った。弥太七疾(と)く右手を放して剣を挙げ、左へ跳ぶ。追詰めた新太郎足を払う、弥太七右足を挙げて新太郎の面へ打ちを入れる。刹那、空を打たせて新太郎、踏込みざま真向から、
「やっ!」
と斬った。額から鼻まで――。
六
千代姫の駕籠は、高原の道を、暖かい早春の陽に照されながら進んでいた。
新太郎は二丁程遅れて、山谷の美しい風景をめでながら跟いて行く。絶好の旅日和だ。
戸里沢で昼をつかおうと停まった時、供をしている青侍の一人がやって来て、
「姫君の思召しでござる」
と蒔絵の行厨(コウチュウ・弁当)を渡した。
「忝う存ずる」
顔をあからめながら受取った。
蓋を開いたが、胸がいっぱいになって、贅をみせた菜の品々、湯気のたつ飯――どうにも箸がつけられぬ。仕方なしに茶店から竹の皮を貰って、中のものをそっくりあけ、包みにして持った。
青侍が来て行厨を持戻る、間もなく駕籠があがった。
戸里沢から興石、それから布山、猿橋にかかる少し手前で、新太郎は自分の後をつけて来る娘の姿をみつけ出した。
「諦められぬとみえる」
新太郎は嘆息しながら、少しずつ姫の列から遅れて行った。
娘は、新太郎が次第に歩調をゆるめるので、自分もそれに倣っていた。しかし、そのうちに新太郎は立停って、道傍の木根に腰を下して了った、身を隠そうとしたが、右が高い畑、左は段々下りの裸な桑で隠れるところが無い、立止って躊躇していると、
「弓江どのではないか」
新太郎が声をかけた。
「此方へ参られい」
「――」
弓江は答えずに後へ帰ろうとしたが、思いとまってじっと新太郎をみつめている。
「お厭か―――、さらば拙者が参ろう」
新太郎は立上って戻った。
「未だ、お一人か」
新太郎が訊く。
弓江は答えない。答えれば、自分の心が乱れそうなのだ、生爪を剥がして、道に迷っている時、親切にしてくれた恩――そんな恩は兄の仇という恨みに代え難いけれど、新太郎の自分を見る澄んだ眸子には抗うことの出来ぬふしぎな好意を惹かれる。
ふしぎな好意――。
「其許は原の宿のこと、御存じか」
「――」
弓江は頷いた。
「それで益々拙者が憎うなったのであろう」
「――」
弓江は強く頭を振った。
「そうでない、ほう」
新太郎は微笑しながら、
「ただ、飽くまで兄上二人の仇を討ち度いと思われるのだな?」
弓江は新太郎の眼を見た。恐らく自分では気付かぬであろうが、その眼は仇を見る憎しみの色ではなく、抑えきれぬ愛慕の翳にうるんでいるようだ。
――いかん!
新太郎は外向いた。
「お帰りなされ」
「いえ」
「お帰りなされと申すに、原の宿のこと御存じなれば、拙者に敵して無駄なことお分りでござろう」
弓江は唇を噛んだ。危く涙がこぼれ落ちそうになったのである。
「屈強の武士三名まで倒れた上は、其許が討ちもらしたとしても恥辱ではない、帰って安穏にお暮らしなされ、お分りかな」
そう云いすてると、新太郎は足を早めて駕籠のあとを追った。
弓江は失神したように、新太郎の後姿を、いつまでもそこから見送っていた。
血風笹子峠
一
「榊原殿ではござらぬか」
呼ばれて馬上の武士が振返った。
「おう吉川氏」
道傍に、吉川太伯が立停っている。栗本要助、林壮之助、北村勇造、横川順介らが、その後に控えていた。勝沼で痺れを切らせて逆行して来たところだ。
「意外なところで――」
と吉川が近寄った。
紀伊家の用人榊原庄兵衛、馬をかえして下りると、
「貴殿も――」
と云う。
「斯様なところへ何用あって」
「例の浪人を追って――」
太伯が苦笑しながら、
「安芸と申す、あれか」
「如何にも」
「では――」
云いかけて、後に控えている四名の方へ眼をやる、聞かして宜い人物かどうか分らなかった。
「いや、拙者門弟並びに同志の者でござる」
「左様か」
目礼して、
「その安芸と申す浪人、例の葵坂の御方と同道ではあるまいか」
「さあ――」
太伯が首を傾けて、
「なんにせよ、唯今笹子川を越えたという知らせで、これより峠へ待伏せをかけるところ、新太郎一人のみに眼をつけて居った故」
「さては是も違うか――」
庄兵衛が舌打ちをした。
「葵坂の御方がどうかなされたのでござるか」
「いや、御存じないか知らぬが」
庄兵衛は口早に、
「御方には密かに江戸を脱けて御上洛、仏門に入らるると云うことでござるが、万一にも左様なことに成れば、幕府将来の禍根、御血統の紛争はいよいよ免れぬこと、其他の理由もあって――」
と声を低め、
「実は西条様思召しにて、千代姫は薩摩侯御二男に縁組と御口約遊ばしたのでござる」
「なる程」
「それや是や、途上を擁して、是が非でも江戸へお連戻し申せと云う」
「して、江戸を立たれたのは」
「初め、北家のさだ子姫と御同列にて上洛と探査仕ったのだが、さだ子姫の御行列を途中に検めると御方の姿なく、戻ろうとすると江戸からの飛脚で、御方には甲州街道を信州から木曽路へ向けて発向されたらしいと云う知らせでござった」
「ふむ――」
「そこで其の場より東海道を、箱根から富士の裏をぬけ、甲府へ出たのが昨日、未だそれらしき者の通過せぬ様子故、此方へ向って参ったのでござる」
「相分った」
太伯が膝を打った。
「御方、必ず新太郎めが警護申し居るに相違ござらん。どうも信州高島へ仕官とは訝しく存じたが――なる程、それは人眼を欺く触れ込みであったよ」
「して――」
榊原庄兵衛が、
「その安芸とか申す奴、唯今どの辺まで来て居りますか」
横川順介が、
「笹子川を越えたのが半刻も前でござりますから、最早間もなく見える頃と存じます」
「よし」
榊原が頷いた時、坂を駈け下って来る七八騎の武士があった。
「此所だ」
榊原は高く手を挙げた。
二
大月を朝遅く立って、千代姫の一行は午の刻近く初雁(はつかり)に駕籠を停めた。
ここで早めの午食を軽くしたため、足拵えを改めて峠越えにかかるのだ。
新太郎が草鞋を替えていると、青侍の一人がやって来て、
「笹子川を越す折に、怪しげな奴が居ったがお気付きではござらぬか」
と訊いた。
「どのような」
「若い藩士風の武士で、我らを見ると慌てて此方へ戻ってまいったが」
多分太伯の廻し者だろうと思ったから、
「いや、それなれば拙者に少々心当りがござるよ」
「何者でござる」
「つまらぬ意地で、拙者の首を狙っているのだが、高の知れた奴ら、御心配御無用でござる」
「それなれば宜敷いが」
と青侍は眉をひらいて、
「今しがたも馬上で、妙な奴が一人、峠の方から参って、我らを見るより引返して行ったのが、気にかかってならぬ故――」
「馬上の奴」
新太郎が首を傾げた。
「おおもう一人」
青侍は向うを見て、
「彼所に佇んでいる武家風の娘、あれも我らを見え隠れに跟けて来るように思われるが、矢張り――」
「はははは」
新太郎笑って、
「如何にも、あの娘も拙者の首を狙う別の一人でござる」
「とは又――沢山」
「いや、何人来ようとも、取られる首は一つきり、この一つが又なかなか強情者でのう、おいそれと取られぬから面白うござるよ」
青侍は笑いながら戻った。
千代姫の駕籠があがった。一行は一歩一歩峠へ向って登る――。
太伯め、かかるなら峠だ、と思ったから、新太郎は羽織の下に襷をかけ、袴の股立を取って、刀の目釘にも充分しめりをくれた。編笠はぬいで脇へ、わざと駕籠から後れて登って行く。
途中一度休んで、峠の九合目、左に深い杉林、右が裸岩の崖になっているところまで来ると、不意に駕籠の前方へ、
「わっ――」
といって七、八名の武士が現れた。
「や!」
仰天して見る。
立現れた武土達は、手に手に抜いて、駕籠脇の老女、女房達を追い払う。
「しまった」
御台様一派の追手! と感づいたから、四丁あまりの急坂、足に任せて走登る――と、一丁ばかりのところまで来た時、左手杉林の中から、身仕度甲斐甲斐しい太伯一党五名の者が現れて行手を塞いだ。
「うぬ、計ったな」
新太郎、歯噛みをすると、
「どけ!」
喚きざま、抜いて、突き破ろうとする。
「やるな!」
太伯が叫ぶと、北村勇造が槍を構えて、つつ――と新太郎に肉薄した。
「御駕籠を、お頼み申すぞ!」
叫びながら見ると、二名の青侍、抜きつれて駕籠の両側を護っている。
この時、峠の坂を下から、弓江は、息せき切って駈登って来た。
日は暖かく、風は静かだ。
三
正面から北村が槍、左手に林壮三郎、栗本要助は右手、太伯は三人の後陣だ。
「来い、太伯」
新太郎は叫んだ。
「普通なら遠慮して斬るが、今日は新太郎の命に代えてお護り申す方がある、一刀、一刀必ず致命だから覚悟をしろ」
「宜しー」
太伯が、
「拙者も今度は生きて帰らぬ覚悟、その代りには貴公も必ず討ってみせるぞ」
「心得た!」
と云う、とたんに、
「それっ!」
槍へ一刀、片手なぐりにくれる、
「はっ」
北村が繰込む、瞬間逆にかえして、
「とう!」
右の栗本へ突きを入れる、隙、北村が一足出てさっと槍を、胴へ!
「おっ!」
はねあげる。同時に、
「かつ――」
左から林が肩へ斬りつける。反って躱す新太郎、流れる林の剣を峰で打つより、だだ! と出て北村の真向へ一刀、
「うん!」
首を、すくめて避ける勇造。
きゃあーという女の悲鳴が聞えた。見ると駕籠脇の青侍は一人になっている、女房三人も、懐剣を抜いているが、唯抜いているという丈で、殆ど用をなさぬ、今の悲鳴は老女であろう、駕籠の側に、俯伏せに倒れているのが見える。
青侍はいま、完全に七八名の者に取囲まれて、苦戦の最中だ。
「うぬー」
と思うと、猛然、踏込んだ新太郎、
「それっ!」
と栗本へ空打ちを入れる、同時に脇からさっと槍を繰出した北村の胴へ、片手なぐりを一刀くれた。北村が避けて退るより疾く、斬り込んで来た栗本の太刀を空にやって右へ! 林壮三郎の面をのぞんで一刀。
「や!」
とあびせた。壮三郎が右へ廻るとたんに上段から要助へ斬りつける偽勢を見せて左へ。ぱっと走りぬけると、
「ゆくぞ!」
おめきながら太伯へ突を入れた。
「小癪な!」
身を捻って打落しにかかる太伯、新太郎は刀を下げて体当りをくれる。
「くそっ!」
太伯、半身になり損じて体が崩れる。新太郎は歩を転じて、ぱっと走りだした。
「待て!」
「やるな!」
と叫ぶ声を後に、新太郎は必死に坂をかけ登った。
残る一人の青侍を、辛うじて斬り伏せて、まさに駕籠の戸を明けようとしていた紀伊家の一党。
「狼藉!」
喚いて駈けつけた新太郎が、
「あ、来た」
と立上る一人を先ず斬った。
之に愕いて駕籠の周囲の者がわっと立つ、新太郎は駕籠を背にすると、
「姫君、新太郎が参りましたぞ、御安堵なさりませ」
と叫んだ。
「新太郎――」
駕籠の中から、恋しい人の声だ、
「はい」
「私は、覚悟が出来ています」
「はい」
四
千代姫の声は澄んでいる、
「新太郎」
「聞いて居ります」
「そなたの声が聞えなくなったら、私は此所で自害します」
「お姫さま」
新太郎は歓喜の声だ、
「新太郎はめったには死にませぬ、必ず此の場を切抜けます」
「おまえが生きている間は、私も生きています、おまえが死んだら、その時は私も死にます――」
「そのお言葉が千人力です、新太郎は強うござりますぞ」
そうだ、新太郎の全身に、むらむらと闘志が湧いて来た、頭から爪先まで、脈々と戦闘力がみなぎった。剣と体と心が、炎々たる烈火のように燃えあがった。
「さあ、来い!」
叫ぶと、いきなり刀を振って、並居る紀伊党へ斬込む。ぱっと散った。
追ついて来た太伯ら五人、
「引受けた!」
と叫んで、北村勇造が前へ出た。
「槍持ち!」
新太郎が喚く、
「今度は斬るぞ!」
「くそっ!」
さっと突出す、充分に踏込ませて、穂先をひっ外すと、
「それっ!」
と槍を七分目から斬放す、
「やっ」
かえしの太刀で北村の胴へなかばまで割込んだ。刹那! 栗本要助がうしろへ廻る、
「此奴!」
と薙いで、余ったやつを、
「えいっ!」
正に左から打ちを入れようとしていた紀伊党の一人へ突込んだ、充分入る。
「があ――」
異様に喚いて前のめりに倒れる。
「新太郎――」
千代姫の声だ。
「お姫さま――」
答える、刹那! 太伯が片手突に、猛烈な突きを入れて来た。危くかわして右足を、ぱっと太伯の右足にかけた、
「あっ!」
体の重心が浮いていたから、だだだとのめる。新太郎は跳躍して、駕籠の向うへ廻る紀伊党へ、
「さがれっ!」
と斬込んだ。
ぱっと散ったが、新太郎は足場の悪さを感じた。その道を、半丁あまりも行ったところに、ちょっとの間だが切通しになっている箇所がある、彼所まで行こう――と思った。
「お姫さま」
「はい」
「御駕籠をお出になって頂けませぬか」
「出ましょう」
直に駕籠の戸が中から明いた。
「向うの切通しまで参り度いのです、これでは手間が掛ってやりきれません」
「はい」
新太郎は静かに歩を転じた。
「お姫さま」
「新太郎!」
「先夜――安藤坂の闇夜のこと、覚えておいでなさりますか」
「覚えています」
「では、あの時のように、私の背中についておいでなさりませ」
「はい」
千代姫は懐剣の柄を握っていた。
切通しまで来た。
「お姫さま」
五
「はい」
「切通しの向うへおいで下さい」
千代姫は、云われる通り切通しを上へ登った。左も右も、十四五丈の巌だ、道の幅は一間そこそこ、新太郎は血刀を提げて、道のまん中に討手を迎えた。
紀伊党は四人を失った。吉川党は一人を失った。指揮をしている榊原庄兵衛を入れても、全部で九人しか残ってはいない。
「来い!」
新太郎が叫ぶ。
栗本要助が進んで来た。神谷源心道場で麒麟と云われた男。だが――力と頼む槍の勇造を斬られているから、士気充分でない、それを押殺して一気に勝ちを取ろうと肉薄した。
「えいっ!」
真向から斬って来る剣、
「心得た!」
右へ転じて、立直ろうとするはなを、引落すよう斬った、胸を脾腹へかけて割る。
「む――」
のめって崖へ身体ごとぶっつかったが、そのまま栗本はそこへ倒れて了った。
この間に、榊原庄兵衛が、二人ばかり連れてそっと、切通しの下を杉林の方へ入って行ったのには、流石に新太郎も気がつかなかった。
「行くぞ!」
林壮三郎が迫って来る。
その時、弓江が、小太刀を抜いて、太伯の脇をすり抜けながら、
「兄の敵!」
と呼びかけて詰め寄った。足場が狭い。
「危い、邪魔だ」
林が振向く、とたんに新太郎が踏込んで、
「そらっ!」
と面へあびせた。
「おう!」
受ける剣、だが新太郎の刀は、面とは逆に胴へ来た。江戸で由沢珂軒から呉々も注意されたのは此の手である。
「あ!」
と思って身体をひらいたが、正に胴に入った、利那! やけくそと、死物狂いで、壮三郎は得意の投げ突きを入れた。しかし、剣尖は狭い崖の巌に当って、かちりと鳴るばかり、一歩右足をひいた新太郎の剣は、既にこの時林の頸と肩とを斬っていた。壮三郎が反さまに倒れる。
「兄の――敵!」
同時に弓江が突いて来た。
「危い!」
新太郎は身をひらいて、弓江の手を取る。
「諦めい、弓江殿」
「敵! 敵!」
なかば夢中で叫びながら、つかまれた手を放そうともがく。其の時、吉川太伯が進み出て来た。
「みごとだ、安芸氏」
太伯は蒼白な顔に、冷ややかな笑いを浮べながらいう。
「来い!」
新太郎は弓江を突き放した。
「今度こそ斬るぞ」
「斬られよう、だが――拙者の方にも必至の法があるぞ、片腕を取られ、胴を割られて、進退の自由を奪われた吉川太伯が、此の一手だけは天下に誇れる積りだ、みごと受けてみられい、この突きを!」
太伯は右手の剣を、肩から剣尖まで、一直線にして、ぴたり新太郎の胸間へつけた。
「面白い、受けてみようぞ」
新太郎は、剣を正しく天にぎして、ぐっと太伯の突きの手に構えた。
不意に切通しの上で、
「あ――、新太郎」
と叫ぶ声。
■ 六
新太郎は仰天した。
――お姫さま。
叫ぼうとするが、太伯のつけた突きの剣、微動も許さぬ殺気だ。
「新太郎、来て!」
再び姫の叫ぶ声。しなしたり、背後に敵が廻ったのである。
「頼む、頼む、太伯」
新太郎が叫んだ。
「拙者の命に代え難き御方、この勝負預ってくれ」
「――」
太伯無言でずいと出る。
「新太郎――」
姫の声はやや遠のく。
「太伯! 頼む、見逃してくれ、三度まで拙者は斬るべきを斬らなかった。たった一度でよい、此の場はこのまま預ってくれ!」
「――」
太伯は依然として答えず。
「――新太郎!」
姫の声は半分にも聞えぬ。
「お姫さま」
新太郎が叫ぶ、刹那!
「いえッ!」
太伯の身が、弾丸のように、直線に伸びる剣と共に新太郎へおどりかかった。
「おッ!」
身を沈めたが、切尖は左肩を貫いた。
「くそッ!」
カッとなって、体当りに来た太伯の股をすくう。腰が砕けていたから転倒する太伯。新太郎は身を翻して上へ。
「待て!」
と太伯が叫ぶ。
「お姫さま――」
夢中で、駐け登った。
頂上。白い風、荒涼たる道、左手に五六頭の馬が、枯れ草をはんでいるばかり。
「お姫さま――」
絶叫する。
「――新、太、郎――」
遙かに、遙かに聞えて来る声、まさに峠を西へ下って行く気配だ。
「うぬ、やるか」
新太郎、馬の一頭を引寄せて、轡を取ろうとしたが、左手が利かない。血刀を口に銜えると右手で支えて飛乗った。
馬腹をけって道を下へ――。
追った、追った、道も數も無い。
「お姫さま――」
と呼び、
「新太郎――」
と答える、声を当てに遮二無二ものの十四五丁も宙を飛ばして行くと、千代姫を馬上に抱き辣めた榊原庄兵衛を先頭に、二名の騎士が後乗をして行くのが見えた。
「待て、待て――」
煽りに煽って追いついた。
それと知るより、後乗の一名は急に馬首をかえし、刀を抜いて逆襲の態度をとった。新太郎は右手の手綱を放して、刀を握りかえるより、股で馬腹を緊めながら、
「小癪な、退けい!」
喚きつつ、馬ごと相手に衝きかかった。相手は馬をひらりとかわして、横なぐりに斬ってくる、新太郎はその太刀をはねあげて、
「死ね!」
と面へ割りつけた。
「ぎゃあ!」
のけぞって、落馬するのには眼もくれず、
「お姫さま――」
叫び叫び、馬をかって追い継いだ。更に新太郎迫ると見るより、残った後乗の一人が、馬首をめぐらせて迎え撃ちに出たが、これも無論新太郎の敵ではなかった。
七
追いついた。
新太郎は遂に追いついた。馬が、榊原の馬に平行した時、
「やっ!」
と叫んで、新太郎の刀が、庄兵衛の後首を喉まで斬った。
「うむ!」
がくり前へ一度のめったが、手綱を絞って馬上に耐える庄兵衛。新太郎は自分の馬を、相手の前へ廻して足を止めると、ずり落ちて来る庄兵衛の手から、千代姫の体を奪うように抱き取った。
「新太郎」
「お姫さま!」
姫は、しっかと、新太郎の胸にすがる。
庄兵衛は道の上に俯伏せになって、右手で確と喉頸を押えているが、指の股から、迸るように溢れ出る血をどうする事も出来ず、低い呻きを続けている。
「最早、大丈夫で、ござります」
「はい」
「供の侍は、両名とも、絶命、御老女も、恐らく命はござりますまい」
「可哀相に――」
「致し方なきこと、姫君の御無事が何よりのことで、ござります」
「そして――おまえも」
「――」
新太郎は、ずんと、心臓へつきあげてくるものを感じた。が――辛うじて己を制しながら、姫を静かに押しへだてて、
「さ、兎も角この場を――」
「何所へ――?」
「いずれにもせよ、追手から遁れた上で」
新太郎は自分の乗ってきた馬を曳き寄せて、それへ姫をたすけ乗せ、自分は、血で汚れている榊原庄兵衛の乗馬にまたがった。
「あ、おまえ、左の手をどうしました」
「些かの手傷、案ずる程のものではござりませぬ、や――蹄の音、見られてはなりませぬ故急いで」
新太郎は、姫の馬の手綱を取ると、馬腹を蹴って、道を右へ、遙かに聞えてくる渓流の方へと駆って行った。
間もなく――。
吉川太伯、紀伊党の侍二人、それに弓江との四人が、馬を連ねて駈けつけて来た。
「あ、あれにも誰か」
道傍に倒れている庄兵衛を見つけて、紀伊党の一人が叫ぶ。馬を降りて来て、
「おう、榊原殿!」
太伯も傍へ来たが、検めて見るまでもなく頸部の重傷だ、暗然と頭を振って、
「お気の毒に……」
「御用人!」
一人が榊原を、静かに抱き起して、
「御用人! 岡田でござる、お気を慥かに、浅傷でござりますぞ!」
「う――む」
榊原はかすかに呻くばかり、眼は明いているが、もう視力はないらしい。
「九人も来て、残ったは我ら両名」
もう一人が拳をふるわせて、如何にも面目なげに、残念そうにいった。
太伯は、弓江の方へ寄って、
「其許は、これからどうなさる」
「はあ」
弓江は蒼白な面に、固い決意の色を見せながら、
「兄の仇を討たねば、江戸へは帰りませぬつもり。どんな辛苦をしましても、新太郎を討って――」
「なる程、立派なお覚悟」
太伯は頷いて、
「拙者もこのままでは帰れぬ仕儀、それでは御同道なさらぬか」
「はあ――」
弓江は、微かに頷いた。
愛憎他生
一
――かっこう!
若葉の梢をかすめて、澄んだ音が、もう一声、向うへ飛びながら、
――かっこう!
と鳴いた。
「新太郎」
「は!」
「いまのは、何という鳥だえ」
新太郎は木剣をさげて、
「は、つい聞き損じましたが、どのように鳴きました」
云うとき、ずっと彼方で又、
――かっこう!
と鳴いた。
「それ、いまの声」
「おう」
新太郎はなつかしそうに、
「随分久しく聞かぬ――、あれは郭公鳥と申し、また呼子鳥とも云いまする」
「ああ、あれが――」
姫は縁先から、庭下駄を足に、下へおりて来て、裏山の方へ眼をやった。
「新太郎の故郷では、郭公の声を聞きますると、夏になったと申します。故郷を離れて七年――、あの声を聞くにつけ、そぞろに村岡の山河が思出されてなりませぬ」
――かっこう!
今度は近くへ来たらしい。
「あ、あの様に――」
姫は、銀緑の若芽を綴った水楢の梢を指しながら、浮々と云った。
「声の割に、かたちの小さい鳥だこと――」
「友を呼んで居るのでしょう」
「真似てみようかしらん」
姫は両の手で口を囲って、
「――かっこう」
と叫んだ。
梢の鳥は、くくと首を傾けて、あたりを気急しく見廻していたが、
「――かっこう!」
もう一度姫が叫ぶと、上の枝へとび移りながら、澄き透った声で、
――かっこう!
と鳴いた。
「まあ、返辞をしましたよ。新太郎、おまえもやって御覧」
新太郎は鳥の方へ、
「果報者め」
と微笑をおくりながら、
「将軍家の姫君にお声をかけられるなど、其の方は甲斐一国、鳥仲間での果報者だぞ」
「将軍の娘――」
姫は眼をおとして、
「私はそれが、どんなに呪わしいか――」
「もうそれは」
と新太郎が静かに、
「仰せられぬ筈ではござりませぬか」
「ああ!」
姫は眼を空へ放った。
「此所には憎しみも嫉みも無い、巧も綾もない、若葉に戯れる風、渓川のせせらぎ、郭公の声――こんな処で、将軍の娘などという、上辺ばかりの衣装を棄て、心静かに一生を送れたら――」
「自然の相は、このように美しゅうござりまするが、此処にも愛憎嫉羨はござります、花散らす風、月隠す雲、草木を啖う虫――生あるところ争闘は絶えませぬ」
「私の云うのは、将軍の娘という衣を脱ぎ度いということです」
「――」
「そこで、此処でー」
姫の声は、熱く、ふるえを帯びてきた。
「この一生――」
「姫君」
新太郎が制した、
「庵主が戻られたようです」
二
此所は甲斐御嶽の山中、奥の滝を更に一里余も北へ入った、無明院という草庵、笹子峠を逃れて来た新太郎と千代姫は、庵主道善の好意で、足を停めること既に六十日になる。
新太郎の左肩の傷も、此頃ではどうやらかたまったらしい、筋が詰って、左へ大きく廻すことの出来ぬのが遺憾だが、木剣を振るにもさして苦痛は覚えなくなった。
「御稽古か――?」
柴折戸を明けて庭へ入って来ながら、庵主は柔和な頬笑みを見せて、
「御精が出ることのう」
「お陰で、どうやら木剣も、自由に扱えるように相成った」
「重畳々々」
庵主は頷きながら縁へ上る、
「骨を傷めて居る故、素人療治ではどうかと案じたが、無事に直って望外じゃった、鹿蹄草(いちやくそう)は金瘡の妙薬、医者の手遠き折の心得に覚えて置きなさるが宜い」
「有難う存じます」
庵主はふと新太郎に眼配せして、
「ちと、内談があるがの」
と云う。
新太郎は頷いて、木剣をそこへ置くと、庵主のあとから縁へあがった。
「此方が宜かろう」
道善は自分の居間へ入った。
「何か――?」
「実はのう」
道善は低い声で、
「いま下の妙光院というへ立寄ったのじゃが、そこに旅の武家と、若い女性が居った」
「はあ――」
「それが、どうも貴殿を探ねて居る者らしい」
「どういう――」
「武家の方は、たしか吉川太伯と云う」
「――太伯」
新太郎が頷いた。
「女性の方は、諏訪弓江とか」
「覚えござります」
「そう!」
庵主は庭の方を見やって、
「女性の方は、兄の仇と申していたし、吉川とか云うは、武道の意地と申して、たしかに貴殿を狙って来た様子じゃ」
「仇と呼ばれる理由はござりませぬが、致し方の無い事情で、その娘につけ狙わるること承知して居りました」
庵主は頷いて、
「わしは別に、その理由を知ろうとも思わぬし、また知ったとて益無いことじゃが、両名は貴殿が此の庵に居らるること、たしかにつき止めて来たらしく思われる故、一応貴殿の存意を計るべきかと思って、のう」
「御配慮かたじけのう存じます」
「そこで――」
と庵主はまた庭に眼をやって、
「どうなさるな」
「は」
「傷もほぼ本復、此の上此所に逗留なさるも無駄であろうし、お連れの方はいずれ京へ上られねばならぬと聞いている、ここらで出立なされたが御分別ではあるまいか」
「種々御心配を掛け――」
「なに、礼には及ばぬこと、それよりも自分の事を」
「御説の如く私も!」
「出立なさるか」
「本来なれば迎討って、勝負を決すべきでありますが、弓江と申す娘――無益に斬るも詮なき業、一時立退いたが宜敷いかと――」
「それそれ」
庵主は頷いた。
「では直に仕度をなさい、いつ両名が参らぬとも知れぬので、のう」
三
併しおそかった。
旅装をととのえて、新太郎と千代姫が縁先へ下りた時、柴折戸を明けて、吉川太伯、弓江の二人が入って来た。
「安芸氏、久濶じゃ!」
太伯が声をかけた。
「おう!」
新太郎が顔をあげる時、弓江は小太刀を既に抜き放って、
「兄の敵!」
と叫んでいる。
「心尽しも無駄であったか」
庵主が悲し気に首を振る。千代姫は縁の上で、鋭く弓江をにらみすえた。
新太郎はしばらく黙っていたが、剣を持ってすっと立つと、
「やろう!」
と立った、
「面倒だ、庵主殿お庭を拝借仕るぞ!」
「致し方あるまい」
庵主はうなずいて珠数を指にかけた。
「斬るも斬らるるも修羅妄執、恩怨憎愛他生律。姫よ――心を落着けて御覧あれ、これが現世の地獄変じゃ」
新太郎は抜いて、鞘をそれへ置くと、つつ――と庭へ下りて行った。
「弓江殿、かねての約束、拙者が先を仕るぞ!」
太伯も抜いた。弓江は少しさがって、隙あらば打込もうと構えている。
「今日は邪魔もなし」
太伯がいう、
「心措きなく勝負が出来そうだ、笹子峠では先勝後負、今日こそ死生を決そうぞ」
「心得た、いざ!」
新太郎は青眼にとった。
太伯は例の、右手をぐんと伸ばした直線の構え、剣尖を新太郎の胸元へつけて、はっと呼吸を納めた。
勝負は一瞬に決した。太伯必殺の不思議な突きにどう応ずるか、この庵に足を停めて以来、新太郎は毎日案を練っていたのだ。
「えい――っ!」
太伯の上体が、直線を描く剣とともに跳躍した時。新太郎は体を右へ傾け、籠手を引いて払う、同時にその剣は太伯の左面に飛んだ、
「がっ!」
立直ろうとする太伯、しかしすでに新太郎の二の太刀は横さまに半ば以上、太伯の頸を斬り放していた。血しぶきを飛ばしながら、だだだ二、三歩のめって俯伏せに倒れる太伯。
蒼白に顔面を痙攣らせていた弓江が、
「兄の敵――勝負!」
と叫んだ。
「来い!」
新太郎が血刀を前へ突き出した、千代姫が縁の上から、
「新太郎!」
と叫んだ時、弓江は、
「や!」
と叫んで、法る型もなく、突きの構えのまま新太郎の剣へとびかかった。
「えいっ!」
跳違えて、利腕をとる新太郎、左は娘の脾腹へ当っていた。
「む――」
歯を喰いしばって気絶する弓江だ。
「御庵主!」
「おう」
「庭先を汚しました、申訳ござらぬがお赦し下され」
「何の僧に死人は付き物じゃ。その娘御は――?」
「当身でござる、このままにおきましても、間もなく息をふきかえすことでござろうよ」
「では僧が預り申そう」
「何卒そのように」
新太郎は刀を拭って鞘に。
「蘇生つかまつったら、仇討などはあきらめて、江戸へ立帰るようおさとし下されい」
「きくか、きくまいか、のう――瞋恚(しんい)は九劫滅せず、と申して慈悲光も届かぬ煩悩じゃ。さ、また面倒が起きては悪い、立たれるがよかろう――」
「は、では仰せに甘えて、姫」
「はい」
千代姫は下へおりた。
「長々とお世話、いずれ縁もござらば」
「道中気をつけて参られい」
「御庵主さま、御壮健に――」
姫も名残惜しげに見上げた。庵主は珠数を揉んで、慈悲溢るる眼を二人に向けた。
「御仏の加護を祈りまするぞ」
「さらば――」
ふたりは外へ。
――かっこう!
鳥が鳴く。若芽萌ゆる甲斐路を新太郎と千代姫は京へ向けて――
愛読、ありがとうございました




 野村胡堂の長編連載「三万両五十三次」
野村胡堂の長編連載「三万両五十三次」 朗読新連載! 山本周五郎AudioBook 「長編 五辨の椿」
朗読新連載! 山本周五郎AudioBook 「長編 五辨の椿」 【眠くなる朗読/宮沢賢治】【セロ弾きのゴーシュ】 ナレーター七味春五郎 発行元丸竹書房
【眠くなる朗読/宮沢賢治】【セロ弾きのゴーシュ】 ナレーター七味春五郎 発行元丸竹書房 【朗読】芥川龍之介 睡眠導入作業用AudioBook 珠玉の短編を十一作詰め合わせしております。 ナレーター七味春五郎 発行元丸竹書房
【朗読】芥川龍之介 睡眠導入作業用AudioBook 珠玉の短編を十一作詰め合わせしております。 ナレーター七味春五郎 発行元丸竹書房