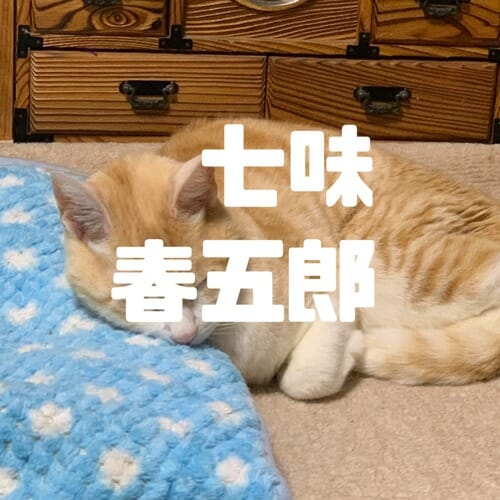七味春五郎の新作 連載開始!
新撰組八犬伝!
幕末、最後の犬士たちが日本を救う! 数千年の争いに、決着をつけるのは誰なのか? 古代より続く、天皇家と里見一族の物語。最後の周期に、新撰組を交えて、ついに決着!
- 新撰組八犬伝を連載中! クリック!
-
御家人奥村仁右衛門は、師匠近藤勇の死を見届け、沖田総司に別れを告げ、上野寛永寺の彰義隊の戦争に参加していた。
黒門口での激闘で意識をなくした彼は、赤子の泣き声に目を覚ます――
八犬伝を題材に、全く新しい新選組の物語が幕を開ける
新撰組八犬伝 ~ 第一輯 ~
note でも、掲載しています。
ノベルアップ+ にも作品を投稿しております。
コラム新撰組八犬伝の世界、特集ページを作成しました。七味春五郎が新撰組八犬伝について、四方山語っております。 縦書き特設ページもできました! 朗読動画もご用意しました https://youtu.be/[…]
新撰組八犬伝、堂々開幕!
幕末、最後の犬士たちが日本を救う! 数千年の争いに、決着をつけるのは誰なのか? 古代より続く、天皇家と里見一族の物語。最後の周期に、新撰組を交えて、ついに決着!
新選組八犬伝における玉の持ち主です
近藤勇=義
土方歳三=信
沖田総司=勇
斎藤一=智
永倉新八=礼
原田左之助=孝
井上源三朗=忠
奥村仁右衛門=仁
試衞館組は、藤堂、山南がいますが、祟り神との戦いで、すでに死亡ということに
現在、奥村と原田が、祟り憑きに落ちた大石鍬次郎と交戦中です
新選組八犬伝の用語集
第一輯
今回の周期では、新撰組として、犬士は結集。もともと表の家人であった奥村仁右衛門が最後の一人、であった。
魂のつながりをもち、ちゅ大法師は、最後の周期とみて、犬士たちを見守っているが、その真意は――
新選組八犬伝では、犬江新兵衛が、所持している。この時点では、孝の珠は、原田左之助の手にわたっており、犬塚信乃はすでに亡くなっていると思われる。先代の犬士である、新兵衛が犬塚信乃より譲り受けたのかもしれない。
新撰組八犬伝、では、馬琴も里見一族のもので、八犬伝は、なにかを予言しているともささやかれるが。
五次元では、時間の流れが一方向ではないため、どの時代に逃れることもできた。
始皇は、未来を書き換えるために、もちこんだ科学の品を、遺跡として封印している。遠い未来に宇宙人とたたかうためである。
始皇は過去に生きようとしたが、未来人の一部はこれをよしとせず、荒廃した未来の地球と、過去の地球をいれかえることで、ふたたび人の住める星にしようとしている。始皇は、過去の人々を守るために、反逆した未来人を五次元に封じたのである。
ちなみに作中表現される穢土、や、黄泉の国、は、未来の地球のこと。
未来の地球と、過去の地球は、タイムパラドックスを防ぐために、別の時空として枝分かれするはずであったが、時の整合性が働き、一本の時間軸にまとまろうとしている。
この悪霊に憑かれた状態を、祟り憑き、祟り落ちといわれている。ねじまげ世界の冒険の、わるいものに近い。
祟り神がいるのは、五次元のため、あらゆる時代に干渉してくる。
封じられた五次元には、この未来人以外にも、何者かが存在暗躍しているようだが、この存在については、おいおい語られる予定――
スナイドル銃ともに、入ってきた時期は、ほぼ等しく、南北戦争の余剰品が、幕末日本を動かします。スナイドルは、初期陸軍の主力兵器で、西南戦争でも活躍しました。
もともと、戊辰戦争で、薩摩藩や長岡藩などが導入していましたが、西南戦争時は、鹿児島の武器は大阪に持ち去られたあとで、エンフィールド銃しか装備できませんでした。スナイドルは、もともとエンフィールド銃を改修して後装式とした小銃で、旧式のエンフィールド(前装式)で苦戦を強いられました。
ちなみに、上野戦争当日では、長州軍がこの新式銃を装備していたのですが、当日は操作の仕方がわからず、加賀屋敷までとってかえしたという一幕もありました。(そのせいで黒門口にいた薩摩藩主力との同時攻撃に遅れるという不手際でした。)
さらにちなみにですが、会津の戸ノ口原の戦いで、旧式のゲベール銃を装備した白虎隊を打ち破ったのは、わずか十挺のスナイドル銃でありました。
下記のサイトに詳しいです。
第一輯の舞台
慶応四年、主な出来事
慶応四年、一月三日には、薩摩長州藩兵と、幕府軍が激突しています。
大阪城にいた徳川慶喜が、海路江戸に脱したのは、一月六日のこと。
翌七日には、新政府により、徳川慶喜追討令が出されています。
十日、慶喜は官位を剥奪され、新政府は、幕府領を直轄とします。慶喜は十一日に、江戸につきました。
二月
九日、有栖川宮が、東征大総督に就任。十二日、慶喜は、寛永寺で謹慎生活に。
十五日、東征軍、京を発つ。
二十三日、彰義隊発足。
三月
六日、駿府城で群議が開かれ、江戸城総攻撃が、三月十五日に決まる。
九日、勝海舟の使者、山岡鉄舟が駿府に到着、西郷隆盛と会見。慶喜処分など七箇条を提案。
十三日、江戸高輪の薩摩藩邸にて、海舟西郷の会見。翌十四日、江戸無血開城にて交渉成立す。
四月
四日、東海道先鋒総督勅使が江戸城西の丸に入る。
十一日、慶喜、水戸へ発つ。
五月
十五日、東征軍、彰義隊への総攻撃を開始。劇中は、この十五日当日よりはじまります。
謹慎の間と、徳川慶喜
徳川慶喜が謹慎した部屋は、葵の間、として、寛永寺に現存しています。元は大慈院にあったものを、大正三年の改築で、移築保存されたそうです。十二畳半と十畳の二間続きであったものを、十畳と八畳の二間になりました。慶喜は、ここで助命嘆願に奔走しています。果ては輪王寺宮まで担ぎ出す事態になりました。
輪王寺宮は、作中にも登場する覚王院義観らをつれて、駿府に赴きます。輪王寺宮、このとき二十才。輪王寺宮だけでなく、明治天皇の叔母に当たる和宮も、勝海舟の朝廷工作に動いています。
江戸を出立したのは、二月二十一日。彰義隊の戦いまでは、四ヶ月あります。三月七日には、有栖川宮と対面し、慶喜の謝罪状と、東征中止の嘆願の嘆願書を提出。
ところが、ここで問題になったのが、甲陽鎮撫隊こと、新撰組なのです。甲府に兵をおくったことを敵対行動とみなされたわけです。甲州勝沼の戦いは、三月六日のことで最悪のタイミングであったわけです。
これもあってか、宮に対する対応もけんもほろろといったところで、このときの新政府の態度が義観は許せなかった。道中では、朝廷軍に囲まれ、宮の御輿にたいしてまで、狼藉があったらしい。薩長兵のうたったこんな歌がのこっています。
「雨の降るよな鉄砲玉の中へ、上る宮さんの気が知れぬ、とことんやれ、とんやれな」
義観は強硬な主戦派になりました。
こうしたことが、慶喜退去後も彰義隊を駐屯させ、上野戦争へといたる布石となっていくのです。
覚王院義観
覚王院義観は、寛永寺の事務方をとりしきる最高責任者でした。これを「執当役」といいます。新撰組八犬伝では、玉梓としっぽりやったり、あっさり裏切られたりとさんざんであります。
元は、武州新座群根岸村の人。金子劇蔵とよばれたころからの神童で、五才で四書五経を暗記したと伝わります。二十六才で、真如院住職となり、覚王院の因業を賜ったのは、四十四才のとき。
覚王院義観は、宮の戦いが終わった後、仙台で捕らえられ、伝馬町の牢に入れられます。明治二年四十六才で病没とありますが、絶食による死亡との説もあるようです。
執当職にのぼりつめた男にしては、あまりにさみしい最後となりました。
有栖川宮の諸事情
実は有栖川宮熾仁親王は、先の和宮との婚約が決まっていたという過去があります。幕府の横やりで破談となり、和宮は、前将軍家茂に降嫁した過去があります。
ちなみに、この熾仁親王は、慶応三年に、慶喜の妹にあたる貞子と婚約しており、維新後に結婚しています。熾仁親王の妹・幟子女王は、慶喜の兄にして水戸藩主、徳川慶篤に嫁いでいます。さらにさかのぼれば、慶喜の父、徳川斉昭の正室・吉子女王は、熾仁親王の曾祖父の娘、つまり熾仁、幟子の大叔母になります。さらに遡れば、第十二代将軍徳川家慶の正室喬子女王は、吉子女王の兄弟。慶喜からみた、叔母ですね。ああ、ややこしい。水戸、徳川、有栖川宮との間には、複雑な血縁となっています。なのに、塩対応だったんですねえ。複雑!
もう少しつけたすと、熾仁親王の弟、威仁親王の娘は、慶喜の嗣子・徳川慶久にとついでおります。
雨の上野戦争
慶応四年、五月十五日の上野戦争まっただ中。この年は、三月から雨がつづき、四月も梅雨のようであったといいます(閏年で四月が二度あった)。五月に入っても、晴天が三日と続かず、十日からは連日の雨。河川は堤をやぶって、町々を濁流がおかし、隅田川では橋の上まで水が上がり、流されぬよう大きな石を運び入れる始末。川沿いの田畑は水没し、深い所では五尺もあったといいます。低地では、家の屋根に助けを求める人の姿がみられたそうです。
前日も雨。大村益次郎は、諸藩兵を配置につかせ、その総数は二万あまり。
十五日の攻撃が布告されると、三千人いた隊員は、千名ばかりに減ったといいます。彰義隊にいれば、女にもてるし、箔がつく。おまけに喰うには困らない、といったぐあいで邪な連中がかなり混ざっていたのでしょう。このへんは、烏合の衆の悲しさですが、なにせ、彰義隊は、徳川家として結成された部隊ではないのです。が、残った連中の指揮は高く、周囲の町民や、博徒連中を動員して、寛永寺周辺に木柵を張り巡らします。
十四日夕刻には、上野近辺を太鼓を打ちつつ歩き、立ち退くよう触れてまわったので、上野は騒然となるのでした。
官軍が出立をした七つ刻(午前四時)には霧雨であったようです。のちに、土砂降りとなり、暴雨であった、との記録もあります。
新撰組八犬伝の時代
史実の中の新撰組
新撰組八犬伝では、裏の家人として、主に京の治安を守ってきました。祟り神と戦い、祟り憑きを祓い、メンバーのほとんどが玉持ちという強力な部隊です。京の治安の表舞台は、京都見廻組が担当。
新撰組のほとんどは、里見の血縁者です。宝玉の導きにより、この周期の八犬士として京に集結した新撰組ですが、物語の冒頭では、部隊はバラバラになっています。沖田総司は史実の通り、千駄ヶ谷の植木屋平五郎宅の離れで療養中です。原田左之助は、輪王寺宮護衛のため、上野寛永寺へ。このあたりも史実のままですね。
それでは、新選組八犬伝の裏話を交えながら、史実の中の新撰組を見ていきましょう。
新撰組の母体・天然理心流の歴史
天然理心流の創始者は遠江の人で、近藤内蔵之助、です。天真正伝神道流を学び、江戸の薬研堀に道場を開いたのが、寛政初期のこと。二代目の近藤三助は、多摩群戸吹村の名主さんで、内蔵之助の養子になり、二代目を拝命。
二代目の三助さんは、道場経営の才があったのか、天然理心流は勢力を拡大していきます。内蔵之助のころも、多摩や相模に出稽古を行っていたようですが、三助さんの時代には、八王子だけで門人が1500人を数えたといいます。
剣術のほか、柔術、小具足術、棒術をふくんだ統合武術でした。剣術なら、剣術のみといった感じで個別に学ぶことができ、三代目の近藤周助は、剣術のみを伝授していたようです。
これにはわけがあって、文政二年。三助さんは急死してしまいます。46才の若さで、印可、免許を誰にも与えていませんでした。三助さん没後は、内蔵之助の高弟であった小幡万兵衛が指導を続け、指南免許を授けていったようです。
三代目近藤周助、こと嶋崎周助は、三助さんから、剣術の免許だけを授かっていたようです。近藤姓をつぐのは、三助さんの死から十一年後のことで、他に増田蔵六や桑原英助など、各地で天然理心流道場を開いていたものたちはいました。おそらくは、増田蔵六は八王子千人同心であったため、道統をつぐつもりがなく、桑原英助(弟子に講武所師範となった小野田東市がおられます)は名主であったなどの事情があり、剣術一本で身を立てていた嶋崎周助が、天然理心流三代目をついだといわれています。
近藤勇のもう一人の義兄弟に、小島鹿之助という人がいます。 小野路村の名主だった人で、近藤周助の門人。新撰組のパトロンにもなりました。ちなみに、土方歳三の親戚です。佐藤彦五郎とも義兄弟の契りをかわしていますが、天然理心流というつながりもある[…]
新撰組八犬伝の登場人物
八犬士側
近藤の試衛館に参加し、沖田らとともに腕をみがいた。御家人のため、浪士組には参加せず。 時代の変遷とともに、に組み込まれ、後、伝習隊に所属。士官として部隊を指揮した。長州征討、鳥羽伏見の戦いと、幕末の戦いに参加しつづけるが、ほとんど負け戦であった。新撰組の面々とは、京都で旧交をあたためあう。 江戸に戻ってのちは、伝習隊を脱し、甲陽鎮撫隊に参加。師匠筋であった近藤の処刑を目撃することになる。
ビジョンと呼ばれる近い将来を見通す、能力をもっている。
さて、仁右衛門の服装ですが、胴丸をつけていますけれども、側線いりのズボンを履いた描写があります。これは、伝習隊に配布された制服で、基本的には、洋装です。ちなみに、白虎隊の少年たちも、洋装だったそうです。洋装となったのは、藩の方針ですが、全員に行き渡るはずもなく、母親が手縫いしてくれた物で出陣したそうで、格好はまちまちだったようですね。会津戦争は、四月二十日から九月二十二日までなので、戦争そのものは始まっていますが、白虎隊の悲劇はもう少し先の話。
新撰組
信の珠の持ち主。仁右衛門と同じく、ビジョンをみる能力をもっている。
史実なら、四月十九日には、宇都宮城を攻略しています。このときの足を負傷しており、同二十九日には、若松城下町の清水屋で宿をとっています。戦列に復帰するのは、六月下旬以降であったようです。