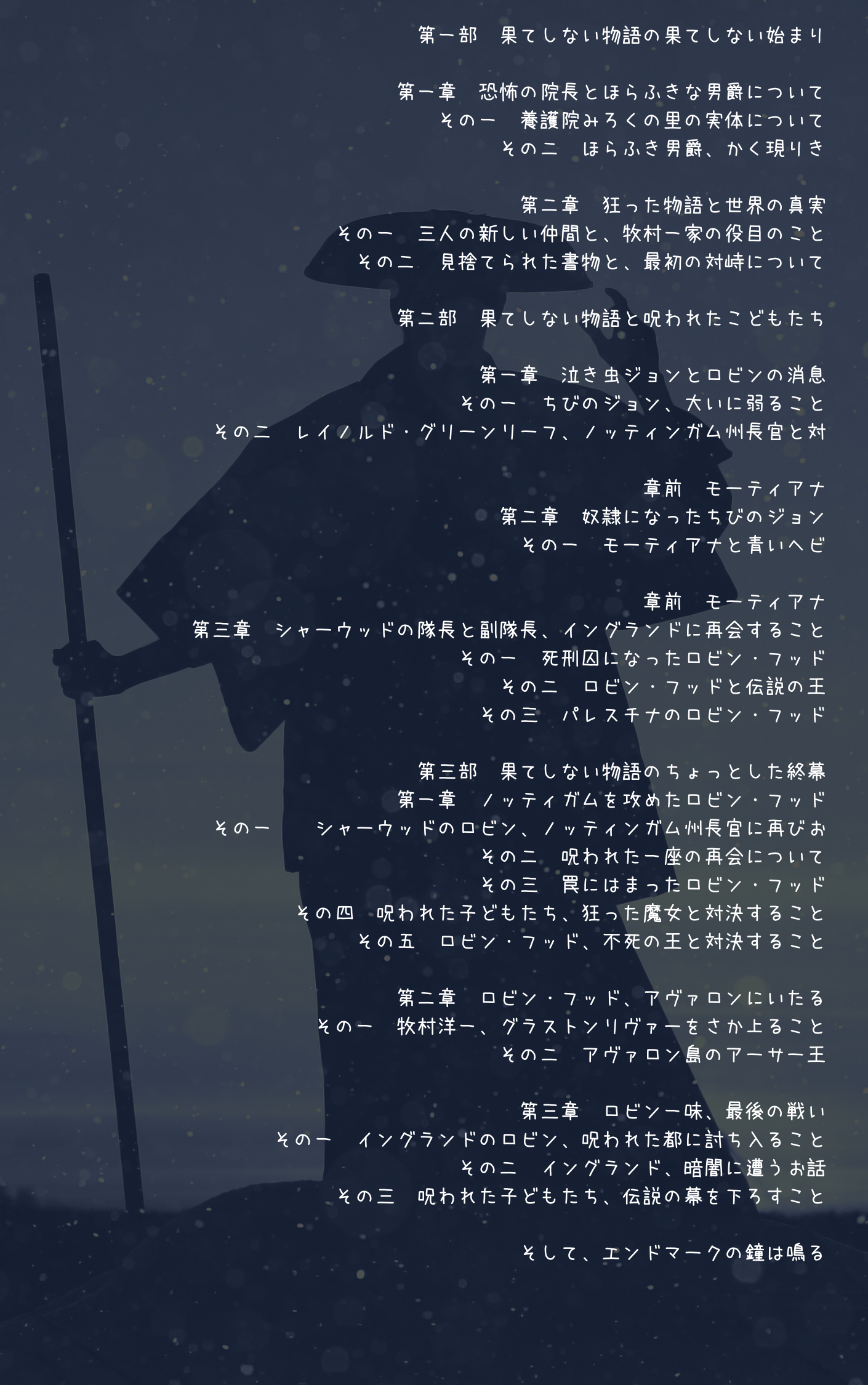主人公、牧村洋一は、突然の事故で両親を亡くしてしまいます。預けられた擁護院の院長は、児童を虐待するサイコな奴です。洋一もまた虐待をうけ、身も心もボロボロになります。 そんな彼を救いに来たのが、ミュンヒハウゼンと名乗る老人です。彼は、映画にもなったあのほらふき男爵その人と名乗るのです。一緒にいるのは、浮世絵から抜け出たのかと疑わしき、侍の親子。 彼らは洋一こそは、本の世界を守ってきた一族の最後の生き残りであり、両親は「伝説の書」とよばれる赤本を所持していたと彼に告げます。 人々の心が離れたいま、物語は力をなくし、善が悪に負け、登場人物はその目的を見失い、荒廃しきっているのだと。そのすべてを主導して、あまつさえ、洋一の両親を奪った憎き仇こそ、ウィンディゴ…… 最初こそまったく信じていなかった洋一ですが、生まれ育った図書館に戻ってみると、そこでは忘れられた書物たちが、荒れ狂っていて…… 普通の小学生にすぎない洋一が、伝説の書を胸に、本の世界へと飛び込みます。 今回冒険する物語の舞台は、「ロビン・フッドの冒険」 旅を通じて、洋一はサムライの少年、奥村太助とも、しだいに絆を深め、互いを助け合い、ともにウィンディゴに立ち向かおうとします。 けれど、伝説の書は、洋一の見方などではなく、彼をのろい殺そうとしていて…… ただの小学生だった洋一が、物語を通じて、少しずつ成長していきます。果たして、洋一と太助は、ウィンディゴを打ち倒し、物語の世界を救うことができるのか? というのがおおまかなあらすじとなっております。 物語には、もちろんちびのジョンや、赤服ウィルなどの、有名人物が、続々と登場してきます。 おまけに物語は○ー○ー王の世界とも混ざり合ってしまっています。 物語を改編するウィンディゴを相手に、洋一は創造の力で、打ち勝つことができるのか、というのが見所となっております。
第一部 果てしない物語の果てしない始まり
第一章 恐怖の院長とほらふきな男爵について
その一 養護院みろくの里の実体について
1
果てしない夜の森のなか、洋一少年が思いをはせていたあの日というのは、冬も間中の寒い夜のことだった。
その日、古い石油ストーブの前で、彼は毛布にくるまっていた。外をわたる風に、洋館の窓はゆれていた。そうして、ただ一人、お気にいりの本を膝におき、クリームパンと瓶詰めの牛乳に手をのばしていたその間に、彼の両親は、この世の人ではなくなった。手の届かぬところに、行ってしまったのである。
警官が訪ねてきたのは、洋一が、そろそろ時間の遅いのを心配しはじめたころだった。
玄関に応対に出て、そこで三人の警官から事情を聞いた。聞いているうちに、彼の手からは、牛乳とパンと、毛布が落ちた。ほとんど飲み終えていた牛乳が、床にこぼれ、その白い液体は、彼の真っ白になった脳裏に、いやに強く焼き付けられた。
いやな、予感がした。
彼は毛布をもったまま、警官に誘われた。パトカーに乗るのは初めてだった。隣にすわる警官たちは、いたわりの目を向けていた。
パトカーは、サイレン音を鳴らしもしなかった……
2
洋一は病院までつれていかれたが、両親には会わせてもらえなかった(二人の体が、すっかり燃えたことを知ったのは、ずっと後のことである)。
洋一のまわりで、時間だけが、呆然とながれていった。死というものは、大人でも理解しがたいものであったし、両親の死を受け入れるには、彼はまだ幼すぎた。相談をしようにも、となりにいる警官は、洋一には、ちょっとばかりおっかなかった。友達に電話をしたかったが、夜も遅いし、どこからどこにかければいいのかもわからなかった。電話番号のひかえすらない。
洋一は、父さんと母さんはまだ手術室にいて、まだ治療を受けているにすぎないんだ、と、そんな考えにしがみついた。呆然とはさきほど述べたが、彼の脳みそは、大部分が、考えることを放棄したかのようだった。
やがてそんな時間も過ぎ、病院の安置室の長椅子にすわりこむ洋一の前に、役所の人間が現れた。彼らはもう、あの屋敷には住めないこと、法律により、養護院で暮らさねばならないことを告げた。洋一には、 親戚がいなかった。彼の唯一の身内は、安置室にいるから、独りぼっちになったわけだ。肉体的にも、精神的にも……。
役所から来た女は、足立という名前で、きれいだが冷たい感じのする、背の高い女性だった。冷えきっていたのは、洋一の身と心の方だったから、そんなふうに感じたのかもしれない。
ともかく、洋一は病院をでると、その人の車に乗せられ、いったんは、自宅の図書館までつれもどされた。服や、身のまわりの品を、持っていくためである。
足立は、屋敷までの道々、養護院はどんなところか、そこではどんなふうに暮らさねばならないかを、話してくれた。また、屋敷にはときおりもどっていいこと、そのおりは養護院の院長を通し、自分に連絡をつけることを約束させた。鍵はわたしが持っておくから、心配しなくていいのよ……。
車のヘッドライトは、夜の無機質な街を照らしていた。車はゆったりだとも、速かったともいえる。時間の感覚が、なかったのだ。
洋一は足立の方は見ずに、窓の外ばかり向いていた。外に知り合いがいないか、友達が呼び止めてくれはしないかと、そんな姿ばかりを探していた。
ときおり、足立の車は、柳やんやカッツンの家の前を通ったが、どの家並みも明かりは消えていて、彼の期待した友人の姿は、どこにもなかった。
屋敷につくと、洋一は、わざとゆっくり自室に向かった。後ろから、足立が屋敷を見回し、感嘆の声を上げるのが聞こえた。家具や、造りの広壮なことに驚いたのである。屋敷だけを見ていると、洋一の家は、とほうもないお金持ちだと人は思うのだが、じっさいには、つつましやかな生活だった。
洋一は旅行用のバッグを探し出し、子供の頭でいるだろうと思われるものを、バッグの中にほうりこんでいった。その間も、外で物音がするたびに窓に駆け寄り、両親か、あるいはクラスメートの姿をさがした。そのたびに、がっかりしては引き返すのだった。
阿部先生は、なんでこんなときにかぎってきてくれないんだろう。今が一番肝腎なときじゃないか、文化祭や体育祭より大事なときだと、彼は思った。
洋一は、パンツをたくさんと、ズボンを少々、セーターを一枚用意した。たまに戻ってこられると足立は言っていたから、ゲームやおもちゃは持っていくのを控えることにした。養護院がどんなところかわからないし、山さんみたいな、いやなやつがいたら、ゲームをとられないともかぎらない。
それから、養護院はどこにあるんだろう、これまでの学校に通えるんだろうかと不安に思って、最悪の結果を予想した。だから、足立に訊くのは控えることにした。たびたび戻ってきたかったから、わざと置いていったものもあった。帰るときの、口実になるように。
つまるところは、こういうことだ。
洋一は、ちょっと待ってよ、と言いたかった。車に乗っている間も、カバンに服をつめている間も、ずっとそう言いたかった。足立が、もう屋敷にはなかなか戻れないだろう、とか、はやく新しい親御さんが見つかるといいのだけれど、と言っているときは、とくに強くそう言いたかった。彼にはろくすっぽわけがわからなかった。人が死ぬだとか、両親にはもう会えないだとか、こんなときの世の中の仕組みだとか……
そんなことを理解するには、彼の心は柔軟でありすぎたのかもしれない。だけど、洋一だって、もうどうにもならないということは、わかっていた。
荷造りはすんだ。足立の車はゆるやかに発車して、屋敷につづく坂道を、ゆっくりと下った。洋一はシートにへばりつくようにして、その道と屋敷を、視界におさめつづけた。
自宅のある丘を離れ、あの林が見えなくなると、洋一はゆっくりと前をむいて、座り直した。

ねじまげシリーズの最新記事8件
-
- 2021年4月10日
ねじまげ物語の冒険 全文掲載!
-
- 2020年8月19日
七味春五郎著 ねじまげ物語の冒険をご紹介! 発行元丸竹書房
-
- 2020年8月19日
七味春五郎著 ねじまげ世界の冒険をご紹介! 発行元丸竹書房
-
- 2020年3月29日
ねじまげ世界の冒険 第三巻