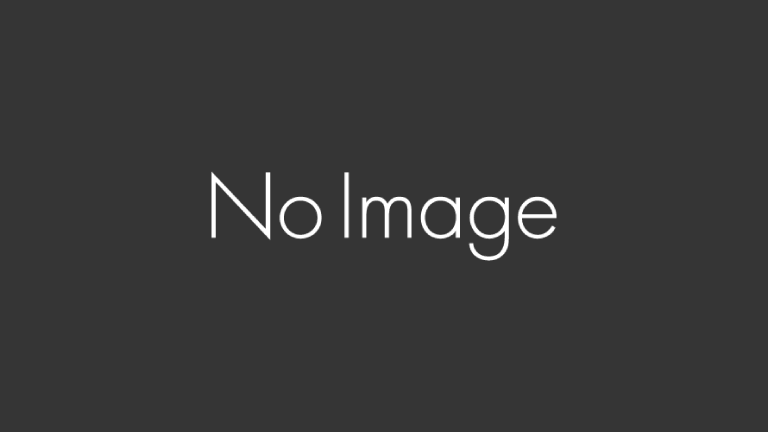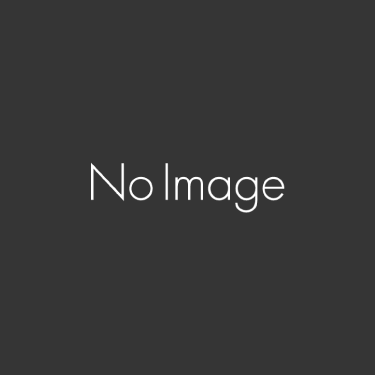「若殿女難記」主な登場人物
若殿 大助(わかどの だいすけ) / 伝吉(でんきち)
美作津山藩の若殿。世継ぎ争いで国許へ追いやられていたが、再び世子として迎えられる。一見放蕩無頼に見えるが、その裏には深い思惑がある。金谷の宿では「伝吉」と名乗る。
五十塚 紋太夫(いそづか もんだゆう)
森家江戸邸の物頭格。若殿すり替えを企む奸臣の一味で、伝吉を若殿に仕立て上げる。
宙野 儀兵衛(そらの ぎへえ)
五十塚の配下で、若殿(伝吉)の世話役を務める。小脳の皺が多いという眼つきを持つ。
おそめ
東海道金谷の宿はずれにある「なまめかしい一廓」の令嬢。伝吉に魅了される。
双葉(ふたば)
森家江戸邸の腰元。若殿(伝吉)に気に入られ、その言動に翻弄される。
森 伯耆守 長武(もり ほうきのかみ ながたけ)
津山藩主で若殿大助の父。病床に伏せっており、世継ぎ問題を抱える。
梱方 万里(こりかた ばんり)
森家江戸家老。若殿大助擁立の主唱者であり、奸臣一味に追放されようとする忠臣。
増井 琴太夫(ますい きんだゆう)
筆頭年寄。奸臣一味の中心人物の一人。
小林 三之丞(こばやし さんじょう)
大目付。奸臣一味の中心人物の一人。
角田 精一郎(かくた せいいちろう)
中老。奸臣一味の中心人物の一人。
「若殿女難記」物語と朗読
あらすじ
東海道金谷の宿はずれにある「なまめかしい一廓」に、毎晩通う美男の侍客「伝吉」がいた。彼は金遣いが荒く、言葉遣いは下品だが、なぜか周囲の女性たちを魅了する。実はこの伝吉、美作津山藩の若殿・大助に瓜二つの男で、藩の奸臣たちが世継ぎ争いのために若殿をすり替えるという恐ろしい企みを進めていたのだった。伝吉は若殿として江戸へ向かう道中で、その放蕩ぶりを遺憾なく発揮し、周囲を呆れさせる。しかし、江戸の上屋敷に到着し、病床の父・伯耆守との対面、そして家臣たちの引見という大役をこなす中で、若殿(伝吉)の真の狙いが明らかになっていく。奸臣たちの企みを逆手に取り、自ら「女難」を装いながら、藩の不正を暴き、忠臣を救い出す若殿の痛快な活躍が描かれる。果たして、若殿は無事に藩を立て直すことができるのか、そして彼の真の姿とは?
Q&Aコーナー
「若殿すり替え」とは、奸臣たちが藩の実権を掌握するために企てた陰謀です。本来の若殿・大助が世継ぎ争いで国許へ追いやられていたのを良いことに、彼に瓜二つの「伝吉」という男を身代わりとして江戸へ迎え入れ、傀儡の若殿として利用しようとしました。これによって、彼らは邪魔な忠臣たちを追放し、藩政を意のままに操ることを目論んでいました。
しかし、物語の終盤で明らかになるように、この企みは若殿大助自身の深謀遠慮によって逆手に取られ、奸臣たちの不正を暴くための罠として機能します。
作中に登場する「なまめかしい一廓」は、東海道金谷の宿場外れにある、遊女や飯盛女が客を取るような場所を指しています。直接的に「遊郭」とは明言されていませんが、「店先にさまざまな屋号を染出した色暖簾を掛け、紅白粉の濃い化粧をしたなまめかしい令嬢たちが並んでいる」という描写から、旅人をもてなす茶屋や小料理屋を装いつつ、実際には性的なサービスを提供する場所であったことが示唆されます。
江戸時代の宿場町には、旅人の疲れを癒すためのこうした施設が少なからず存在しました。物語では、伝吉(若殿)がここで放蕩ぶりを発揮し、その言動が周囲を驚かせる場面が描かれています。
作中で描かれる「御前会議」は、藩主(伯耆守)が病床にありながらも臨席し、藩の重臣たちが集まって行われる非常に重要な会議です。この会議は、奸臣一味が忠臣たちを追放し、藩政を掌握するための最終的な舞台として設定されました。
若殿(伝吉)がこの会議で、奸臣たちが捏造した罪状ではなく、彼ら自身の不正を読み上げることで、一味の企みが白日の下に晒されることになります。これは、藩の命運を左右する極めて重要な局面であり、若殿の機転と勇気が試される場として描かれています。