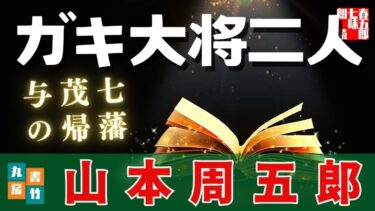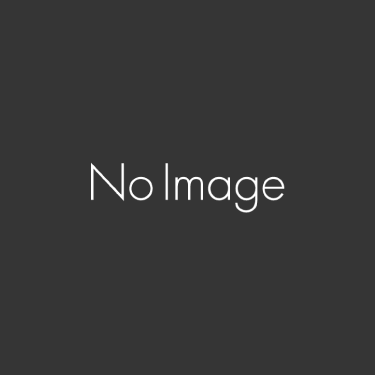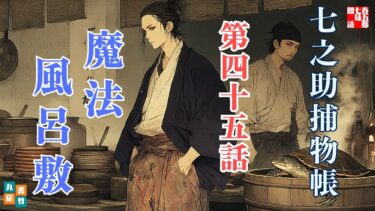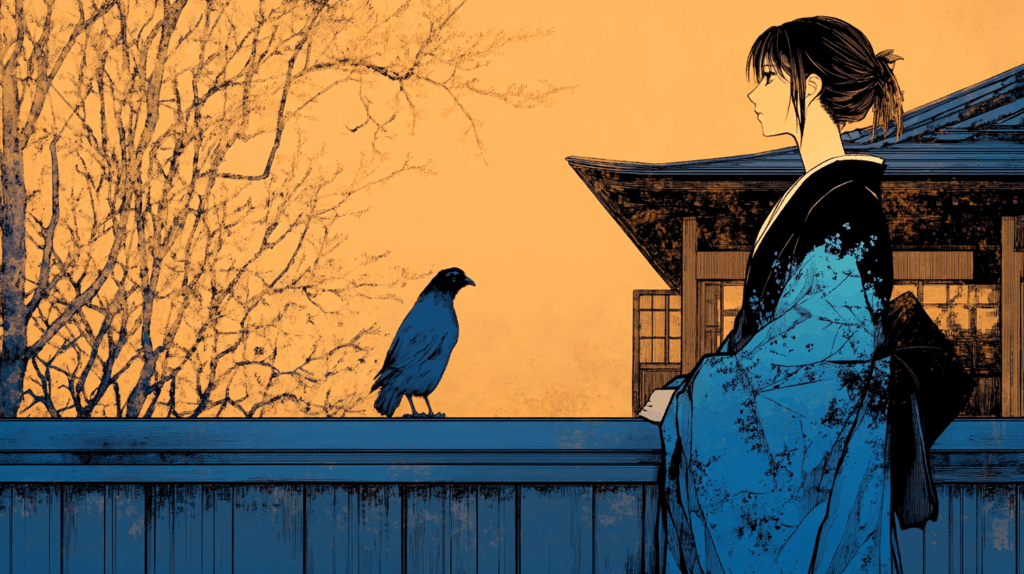
七之助捕物帳
鳥追いお巻
納言恭平 著
作品・作者紹介
著者:納言恭平(なごん きょうへい)
昭和期に活躍した時代小説作家。ユーモアと人情味あふれる捕物帖を得意とし、「七之助捕物帳」シリーズなどで人気を博しました。軽快な筆致と粋な江戸の風情を描き出す作風で、多くの読者に親しまれました。
七之助捕物帳シリーズについて
花川戸に住む御用聞の七之助を主人公とする捕物帖シリーズ。しっかり者の恋女房お雪や、そそっかしいが憎めない子分の音吉といった個性的な面々に支えられながら、江戸で起こる難事件を鮮やかに解決していきます。謎解きの面白さに加え、登場人物たちの軽妙なやり取りが魅力の人気シリーズです。
主な登場人物
本作「鳥追お巻」について
本作は、1941年(昭和16年)に雑誌「ユーモアクラブ」で発表された作品です。旗本くずれのやくざ侍が殺人の罪で捕らえられた事件の裏に、複雑な男女の情痴と、噂の女太夫「鳥追お巻」の影がちらつきます。七之助が幾重にも仕掛けられた嘘と芝居を見抜き、事件の真相に迫っていく痛快な一編です。
- 七之助(しちのすけ): 花川戸に住む御用聞。本作の主人公。
- お雪(おゆき): 七之助の恋女房。
- お由(およし): 船宿「真珠屋」の女中。事件の相談を七之助に持ちかける。
- 荒川 千五郎(あらかわ せんごろう): 旗本くずれの侍。殺人容疑で捕らえられる。
- 浜中 茂平次(はまなか もへいじ): 八丁堀の同心。千五郎を捕らえた張本人。
- 音吉(おときち): 七之助の子分。そそっかしいが、聞き込みが得意。
- 鳥追 お巻(とりおい おまき): 噂の女太夫。博徒の親分の若後家で、事件の鍵を握る人物。
- 笹屋 弁吉(ささや べんきち): 料理屋「笹屋」の主人。娘のお三重を溺愛している。
- お三重(おみえ): 笹屋の娘。千五郎と駆け落ちした過去を持つ。
本作のあらすじ・動画掲載
あらすじ
ある朝、花川戸の御用聞・七之助のもとへ、船宿「真珠屋」の女中お由が血相を変えて駆け込んできた。馴染み客の荒川千五郎という侍が、人を殺し庭に埋めているところを八丁堀の同心に捕らえられたが、千五郎は昨夜から真珠屋に泊まっており、犯行は不可能だというのだ。
事件を調べ始めた七之助。捕らえた同心の浜中茂平次は、現場を押さえたのだから犯人は千五郎に間違いないと自信満々だ。殺された男の腕には「おみえいのち」という刺青があり、その女こそ、千五郎が三年前に駆け落ちした料理屋「笹屋」の娘お三重だった。
ところが、捜査を進めるうちに、千五郎を庇うかのような関係者の証言が次々と現れる。さらに、事件の影には、謎多き女太夫「鳥追お巻」の存在が浮かび上がる。一体誰が嘘をついているのか?七之助は、子分の音吉と共に、複雑に絡んだ人間関係の糸を解きほぐし、事件の真相に迫る。
朗読動画
本文掲載
Q&Aコーナー
Q1: 「七之助捕物帳」シリーズの特徴は何ですか?
A1: 主人公・七之助の明快な推理はもちろん、彼を支える恋女房のお雪や子分の音吉など、人間味あふれる登場人物たちのやり取りが大きな魅力です。事件の謎解きだけでなく、江戸の人々の暮らしや人情が生き生きと描かれています。Q2: 「鳥追お巻」というタイトルはどういう意味ですか?
A2: 「鳥追」とは、正月の門付け芸の一種で、美しい衣装を着た女太夫が三味線を弾きながら家々を回るものです。本作に登場する「お巻」は、元は博徒の妻でありながら、この鳥追となって巷で噂の的となっている美女で、物語の重要な鍵を握る人物です。Q3: この物語の見どころはどこですか?
A3: 一人の男をめぐる複数の女性たちの証言が食い違い、誰が真実を語っているのか分からない、というサスペンスフルな展開が見どころです。また、七之助と子分・音吉のコミカルなコンビが、シリアスな事件の中にユーモアをもたらし、物語に緩急をつけています。納言恭平 七之助捕物帳 鳥追お巻 真珠屋のお由 花川戸の御用聞七之助が、恋女房お雪の給仕で朝飯をすませたところへ、玄関の格子の開く音がして、 「ごめん下さいまし。親分さんは御在宅でございましょうか?」 なにか取乱しているらしい女の声。 「はい」 お雪が取次に出てみると、玄関には、眼を釣り上げびんの毛を乱した若い女が、息を切らしながら立っている。 「あの、どなたさまで——?」 「はい。私は、裏門代地の船宿、真珠屋の女中でお由と申す者でございますが、至急御相談の筋がございまして。親分さんにお眼にかかりたいのでございます」 「上ってもらいねぇ」 玄関の声が聞えたとみえて、七之助が、奥の室からど鳴った。 「私は、裏門代地の……」 七之助の前に、固苦しく膝を折ったお由が、もう一度玄関の名乗を繰り返しかけるのを、七之助は軽く制して、 「聞いたよ、聞いたよ。裏門代地の真珠屋のお由さん。で――なんですかい。あっしに用事というのは」 「はい。じつは、私の知合の人が、無実の罪で、八丁堀の旦那さまに引かれて行ったのでございます」 「落ちついて、くわしく話してみなせえ」 「はい。……その方は、向島の、梅屋敷の近所にお住いになっていらっしゃる、荒川千五郎さまとおっしゃる方でございます。昨夜は、宵のうちか私共にお見えになりまして、御酒をお過しになりましたものですから、そっと掻巻を掛けまして、そのままお泊め申したのでございます。……荒川さまは、御酒をお過しになりますと、朝は、大早くお眼覚めになる性質でございまして、今朝ほども、夜が明けると間もなく、湯殿番の清どんを起してかえって行かれました。……あら、御新造さん、どうかもう、おかまい下さいますな」 お由は、番茶をすすめて黙って引下りかけたお雪に、礼を言って、 「すると、荒川さまがお帰りになりましたすぐ後で、清どんが、その室に落ちていた荒川さまの財布に気がついたのでございます。清どんはすぐ後を追いました。でも、清どんは、足が不自由なものですから、お屋敷に行き着くまで、とうとう追いつくことができませんでした。そしたら、どうした間違いでございましょう。清どんが、やっとそこへ行き着きました時には、もう、荒川さまは、八丁堀の旦那さまに叱られながら、お引立てられなされるところだったそうでございます」 「八丁堀の旦那は、荒川さんの屋敷に張り込んで、帰途(かえり)を待ち伏せていたんだろう」 「いいえ。清どんも、真先にそう思ったんだそうですが、事情をきくとそうではなかったんだそうでございます」 「はて?」 「人を殺して、殺した人間を庭の隅に埋けようとしてなさるところを、八丁堀の旦那さまに、お捕りになったんだそうでございます。……ねえ、親分さん、清どんが、小半刻も経ってから、荒川さまの後を追っかけたのでもあればともかく、ほんの一足ちがいだったんですもの。私には、いかになんでも、荒川さまにそんな早業がおできになろうとは思われません。それになんです。八丁堀の旦那さまが、丁度その時に、荒川さまの屋敷にお出向きになったというのもあんまり都合よくできているではございませんか。……私、これはなにか、きっとわけのあることに違いないと思いましたものですから、こうして、親分さんに御相談に上ったのでございます」 「そうか。よろしい。なんとか当ってみやしょう」 七之助は、胸板をたたくような調子でお由の頼みを引き受けた。 お由の顔にも、ほっとした安心の表情が浮んだ。そして、落ちついた手つきで番茶の茶碗を押しいただいた。 庭の殺人鬼 「おや。もう嗅ぎつけたのか」 伝馬町牢屋敷。調所の休息部屋で、ぷかり、ぷかり、いい心地そうにたばこの煙をふかしていた八丁堀同心の浜中茂平次は、苦笑をもらしながら七之助を迎えた。 「へえ。しょうべえですからね。でも、あっしの家とは眼と鼻の間みてえな向島だてえのに、手柄の一人占とは、旦那も人が悪いな」 「なに。そんなわけじゃないけれど、御用が呆気なく片づいちまったもんだから、お前の智恵を借りるまでもなかったんだ」 「へえ。もう、片づいちまったんですかい?」 「なにしろ、現場を押えたんだから、うんもすうもない。早速、吟味中入牢の手続をとって、今一休みしていたところだ」 「おやおや」 七之助はがっかりしたように呟いて、 「でも、あっしも、折角地獄耳にはさんで、なにかお手いをさせてもらいてえと、とんで来たんですから、土産話だけでも聞かしておくんなさいよ」 「おお、そんなことなら——」 手柄話なら、茂平次も好きな男だ。たばこの吸殻を灰吹に落すと、器用な手つきで、きせるをポンと筒に戻して、 「なんだ。きっかけは、その、今朝程早く、奉行書に投書をした奴があるんだ。向島は梅屋敷の近く、荒川千五郎という、旗本くずれのやくざ侍の屋敷内に人が殺されている——という簡単な文句なんだがね。わしは昨夜、泊りの番でな、欠伸を噛み殺しながら帰支度をしているところへ、急のお呼び出しでな。交替が来るまでには間があるからお前行けといわれたんだ」 七之助は、相槌がわりに頷いた。 「手先を連れて向島へ駕籠をとばすと、荒川の家はすぐに分った。梅屋敷の門前、畠の中の一軒家だ。屋敷のなかにも、周囲にも、松が多くってな、風流な家だぜ。しかし、門に近づくとおどろいた。まるで空屋敷だ。門も塀も朽ち果てているし、庭は——庭なんてんじゃない。藪だ。草は伸び放題に伸びているし、うっかり踏み込みでもしようものなら蛇でも踏んづけそうなぐあいなんだ」 茂平次の蛇ぎらいは誰でも知っている。それを思い出したから、七之助は、思わず、くすりと失笑った。 「なにが可笑しい。笑いごとじゃないよ。……気がつくと、その草の茂みが踏み荒されている。で、その跡を眼で辿ると、庭の片隅で、草の葉末が動いているじゃないか。……蛇のことなんか一ぺんに忘れて飛び込んで行ったぜ。驚いたね。荒川の奴、庭土を掘り返して、殺した奴の体を埋け込んでいるところだったんだ」 「荒川千五郎は、自分でその男を殺したんだと白状したんですかい?」 「うむ、他愛なくな。往生際のいい奴さ。しかし、こちらは、張合抜がして、一向につまらないがね」 茂平次、いかにもつまらなそうに苦笑した。 うわさの女太夫 音吉ののっぺり顔が、休息部屋の入口からのぞき込んだ。気がつくと、なにか意気込んでいる眼の色が、七之助を招いている。 「いいから、入れ!」 と、言って、 「旦那、音吉がなにか拾って来た様子ですぜ。……なんだ、音。なにか、かわったことでもあったか?」 音吉は、浜中茂平次に、心安立てのおじぎを一つ、ぺこりとすると、 「あったの、なんのって。あっしが、親分の命令どおり、あそこの見張りに参りやすと、駕籠舁を連れた町人ていの男が、一足先に行ってやしてね。物置小屋の中から、猿ぐつわをかませた若い御新造を助け出しているじゃあ、ありませんか」 「ううむ」 茂平次は残念そうに唸った。 「お前、駕籠の行先を突き止めたか?」 「へえ、行徳河岸の笹屋でさ。裏門から送り込むところまで、見届けて参りやしたぜ」 「そうか。分った!」 茂平次が、しめたとばかり、膝を叩いた。 「そうか。笹屋の娘をたぶらかして連れ出したのは、彼奴——荒川千五郎だったのか。あの頃、一寸評判になった事件だから、むろん、お前たちも知っているだろうが、笹屋に、お三重という縹緻好しの娘がいてな。その娘の顔を一眼見たさに、ずいぶん無理な工面をして、料理を食いに通った連中もいるんだ。だから、あの娘が、旗本くずれのやくざと駈落をしたと聞いた時には、色男連、歯ぎしりして口惜しがったものさ。あれから、三年にもなるかな。そうか、読めた。……こう、花川戸の荒川千五郎が、庭の隅に埋けかけていた男の腕に、おみえいのち――という刺青が彫ってあるぜ」 「そこまでは辻褄が合いやすね。でも、笹屋はどうして、娘が物置に放り込まれているのを知ったんでしょう。旦那さえ、お気づきにならなかったことなんでしょう」 「う、うむ……。笹屋を洗って見よう。お前、一緒に行くか」 「お供致しやしょう」 笹屋では、八丁堀同心の出張ときくと、鄭重に一室に招じ上げて、間もなく、当主の笹屋弁吉が挨拶にまかり出た。 「娘がかえって来たそうだな。でも、お前どうして、娘の居所を知ったんだ。物置小屋の中へ閉じ込められていたなんて、わしさえ気がつかなかったのを、お前、どうして知ったか。誰が教えてくれたんだ」 はげしい心の動揺も瞬間。弁吉は、静かに観念の眼を閉じると、 「それが、どこの誰だか分りませんが、駕籠舁みたいな風態の男が、裏口から参りやしてね。教えて行ってくれたんです。一応は酒代のかたりかとも疑ってみやしたけれど、かたられるつもりで小粒をひねりやして、念のために、教えられた場所に行ってみやすと、その男の言葉は、嘘じゃ、なかったんです」 茂平次は、七之助と顔を見合せた。分らんというように、七之助は頭を振った。 「じゃ、とにかく、当人に会おう」 「えっ、娘にですか?」 「そう。いろいろ、当人にきかんことには、詮議は進まん」 「そうですか。でも、旦那、まだ、娘をお調になっても無駄でございます。よほどひどい目に合わされたか、なんかとみえまして、すっかり正気を失ってるんです。それに、出入りの医者も当分誰にも会わせちゃいかんと言いますので」 根が人の善い茂平次。それでも無理にとは言い張れなかった。では娘が正気づいたら忘れないように知らせてくれ、と言い残して、笹屋の玄関を引き上げて行く。 門の外へ出ると、破れ三味線を抱いて、折からそこを通りかかった女太夫が、笠を傾けて、にっこりと音吉に微笑んだ。 だが、その微笑の中には、なにかあわてた表情があった。ふるいつきたい程いい後姿を見せて遠ざかって行く足どりにも、逃げるような遽しさがあった。 「音、知っているのか」 「へっ、今時、浅草に住んでいて、あの女を知らないんじゃ、もぐりだと言われても仕方がありやせんぜ。田原町の鳥追お巻たあ、あの女のことでげすよ」 「あれが鳥追お巻か。道理で、非人の娘にしちゃ、ようすがよすぎると思った」 茂平次が、くそ真面目な顔つきで、女太夫の後姿を見直したので、音吉、すっかり嬉しがって笑ってしまった。 鳥追お巻といえば、当時、下谷、浅草界隈では、噂に高い女の一人。 というのが――。 門付に出る女太夫は、非人の女と限られているのに、お巻だけは、れっきとした町家の生で、下谷坂本町の博徒の親分、山鉄の若後家なのだ。山鉄が死んだのは二年前。山鉄は、生きている時分から、一家の締めくくりは女房のお巻に任せっきりにしていたくらいだから、重立った子分たちは、山鉄の通夜の席で、お巻を姐御と立てつづけることに決めたのだ。しかし、お巻はきっぱりそれを断った。一の子分の嘉次郎に山鉄の名跡を継がせると、自分は浅草田原町の小粋な構えの家を借りて隠居をしてしまった。 しかし、年もまだ二十八。縹緻はよし、姿はよし、隠居をしたといっても、神妙に家の中に引っ込んでばかりもいられない。思いついたのが女太夫だ。正月の元旦から十五日までは、この門付の女太夫を鳥追という。非人の妻女のすることだが、おこよ源三郎なんて恋物語にまで仕組まれているくらいで、見た眼になかなか色っぽい。 で、お巻。退屈になると、破れ三味線を抱いて編笠をかぶって、ふらふらと、流に出て行く。そのようすがばかにいいものだから、いつしか、鳥追お巻の噂は、ぱっと、下谷、浅草界隈にひろがってしまった。 が――一方では又。 山鉄一家に揉めごとでもあって、嘉次郎の睨みでは収まりのつかない時には、姐御どうか――とお巻のところへ持ち込んで行く。それをお巻は、昔取った鉄火な調子で、水の流るるようなさばきをつけてやっているのだとも、噂されている。 「音」 七之助はわれに返ったように、 「お前、近頃、お巻のことで、なにか艶種の噂でも聞いちゃいまいな」 「さあ、一向。それだけは、あの女、つつしんでるんじゃねえでしょうか。なんでも、男嫌えだってうわさですぜ」 「あのきりょうで、男嫌いとはもったいない話だな」 と、浜中茂平次。どういう風の吹きまわしか、取り澄ました顔から、何度も笑談のとび出る日だ。 音吉大活躍 聞込みは音吉の独壇場だ。 翌る日一日、こま鼠のように江戸の街中を駈けずりまわって、夕方、花川戸の家へ舞い戻った時には、耳寄りな土産を、耳袋に一杯詰め込んでいた。 荒川千五郎は、千五百石取の旗本の二男坊だが、二十歳の頃から身を持ち崩して屋敷に寄りつかない。むろん親元から勘当の身になっている。なにをして食っているのか知らないが、とにかく金の使いっぷりもしみったれている方ではないし、荒れ果てているとはいえ、梅屋敷の近くに一軒家を借りて住んでいるくらいだから、どこかに金穴を握っているに違いない。 門の外へ出ると、破れ三味線を抱いて、折からそこを通りかかった女太夫が、笠を傾けて、にっこりと音吉に微笑んだ。 行徳河岸の料理屋、笹屋の娘お三重を連れ出したのは三年前だ。むろん相手が相手だから、親父の弁吉が二人の仲を許す筈はない。笹屋では、お三重の居所がわかると、何度も迎えの使を出したり、弁吉が自分で連れ戻しに行ったこともあるが、お三重は、がんとしてそれに応じない。骨の髄まで惚れ抜いているのだから手がつけられない。そこで笹屋でも、この頃ではもう、ホトホト匙を投げている形だった。 昨日の朝、荒川千五郎が庭の隅に埋けかけていた男の身許は、樽新道の呉服問屋、丹後屋の伜。新六。笹屋のお三重とは許嫁の間柄で、自分の腕に——おこえいのち——と刺青を彫っていたくらいだから、そのお三重が荒川千五郎にだまされると、すっかり身を持ちくずして人間がかわってしまった。とどのつまり、親からも勘当を言い渡されて、それ以来、杳として消息を絶っているのだという。 「荒川とお三重は、以来、仲よくやっていたのかね」 音吉のおしゃべりが一段落ついたところで、七之助が、こう訊ねた。 「ああ、それそれ、親分。野郎、許嫁まである女を、無理に言うことをきかせて連れ出しておきながら、あんな男のことだ。なに、長続きをするもんかね。間もなく、お三重は放ったらかしにして勝手の仕放題だったらしいんでさ。そら、昨日の朝、荒川のことを親分のところに頼みに来た真珠屋のお由。彼女なんかも臭うがすぜ」 「それにしては、よく、お三重を放り出さなかったもんだね」 「あっしもそう思いやしてね。いろいろ探ってみたんでげすが、いや、あの手合の考えなんて、腑に落ちないことだらけですぜ。あの野郎、こんなことを、人に語ったそうでげす。――女ってもなあ、一度夫婦だなんて仲になったら、邪魔になるからって、放り出せるもんじゃねえ。女の方から諦めをつけてくれない限り、可哀想で別れられるもんじゃ無えってね。あんな悪党にも、人間の涙が残ってるなんて、あっしゃ解せませんや」 「それがわからねえのか。人間、根っからの悪党なんて、滅多にいねえってことよ」 「さいでげしょうか」 わかったのかわからないのか、音吉は、しさいらしく頤をつまんだが、 「あっ、そうそう。あっしゃ、大事なことを、うっかり忘れるところでしたよ」 「ほう、なんだ?」 「お三重のことでさ。笹屋では、お三重はまだ、正気を失ったままだなんて言っとりやすが、ありゃあ、どうも、はじめっから眉唾ものの様子ですぜ。笹屋にはたらいている仲居のおもとてえ女があっしの幼馴染でげしてね。こいつの口から手繰り出したんでげすが、お三重は弁吉のために、どうやら、庭の奥の離家に押込められているような様子ですぜ」 離家の秘密 又夜が明けて、三日目の朝。 今日も、七之助から何事か言いつかった音吉は、欣喜雀躍、大はしゃぎにはしゃぎながら、鉄砲玉のように花川戸の家をとび出して行く。 その後から、七之助も、お雪に送り出されて、八丁堀へ——。 昨夜のうちに使をやってあったので、浜中茂平次も、一足おくれて奉行所の溜に顔を出した。二人打連れて、目的の場所は行徳河岸の笹屋。勝手に庭木戸を押してなかに入ろうとするのを、雇人がとび出して来て遮ったが、銀磨きの十手の端をちらりと見せると、蛇にでも噛みつかれたような顔つきをして手を引っ込めた。 庭の奥。泉水を前にした樹の間がくれに、茶室めいた離家の障子が見える。飛石を渡る足音が聞えたのか、すっ、と、細目に障子が開いて、又すぐ、ぴしっと閉まった。障子の内では、なにかあわてふためいている気配がしている。 「笹屋!」 縁側から、咎めるように茂平次が呼んだ。一瞬、しいんとして返事がない。 「開けろ。開けなきゃ、踏み込むぜ」 「へ、へい」 ふるえ声だ。がたがたと障子が動いた。たった二日の間に、見違える程眼の落ち窪んだ弁吉のうしろに、一人の若い女が、落花のように俯伏している。 「笹屋。よくも俺たちをこけにしたな」 片膝つきに、じりじりと縁側に上ると、茂平次は十手の先を、青畳に突っ張った。 「いえ。け、決してそんな——」 「黙らっしゃい。娘は正気を失っているから、会っても無駄だなんて――。お前、娘ははじめっから、ここに押込んでたんじゃないか。なんのこんたんがあって、お上の御用の邪魔立てをするんだ」 「だ、旦那さま!」 俯伏していた顔をきっと捧げて、お三重が叫んだ。 「どうぞ、お父さんをかんべんしてやっておくんなさいまし。お父さんは、私の罪をかばいたいのでございます」 「こ、これ、お三重。な、な、なにを、途方もねえことを言い出すんだ」 「いいえ、お父さん。私。自分で犯した罪をのがれたいとは思いません」 「な、な、なにを、血迷ったことを言い出すんだ」 「笹屋。お前、ちっと、黙っていたらどうだ。正気の言葉か、血迷っているのか。そりゃあ、十分 調べた上で、お上で審きをつけて下さる」 七之助の言葉に、笹屋弁吉は、今はすべてを観念したものの如く、神妙に領ずいて、頭を垂れた。 「では申し上げます」 蒼白な顔に鬢の毛が乱れて――しかし、意外にも落ちついた口調だった。 あの前の晩。いつしか夜も更けて、今夜も千五郎はかえって来そうにないし、諦めて寝床に入ろうとしていると、 「お三重さん、お三重さん」 ホトホトと戸を叩きながら、低声に、彼女を呼ぶ者があった。 一瞬、お三重は、息の根が止るかと思った。ついで、破れよとばかり、胸の鼓動がはげしくなった。彼女の名をお三重さんと呼ぶ。それは、丹後屋の新六のほかにはない筈だ。自分のために身を持ち崩して、この日頃、消息も知れない男。その男が、深夜に戸を叩いて、昔、聞き馴れた呼名で、自分を呼んでいるのだ。 お三重は、手燭を持って、そっと、縁板を踏んだ。一息深く息を吸い込んで、気持を落ちつけてから、 「どなたさま?」 雨戸に向ってたずねる。 「新六だよ」 「まっ、新六さん!」 「別れに来たんだ。一寸でいい、顔を見せてくれ。江戸に居られないことをしでかして、草鞋をはくんだ。もう、二度と、江戸の土を踏めるかどうかわからないんだ」 「待って下さい。今開けますから」 お三重は、あわてて心張棒をはずし、一枚の雨戸を繰った。 「お三重っ!」 その瞬間。急に、新六の口調がかわって、彼の手が、お三重の裾をつかんでいた。 「あ!」 逃れようとして、かえって、縁から引下されたのと、新六の右手に、きらっと、一閃光りものの走ったのが一緒だった。しかし、いきおいあまって、庭の草の中につんのめったお三重は、背後に、 「ううむっ!」 という、新六の、断末魔の呻きを聞いたのである。 お三重を縁側から引下したおのが力で、新六は、お三重とは反対側——縁に向ってはげしくのめって、逆手に持った短刀を、われとわが胸に突き刺していた。 お三重は茫然自失した。腰が抜けたか、新六の死体のかたわらに坐り込んだまま、立ち上ることも出来ない。 ながい時間のようでもあり、ほんの一瞬であったような気もする。やがて夜が明けたのだ。……はっと気がつくと、荒れ放題に荒れた庭草を分けて、誰かこちらに近づいて来る。夫の荒川千五郎だった。 千五郎は、その場の光景を一眼見ると、草の中から、獲物にとびつく猫のように身を躍らせて、あっとおどろく間もなく、お三重の両手を縛り上猿ぐつわを噛ませた。それから、軽々と抱き運んで、物置小屋に閉じ込めてしまったのである。 「荒川さんは、どうしてお前さんをそんな眼に合せたんだろう。お前、なにか心当りはないのかい?」 七之助が訊ねた。 「はい。よくはわかりませんけれど、お父さんから聞きますと、夫は私の罪を引き受けて、お役人さんに引かれて行ったようす。私の口を塞ぐためにあんなことをしたんではございますまいか」 「ハハハハ……」 突然、茂平次は腹を揺って笑い出した。 茂平次は、お三重の監視を弁吉に任せると、七之助を促して外へ出た。 「どこまで惚れているか底が知れない」 茂平次は呟くように言った。 「じゃ、旦那は、お三重の申条を作りごとだてえお見込みですか」 ——と七之助。 「きまってるじゃないか。千五郎の罪を自分で引受けようとしているのだ」 「しかし、真珠屋のお由は、千五郎は朝まで真珠屋に寝ていたと申し立てているじゃありませんか」 「なあに、あの女だって千五郎をかばっているんだよ。風呂番の清作ぐらい、抱き込むのはわけもないことだ。花川戸の、見ていてくれ。今に、あいつらにも泥を吐かせてやるから」 お巻の告白 ざっと一風呂浴びて家にかえると、その間に音吉の顔が待ちくたびれていた。 「おっ、もうかえっていたのか。いつもながら、お前の聞き込みの早さは人間業じゃねえな」 ほめられて相好を崩した音吉。てれ臭そうに顔を撫でながら、 「なに、あっしなざほんの使いやっこだ。やっぱり、親分の眼力は凄えや。親分の見込みどおり、丹後屋の新六は、山鉄一家の三下に住込んでいやしたぜ。それが、近頃、なにか、身内の者に顔向けのならねえことを仕出来して、逃げまわっていたらしい」 「そうか。そうだと思ったんだ。じゃあ、支度だ、支度だ」 七之助は濡手拭を女房の手に渡し乍ら、忙しそうな声を立てた。 間もなく二人が乗り込んで行ったのは、田原町の鳥追お巻の家。 「やいやい、人騒がせなことをするじゃねえか」 のっけから、相手の度胆を抜くように、怒鳴りつける七之助。だが、お巻は、落ちつき払った涼 しい顔で、 「なんですね。騒々しいのは親分の方じゃござんせんか。おどし文句は私にゃ利きませんよ。なんかききたいことがあるんならはっきり言っておくんなさいよ」 「違えねえ、相手を見損ったようだ」 七之助はあっさりと笑いとばして、 「丹後屋の新六の死体を、荒川の屋敷にかつぎ込ませたのはお前のしわざだろう?」 なんとか言いくるめるかと思いの外 「ああ、あたしが仕組んだ芝居だよ。嗅ぎつけられたからには、じたばたしたってはじまらないから、あっさりと兜を脱ぎますがね。あの奴、しょうのない奴だから、なんか、身内の面よごしみたいなことでも仕出来したんでしょう。凝らしめの折檻をしているうちに、打所が悪くって死んじまったらしい。あたしゃ、後仕末の相談を受けたから、じゃ、荒川の屋敷に放り込んでおけ、って、智恵を借してやったんですよ」 眼先の見える女だけに、往生際はさっぱりと気持がよかった。 「そんなことだろうと思ったんだ。新六と荒川夫婦の因縁を知っていたら、誰だって考えそうな細工だからな。……奉行所に投書をしたのもお前のしわざだな?」 なげぶみ 「ええ、そう。……でも、親分、新六が山鉄の飯を食ってるって、どうしてこんなに早くわかったんです?」 「どうしてって、お前が教えてくれたんじゃねえか」 「えっ!」 「笹屋の近くに、ようすを見に来たりするから、尻尾をつかまれるんだ」 七之助は笑い出した。 「なあんだ、女はやっぱり女だね」 ——と、これはお巻の自嘲的なつぶやき。 「姐御」 相かわらずの笑を含んで七之助が、しかし言葉の調子は改めた。 「察するところ、お前、荒川千五郎に肱鉄を食ったな」 「えっ! 親分、人が悪いね。そんな図星まで指して、女に恥を掻かせるもんじゃないよ」 いい加減の出鱈目でも放置しているかのように、お巻の態度は落ちついていた。 生れかわった男 山鉄一家の中から、下手人が名乗り出て、この一件はあっさりと解決した。 「丹後屋の新六は死骸になって庭先にころがっている。そのかたわらには、お三重が腰を抜かしている。あっしはそれを見たんだ。どうしたって、新六を手に掛けたのはお三重のしわざだと思われようじゃありませんか。あっしはその時ほどお三重を可哀想な女だと思ったことはありませんよ。笹屋みたいな大家の娘に生れて、苦労も知らずに育った女が、あっしみたいな男を亭主に持ったばかりに、さんざっぱら苦労を重ねた挙句、人殺しの大罪まで犯してしまったんだ。それもみんあっしの所為だと思いやすとね。つい、その、なんとかして助けてやりてえと、あっしみたいな男でも・・・・・・」 千五郎は鼻をつまらせた。 一件落着して、伝馬町の仮牢から放たれた荒川千五郎。早速、菓子折をぶら下げて、花川戸の家を訪ねているところだった。 「それで、お三重さんの口をふさぐために、あんな荒療治をなすったんだね」――と七之助。 「へえ。……とっさの場合で、少々あがったんでしょうね。口ふさぎはよいけれど、誰も気がつかなかったら、お三重は物置小屋の中で干上ってしまうだろうてえことに気がつかなかったのは一代の不覚でさ。しかし、助け出されたら、お三重は自分で名乗り出てあっしの無実を晴らそうとするにちがいない。あっしは、すっかり途方に暮れやしたぜ。そのうちに、ふとおもいついたのは、笹屋のおやじさんです。あのおやじさんに知らせることができたら、あっしを憎んでいなさるから、あっしを罪におとしても、お三重をかばって下さるだろうとこう考えたんです。……すると、丁度うまい具合に、浜中の旦那が小水を催してくれましてね。源兵衛橋の袂で、駕籠を休めて用足しなすっている隙に、あっしは、駕籠屋を駕籠の口に呼んでね、酒代をくれるにちがいないからこっそり笹屋の人に知らせてくれと、うまく抱き込んでやったんですよ」 それも七之助の推察どおりだったので、黙ってうなずいた口元に、会心の微笑が浮んだ。 「ねえ、親分。お三重は、八丁堀の役人に、下手人だと申立てたそうですが、するてえと、ほんとの下手人はあっしだとでも思いちがいしたんでしょうか」 「そうらしいぜ。後でそうだと言っていた。……荒川さん、お前、まだ、お三重さんには会いなさらねえのか」 「へえ。笹屋で会わせてくれないんです。でも、あっしは、お三重の心だけは信じています」 「そりゃあそうだろうが、お前さんの心はどうだい?」 「親分。あっしゃ、ざっくばらんに言っちまいますがね。あっしも、心底、お三重に惚れているらしい。今までは、これほど惚れているとは気がつかなかったが、今度のことで、あっしあ、自分の本心を、はじめてはっきり見たような気がします。これまで、どうしてあんなに苦労をさせたかと、あっしあ、この身を八つ裂きにしたいくらいですよ」 「ふうむ。お前さんに、ほんとに心を入れかえる決心があるなら、笹屋の主人には、おれから口を利いてあげてもいいぜ」 「有難うございます」 千五郎は心から頭を下げて、 「これから何年か経って、ほんとにまともな男一匹に、生れかわったら、その時改めてお願いに上ります」 「ちっ。眼ん中にごみが入りやがった」 庭先で、朝顔の鉢の手入れをしていた音吉が、そんな誤魔化しを言って、自分の顔に拡を曲げた。