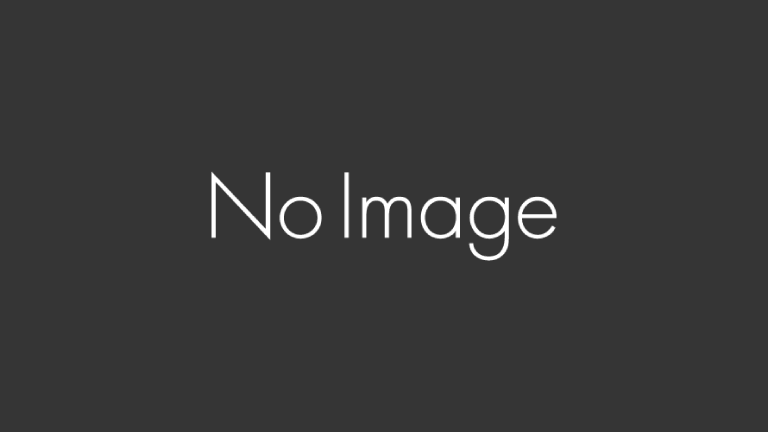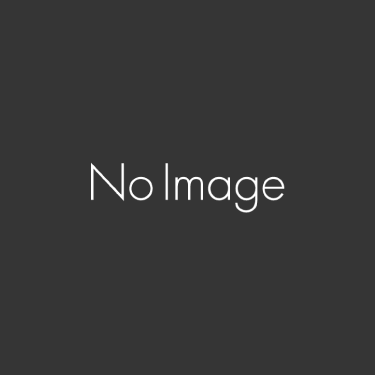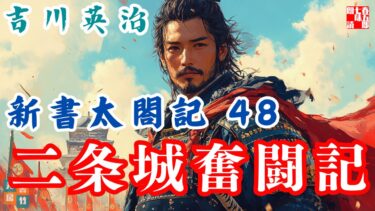新書太閤記
チャッピー:
harugoro:
チャッピー:
harugoro:
チャッピー:
harugoro:
チャッピー:
この回のあらすじ
洞ヶ嶺から下鳥羽の本陣に戻った明智光秀。兵力は1万6千ほど集まるも、細川藤孝・筒井順慶の援軍を得られなかったことに一抹の不安を抱いていた。そこへ京の町人たちが地子銭免除の礼として粽(ちまき)を献上するが、光秀は笹の皮がこびりついたまま口に入れそうになり吐き出す。その様子を見た町人たちは「あの大将は負ける」と噂する。
その直後、施薬院秀成(せやくいん しゅうせい)が光秀を訪ね、驚くべき報をもたらす。羽柴秀吉が、すでに尼ヶ崎に到着しているというのだ。さらに秀吉からの「戦場で一騎打ちで決着をつけよう」との決戦状とも言える伝言を聞き、光秀はついに全軍に夜間の桂川渡河を命令。決戦の地・山崎へ進軍し、御坊塚に本陣を構える。
天正十年六月十三日、未明。両軍が対峙する中、決戦の要衝・天王山にて、先に山頂を奪わんとする両軍の先駆け部隊(明智方・松田隊と秀吉方・中川、堀尾、高山らの部隊)が激突。ついに山崎の戦いの火ぶたが切られた。
主な登場人物
- 明智光秀: 本能寺の変の後、天下統一を目指す。下鳥羽に本陣を敷く。
- 羽柴秀吉: 中国大返しにより、驚異的な速さで尼ヶ崎に到着。光秀討伐に燃える。
- 施薬院秀成: 医師。信長の命で中国にいたが、秀吉から暇を出され、光秀に秀吉の伝言を伝える。
- 中川瀬兵衛(清秀): 秀吉方の先鋒。天王山一番乗りの功を狙う。
- 堀尾茂助(吉晴): 秀吉方の将。山登りが得意で、天王山へ先駆けする。
- 高山右近: 秀吉方の将。山崎に陣を敷く。
- 松田太郎左衛門: 明智方の将。光秀の命を受け、天王山の占拠に向かう。
- 中川淵之助(重定): 高山右近の配下。誰よりも早く天王山に登り、岩陰で居眠りしていた猛者。
粽のこと
光秀が、むなしく洞ヶ嶺を去って、下鳥羽の本陣へ帰って来た頃――十一日の午頃――には、すでに一方の秀吉は尼ヶ崎に着いて、一睡の快をとっている時刻だったのである。
光秀の本陣は、下鳥羽の秋山という一丘にあった。
この日の暑さは、尼ヶ崎の禅寺も、この丘も変りはない。光秀はもどると直ちに諸将を会して帷幕のうちに作戦方針を議した。――とはいえまだ、いよいよ当面の敵とわかった秀吉が、ここから指呼のあいだ尼ヶ崎に来ていようなどとは思いも寄らないふうであった。この先鋒部隊や先発の小荷駄隊は摂津口にぽつぽつ現われても、秀吉自身が到着するのはなお数日を要するものと観ていたのである。
しかしこれをさして彼の叡智の混乱というのは当らない。彼はそのすぐれたる常識をもって常識の水準からこう判断を下したに過ぎない。しかもこの判断は世人すべての常識でもあったのだ。
「では、即刻工事を急がせましょう」
明智茂朝がまっ先に帷幕から出て行った。評議は時をうつさず終ったのである。茂朝は駒をよせて淀へ急いだ。急遽、淀城に補強工事を加えて、敵に備えるためだった。
淀を右塁とし、勝龍寺の城を左塁とし、能勢、亀山の諸峰と、小倉之池に狭められたこの京口の隘路を取って、羽柴軍を撃摧せんとなす準備行動のそれは第一歩とみられた。
また、前々から、散陣的に、淀川の対岸から山崎方面へ出しておいた幾つかの部隊にも伝令をとばして、
「勝龍寺へ籠って、防塁をかため、満を持して、敵を待て」
と伝えさせた。
伏見には家臣池田織部を。宇治には奥田庄太夫を。淀には番頭大炊助を。また勝龍寺の城には、三宅綱朝をそれぞれ籠めてある。
配するに万全を期しているが、敵方の兵数を推し量るとき、光秀はなお一抹の弱味を抱かずにいられなかった。朝来、午を過ぎても、諸方から麾下に集まって来る兵は相当あったが、いずれも近畿の小武門や浪牢の徒で、いわば、名もなき輩が出世のいとぐちを求めて来るに過ぎなかった。大量の兵力をひっさげて、一方の将たらんといって来るような曠ある参加者はほとんどなかった。
「いまのところで、味方の兵数はどれ程にのぼっておるか。勝龍寺、洞ヶ嶺、淀なども合わせて――」
光秀が左右に質すと、祐筆は着到帳と、亀山以来の譜代の者と合算し、また安土、坂本その他、遠くに散在してある兵力とを差引いて、次のように書き出して、光秀へ示した。
斎藤利三の隊 二千人
阿閉貞秀。明智茂朝の隊 三千人
藤田伝五。伊勢貞興の隊 二千人
津田信春。村上清国の隊 二千人
並河掃部。松田政近の隊 二千人
――御本軍 約五千
ざっと、計一万六千である。光秀は心のうちでつぶやいた。
「……もし丹後の細川と大和の筒井だにこれへ加わっていたならば、日本中部を縦断して、われは絶対に不敗の態勢を取り得たであろうに」
すでに作戦方針を決定した後までも、彼は甚だ兵力の差に重点をおいて苦慮した。
由来、彼の頭脳は計数的であって、にわかに、寡をもって衆を破るが如き飛躍は、ひらめいて来なかった。
それと、秀吉と直面するの大戦を前にしたが、どこかに一抹、敗戦を意識する気おくれが潜んでいた。これは決定的な敗戦の因をなすものであるが、光秀の性格とここ数日の齟齬がかくさせたもので、彼自身にも、どうにもならないものだったろう。
彼は、彼自身で起した怒濤の高さに、今や溺るる怖れすら自覚していた。しかし、それは表面の彼の姿ではない。彼自身も気づかないでいる潜在意識においてである。
その夕方、この下鳥羽の陣へ、一群の町人たちが伺候した。京都の町代表たちで、
「地子銭御免除の御礼のため、町民一同に代って参じましたもので――」
とのことだった。そして、祝福の意を表するため、
「御合戦の大勝利をお祈り申しあげ、併せてお門立ちのお祝いまでに――」
と、手製の粽を献上した。
これらの者を迎えて、扈従の将星を左右に繞らし、悠然と床几に倚っている光秀のすがたには、まさに新しき「天下人」たるの威風に欠けるものはなかった。
侍座の一将は、京都市民のよろこびと、献上の粽とを、光秀の前に披露して後、一同へ向って、
「洛内の取締りは、厳に戒めてあるが、なお日も浅いゆえ、さまざまな流言も撒かれ、陰にあっては、御行動を誹謗し奉るような説をなす者もあろう。しかし政をなす主権者に悪行あるときは、それを廃せし例は、わが朝のみならず、唐土にもあることで、周武がその主紂王を弑し、諸民の困窮を救い、周の八百六十年の基を開いたのを見てもわかろう。わけてわが日の本は上に万代不易の大君がおわしての武門であり、将軍職でもあれば、決して一信長が絶対の天下人でなければならぬ理由はない。汝らも、この辺をよく弁えて、市民の者が妄説に惑わされたりすることのないようによく努めい」
と、申し渡した。
光秀も、一言与えた。そして折角、志の粽だからといって、彼らのいる前で、そのうちの一つを取って喰べた。
ところが、剥ぎ取った粽の笹が、まだ少しこびりついていたとみえて、光秀は横を向いて舌のさきからベッと吐き捨てた。
「――あかんぜ、あの御大将は。きっとあきまへんぜ」
帰り途。口さがない京童の性を持っている代表たちは、口々に語り合って行った。
「粽の皮はよう残るもんじゃ。それをよう見もせず口に入れるような大将ではあきまへんわい。戦いは明智方の負けでっしゃろ」
このことを、後の諸書が、みな誇称して、光秀が粽を笹の皮ぐるみ喰ったというように伝えているが、恐らくこの程度に過ぎない小事であったろう。
けれど京都人は由来、人に接すると、そうした小事を見つけて、すぐ相手の寸尺を量る性癖をもっている。中原へ中原へと、古来から多くの武門が侵入して来ては没落し、あらゆる有為転変を、いつも被治者の立場から長い眼で見て来たため、自然養われて来たものかと思われる。
桂川
法体の施薬院秀成が、
「惟任どのにお目にかかりたい」
と、下鳥羽の本陣を訪ねて来たのは、京都町民の代表者たちが、そこを辞してから間もない頃だった。
光秀は、藤田伝五、その他四、五の将を交えて、兵糧をつかっていた折である。
伝五の報告で、筒井の変節はもうあきらかだったが、なお順慶の余りなる豹変ぶりには、ここでも諸将の憤りのたねとなって、武門の風上にも置けぬ男と罵られていた。
そこへの取次であった。
「はてな、施薬院が?」
光秀は眉をひそめた。施薬院は本能寺変の少し前に、信長から中国の陣へ差向けられていた者である。
「ま、通せ。――ともかく」
気のゆるせぬ心地もするが、また多大な感興と好奇も抱いた。秀吉の近状を知る者として、絶好な便りとも考えて面会したのである。
「まずは、御健勝で」
と、施薬院は事もなげに平常どおりな挨拶をのべた。信長のことにはすこしも触れて来ないのが、光秀には何となく痛痒い気がした。
「お許は、中国へ下ったばかりと聞いていたが、どうして、にわかに立ち帰って来たか」
「筑前どのが、直ちに、京都へ攻め上られるため、われらの如きは、足手纏いと思し召されたのでしょう。急に、お暇を下されたので、早々立ち帰って来たわけでございまする」
「なるほど……ムムム」
と頷いてから、ほんの言葉のつぎ足しに過ぎないような語調で、
「筑前は達者か」
と、訊いた。施薬院も、至極、無造作に、
「はいはい、いよいよ頑健な御様子に見られました」
と、答え、
「あのお方の御精力というものは底がわかりません」
と、問われぬことまでいった。
「筑前には早や、毛利と和睦して、北上の途中にあると聞くが、お許がこれへ来る頃には、どの辺まで来ておったか」
「何を仰せられます」
施薬院はその迂を嗤うように、
「もはや、ついそこの、尼ヶ崎まで来ていらっしゃいます。それも今朝ほどのことです」
「えッ……?」
「まだ御存じなかったので」
「先鋒ではないのか」
「おそらく先鋒の方がおくれたでしょう。筑前どの自身、紛れもなく着いております。途中の風雨も陸路船路も、ほとんど、不眠不休のおいそぎ方で」
「……そ、そうか」
語気やや紊れるのを、光秀は強いて沈着をよそおいながら、
「尼ヶ崎では面会いたしたか」
「余りに夥しい軍馬を見、わざと通り過ぎて参りました」
「兵数は」
「わかりませぬ。武家なれば目づもりでも知れましょうが」
「尼ヶ崎へは立ち寄らず、この下鳥羽のわが陣へ立ち寄ったのは、何か用向きがあってのことか」
「中国でお暇をいただく折、日向守に会うたら申し伝えよと、筑前どのからお言伝てを頼まれておりましたので――」
「筑前からこの光秀へ言伝てとな? ……。おもしろい。何と云いおったか」
光秀は異常な昂奮を抱いた。人をもって言伝てして来たことばといえ、まさにそれは、敵将の決戦状ともいえるものと思ったからである。
施薬院は、次のように、それを伝えた。
「中国でお別れする折、道中用心のためにと、私へ手ずからお槍を一本下された上。――さて、筑前どのがいわれるには、その方は仕合せな仁じゃ、いずれ光秀と会うだろうが、このところ、後の天下は、光秀が取るか、自分が取るかだ。その両将のいずれにも心証のよいその方の家はまことに安全を保証されているものといわねばならん。――ついては、自分より先に光秀に面会いたした折は、筑前がかく申しおったといえ。……そう仰せられまして」
と、施薬院は、ここでちょっと、額の汗を、懐紙で軽くたたいた。そして秀吉の口吻そのままいった。
「――日向守とは毎度会いはいたして来たが、戦場で会うは初めて。大将と大将とが、直の太刀打ちいたすも、数日のうちにある。主君の敵なれば、部下の槍も待たず、かならず直の太刀打ちいたして、勝負を決すであろう。日向にも左様に心得おられ候え――と、かように屹と仰せられました」
「…………」
光秀はあきらかに感情をうごかしている。しかしじっと押し黙って聞いていた。がやがて、その硬直を解くと、しずかに一笑を見せて、
「筑前が云いそうなことよの」
と、立って、うしろに立て懸けてある槍を取り、施薬院に与えて、こう云い足した。
「言伝てたしかに聞いた。大儀である。――秀吉からも一槍を貰うたそうだが、わしからも贈ろう。洛中はまだ物騒じゃ。供の者に持たせて、用心怠りなく帰るがよい」
施薬院が辞去した頃は、すでに下鳥羽は宵だった。風が出て、雲脚が迅くなりかけている。
「暗いぞ。気をつけて参れよ」
光秀はそれを見送って、陣外の丘の端に佇んでいた。――が、彼を送るのが主ではなく、白眼、天を仰いでいたのである。
「降りそうな……」
と、彼は独りつぶやいた。この風では降りもしないかと思われる一方に出た呟きだった。戦いに臨まんとするや、まず気象を見定めておくことは将の肚として重要である。光秀はかなり長く雲のうごきや風の方向を案じていた。
さらに、脚下の淀川を見た。
チラチラ、と風にそよぐ小さい灯は、味方の哨戒舟であろう。大河のうねりは白く、山崎その他、摂津一円は、ただ漆にひとしい闇でしかない。
「筑前風情が、何ほどのことを! ……」
この河の、はるか海口、尼ヶ崎の空へむかって光秀のひとみが、光芒を放ったようにすわったとき、彼のくちびるはかつて吐いたことのない強い語気をもらした。
「作左。作左。作左衛門はおらぬかッ」
彼のすがたが大股に身をひるがえして元の営内にもどって行くとき、暗い烈風は、しきりに附近の幕舎に大きな波を立てていた。
「はいッ。堀与次郎、おりまする」
「堀か。そちでよい。すぐ貝を吹け。――全軍に出陣の用意をと」
陣払いの終るあいだに、光秀は洞ヶ嶺、伏見、淀、その他の味方へ、急使を派した。遠くは、坂本城にある従兄弟の光春へも、
(――退いて防がんよりは、前進して彼を邀撃、一戦に大事を決せん)
の覚悟を告げて、その来援を促して発したのである。
夜は二更。星ひとつ見えない。
軽捷な戦闘隊をまず丘から降ろして、桂川の上下を見張らせ、荷駄、本隊、後軍とつづいた。
驟雨が来た。全軍、渡河を半ばにしつつ、真っ白な雨に打たれた。
風も伴っている。西北の冷たい風だった。暗い川上を望みながら足軽たちはつぶやいた。
「この川の水も、この風も、丹波の山を越えて来たものだ」
昼ならば見えもしよう。老坂も遠くはない。その老坂を越え、丹波亀山の故郷もとを出て来たのは、つい十日余の前だったが、彼らには、三年も四年も前のことだったように回顧された。
「溺れるなよ。火縄を濡らすなよ」
部将は、組々の者へ注意していた。山岳地方は、大雨だったにちがいない。桂川の水勢は常よりも烈しかった。
槍隊は、槍と槍をつなぎ持ちにして渉り、鉄砲隊は銃座と筒口を持ち合って越えた。
光秀をかこむ騎馬の一隊は、迅い水泡を残して対岸へ上がっていた。どこともなく前方の闇でパチパチと湿っぽい銃音が断続して聞え、民家の火か、単なる篝か、遠くに火花が見えたが、小銃の音が止むと同時に、それらの閃きも消えて、真の闇に還っていた。
「お味方の先駆が、敵の斥候隊を追い払ったものでござります。火花もまた、円明寺川附近の農家へ、敵の小勢が、逃げるに当って、火を放けたのでしたが、直ちに、消しとめました」
伝令将校から報告がある。
光秀は意に介するなく、久我畷をすすみ、味方の勝龍寺城には入らず、わざとそこから西南方約五、六町ほどの御坊塚に本陣をさだめた。
この二、三日の天気癖である雨はすぐ霽って、墨を流したような濃淡を見せている空に星すら燦めき出している。
「――敵もしずかだの」
光秀は御坊塚に立つと、山崎方面の闇を一望して呟いた。
すでに秀吉の軍と、わずか半里を隔てて相対したと思う無量な感慨と緊張とが、その語の底に大きく呼吸をしていた。
ここを全軍の基点として、勝龍寺を後方の補給兵站基地とし、さらに西南方の淀から円明寺川の一線を扇なりに引いた。前衛各部隊をそれぞれ配し終った頃――夜はすでに明け近く、淀の長流もほのぼの所在を描き初めていた。
突然。
天王山の一面に烈しい銃声が谺し出した。陽はまだ昇らず、雲は暗く霧は深い。天正十年六月十三日。山崎街道にもまだ一馬のいななきすら聞えない時刻であった。
火ぶた
両軍が山崎に会して、この晨を、生の日か死の日かと期して相対峙したとき、秀吉から光秀へ「戦書」を送ったとも伝えられているが、果たして、そういう余裕があったかどうか。
また、そうした古法の陣押しによって、接戦の口火が切られたかどうか。
事実は。
光秀もまた御坊塚に着陣して間もない頃。また秀吉も、まだ後方の富田に在って、大坂から神戸信孝の来会あるを待っていた――十三日未明――まだ暗いうちに、期せずして、秀吉方の山之手隊と、明智軍の奇襲部隊とは、暁闇のうちに、もう激烈なこの日の序戦に入ったのである。
――今しがた。
天王山方面に聞えた烈しい銃声がそれである。夜来、折々湿っぽい小銃音の小ぜり合いはしていたが、このときのものは、
「すわ!」
と、耳あるほどな者はみな毛穴をよだてて、やがての戦況如何にと、彼方なる雲か山かの一山影を凝視していた。
北軍光秀の陣営御坊塚から見るときは、天王山はここから約二十余町の西南にあって、その左の麓に、一すじの山崎街道と、一条の大河とを擁している。河はもちろん淀である。
山頂はかなり高く嶮しく、最高二千七百尺はある。別名をこもりの松山ともいい、宝寺の山ともいう。峨々たる岩山で、全山、松の木が多い。
――きのう秀吉の本軍が富田大塚附近まで進出すると、麾下の諸将はみなまッ先に、この山に目をそそいでいた。
「あれは何山というか」
「あの東麓が山崎の駅か」
「敵の勝龍寺は、あの山の、どの辺の方角にあたるか」
など口々に土地の案内者に問いただしていた。
地理に詳しい者を陣中に伴うことは、どの隊でも必携の具としていた。それに問うて、天王山の軍事的価値に目をつけたこともまた、多少戦略眼のある人々のあいだではみな一致していた。
「あすの合戦はあの山を先に占めて、高地から敵を俯瞰して打つの有利に立った方がまず勝ちであろう」
また必然、諸将の胸には、
「――先駆けて遮二無二、天王山にお味方の旗を立てた者こそ平野の一番首よりも、戦功第一の誉れたらん」
と、ひそかに期するものがあったので、十三日の前夜、それを秀吉に献言し、或いは、みずからそこに赴かんと願い出た諸将が、幾人もあったらしい。
「いずれは明日一日できまる戦いと観る。淀、山崎、天王山を中心に、死ぬも生きるも、およそ数里の外には出まい。われと思わんものは行け。ただし、味方争いするな。わたくしの功を競うな。ただ念ぜよ。故右大臣信長公の在天の霊と、弓矢八幡の照覧を」
が、秀吉のゆるしを得るや、勇躍して、真夜中のうちに、ここを立って天王山へ長駆したもの、鉄砲大将の中村孫兵次、堀秀政、堀尾茂助など、黒白もわかぬ一勢であった。
南軍秀吉の麾下がみな目をつけた重要な地点を、北軍の光秀が、迂闊に見のがしているわけは絶対にない。
光秀が、長駆、桂川を渡って、にわかに御坊塚まで出る決断をとったのも。
――同時に天王山を占めて。
と、作戦態勢をすでに描いていたればこその行動だった。
この辺の地理に明るいことにおいては、敵の先鋒の中川清秀や高山右近にもゆずらない光秀でもある。かつは、同じ山河の地勢を観るにしても、光秀の観るところおのずから彼ら以上のものを観ていよう。
で、光秀は、桂川を越えて、久我畷を行軍中に、もうその途中から一軍を割いて、
「下海印寺村を北に見、天王山の北側より攀じ登って、山上を取れ。敵襲せ来るも、構えて、要地を譲るな」
と、激励して、そこへ送っていたのであった。
命をうけた者は、勝龍寺城にいた松田太郎左衛門で、並河掃部の配下であり、この辺の地理に精通しているところから特に選ばれたものである。
松田太郎左衛門は、弓鉄砲組をあわせ、約七百余の兵をひきつれて急いだ。
ずいぶん迅速といわねばならない。光秀の司令も行動も、決して戦機を外してはいなかったのである。
にも関わらず、この時すでに、南麓の広瀬方面を突破して来た秀吉の諸勢は、先を争って、山へ取ッついていた。
しかし、なお真ッ暗な時分であるし、土地に不案内の将士が多い。
「登り道がある」
「そこは登れまい」
「いや、登れる」
「間違った。このさき、崖だ」
などと麓を巡って、各々攀路を捜り合うにあせっていた。
ここまではほとんど後先なく、一斉にかたまって来た堀秀政の隊、中村孫兵次の隊、堀尾茂助の隊なども、忽ち分散して、あなたこなたに、石ころを落し、灌木を掻き分け、騒然と、麓一帯に物音を起しているに過ぎなかった。
さきに――前日の昼――先鋒部隊を命じられて、山崎まで出ていた高山右近と中川瀬兵衛の陣も、ここから近いのである。
わけて瀬兵衛は、高山右近に先んじられて、山崎の町から関門の閉め出しを喰って、この山之手方面へ陣していたので、忽ち味方の奇兵的行動に感づいた。
「そこの要地たることは、此方とて気づかぬではないが、筑前どのの命令もまたず、みだりに逸まった行動を起してはと、ふかくみずから慎んでいたのだ。――さるを、後方にひかえていた諸隊が、われらにも無断で、先駆けするとは怪しからぬ。その分なれば、瀬兵衛とて、彼らごときにおくれるものではない」
憤然と、旗本数名、銃士わずかを連れたのみで、山麓から数町上の宝寺へ駈けあがって行った。
この道こそ、唯一の登り口で、あとは容易に頂へ行けない樵夫道にすぎない。瀬兵衛は、それを知っていただけに早かった。しかし宝寺の門前まで近づいてみると、もう先に来て、そこの山門の扉を、大声あげながら叩いている一群の武者があった。
「誰だッ。味方か」
瀬兵衛が、声をかけると、山門の下の人影は、振り向きもせず、
「問うもおろか」
と、答えた。
これは堀尾茂助の声だった。
茂助吉晴は、いまでこそ、錚々たる羽柴麾下の一将だが、その青年期までは、岐阜の稲葉山つづきの山岳中に育った自然児である。彼の眼をもって見るときは、この天王山の如きは、ほんの一小丘としか思われないにちがいない。
「寺僧、起きろッ。山門を開けぬと踏みやぶるぞ」
堀尾の部下は、そこを叩きつづけている。戦いを予感して、寺内ふかく潜んでいた僧は、やがて紙燭を持って出て来た。そして山門をあけるや否、どこかへ隠れてしまった。
「つかまえろ、一名、道案内に――」
瀬兵衛たちが、それを求めているうちに、堀尾茂助の主従は、十数名しか見えなかったが、わき目もふらず境内を駈けて、裏山の道へのぼっていた。
瀬兵衛は、それを見送って、舌打ちしながら、捕えた僧を追い立てて、
「山上まで、案内せい。早く早く」
と、槍で脅していた。
とこうするうちに、山崎の町に陣していた高山右近の部下までこれへなだれて来た。――実にこの未明に行われた天王山先陣の士気の烈しさには、味方と味方のあいだにおいてすら相ゆるさぬものを互いに示していた。
味方と味方の負けじ魂は、時にきわどい摩擦を起こすし、全戦局を過るような危険もなしとはしないが、さりとて、この気魄もないような気魄では、敵と相見えても、直ちに、霊魂そのものとなって、身を投げこむことはできない。
功を競うべからずであるが、男は各々磨き合え、恥はたがいに恥と知れ、というのが秀吉のこころであったろう。
とまれ、この暁闇中天王山一番駈けは、いったい誰が早かったのか、どこの部隊が先駆だったのか、ほとんど我武者羅のあらそいで、後の軍功によるも、記録によるも、皆目、見当がつかない。
ISO 639-1コードjaは言語名Japaneseを表します。堀、堀尾、中川、高山、中村各家それぞれ自家の先登をその家の記録には主張しているし、「堀家家譜」「川角太閤記」「池田家譜集成」「武功雑記」「明智軍記」などの諸書の記載も、また、みなまちまちになっている。
しかし、想像に難くないのは、いずれにしても、逸早く山上近くに達した人数は、各隊のうちの極めて少数だけで、それも一将の下の一隊と限らず、諸将の部下が交じり合って、偶然、早足者だけの混成部隊となっていたろうと思われることである。
道は嶮しいし、夜はまだ明けないし、味方には違いないが、誰の手勢やら組やら分らない中に伍して、ここの将士はただえいえいと山上へ急いだのだった。そして、はや頂上も近いかと思われた頃、いきなり方角も知れないところからつるべ撃ちに弾をうけた。
撃ち出したのはもちろん明智方の松田太郎左衛門の銃隊である。
しかし、松田勢が先に火ぶたを切ったからといって、天王山の山上を先に踏んだのは明智方であったかといえば、そうはいえないものがある。
なぜならば、それよりずっと前に、羽柴方の侍、山川七右衛門、山川小七、岸九兵衛の三名が、こっそりそこへ登っていた。そしてまだ人気なき山上や麓の闇を見下ろしながら、
「この要地を真ッ先に乗っ取った者は恐らくわれらが一番であろう。この三名を措いてはあるまい」
と、遅れている味方や、まだ気配もない敵の静かさを嗤っていた。
すると、どこやらで、
「やかましい。黙ってその辺に身を伏せておれ」
と、叱った者がある。
驚いて、あたりを見廻すと、何ぞ図らん、自分たちより先に、この山上に来て、岩陰にうずくまり、居眠りをしていた男があった。
「誰か」
と、訊くと、
「高山右近の手の者、中川淵之助重定」
と、答え、
「貴公たちが、がやがやいうので、折角、敵が来るまで一睡りと思っていたのに、眼をさまされてしもうたではないか。ただ高い所へ登っただけでは、てがらでも何でもない。お互いにてがらを談じ合うていいのは、明智を全滅してからのことだろう。まだ勝敗もわからぬうちに、はしゃぐのはちと早過ぎはせんかの」
ひどく愛想の悪い男である。こうぶつぶついうと、彼はまた自分の膝を抱えて居眠りを始めている。
しばらく経つとここへまた、中川家の臣、阿部仁右衛門も登って来た。二人の鉄砲足軽も一しょだった。――で、山上にはこの頃すでに七名の羽柴方がいたわけだった。
そのうちに麓の宝寺やその他の方角から、味方の大勢の声がかすかに聞えて来たし、同時に――ほとんど同じゅうして――北側の下海印寺方面からも、すさまじい勢いで、明智方の松田隊七百が、これも先は、先頭、後は後、隊伍の順もなく、先登を争って、あらしの如く駈け登って来た。
Next sentence.「まだ撃つな」
例の仏頂面した中川淵之助は、あだかも自分が、この手の指揮者でもあるように、逸りかける他の六名を戒めて云った。
「――ずんと敵をそばまで引きつけてから一度に撃て。この下の道の曲り角に、白いものが見えるだろうが。あれは俺が松の枝に括しつけておいた白鉢巻の小布だ。銃の標的をあの下に狙いさだめておけ。そして敵の影がそこを曲って来たら、途端に浴びせかけるのだ」
小面の憎い味方だが、云い分は良策だし、頼もしいところもあるので、みなその言に従って、敵の来るのを、待ち構えていた。
ところが、松田太郎左衛門の先鋒隊は、まだ山上に間のある八分所からはや後方の山腹に羽柴勢の影を認めたので、忽ち機先を取る戦法に出て、一斉に銃火を浴せかけたのであった。
当然、羽柴方も応射した。
しかし、これはまだ距離も距離だし、暗くもあり、敵味方とも極めて目標の不的確な気勢射撃に過ぎなかったので、どっちに取っても、大した効はない。
むしろ、七名の小人数ではあったが、この途端に、山上から数百歩駈け下りて来て、明智兵の影を認めるや否、銃先下がりに撃って来たわずかな弾丸のほうが、はるかに奇効を奏した。
最初の七発の弾のうち、三弾は確かに敵を仆した。のみならず多寡はともかく頭上に羽柴勢の現われたことは、明智勢をして少なからずあわてさせた。敵の顔まで見える距離で敵を見たのは、この大決戦において、この一瞬が初めてであったのだから、全隊が一時ぎくと衝撃をうけたことには相違ない。
敵の形相も、阿修羅の姿も、戦いが酣となって、自分もそれとなったときは、何でもないものであるが、もっとも不気味なのは、初めに接近したときである。
その刹那には、敵と名のついた者は、人にもあらぬ悪鬼か羅刹の如き感じがするものだった。しかしこれは、敵方が視る心理も同様なのであるから、その殺気に眩いをせず、日頃の丹田で、沈着に押し迫った方が、序の勝口を取ることはいうまでもない。
松田隊の先頭には、主将の太郎左衛門はいなかった。太郎左衛門の部下の将、辻義助が指揮に立って来たものである。義助は、よく肚もすわっていた侍とみえ、すぐ奇襲の敵が六、七人に過ぎないことを看破して、
「騒ぐな。小勢だ」
と、不利な低地を取っているため怯みがちな味方を励まし、
「銃口をみなあの上の岩角にあつめろ。一斉に撃て」
と、呶鳴った。
少なくも、七、八十挺はあろうかと思われる鉄砲の影がうごいた。それが皆、ひとつ焦点へ銃口を向けたのである。上の岩頭に立っていた七名は、当然、蜂の巣となるべき的に位置していた。
――と。中川淵之助は、他の岸九兵衛、阿部仁右衛門、山川兄弟などに対って、
「間に合わん。俺は突ッこむぜ」
云い捨てると、鉄砲を捨てて高きから低き敵へ、猛然駈け向って行った。
一弾放つと、一弾こめて、火縄を点じ関金を引くまで、かなりの時を要するのが、この時代の火器のどうしてもまぬかれ難い弱点だった。
殊に、明智方の銃士は、桂川を渉るとき、驟雨のために、だいぶ装備を濡らしている。中には幾筋もの切火縄がみな役に立たず、後に退っている者もいた。
その虚を衝いたのである。淵之助に倣って、阿部仁右衛門も岸九兵衛も、劣らじと、捨身に出た。パパパッと慌てた弾煙が立った。こう撃つ弾は中っていないこと確かである。淵之助の陣刀は、もうそこらの敵を薙ぎ分けていた。山川七右衛門の弟小七は、素手で取っ組んでいた。槍を向けて来た敵がいたので、その槍欲しやと奪いにかかったためである。