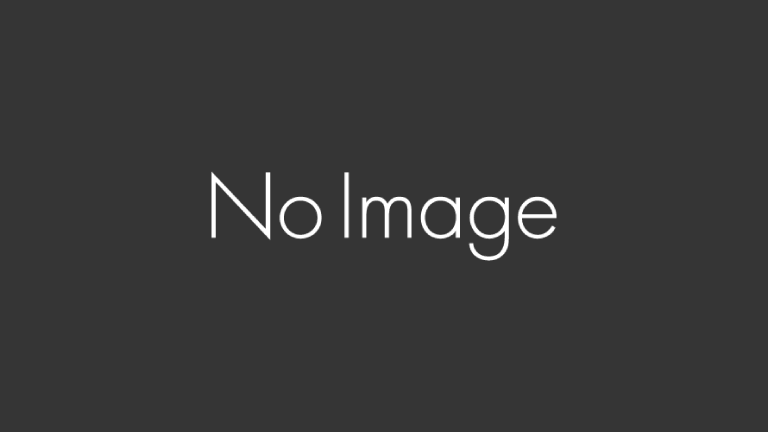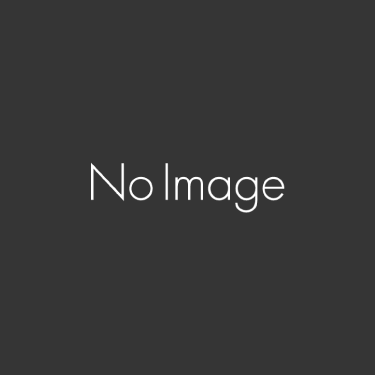作品紹介
「烏」について
「烏」は、山本周五郎による短編小説です。雪深い山奥を舞台に、幕末から明治維新にかけての激動の時代に翻弄される人々の姿と、純粋な少女と一羽の烏の絆、そして悲劇的な運命を描いています。
物語は、尊皇攘夷を掲げる若き志士と、彼を匿う少女、そしてその家族を中心に展開します。時代の波が静かな山里にも及び、登場人物たちはそれぞれの立場や信念、そして人間的な情愛の間で葛藤します。山本周五郎特有の、市井の人々の生き様や人情の機微を鋭く、かつ温かい眼差しで描く作風が際立っており、短い物語の中に深い感動と余韻を残します。
特に、言葉を真似る賢い烏「勘太」の存在は、物語に独特の彩りを与えるだけでなく、人間世界の厳しさや悲しさを際立たせる役割も担っています。忠義、犠牲、家族愛、そして人間と動物との間に通う純粋な心といったテーマが、美しい自然描写とともに織りなされ、読者の心を打ちます。
作者: 山本周五郎について
山本周五郎(やまもと しゅうごろう、1903年 – 1967年)は、日本の小説家。本名は清水三十六(しみず さとむ)。数多くの時代小説、歴史小説を手掛け、庶民の哀歓や武士の生き様を、人間味豊かに描き出しました。「樅ノ木は残った」「赤ひげ診療譚」「日本婦道記」など、映画化やドラマ化された作品も多数あります。
大衆文学作家として広く親しまれながらも、その文学性は高く評価されており、直木賞の候補に何度も推されましたが、本人は受賞を固辞し続けたことでも知られています。「季節のない街」で芸術選奨文部大臣賞を受賞しましたが、これも辞退しました。読者のために書くという姿勢を貫いた作家です。
主な登場人物
-
お文 (おぶん)
物語の主人公の一人。十七歳。美作国津山の城下から三里ほど北の鷲尾山中腹で、猟師の父と暮らす心優しい少女。拾ってきた子烏の勘太を可愛がっている。純粋で情け深く、追われる身の金之助を匿う。
-
勘太 (かんた)
お文が育てた烏。非常によく懐いており、人の言葉を巧みに真似る。物語の重要な局面で、その能力が思わぬ形で影響を与える。お文への忠誠心が強い。
-
太兵衛 (たへえ)
お文の父親。「野猪の太兵衛」と呼ばれる猪狩りの名人。乱暴で強情な一面もあるが、娘のお文には優しい。幕府寄りな考えを持つ。物語の終盤で悲劇的な決断を下す。
-
梶 金之助 (かじ きんのすけ)
十五歳の少年。京都の土佐屋敷にいる足軽の子で、勤王方として活動している。津山藩の動向を探るために訪れ、追手に追われて深手を負い、お文に助けられる。純粋で正義感が強い。
-
追手の侍たち
津山藩の侍。金之助を勤王浪士の手先として追っている。威圧的で、目的のためには手段を選ばない。
あらすじ・本文・動画
あらすじ
美作国鷲尾山の雪深い山中で、猟師の父・太兵衛と暮らす十七歳のお文は、ある吹雪の夜、傷ついた少年・梶金之助を匿う。金之助は勤王の志士で、津山藩の侍に追われていた。お文の機転と、彼女が飼う烏・勘太の言葉の模倣によって、追手の危機を一度は逃れる。
しかし、父・太兵衛は金之助にかけられた懸賞金と自身の立場から、非情な決断をする。お文は金之助を逃がそうとするが、その父の企みに気づき、金之助を救うため自ら犠牲となる悲劇が訪れる。
数年後、明治の世になり、陸軍中尉となった金之助が恩返しのためお文の家を訪れるが、そこは廃屋と化し、お文の悲しい最期と太兵衛の失踪を知る由もなかった。ただ、勘太だけがお文の墓を守るように、いつまでもその場を離れなかった。
オーディオブック動画
本文を読む
一
「おい、お文、起きねえか」
「………うるさいわよ」
「起きねえか、もう夜が明けたぞ」
「お黙り、勘太」
お文は粗朶を折って切炉の火へくべながら、振返って叱りつけた。
「おまえ、お馬鹿さんよ、まだ日が暮れきりじゃないの。町へ行ったお父っさんだって帰って来ないし、おまえ、鳥のくせに昼間と夜の区別もつかないのね」
「くうくうくう、かっ」
柱の止り木にいた鳥の勘太は、お文に叱られたのが恥ずかしいとでもいうように、ひょいと身をすくめながら畳の上へ飛びおりた。
外は雪である。
時おり、樹の枝から雪塊の落ちる音が、ばさっ、ばさっと聞える他には、ひっそりとして物音もない静けさだ。
お文は十七になる。……父親の太兵衛は猟人で、「野猪の太兵衛」と云えばこの附近で知らぬ者はない、猪狩りの名人であると共に、乱暴で強情で、いちど暴れだしたら手がつけられない男だった。けれど娘のお文にだけは、荒い声もかけられぬ優しい父で、どんなに乱暴をしているときでも、お文の顔を見ると仔猫のように温和しくなるのが例であった。
此処は美作の国津山の城下から、三里ほど北へ入った鷲尾山の中腹で、昼でも人の通ることなどは稀にしかない、まして冬のあいだは雪に埋れて、十日も二十日も人の声を聞かずに過すことが珍しくなかった。……お文は此処で生まれ、此処で育って来たのだけれど、感じ易い乙女心に変りはなく、独りで留守をする晩などはしみいるような淋しさに襲われる、……そんなとき、少しでも慰め相手になるようにと、去年の夏太兵衛は一羽の子烏を拾って来て与えた。
まだ巣立ったばかりの雛であったが、お文は直ぐに「勘太」という名をつけ、片時も肌から離さぬように可愛がって育てた。……勘太もよくお文に懐いた、まるで赤子が母親のふところを慕うように、どんなときでもお文の側から離れない、殊にこの頃は人の言葉をよく真似るようになって、ふと太兵衛の口真似などをしては、お文を笑わせるのであった。
「……お父っさんのおそいこと……」
お文は炉に懸けた芋粥鍋の蓋を直しながらふと呟いた。……獲物を町へ売りに行ったまま、もう七時を過ぎたのにまだ太兵衛は帰って来ない、
「なにか間違いでもあったのじゃないかしら」
そう呟いたとき不意に、
がらがら、どしん。という烈しい物音が台所で起った。……お文は勘太が悪戯をしたものと思って、
「まあ、嫌よ勘太、またなにかお悪戯ね」
と云いながら立って障子を明けた。見ると水口の戸が明いて、雪まみれになった少年が、のめり込んだ姿のまま倒れている、お文はぎょっとして立ち竦んだが、これはきっと道に迷って来たのだと思い、急いで側へ寄りながら、
「あなたどうなさいました」
と肩へ手をかけて云った。
少年は顔をあげた、色の白い頬が緋牡丹の花を散らしたように血に塗れていた。……お文が思わず震えながら身を退くと、少年はその裾へ縋りつくようにして、
「お願いです、暫く匿って下さい」
と嗄れた声で云った、「私は悪者ではありません、けれども訳があって追われているんです、どうか暫くのあいだ隠れさせて下さい」
お文は少年の眼を見た。
いい眼である、勘太が餌をねだって身をすり寄せるときのような、濁りのない、青みのさした美しい眸だった。
「……さあお立ちなさい」
「隠して呉れますか」
「大丈夫きっと匿ってあげます」
「有難う、恩に着ます」
少年は感謝の籠った眼でお文を見上げた。
手を貸して援け起してみると、少年は右の高股にも刀傷を受けていた。……抱えるようにして炉端へ連れて行ったお文は、父親が猟に出るとき持って行く薬箱を取出し、馴れた手つきで直ぐに傷の手当をした。
「こんなひどい怪我をしていて、よく此処まで来られましたのね」
「なにをこんな傷ぐらい」少年は薬がしみるので眉をしかめながら、けれど元気な声で云った。
「天子さまのために、少しでもお役に立つと思えば、足の一本や片腕ぐらい取られたって平気ですよ」
「まあ、……ではあなたは」
「ええ私は天朝さまのために働いているんです」
少年は昂然と額をあげて云った。
二
「津山藩がどう動くか、禁裏さまへお味方をするか幕府へ付くか、その様子をさぐるために来たんです。……お姉さんは勤王方でしょう」
「ええ。ええ。そうよ」
「そうだと思った。さっきお姉さんの顔を見たとき直ぐに、きっと天子さまのお味方だと思いましたよ」
「あなたは幾つになるの」お文は少年に見詰められるのが苦しそうに、睫のながい眼を伏せながら訊いた。
「私は十五です、名は梶金之助」
「……金之助さん」
「京都の土佐屋敷にいる足軽の子です」
「十五くらいの年でよくそんなお役に立つことができるわね、やっぱりお侍さまの子だわ」
「侍の子でなくったって」
金之助は肩をそびやかしながら、「……誰だって今はお国のために働くべき時ですよ、私たちの友達もみんな働いてます。女だって年寄だって、みんな起ちあがってお国のためにお役に立つべき時なんです。……もう直ぐだ、幕府を倒して、もう直ぐ天子さまの日本になるんだ、もう直ぐ新しい日本の陽がさしてくるんですよ」
そう云って少年は固く唇をひき結んだ。
津山藩の松平慶倫は徳川親藩の一人であったから、領民たちの多くは幕府の恩顧を重んじ、勤王の正しいことを解しない者が多数を占めていた。……殊にお文は、父親の太兵衛が日頃から歌を唄うように、将軍さま将軍さまと云うのを知っているので、父が帰って来て若し金之助の正体が分ったらと思うと、考えただけでも胸の震える感じだった。
「……ねえ金之助さま」
お文はようやく傷の手当を終りながら、
「あたしには、あなたが立派なお役に立っている人だということが分るけれど、此処は徳川の御親藩でしょう、だから」
「だから世の中のことをよく知らない人たちは、あなたの立派なお役目が分らないと思うの、殊にこんな山の中に暮している者は、御領主さまの他に偉い人はないと思っているんですから。……若し父が帰って来ても今のお話は内緒にしていて下さいましね、でないとどんな間違いが起るかも知れませんから」
「知ってます、私だってこんなことを人の見境もなく云いはしません、お姉さまなら……よく分って下さると思ったから」
「お文、帰ったぞ、帰ったぞ、お文」
いきなり勘太が叫びだしたので、思わず二人はぎょっとして振返った。
……その驚いた様子が面白いとでもいうように、勘太は隅の方でばたばたと羽搏きをしながら、
「くうくうくう、かっ、かっ」
と喉を鳴らした。
「馬鹿ねえ、吃驚するじゃないの勘太」
「いまのは……あの鳥ですか」
「ええそう、よく人声を真似るでしょう、あたしが馴らしましたの。……勘太、納戸へ入っておいで、おまえお客さまに失礼よ!」
そう云っているとき、この家の表へ人の近づく気配がして、
「お文、帰ったぞ」
と呼ぶ声がした。……いま勘太が真似たのとそっくりの声である。
「大丈夫、お父さんですわ」
お文が金之助に云って立ちあがると、雨戸を明けて、雪まみれになった太兵衛が入って来た。お文は急いで蓑笠を脱がす手伝いをしながら、「お父っさん、お客さまがあるのよ」
「誰だ、……見馴れねえ人だが」
「院庄の武家屋敷へ御奉公していた人だよ、国許からお母さんが急病だという知らせが来たのに、お屋敷ではお暇を呉れないのですって、それで逃げだして来たのだけれど、……途中で転んで足に怪我をなすったのよ」
「それはお気の毒な、……傷は重いのか」
「いまお手当をしてあげたわ、今夜ひと晩泊めてあげたいのですけど、いいわね」
「そんなこたあ訊くまでもねえ」
「それに、……そのお屋敷から追手が掛っているのよ。いいえ、なにも悪いことをした訳じゃないの、約束の年期が切れないのに逃げだしたっていうので、それで追手を寄越したんですって」
「そんな無道理なお屋敷が今でもあるのかなあ、お侍の家風もだんだん悪くなるばかりだ。……湯をとって呉んな」
「はい唯今。……お父っさん、その追手が来たら匿ってあげて下さいましね」
「いいとも、おらに任せて置け」お文が洗足盥へ湯を汲んで来たとき、……坂を登って来る四五人の人声が聞えた。
「あ! 追手だわ」お文は盥を其処へ置くと、「金之助さま、早く」
「お、納戸へ入れてあげろ、空き葛籠の中へ入って、壁にある熊の皮を上から……」
上へ駆けあがったお文は、金之助を援け起して納戸へ入って行った。
三
「明けろ、明けろ」
雨戸を叩きながら呼び立てる、そのひと声ずつがお文には、まるで胸へ錐を揉込まれるように思えた。
「明けないか!」
「どうぞお明け下さいまし」太兵衛はお文に手伝わせて、態とゆっくり足を洗いながら云った。
「山家のことで別に鍵もございませんから」
半分まで聞かず、荒々しく戸をひき明けざま、五人の侍たちが土間に入って来た。
「なにか御用でござりますか」
「……此処へ少年が一人来た筈だ」先頭にいた一人が、簔の下で大剣の鍔元をぐっと握りながら云った、
「我々は足跡を跟けて来たのだ、この雪で他へ行く筈はない、来たであろうな」
「隠しでもするとその方共のためにもならんぞ」
「何処にいる、出せ!」
侍たちの喚きたてるのを、太兵衛は静かに聞いていたが、
「この通り狭い山家で、隅から隅までお見通しでございます、わしもいま町から帰って来たばかりですが、……その足跡というのはわしのではございませんか」
「黙れ、そんな子供騙しに乗る我々ではない」
「ええ面倒だ、家捜しをしろ」
止める隙もない、そう叫ぶと共に、五人の侍は土足のまま上へとび上った。……見るなりお文はあっと声をあげようとしたが、太兵衛はそれを眼で叱って、
「どうぞ御存分に」と平気な声で云った、「障子の向うが台所、右の襖は納戸でございます。剥いだばかりの熊の皮がございますから、お手を汚さぬようになさいまして」
――神さま、どうぞお護り下さい。
お文は固く眼を閉じて祈った。――どうぞ金之助さまが御無事でありますように、あの子はお国のために命を捨てて働いているのです、どうぞお護り下さいまし。
一秒が一日ほどの長さにも思えた。
侍たちは有ゆる物を引繰り返し、どんな隅をも残さず突き廻した。納戸の中とて同様である。然し「剥いだばかり」という熊の毛皮には、さすがに無気味で手がつけられなかったのか、やがて失望した様子で出て来た。
「いないらしい」「とすると石谷の方へ行ったのか知れぬ」
「足跡はたしかに此方だったが」
そんなことを呟きながら、五人とも土間へ下りる。とたんに、……納戸の中から、金之助の声で、
「もう行きましたか」
と云うのがはっきりと聞えて来た。
みんな一時に振返った。太兵衛も、お文も、もう駄目だと思った。……五人の侍はそれより疾く、脱兎のように納戸へ殺到した。
――神さま!
お文はぎゅっと胸を抱きしめた。
然しがらっと襖を引明けたとき、納戸の中から烏の勘太が、ばたばたと烈しく羽風をたてながら飛びだして来たので不意を食った五人の侍たちはあっと身を退いた。
「もう行ったか」
勘太はそのままひょいと止り木へおりながら叫んだ。……いまの金之助の声とよく似ている、
「くうくう、もう行ったか、行ったか……」
「お文、起きねえか、夜が明けたぞ。くうくう、かっかっ、お文、もう行ったか」侍たちは茫然と、眼を瞠ったまま、勘太の叫ぶのを見守っていた。……お文はほっと太息をつきながら、
「わたくしの鳥でございますの」
と侍たちに説明した、「……よく人声を真似ますので、皆さんがたびたびお間違えになりますわ、勘太、此方へおいで」
「なあんだ、人真似鳥か」
と侍たちは苦笑しながら、
「まるで鸚鵡のようなやつだな」
「吃驚させ居った」
そう云って土間へ下りた。……そして、そのまま立去ろうとしたが、中の一人が戸口で振返ると、
「騒がせて気の毒だったな、許して呉れ。その少年というのは勤王浪士の手先なのだ、若しみつけたら捕えて呉れ」
「勤王浪士の手先ですと」
「斬り倒しても御褒美が出る、銀十枚だぞ」
そう云って侍たちは立去った。
太兵衛はそれを見送ってから、炉端へ坐ってお文を側へ呼んだ。……そして町から買って来た包を解きながら、
「それ、お土産だぞ」
「まあ……あたしに?」
「明けてみろ」
お文は外でまだ侍たちが聴いているかも知れないと思ったので、態と大きな声をあげながら包を解きにかかった。
四
包の中から出たのは貧しい土の雛人形だった。
「あらお雛さまね。……まあ可愛いこと」
「安物だがな、もう直ぐお節句だから買って来たのよ、安物で気に入るまいが」
「いいえ、いいえ!」
お文は小さな雛を犇と胸へ抱き緊めながら、
「嬉しいわお父っさん、あたし欲しかったの、ちょうどこんなくらいなのが欲しかったのよ。嬉しい……あたし泣きそうになってしまうわ」
「そんな物が、そんなに嬉しいか」
太兵衛はふっと眼をうるませた。
「……尤もおまえには貧乏ばかりさせて、今日まで紙人形ひとつ買って遣れなかったからな。金さえあれば大きな雛壇へ、いっぱいお雛様も買ってやれるし、綺麗な着物だって、紅白粉だって、髪油も簪も、なんでも好きな物を買って遣れるんだが、おらはこの通りしがねえ猟人だから」
「いや、いやよお父っさん、そんなこと云うとあたし怒るわ。あたしお父っさんが丈夫でいつまでも父娘仲良く暮せたらそれがいちばん仕合せなんですもの」
「仕合せというものをおまえは知らないからそう云うんだ、本当の仕合せというのはな……」
云いかけたまま、ふと太兵衛は言葉を変えた。
「お文……もういいだろう」
「お客さま?」
「お侍たちはもう谷へ下りた時分だ、おまえは早く支度をさせて、今のうちにお逃し申しな、この裏から鷲尾の峰を越えて行けば神庭へ出られる、あの猫岩の道をよく教えてあげろ」
「お父っさんはどうするの」
「おらは谷の方を見張ってる。……また戻って来ると面倒だから早くしろよ」
そう云って太兵衛は出て行った。
お文は直ぐに納戸から金之助を連れ出して来た。……金之助はさっきの失敗を恥じている様子で、顔を赤くしながら詫びた、
「済みません、息が苦しかったものだから」
「いいのよ、勘太が大変なお手柄をしたから却って疑いを晴したくらいですわ。それより……直ぐお立ちなさいまし」
「そうします、御迷惑をかけました」
「お泊めしたいのだけれど、また戻って来ないとも限りませんから、今のうち逆の方へ逃げる方がいいわ」
云いながら手早く身支度をしてやる。……少年は傷ついた右足を曳くようにして、然し元気な様子で裏口へ出た。
「その雑木林の中に道があるでしょ、林が明いているから分ります、それを真直に登ると左に猫のような形をした岩が見えますわ、その岩の向うを右へ登るとこの山の峰ですから、それを越して谷沿いにいらっしゃい、そうすれば神庭へ行けます」
「分りました、ではお別れします」
「どうか御無事で……」
「今夜の御恩は忘れません、若し生きていられたら、いつかまたお眼にかかりに来ます」
「待っていますわ、金之助さま」
「では左様なら、お姉さん」
金之助は、泪にうるんだ眼でじっとお文の顔を見守った。……お文も少年の眼を、まるで自分の頭に焼付けたいとでもいうように見つめた。
金之助は去って行った。
雪のなかを、片足を曳きずりながら、それでもかなり敏捷な足どりで去って行った。……お文は長いあいだ見送っていたが、やがて力の抜けたような気持で家へ入った。
「お父っさん――到頭、行ってしまったわ。」
そう思ってふと気付くと、父親がまだ帰っていない。……まだ表で見張っているかと、急いでみたが、表にも姿が見えなかった。
お文はなんども呼んでみた。
然し自分の声が木魂を返すばかりで、何処からも父の返辞は聞えて来なかった。……お文は急に不安になった、
「金さえあったら」と呟いていた父の顔つきと、
「褒美には銀十枚やる。」
と云った時の言葉とが頭の中で渦を巻いた。
お文は家の中へとび込んだ。……鉄砲が無かった、さっきまで壁に架けてあった鉄砲が見えない。お文は身を震わせて立ち竦んだ。
「お父っさんは、……お父っさんは」
鉄砲を持って少年を狙っている姿が見える。
勤王浪士の手先、銀十枚の褒美。……太兵衛がこれを見逃す筈はない、彼はいま鉄砲を持って金之助を狙っている。お文は狂気のように裏口からとびだした。
「いけない、あの人を射っては、……あの人はお国のために働いているんです、お父っさん」
お文は雪のなかを、鞠のように転げながら走って行った。
五
明治五年の秋のなかばであった。
麻買い商人と見える旅人が二人、曽て野猪の太兵衛とその娘の住んでいた家の横手で、小さな墓石を見ながら、土地の農夫の話を聞いていた。
「……それで娘は、その子供の身代りになって、鉄砲に撃たれて死んでしまったのです。親父の太兵衛は野猪という綽名のある暴れ者でしたが、自分の射ったのが娘だということを知ると、その場から行方知れずになってしまいました。……なんでも高野山へあがって坊主になったとか、雲水姿でお遍路をしているとか申しますが、本当のところはいまだに分らないのでございますよ」
「さても気の毒な話だ」
旅人たちは溜息をつきながら、
「御維新になるまでは、色々な人が色々苦労や悲しいめに遭ったのだな。……まあお花でも供えて行こう」
「いい土産話ができました、お礼を申します」
二人は道傍から野菊を折って来て供えると、小さな墓の前へぬかずいて唱名したのち、農夫と一緒に坂を下って立去った。
すると程なく、いま旅人たちの去った方から、陸軍中尉の軍服を着た青年が一人、足早に登って来て太兵衛の家の前に立った。色白で、眼の美しい美青年である、
「ああ、いない」
立ち腐れになった家をひと眼見て、いかにも落胆したように青年は呟いた。
「出世した姿を見て貰い、あの晩のお礼も云いたかったのに。……やっぱり、会えない気がしていたのが本当になった、残念だな」
梶金之助である。
今では陸軍中尉で、大阪鎮台に勤務しているが、賜暇を貰って土佐へ帰る途中、この津山へ廻って来たのであった。
彼はなにも知らない、お文が自分の身代りになって父に射たれたことも、太兵衛が行方知れずになったことも、なにも知らないのである。
曽て危い命を救われた家は、荒れに荒れ、あたりは芒が生い茂っている。……金之助は去り難い様子で、やや暫くのあいだ廃屋の周りを歩いていたが、やがて思い切ったように、然し渋りがちな足どりで元来た方へと去って行った。
静かである……。
山のよく澄んだ空気に、秋の光が匂うほど輝いている。時おり微風が来ると、樹々の枝から枯葉がはらはらと散り落ちる。
「くうくう」
低い鳥の喉声が聞えた。
誰も気付かない墓の横手に、一羽の鳥が寒そうに身を竦めている。……散る枯葉が、かさりと音を立てると、彼はつむっていた眼を明け、身震いをして叫ぶ、
「お文、起きねえか、……お文」
ひどく嗄れた声であった。「もう夜が明けたぞ、起きねえか、お文」
さあっと枯葉が渦を巻いた。……鳥は再び眼をつむった。まるで墓守りでもあるかのように、いつまでも其処に立ちつくしていた。