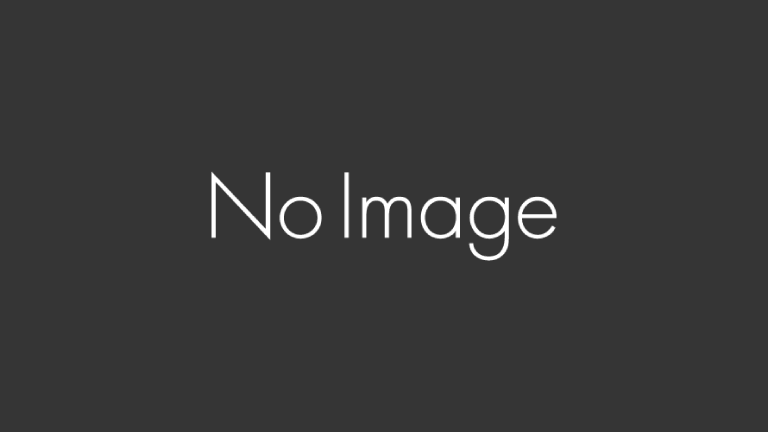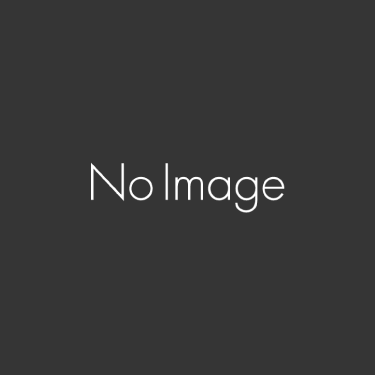江戸時代の岡っ引きと与力・同心に関するQ&A
江戸時代の警察組織(岡っ引き、与力、同心)に関する質問とその回答をまとめています。
Q: 銭形平次に登場する岡っ引き、常に十手を持ち歩いている描写ばかり。実際は?
「銭形平次」などの時代劇では、岡っ引きが常に十手を携帯している描写がよく見られますが、実際の江戸時代では、その状況はもう少し複雑でした。
十手の携帯について:
- 同心(町奉行所の役人)の正式装備: 十手は、町奉行所の役人である同心にとっては正式な装備であり、常に携帯していました。
- 岡っ引き(目明かし)の場合:
- 基本的に常時携帯はしていなかった: 岡っ引きが常に十手を持ち歩くことは稀で、必要に応じて同心から貸し出される、あるいは事件解決後に返却されるのが一般的だったと言われています。
- 「身分証明書」としての意味合い: 時代劇で描かれるように、十手は捕り物具としての機能よりも、むしろ岡っ引きが同心の配下であること、つまり「警察手帳」や「身分証明書」のような役割を担っていた側面が強いです。聞き込みの際に懐から見せて威圧する、といった使われ方もあったようです。
- 特別な許可が必要: 民間人である岡っ引きが十手を持つためには、特別な許可が必要な武器でした。一般の町人が十手を持つことは禁じられていました。
- 房の有無: 房のついた十手は同心以上の身分の者が持っていたとされ、岡っ引きの十手には房が付かないのが一般的だったという説もあります。
「銭形平次」の描写について:
「銭形平次」のような時代劇は、エンターテイメントとしての面白さを追求するため、史実とは異なる脚色が加えられている部分が多くあります。常に十手を持ち歩き、それを武器として投げたりする平次の描写は、物語を盛り上げるための演出と考えるのが自然でしょう。
実際の岡っ引きは、犯罪者上がりの者や裏社会に通じた者が多く、必ずしも品行方正な人物ばかりではなかったとも言われています。彼らは、同心の手足となって情報収集や聞き込みを行う役割が主で、実際の捕縛には同心の指示が必要でした。
まとめると、「銭形平次」の十手の描写は、あくまでフィクションとしての面白さを追求したものであり、実際の岡っ引きは、常に十手を携帯していたわけではなく、その役割も時代劇のイメージとは異なる部分が多かったと言えます。
Q: 同心と与力のちがいを教えてください
江戸時代の町奉行所における「与力(よりき)」と「同心(どうしん)」は、現代の警察組織における階級のような関係にあり、それぞれ異なる役割を担っていました。
与力(よりき):
- 身分・地位: 同心よりも上位の役職で、御家人(旗本の下の身分)に属します。騎乗が許される身分でした(そのため「一騎、二騎」と数えられます)。
- 役割:
- 町奉行を補佐し、行政、司法、警察の各方面で広範な業務を担当しました。
- 同心の指揮・監督を行い、捜査や裁判の指揮を執りました。
- 町与力は、江戸の人々が選ぶ「男の中の男」(与力、力士、火消しの頭)の一人に数えられるほど、尊敬される存在でした。
- 禄高(給与): 同心よりも高く、おおむね200石程度の知行(領地からの収入)が与えられました。
- 居住地: 八丁堀に約300坪程度の屋敷を拝領していました。
- 十手の携帯: 十手と刀を並べて差していました。
同心(どうしん):
- 身分・地位: 与力の下に位置する下級役人で、足軽階級に相当します。
- 役割:
- 与力の指揮下で、庶務、見回り、警備といった実務を担当しました。
- 犯罪の捜査や犯人の追捕(逮捕)といった、現場での警察活動が主な仕事でした。
- 「三廻り」(定町廻り、臨時廻り、隠密廻り)と呼ばれるエリート同心も存在し、与力の指揮下ではなく、町奉行から直接命令を受けることもありました。
- 岡っ引き(目明かし)を私的に雇い、情報収集や末端の捜査を任せることもありました。
- 禄高(給与): 与力よりも低く、30俵2人扶持程度でした。
- 居住地: 八丁堀に約100坪程度の屋敷を拝領していました。
- 十手の携帯: 刀のそばではなく、背中に差すのが一般的でした(時代劇では目立つように前に差すこともあります)。
まとめると、与力は現代でいう「幹部警察官」や「管理職」に近い存在で、同心は「一般の警察官」や「現場の捜査員」に近い存在と言えるでしょう。与力が全体を統括し、同心がその指示のもとで実務をこなすという、上下関係がありました。
どちらの役職も、現代の警察官と比べると非常に人数が少なく、江戸の治安維持には岡っ引きのような非公認の協力者の存在が不可欠でした。
Q: 与力は世襲ですか?
はい、江戸時代の与力は、公式には「世襲」ではありませんでした。しかし、実質的には世襲が非常に多く行われていました。
これは、与力が「抱席(かかえせき)」と呼ばれる、一代限りの職位であったためです。つまり、親が引退すると、子が自動的にその職を引き継ぐわけではなく、改めて新規に召し抱えられるという形をとっていました。
しかし、実際には以下の理由から世襲が一般的でした:
- 専門知識の継承: 町奉行所の与力は、江戸の行政、司法、警察といった多岐にわたる専門知識と経験を必要とする役職でした。そのため、親の職務を子が見習いとして学び、その知識と経験を受け継ぐことが、安定した職務遂行のために非常に重要視されました。
- 人脈の維持: 長年その職に就くことで培われた人脈は、情報収集や事件解決に不可欠でした。世襲することで、そうした人脈が引き継がれやすかったと考えられます。
- 町奉行所の安定: 町奉行は数年で異動することが多かったため、世襲で長年奉行所に勤める与力や同心が、奉行所の実務を支える上で重要な役割を担っていました。彼らが職務に関する知識を代々受け継ぐことで、組織の安定が保たれました。
- 養子縁組: もし男子がいなくても、養子を迎えることで事実上の世襲を継続させることができました。
このように、建前上は一代限りであっても、親が引退する前に息子(あるいは養子)が見習いとして親の仕事を手伝い、その後、親の跡を継いで与力として召し抱えられるのが通例でした。
与力は、公には世襲制ではなかったものの、職務の特性と安定的な組織運営の必要性から、実質的には世襲のような形で代々職務が引き継がれていくことが多かったのです。
Q: 同心も世襲?
与力と同様に、同心も公式には世襲ではありませんでしたが、実質的には世襲が非常に多く行われていました。
同心も与力と同じく「抱席(かかえせき)」という一代限りの職位でした。つまり、親が辞職したり亡くなったりしても、子が自動的にその職を継ぐことはなく、改めて新規に幕府に召し抱えられる形がとられていました。
しかし、以下の理由から、実際には世襲が一般的でした:
- 職務の専門性: 同心は、市中の見回り、犯罪捜査、逮捕といった現場での実務を担うため、その職務に精通していることが求められました。親から子へと職務のノウハウや地域の情報が引き継がれることは、治安維持の観点から非常に重要でした。
- 組織の安定: 町奉行所は少人数で広大な江戸の治安を維持していたため、与力と同様に、同心も長年その職に就き、実務を安定的にこなすことが不可欠でした。
- 養子縁組: 後継ぎがいない場合でも、養子を迎えることで家系と職務を継続させることができました。
このように、同心も与力と同様に、建前上は一代限りの職務でしたが、その職務の性質上、事実上は世襲に近い形で代々引き継がれていくことが多かったのです。
Q: 佐々木味津造の近藤右門は、同心ですか?
はい、佐々木味津造の小説『右門捕物帖』の主人公、近藤右門は同心です。
彼は南町奉行所の同心であり、その無口さから「むっつり右門」の異名をとっています。岡っ引きの伝六を配下に置き、数々の難事件を解決していくのが物語の主な内容です。
Q: 半七捕物帳は岡っ引き?
はい、その通りです!
岡本綺堂の代表作である『半七捕物帳』の主人公、半七老人は、江戸時代の岡っ引きでした。
物語は、明治時代になって引退した半七老人が、若い新聞記者である「私」(岡本綺堂自身がモデルとされる)に、かつて自分が岡っ引きとして解決した江戸時代の様々な事件について語る、という形式で進められます。
「半七捕物帳」は、捕物帳というジャンルを確立した画期的な作品であり、岡っ引きという、同心や与力の下で実務を担う町人身分の人物を主人公にしたことで、より市井の視点から江戸の世相や事件を描き出し、当時の読者に大きな支持を得ました。
Q: 与力が主人公の小説はありますか?
はい、与力が主人公の時代小説はいくつかあります。
以下に例を挙げます:
- 稲葉稔さんの『武士の流儀』シリーズ(文春文庫): 若くして隠居した元与力・桜木清兵衛が主人公です。
- 誉田龍一さんの『隼人始末剣 最強の本所方与力』: 本所方与力である上村隼人が主人公の作品です。
- 坂岡真さんの『はぐれ又兵衛例繰控』シリーズ(双葉社): 南町奉行所の例繰方与力・平手又兵衛が主人公です。
- 井川香四郎さんの『梟与力吟味帳』シリーズ: NHKの時代劇「オトコマエ」の原作にもなりました。
これらの作品は、与力の仕事内容や彼らの生活、人間関係なども描かれており、江戸時代の与力について深く知ることができます。
Q: 著作権の切れたものでは?
著作権が切れている与力が主人公の小説となると、数はかなり限られてきます。有名な作家の作品では、同心や岡っ引きが主人公の方が圧倒的に多い傾向があります。
これは、日本の著作権保護期間が著作者の死後70年(2018年以前は死後50年)と長いため、戦前や戦後すぐの作品でなければ、まだ著作権が有効であることが多いためです。
しかし、探せば見つかる可能性はあります。例えば、以下のような視点で探してみると良いでしょう。
検索する際のヒント:
- 明治・大正期の作品: この時期に書かれた小説であれば、すでに著作者の死後70年が経過している可能性があります。
- あまり有名ではない作家の作品: 公立図書館の蔵書などを探すのが有効かもしれません。
「与力 主人公 時代小説 明治 大正 著作権切れ」や「青空文庫 与力」といったキーワードで検索してみることをお勧めします。青空文庫は著作権の切れた作品を公開しているため、そこから探すのが最も確実な方法の一つです。
ただ、前述の通り、与力を主人公にした古典的な著作権切れの時代小説は、同心や岡っ引きが主人公のものに比べると圧倒的に少ないことをご理解ください。