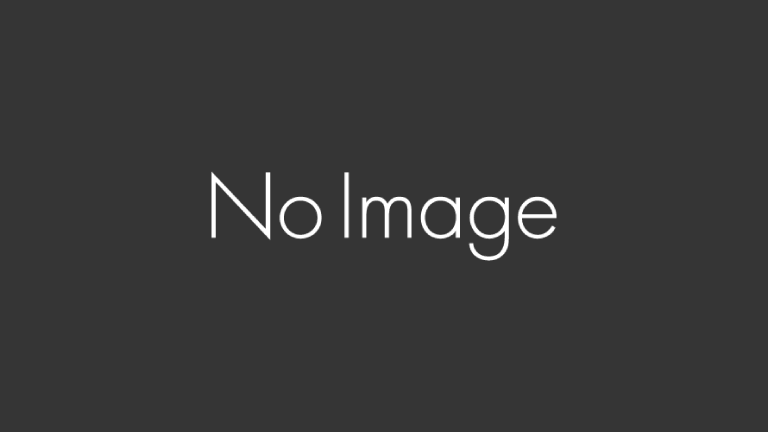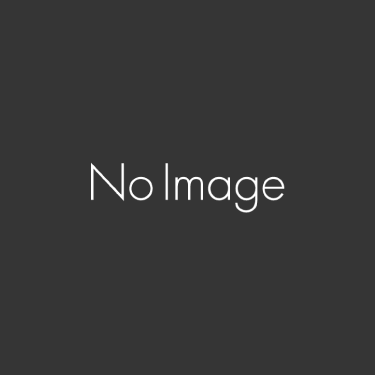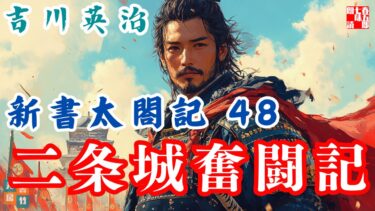新書太閤記
連載第四十三回 「鬮」
作者と作品について
作者:吉川 英治(よしかわ えいじ)
1892年(明治25年)- 1962年(昭和37年)。日本の大衆文学を代表する小説家。神奈川県出身。本名は英次(ひでつぐ)。『宮本武蔵』『三国志』『私本太平記』など、歴史を題材にした数多くの国民的ベストセラーを執筆し、「国民文学作家」と称された。その作品は、平易でありながら格調高い文章で、幅広い読者層から支持を得ている。1960年、文化勲章受章。
作品:『新書太閤記』(しんしょたいこうき)
吉川英治が1938年(昭和13年)から新聞連載を開始した歴史小説。豊臣秀吉の生涯を、織田信長に仕える以前の若き日から天下統一を成し遂げるまで、生き生きと描いている。本作は、従来の講談や立身出世物語としての秀吉像に、人間的な深みと魅力を与え、新たな「太閤記」として絶大な人気を博した。戦国時代の動乱を背景に、秀吉をはじめとする武将たちの葛藤や野望、人間模様が巧みに描出されている。
あらすじ
愛宕山に参籠した光秀は、連歌師の里村紹巴らを招き、表向きは風雅な連歌会を催す。その席で光秀は「ときは今 天が下知る 五月かな」という、謀反の決意を秘めたかのような発句を詠む。一方、参拝の際には神前で一心に祈り、神鬮を引く。一度、二度と凶が出た後、三度目に自らの手で引いた鬮は「大吉」であった。これにより、光秀は自らの計画に天意を得たと確信する。
その夜、光秀は隣室に眠る紹巴が気づくほどに魘され、脳裏では天狗と化した自身が天下の形勢を俯瞰する。彼は、秀吉、家康、藤孝ら諸将の動きを計算し、自らの挙兵が成功する未来を妄信するのだった。夜が明けると、光秀は早々に下山。亀山城に戻った彼は、出陣準備を進める家中の喧騒をよそに、表面上は穏やかに過ごす。しかし、その内面では六月一日と定めた決行の日に向けて、最後の時を待っていた。忠臣・光春は主君の真意を知らぬまま、その静けさに一抹の不安を覚えながら夜を迎えるのだった。
主な登場人物
- 明智 光秀(あけち みつひで):愛宕山にて神意を問い、連歌会で決意を詠み、謀反への確信を深める。
- 里村 紹巴(さとむら じょうは):光秀に招かれた当代随一の連歌師。光秀の異変をかすかに感じ取る。
- 行祐(ぎょうゆう):愛宕山威徳院の僧。連歌会を取り仕切る。
- 明智 光春(あけち みつはる):通称、左馬介。亀山城に合流するも、光秀の静けさに不審を抱く。
- 斎藤 利三(さいとう としみつ):通称、内蔵助。亀山城にて出陣の準備を進める重臣。
- 明智 長閑斎(あけち ちょうかんさい):光秀の叔父。一族の危機を知らず、無邪気に子供たちの相手をする楽天的な老人。
鬮
歌道や茶の友には、礼儀のほかに、階級を超えた心と心の親しいものがある。行祐はすこし仰山な手真似で答えた。
「いや、紹巴どのも、慌てられたにちがいございません。何しろお誘いのお文を手にしたのが、きのうの夕方に近い頃だそうで、しかも場所がこんな不便な所です。誰を誘うてみても余りに急なので埒はあかず、やむなく御子息の心前どのに、お弟子の兼如と御姻戚の里村昌叱どのを加え、お三名だけを連れて来られましたが――前後の時日を伺ってみれば、なるほどずいぶん御無理なお誘いのようで」
「ははは、そうか、そんなにこぼしておったか」
そんなことも、歌よむ仲間には、興の一つらしく、光秀は他念もない容子でおかしがりながら、
「無理とは知ったが、いつも駕籠の迎え、馬の送りで、いと重々しゅう扱っておるから、稀には風流の交わりらしく、苦労して集まるのも、一だんと好かろうかと存じて、場所も此処、時も不意に、誘うたのじゃ。……しかしさすがは里村紹巴、仮病を装うてのがれもせず、嵯峨口からでも五十余町もある山を、あたふたと登って参ったところは、似而非風流ではない。わが友とするに足る漢だ」
行祐、宥源の二僧を先に、東六右衛門やその他の従者をしりえに、光秀もまた高い石段を上っていた。そして少し平地を歩むかと思うとまた次の高い石段があった。
上るに従って、杉や檜の青い闇が深まってゆくのと、夏の日の空が桔梗色にたそがれてくるのと重なって、忽ち夜に近い心地がしてきた。そして一歩一歩、山上の冷気は、麓とは甚だしい差のあることを肌に思わせてくるのでもあった。
「つい、失念しておりましたが、紹巴どのからお詫びおきして賜われと、お言伝てを聞いていました。途中までお迎えに伺うべきですが、きょうの御登山は、おそらく御祈願事第一と存じますゆえ、山廟へのお詣りがおすみ遊ばした頃、ごあいさつに伺いますからと――」
威徳院の客殿に入ってから、行祐がこう伝えると、光秀は黙ってうなずいて見せた。そして一杯の白湯を飲み終るとすぐ、
「何よりはさきに氏神に祈願し、愛宕権現に参詣いたしたい。まだ夕方の仄明るい間に」
と、案内を求めた。
道は掃き清めてある。禰宜は先に立って、拝殿の階を踏み、神あかしを燈した。
光秀は、額ずいた。やや久しいあいだ祈念をこらしていた。
榊の風が、三度、颯、颯、颯と彼の頭上を払った。神官はまた彼の前に神酒の土器を置いた。
光秀は、その後で、
「当社は、火神を祭ると、伺っておるが、左様であるか」
「仰せのとおりにございます」
「火神には、火のもの断ちをして祈れば、霊験疑いなしと聞くが如何であろう?」
「はい、はい。――仰せの通り古来からよくそのように申し伝えられておりますが」
と神官は、光秀の質問には、明答を避けながら、その問いを、却って光秀へ向けて云った。
「火避け火断ちをすれば、火神の霊験で必ず願望が成るとは、里人の信仰ですが、そのような伝説は、いったい何から由来したものでございましょうか」
巧みに話題を転じて、神官のはなしは、いつのまにか神社の縁起に及んでゆく。
当社には、貞観四年頃の旧記もあるということから、またここは松尾の雷神の神別所で遠いむかしは、丹波山城の国境もふくめて、この地方一帯を「阿多古」と称え、阿多古の神山と仰がれていたが、いつの世の頃からか、朝日ヶ嶽、大鷲ヶ峰、高尾山、鎌倉山、龍上などの峰々に仏舎宝塔が建って以来は、五台の仏地としての方がより世上へ聞えが高くなり、修験道の優婆塞たちが天狗を修める道場ともなるに至って、いまではかくの如く神仏併祭のお山となっておりまする――などということから、また、
「――御承知でもございましょうが、盛衰記に――柿本の紀僧正は日本第一の天狗と成って愛宕山の太郎坊と申さるる也――と見えますのは、当山の太郎坊の縁起とされております。もっと古くは、大宝年中、役の小角が、嵯峨山の奥に住みたもうとあるは、この御山なりと、申す説などもございまして、修験者たちにいわせると、いまでもなお当山には天狗が棲んでおると、真しやかに奇蹟を説いて、少しも疑いを容れませぬ」
耳をかしているのかいないのか、その長いはなしの間を、光秀は拝殿の奥にゆらぐ神あかしを見つめていた。そして黙然と起つともう階を降っていた。すでに宵闇がふかい。彼はその足で愛宕権現に賽し、僧たちを白雲寺の前に残して、今度はただひとり、彼方の将軍地蔵の御堂へ詣った。そして、そこでは番僧から神鬮をうけていた。
神鬮は、凶と出た。
彼はまた求めた。
二度めの神鬮も凶であった。
しばらくは石のように凝然としている光秀であったが、次には僧に乞うて、自分の手に神鬮筥を受け、額に捧げて瞑目した。そして自己の祈念を自己の手で振った。
大吉
と、鬮にあらわれた。
光秀は去った。御堂を離れて待っている人々のほうへ歩いて来た。人々は彼が神鬮をひいている様子を、あだかも彼の気まぐれか興味のように遠くから眺めていた。なぜならば光秀の理念的な性格と、その知識人をもって誇りとする彼が何事を判別するにせよ、それを神鬮に託すようなことはあり得ないと決めていたからである。太郎坊の客院であろう、若葉のあいだに、一際白々と燭が見られた。紹巴やほかの輩には、歌会硯に墨などすりつつ、佳吟を想うのほか、はや他事もない宵らしい。
みじか夜
やがて西之坊の広間で、光秀を主とする饗膳の宵が過された。ここでは紹巴やその連れもひとつになり、また山房の住持たちも席に交わった。
放談哄笑、一しきりは、杯よくめぐり、談もよくはずんで、連歌などは、どうでもよいような興じ方であったが、
「夏の夜は短うおざる。余り更けては、百韻の成らぬまに、夜が明けてしまいましょう」
と、ここの院主行祐が、頃をはかって湯潰を出し、ともあれ彼方へと、用意の雅席へ、人々をうながして起った。
べつの部屋には、歌莚ができていた。各々の褥の前に、懐紙も、筥硯も、さあ名吟をたくさんお詠みなさい、とすすめぬばかりに備えられている。
紹巴や昌叱はこの道の達人である。わけて里村紹巴は、宗祇、宗長以来の聞えを当代に持っている者で、信長にも愛せられ、秀吉とも親しく、茶道では堺の宗易とは昵懇だし、顔のひろいことにおいては、無類の社交人でもある。
「さあ、殿、ひとつ御発句を……」
光秀へすすめていう。
しかし光秀はまだ懐紙に手もふれていないし、その肱は、脇息に託し、その面は、若葉時特有なそよぎを持つ庭面の闇へ向けていた。
「御執筆はどなたかの?」
紹巴は、歌の席に、場馴れている。なにくれとなく心をくばり、また席の空気を、息づまるような佗しさにさせまいとする。
座敷の隅に、小机を抱えていた明智家の士、東六右衛門が、
「不束ですが、主君のお申しつけ、もだし難く、私が認めまする」
と、紹巴へ答えた。
紹巴は、如才ない調子で、
「御謙遜でしょう、あなたのお筆ならば、勿体ない程のものです。これなどは――」
と、子息の心前をさして、
「歌の真似詠みは小賢しゅうとも、書とあっては、不勉強なので、ひと前には出せないような文字しか書けません」
父の悪口を、心前は笑いにまぎらして、
「それは御無理です。東どののお父上は、明智家随一の能書家と伺っております。その御子息ですからね」
「すると、おまえの悪筆も、父親のせいか」
「似ないでは、子として、不孝とぞんじまして」
「やりおる」
と紹巴は苦笑して、光秀のほうへ、身をのばしながら、
「――殿。こういう不所存者でございますよ。ちと、お叱り下さい」
と、告げ口した。
「…………」
光秀は、こちらを向いて、にたりと笑ったが、親子の戯れを、よく聞いていたのか否か、あいまいな顔いろであった。
こよいの彼はどことなく変っていた。けれど平常が寡黙で生真面目なほうだから、だれもそれを怪しまなかった。
「御苦吟の体でございまするな」
「発句か」
「さればで」
「いや、できた」
と、光秀は筆を取った。
まず、ひとりが起句を詠むと、次の者が脇句をつける。また受けて前句を出すと、他の者が下の句を附けてゆく。
こうして百韻なり五十韻まで歌い連ねてゆくのだった。文台の執筆者は巻に記して、後で披講する。
当夜の連歌会では、光秀の発句に始まって百韻に及び、終りの揚句も光秀の附句で結ばれたが、後まで伝えられた聯詠はわずか十吟にも足らない。
ときはいま天が下知る五月かな
と、光秀が発句すると、
水上まさる庭の夏山
と、威徳院の行祐がつけ、次に紹巴が、
花落つる流れの末を堰とめて
と、詠み、以下、
風は霞をふき送る風
宥源
春もなほ鐘の響や冴えぬらむ
昌叱
片敷く袖はありあけの霜
心前
うら枯れになりぬる草の枕して
兼如
聞に馴たる野べの松虫
行澄
などとあって終りに心前の、
色も香も酔をすすむる花の下
なる詠に対して、光秀が苦吟の末、
国々はなほ長閑なる時
と附けて百韻を結んだといわれている。
参籠の歌会であるから、詠巻は愛宕権現に納められたはずで、本来この巻は世に伝わりそうなものであるが、本能寺変の後、秀吉から吟味をうけた紹巴が、これを愛宕から取り出して、
(このように夜もすがら百韻に興じ明かしたに相違ございません。日向どのの歌でも、後になって見ればこそ、この時、逆意の兆しすでにありと、察しることもできましょうが、虚心風吟の席、誰があんな大事を予知することができましょう。たとえば明智家の家中すら大部分は本能寺の朝まで、日向どのの胸の中は知らなかったではございませんか)
と、縷々、弁証して、巻は秀吉の手もとへ差し出したままとなったので、以後の伝来は不明になったものという。
すべて、当夜のことは、秘中の秘とされたものか、謎が多い。
紹巴が秀吉に差し出した巻には、光秀の発句、
「――天が下知る」を「天が下なる」と書き直してあったというが、これもどうであろうか。
また、光秀が、苦吟のうちに、粽の皮を剥かずに口へ入れたとか、或いは、紹巴へ向って、
(本能寺の堀は、浅きか深きか)
と訊ねたところ、紹巴が、
(あら勿体なし)
と答えたとか、いかにも真しやかではあるが、これらも乱後の噂にすぎまい。一日にして天下の相貌を一変させた大乱であったから、あとの噂は真偽も紛々と一しきり巷雀を賑わしたにちがいない。同時に紹巴は、彼こそ未然に光秀の計画を知っていた唯一人だ――という嫌疑を一時濃厚にかけられたであろうことも想像するに難くない。
さて、会の後。
もちろんその晩は、みな威徳院の房に泊まったのであるが、部屋数も少ないので、紹巴は光秀の寝室のすぐ隣に眠った。
夏の夜ではあり、心やすい歌の友というので、境のふすまも払ってある。紹巴は枕につく前に、
「山上は蚊もいませんから、今夜は快く眠れましょう。どうも都は蚊が多くて……」
などと問わず語りをしていた。
寺僧が燭を消して退がると、光秀はすぐ寝入っていたように思われた。紹巴のつぶやきにも何の返辞も返さずに――。
枕に顔をあてがうと、戸外の山風は樹々を揺すり、屋の棟を吠えめぐって、さながら天狗の喊の声かと怪しまれてくる。光秀は火神の拝殿で聞いた神官の話がふと思い出されて、漆黒の宇宙に跳梁する天狗の姿を脳裡に描いていた。
天狗が火を咥えて飛ぶ。
大天狗、小天狗、無数の天狗がみな火となって、黒風に翔けまわり、その火が落ちて、火神の御社が、忽ちまた団々たる炬火となる。
――眠りたいものだ。眠ろう。
光秀は思う。彼は夢見ているわけではない。にもかかわらず脳膜はそんな幻想を描いてやまないのである。
寝返りを打つ。
そして、今日はと考える。明ければ二十九日と意識する。夢は天狗と化し、うつつは安土の城を考える。二十九日、二十九日、信長は安土を立ってこの日京都に向う。
うつつと夢のさかいがなくなってゆく。寝入るともなく醒めているともない彼だった。そしてその浅い半睡半醒のうちに、彼と天狗のけじめもなくなっていた。
天狗は雲を踏んで天下を見まわした。一朝の大事を挙げたとき天下はいかなる動きをなすかを俯瞰しておく用心のためである。そして天狗の観るところ、悉くみな自己に有利であった。
まず中国の秀吉は吉川、小早川の大軍と、いまや四つに組んだかたちで、高松の城に釘づけとなっている。もし款を毛利家に通じ、彼に利をもってすれば、あわれ遠征宿年にわたる羽柴秀吉以下の軍は、中国の地を墳墓として、ふたたび都を顧みることはできまい。
いま大坂にあるらしい徳川家康は無二の世渡り上手、すでに信長亡しと見たら、彼の向背もただわが誘いの如何によろう。一たんの憤りはなすであろうと思われる細川藤孝も、わが娘の舅たり、年久しき刎頸の友でもある。嫌とはいうまい、協力しよう。
肉がうずく、血が鳴る。久しく忘れていた青年の血が、ふたたび甦って来たかのように耳までが熱い。――天狗は寝返った。枕の音とともに、うーむとわれ知らず呻いた。
「……殿」
となりの部屋から紹巴が身をもたげて声をかけた。
「殿……。どうか遊ばしましたか」
光秀はかすかにそれを知っていたが、わざと返辞をしなかった。
紹巴はすぐ元の寝息に回っている。みじか夜はすぐ明け放れた。起きるやいな、光秀は人々と別れて、まだ朝霧もふかいうちに下山した。
無用の用
左馬介光春が亀山へ来て、合したのは三十日であった。彼の坂本勢だけでも少なくないところへ、所在の明智衆が近郡からそれぞれ分に応じた人数と家の子を伴って集合しているため、城下は兵と馬に埋められ、辻々には輜重の車馬が輻輳して道も通れぬほどである。急に真夏を思わせて陽はかんかんと照りつけ、行儀のわるい荷駄人夫が物売り店にたかって盛んに喰ったり喚いたりしているかと思えば、兵糧を載せた牛車を挟んで足軽同士の口喧嘩だ。それを見物している女子供の輪と足もとの馬糞牛糞に蠅も唸りをあげて巡っている。
光春は馬上から見て通った。
景観すでに常ならぬものがあった。一歩、城門に入ればなおさらである。
「つづいて、お体はおよろしゅうございますか」
まずは光秀に会った。
「このとおりだ」
光秀は莞爾として見せた。坂本頃よりは、ずっとにこやかである。血色もよい。
「御発足のお日取は」
「少しのばして、月の初め出陣ときめた。物事始まるの日、朔日こそよからめと存じて」
「六月一日ですか。して、安土の方へは」
「その旨、沙汰申した。が、右大臣家には、すでに御入洛であろう」
「二十九日の夕、つつがなく京都にお入りの由です。信忠公には妙覚寺に、右大臣家には本能寺を御宿所として」
「そうとな……」
低く、語尾も消して、光秀はそのまま黙る。
光春はすぐ起って、
「奥曲輪の女房方も和子たちにも久しぶりでお目にかかって来ましょう」
「まず、旅装でも解いて、身を休めたがよい」
ねぎらいながら、光秀は立ち去る従兄弟の背を、飽くなく見送っていた。そのあとでは、吐きも嚥みもできないような胸の閊えを満面にみなぎらしていた。
次の間のまた次の一室では、髪の毛の白さでもすぐその人とわかる斎藤内蔵助利三が、諸将と膝を寄せ合って、軍役帳や書類をくりひろげ、何か凝議していたが、やがて彼一名、光秀の前に来てたずねた。
「……仰せの、小荷駄大荷駄ともすべて、前日の三十日に、山陰へ向けて、先に出発させますか?」
「荷駄? ……むむ、あのことか。いや先発させるのは、皆までには及ぶまい。一部でいい」
そこへ、ひょこりと、実にひょこりとした姿で――光春とともに今日着いたばかりの叔父長閑斎がここを覗いて、
「おや、おりませんな。坂本の殿には、どこへ行かれたか。はて何処に?」
と、きょろきょろ見まわした。いつもながら腹の立つほど陽気で楽天顔をしている老人だった。
出陣の間際であろうと、主君や家中にどんな心配があろうと、いつも変らないおひゃらくな老人よ――と観られて、本丸の諸将からは、一箇の無用人視されている明智長閑斎も、ひとたび向きをかえて、ひょこひょこ奥曲輪の局へ顔をあらわすと、ここでは絶対的な人気で、女房たちから沢山な和子とそのお相手の童まで寄ってたかって、
「オオ、おひゃらく様がお越しなされた」
「おひゃらく様。いつお見え」
と、起っても、坐っても彼のまわりから嬉々たる声と茶目が離れないのであった。
「おひゃらく様。今夜はお泊り?」
「おひゃらく様。御飯はまだ?」
「おひゃらく様。お茶を召せ」
「おひゃらく様。抱いてえ」
「お歌を謡って聞かせてえ」
「踊って見せていの」
膝にのる。じゃれる。からみつく。そのうちに耳の穴をのぞいて、
「おひゃらく様のお耳には、お耳の中から毛が生えている」
「一ぽん、二ほん」
「三ぼん、四ほん……」
節をつけて歌いながら、女童たちが耳の毛を抜いていると、男の子は、背中へ跨がって、
「お馬になれ。お馬になってヒンと嘶け」
と、白髪頭を圧し伏せる。
「ひん、ひん、ひん」
長閑斎は甘んじて這い歩くのである。そしてくしゃみをした途端に、背中の子が落馬した。侍女も傅人も、腹をかかえて笑いこける。
奥の一間で何かしめやかに話しこんでいた光秀の夫人と左馬介光春も、此方を振り向いて、誘い込まれるように笑っていた。
夜に入っても、この笑いさざめきは止まない。光秀のいる本丸とここでは、さながら氷雪にとざされた冬の野と、春の国ほどな相違があった。
「叔父上には、お年もお年、戦陣へお出向きあるよりは、ここにござあって、和子や女子たちの、後顧の者をお傅り下されたほうがありがたい。大殿にも私からそう申しあげておきましょう」
奥曲輪から退がる折、光春がいうと、長閑斎は、
「わしに果せるお役目はまずそれくらいかも知れんな。何しろこのとおり皆が離さんしのう」
と、顧みて苦笑しながら、局中の者を集めて、夜は夜で、得意の「むかし噺」をせがまれ、盛衰記の一節を、おもしろおかしく物語っていた。
出陣までの余す日はあと一日しかない。その夜のうちにも総評議があるかと予期していたが、本丸は寂としているので、彼は二の丸へ入って寝た。
次の日は、月の晦日。光春は終日、心待ちに控えていたが、依然そのことの沙汰はない。夜に入るも何ら本丸の空気にうごきはなく、家臣をやって様子を訊かせると、光秀はすでに寝所へ入って眠ったという。
「……はて?」
光春はあやしんだ。しかし彼も眠るほかなかった。
この回をめぐる Q&A
Q. 物語で描かれた愛宕山での連歌会は、史実なのでしょうか?
A. はい、史実です。この連歌会は「愛宕百韻(あたごひゃくいん)」として知られ、天正10年(1582年)5月28日に愛宕山の威徳院で、光秀と里村紹巴ら数名によって実際に催されました。光秀が詠んだ発句「ときは今 あめが下しる 五月哉」は、彼の謀反の意図を示すものとして、歴史上大変有名な出来事となっています。
Q. 光秀はなぜ、神鬮(おみくじ)を三度も引いたのでしょうか?
A. 最初に二度引いた鬮が「凶」であったため、自らの決意を後押しする「吉」が出るまで引き直したと考えられます。これは、合理主義者であるはずの光秀が、自らの大それた計画に対して神仏の後ろ盾、つまり「天命」を求めずにはいられないほど、精神的に追い詰められていたことの表れです。三度目に自らの手で「大吉」を引いたことで、彼は計画の正当性を確信し、最後の迷いを振り払ったと解釈できます。
Q. 光秀は、本気で天下を取れるという目算があったのでしょうか?
A. 多くの研究者は、光秀が綿密な計画のもと本能寺の変を起こしたと考えています。本文でも、眠れぬ夜に「天狗」と化して天下の形勢を俯瞰し、秀吉が毛利と対峙して動けず、家康や藤孝も味方に引き込めると計算している様子が描かれています。しかし、最大の誤算は秀吉の驚異的な速さの帰還(中国大返し)でした。この「少しの掛け違え」がなければ、「天下人・明智光秀」が誕生した可能性はゼロではなかった、と歴史のifとして語られています。
Q. 本能寺の変の後、明智一族はどうなったのですか?光秀の妻や子供、盟友の光春は?
A. 謀反人の一族として、苛烈な運命を辿りました。
- 妻・煕子(ひろこ): 本能寺の変以前に病死していたとする説が有力です。
- 子供たち: 嫡男・光慶は坂本城で自害したとされますが、他の子供たちの多くは処刑を免れ、落ち延びたり、縁者に匿われたりして血脈を繋いだとされています。有名な細川ガラシャも光秀の娘です。
- 明智光春(左馬介): 山崎の戦いで敗れた後、坂本城で自害したと伝えられています。「湖水渡り」の伝説でも知られる悲劇的な最期でした。
このように、一族の多くは自害や討死を遂げましたが、一部は姓を変えるなどして生き延び、現在もその子孫とされる方々がいらっしゃいます。
Q. 物語に登場する楽天的な叔父・長閑斎の存在には、どのような意味があるのでしょうか?
A. 彼の存在は、明智家が迎える悲劇との鮮やかな対比を生み出しています。出陣を前に緊張が走る本丸と、長閑斎を中心に子供たちの無邪気な笑い声が響く奥曲輪。この「氷雪にとざされた冬の野と、春の国ほどな相違」は、光秀が破壊しようとしている平和な日常の象徴です。何も知らずにいる長閑斎の陽気さが、かえって光秀の孤独と、これから起こる惨劇の残酷さを際立たせる効果を持っています。