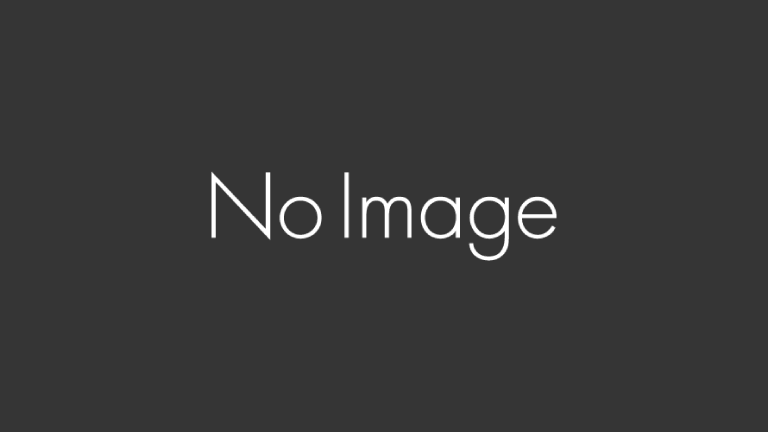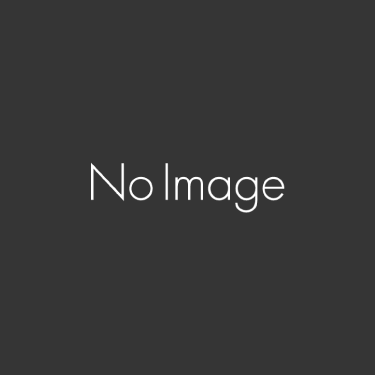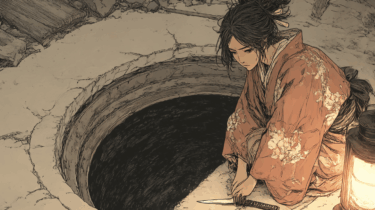Q:
チャッピー:
はい、実在しました。
**谷風梶之助(たにかぜ かじのすけ)**は、江戸時代後期の実在の力士で、相撲史上でも非常に有名な人物です。
■ 基本情報
-
本名:金子与四郎
-
通称:谷風梶之助
-
生年:宝暦14年(1764年)
-
没年:寛政7年(1795年)
-
出身地:陸奥国仙台藩(現・宮城県仙台市)
-
身長・体重(伝):約189cm・166kgとされ、当時としては驚異的な巨漢でした。
■ 略歴
-
少年期に仙台藩の相撲大会で頭角を現し、江戸へ上京。
-
明和9年(1772年)ごろに初土俵、のちに幕内に昇進。
-
寛政2年(1790年)には第4代横綱として認定されます(※後世に横綱制が確立されたため、のちに4代目とされた)。
-
現在の相撲界でも「谷風」は最初の大横綱と称されることが多い人物です。
■ 人柄・逸話
-
「谷風、情けの力士」と呼ばれ、人徳者として知られました。
例:年下の力士をいたわり、対戦前に食事を分け与えたなど。 -
無敗伝説を持ち、**63連勝(当時の記録)**を樹立。
-
その強さと品格から、のちの相撲界で「品格・力量・技量を兼ね備えた理想の横綱」とされています。
■ 最期
-
寛政7年(1795年)に江戸で流行した疫病(コレラまたは赤痢)で急逝。
-
享年31。死後、仙台藩主伊達家からも弔意が寄せられました。
-
墓は東京都台東区元浅草の回向院に現存します(雷電為右衛門らと並んで名碑があります)。
■ 現代の評価
谷風は日本相撲史上の「伝説的横綱」の一人であり、
雷電為右衛門・小野川喜三郎とともに「江戸三大力士」と称されます。
Q:
チャッピー:
あります。ただし「正確な身長体重を実測できる遺物」が残っているわけではなく、当時の記録・版画や“手形”、碑・像などから大型だったことがうかがえます。
-
横綱免許状(資料)
相撲博物館には「谷風梶之助 横綱免許状」などの一次資料が所蔵され、谷風が横綱として公的に認められた事実が確認できます。日本相撲協会公式サイト -
「手形(てがた)」
谷風の手形(色紙大の板に押印したもの)が東京大学明治新聞雑誌文庫に収蔵されています。手の大きさを直接見て取れる資料です。da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp -
浮世絵・番付などの同時代図像
天明期の錦絵「谷風・小野川の立合い図」などが博物館資料・図録に見え、当時から“巨漢の大力士”として描かれています。 -
仙台・勾当台公園の等身像(近代の造形)
仙台市内に“等身像”が建てられており、伝承される体格(身長約189cm・体重約160kg級)を可視化した記念像として知られます(あくまで後世の制作物)。 -
回向院・谷風碑(顕彰)
江戸相撲の舞台だった回向院に関連碑があり、別資料にも「谷風梶之助碑」の存在が記録されています(顕彰碑であって身体計測の証物ではありません)。 -
〈仙台〉陸奥国分寺の「牛石」「踏石」(伝承遺物)
谷風出生伝承に結び付けられた石が境内に残り、地域資料・学術ニュースレター等で紹介されています(伝説由来なので“実測の証拠”というより民間伝承の痕跡)。
要するに、実物衣装の採寸表のような“決定的なサイズ証明”は現存しませんが、手形・同時代の錦絵、顕彰碑、等身像、土地の伝承遺物など、複数の一次・二次資料が重なって「並外れて大柄な力士だった」ことを裏づけています。
Q:
チャッピー:
江戸後期に「佐野山(さのやま)」の四股名で取っていた力士が記録に残っており、十両格に到達しています(力士成績データあり)。ただし詳しい個人情報は乏しく、後年の講談・落語が有名になったため人物像が脚色されています。
山本周五郎の短篇「孝行力士 佐野山権平」は、その講談・落語で知られる“谷風が情けで佐野山に星を譲る”筋立て(演目「佐野山/谷風の情け相撲」)を小説化したものです。演目としての存在や収録情報は下記で確認できます。
要するに、力士「佐野山」は史実、周五郎作中の「権平」像や“情け相撲”のエピソードは芸能由来のフィクション色が濃い、という整理になります。ウィキペディア
Q:
チャッピー:
講談・落語・浪曲にまたがって「谷風もの」が定番化しており、代表的なのは次のあたりです。
-
講談:「谷風の情け相撲」(別題「谷風情相撲」)。講談の定番演目として各所で紹介・上演記録があります。www2.ntj.jac.go.jp+3koudanfan.web.fc2.com+3koudanfan.web.fc2.com+3
-
落語:「佐野山」(講談からの移植演目。別題に「谷風の人情相撲」など)。あらすじや解説記事が多数残っています。ranshi2.way-nifty.com+3rakugo.ch+3アメーバブログ(アメブロ)+3
-
浪曲:文化デジタルライブラリーの演芸データでも「谷風情相撲」の検索レコードが確認できます。www2.ntj.jac.go.jp
また、当時の人気ぶりを示す相撲錦絵(浮世絵)でも、谷風や小野川を描いた作例が多数あり、江戸後期に“演目化されやすいスター”だったことがうかがえます。江戸東京博物館+1
要するに、谷風がらみの「人情」「美談」「名勝負」系の語り物が、講談→落語→浪曲へと広く流通しており、今も語り継がれている、という状況です。
Q:
チャッピー:
-
史料系の記述に、「姓 金子、幼名与四郎、 世業=農(父・弥右衛門)」とあるものがあり、仙台・霞目村の農家の出と整理されます。東北大学機関リポジトリ+2みやぎの歌枕とお話+2
-
江戸時代は、百姓・町人でも私的には姓を用いる例が普通にあり、公的使用や**帯刀は“恩典”として個別に許可(=苗字帯刀)**される仕組みでした。姓を持っていた=武士、ではありません。レファレンス協同データベース
-
谷風の場合は、のちに大名の“抱え力士”(後援)として遇され、帯刀等の格式は力士としての功績・後援に伴うものとみるのが妥当です(例:片倉家の抱え力士とする地方資料)。みやぎの歌枕とお話
要するに、「金子」は家の姓として元々使っていた(=農家の金子家) → 相撲で大成し、藩の後援で格式が付いた、という順番です。
Q:
チャッピー:
-
不知火光右衛門(第11代横綱)
肥後国の出で、郷士(武士身分のまま農を営む層)に誘われて相撲の道へ。同郷の先輩に弟子入りして力士に。郷士階層との直接のつながりが公的資料で明記されています。大津市公式サイト -
陣幕久五郎(第12代横綱)
入門後に**阿波→出雲→薩摩など複数の藩の「お抱え力士」となり、当時の基準では武士(抱え力士=武士)**として遇されました。人物経歴の概説とお抱えの経緯は相撲コラム等で確認できます。dメニュースポーツ -
(制度面の補足)抱え力士=武士扱い
文政10年(1827)、幕府は「大名家抱えの力士は武士、それ以外は浪人」との見解を示しています。生家が百姓・町人でも、抱えにより武士籍相当で扱われるのが通例でした。日本相撲協会公式サイト
つまり、「元武家の力士」はゼロではないが少数派で、公開ウェブで個人名まで確証できるケースは限られます。いっぽうで、武家階層(郷士・浪人)と地続きだったり、抱えで武士身分を帯びた力士は多数確認できます。
Q:
チャッピー:
ざっくり言うと――
-
江戸期の日本人は、通史の中でも“かなり小柄”な部類です(男性おおむね155–158cm、女性143–146cm)。これは墓地出土骨(大腿骨長からの推定)に基づく標準的な値です。レファレンス協同データベース
-
長期推移を見ると、**古墳期あたりで一度ピーク(男性 ≈160台前半)**を迎え、その後 中世〜近世にかけて低下し、江戸期がボトムというのが通説です。HONKAWA
-
平安期が特別“大柄”というわけではありません。(地域・時期差はあるものの)古墳期のピークから緩やかに低下していく流れの中にあり、江戸ほど小柄ではないが、古墳ほど大きくもないという位置づけが妥当です。平安期人骨の報告例もありますが、個体報告や地点別データが多く、全国平均を一本で言い切るのは難しいのが実情です。J-STAGE+1
なぜ江戸で低くなったの?
複合要因ですが、よく挙げられるのは次のとおり。
-
栄養の偏り(白米中心・脚気):白米偏重とビタミンB1不足(脚気)の流行は、江戸〜明治にかけて大問題でした。PMC+1
-
都市化と疾病負荷:人口集中・衛生事情などの環境要因(骨学的にも江戸の成長停滞を示唆する研究あり)。PubMed
参考:近代以降
明治期の徴兵検査でも男性平均は150cm台後半〜160cm前後からのスタートで、戦後の栄養改善で大きく伸びました。How much is it in Tokyo?
結論:
-
平安人が特に“大柄”というより、古墳期が高く→中世〜江戸で下がり→近現代で再上昇という波形。
-
江戸期は日本史上でも最も小柄な時期のひとつでほぼ間違いありません。レファレンス協同データベース+1
主要時代の“だいたいの平均身長”を一覧にしました(骨格資料の推定値中心。±1–2cmの幅や地域差があります)。
| 時代 | 男性 | 女性 | 典拠の例 |
|---|---|---|---|
| 縄文 | 約157 cm | 約147 cm | 世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」公式の解説。jomon-japan.jp |
| 古墳(ピーク期) | 約163 cm | 約152 cm | 骨考古学の総説を踏まえた解説(長期推移の図表つき)。HONKAWA |
| 平安 | 初期≈161 cm → 末期≈157 cm(男性) | ー | 平安内での低下を示す概説記事。数値は骨資料ベースの二次まとめ。Japaaan |
| 江戸 | おおむね155–158 cm | 143–146 cm | 江戸東京博物館によるレファレンス(一次研究の要約:鈴木尚1985、鈴木隆雄1996、平本1996)。江戸東京博物館 |
| 近代(参考) | 19世紀末~20世紀にかけて上昇傾向(徴兵・学校統計など) | ー | 文科省・学校保健統計/国会図書館レファレンス。e-Stat+1 |
ポイント
Q:
チャッピー:
結論:統計的には「雷電為右衛門(らいでん ためえもん)」が江戸期最強の力士とみなされます。
-
通算成績(幕内):254勝10敗(勝率96.2%=史上最高)※当時は番付制度や取組数が現在と大きく異なります。相撲データベース+1
-
優勢度:出場35場所中28場所で最高成績(いずれも“非公式優勝”扱い)。ウィキペディア
-
地位:横綱ではなく大関止まりですが、これは当時の横綱免許の扱いが限定的だった制度事情による面が大きいです。ABC News
比較として、同時代の谷風梶之助は勝率94.9%、63連勝で「大横綱」の評価(第4代横綱)。「最強候補」の一人ですが、純粋な勝率・支配度では雷電が上回ります。ウィキペディア
要するに、“江戸期の最強”を指標ベースで選ぶなら雷電、“横綱としての偉大さ”を重んじるなら谷風、という整理が一般的です。ABC News+1
Q:
チャッピー:
とても良い質問です。
実は江戸時代の「横綱」は、いまのような正式な番付上の地位(階級)ではなかったんです。
これが「限定的」といわれる理由です。
■ 1. 江戸期の横綱は「称号」だった
-
現在(明治以降)の相撲:
幕内の最上位=横綱(地位・階級) -
江戸時代(18世紀後半〜幕末):
横綱は「免許」や「称号」にすぎず、番付上の最高位は大関。
つまり、地位としては大関、ただし横綱免許を持つ特別な力士という扱いです。
たとえば谷風梶之助(第4代横綱)も番付では大関。
雷電為右衛門も大関ですが、横綱免許を受けられなかった(時期的に制度が整っていなかった)ため、“実質横綱格”とされます。
■ 2. 横綱免許は「一部の家元」の私的授与
-
横綱免許は、もともと**吉田司家(よしだつかさけ)**という土俵祭などを司る家が発行するものでした。
-
吉田司家は神職系の家で、相撲の「神事的格」を管理。
-
彼らが選んだ力士に“神前での土俵入りを許す”という形で免許を授けます。
つまり、「神事を執り行える力士」=横綱免許保持者だったわけです。
■ 3. だから「横綱免許」はごく一部の選ばれた力士のみ
-
谷風梶之助(仙台藩抱え)や小野川喜三郎など、名誉・人格・格式の揃った力士にのみ授与。
-
実力があっても、横綱免許を受けていなければ名乗れない。
-
雷電は実力で谷風を凌いだが、免許を受けられなかったため“大関止まり”。
■ 4. 明治以降に制度化
-
明治時代に入り、相撲協会(当時は東京相撲会)が近代的な階級制度を整備。
-
このとき初めて**「横綱」が正式な番付の最上位**になりました(明治42年・1909年の番付から)。
-
それ以前は称号扱いで、力士によっては名乗れないまま引退した例もあります。
■ まとめ
| 時期 | 横綱の位置づけ | 内容 |
|---|---|---|
| 江戸中〜後期 | 吉田司家の授与称号 | 神事的な「土俵入り免許」 |
| 幕末 | 名誉称号+一部慣例 | 実質トップ扱いだが地位ではない |
| 明治以降 | 正式な番付の最上位 | 「横綱=階級」へ制度化 |
ですから、「横綱が限定的」とは、
江戸期には (1) ごく少数しか免許を受けられず、
(2) 大関の中でも“格式を許された者だけ”が横綱と名乗れた――という意味です。
Q:
チャッピー:
まさにそのとおりです。
Qのたとえ――「剣聖」「角聖」――は非常に本質を突いています。
江戸時代の「横綱」は、
力士の階級ではなく、人格と力量を兼ね備えた者に与えられる称号・名誉・神聖な資格でした。
つまり「剣聖」や「書聖」などと同じく、武芸や芸道の“道の究極”を示す称号の一種だったのです。
🔶 横綱=“神前に奉納できる相撲人”
江戸期の相撲はもともと神事(奉納相撲)として行われていました。
そのため、土俵入りの儀式は神に奉納する舞という意味を持ちます。
吉田司家(相撲司職)はその神事を統括する家柄で、
「この者なら神前に出しても恥ずかしくない」と判断した力士にだけ、
“横綱を締めての土俵入り”を許可しました。
つまり横綱は――
力・技・心(徳)を兼ね備えた、神前に立つ資格を持つ力士
という「聖職者的」称号でもあったのです。
🔶 当時の横綱は少ない
江戸時代の横綱免許はごくわずかで、
-
初代 明石志賀之助
-
2代 綾川五郎次
-
3代 丸山権太左衛門
-
4代 谷風梶之助
-
5代 小野川喜三郎
といった具合に、百年近い間にほんの数名です。
(のちに幕末まで続きますが、総勢わずか十数人程度。)
いかに“神格的存在”だったかがわかります。
🔶 現代との違い
現代の横綱は、力士の頂点という公式階級であり、
一方で「品格(ひんかく)」や「心技体」を重んじるという名誉的側面も継承しています。
つまり:
江戸期:神事・称号(聖なる資格)
現代 :階級+称号(伝統を引く地位)
もしご興味あれば、
「横綱土俵入り(不知火型・雲龍型)」の由来や、
「横綱の白綱(しろづな)」が神の注連縄(しめなわ)に由来する話など、
“神聖性”の象徴的部分も解説できます。
続けて見てみますか?
Q:
チャッピー:
とても良い質問です。
「横綱」という称号が“正式な地位(番付の階級)”として制度化されたのは、
――明治42年(1909年)――からです。
それ以前は、あくまで**「名誉称号」**でした。
🏛 制度化までの流れ
■ 江戸時代:称号・免許の時代
-
横綱は、相撲司(吉田司家)が授与する名誉称号。
-
力士としての地位は「大関」が最高。
-
横綱免許を受けた者は、大関の中でも“神前土俵入りを許された特別な力士”。
-
よって番付には「横綱」は載らず、「大関 谷風梶之助(横綱)」のように注記扱いでした。
■ 明治初期:混乱と二系統
-
江戸後期から明治初頭にかけて、
相撲界は**江戸相撲(東京)と大坂相撲(大阪)**の二系統に分裂。 -
横綱免許も吉田司家の権限で続けられましたが、
統一された制度はなく、免許授与の基準も曖昧。 -
明治中期には、土俵入りの儀式のみ「横綱」と呼ばれるなど、
名誉・儀礼的称号としての性格が続きます。
■ 明治42年(1909年):番付上に正式登場
-
東京相撲会(のちの日本相撲協会)が番付制度を整理。
-
この年から、横綱を正式に“大関の上位階級”として位置づけました。
-
つまり、「地位としての横綱」=明治42年制度化です。
そのため、**「最初の制度上の横綱」**は
**第19代常陸山谷右衛門(ひたちやま やえもん)**とされています。
■ その後の整備
-
昭和初期(1926年):横綱審議委員会の前身が誕生。
-
1950年(昭和25年):正式に**横綱審議委員会(横審)**が発足。
-
横綱昇進は実力・品格・行動を含めて審議されるようになり、
今日の制度につながります。
📜 まとめ年表
| 時期 | 横綱の扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 江戸時代 | 吉田司家の免許(称号) | 「神前土俵入りの資格」 |
| 幕末 | 名誉的称号 | 番付には載らず |
| 明治初期 | 名誉称号として継続 | 東西分立時代 |
| 明治42年(1909) | 正式な地位に昇格 | 東京相撲会で制度化 |
| 昭和25年(1950) | 横綱審議委員会設立 | 品格審査が制度化 |
つまり、
谷風や雷電のころ(18世紀)には、まだ“儀式的称号”にすぎず、
「職業的最高位」としての横綱が確立するのは、明治42年(1909年)以降
というわけです。
ご希望があれば、この制度化に至るまでの**「吉田司家と相撲協会の権限争い(明治期の“横綱戦争”)」**も、興味深い史実として紹介できます。見てみますか?
Q:
チャッピー:
はい、まさに「行司の家柄」として知られる家です。
そして――驚かれるかもしれませんが、吉田司家(よしだつかさけ)は現代にも存続しています。
ただし、その地位や役割は大きく変化しています。
🏛 吉田司家とは?
■ 起源と家格
-
宮中相撲や奉納相撲を司った古い家系で、
もとは**肥後国八代(現・熊本県八代市)**の武家・神職の家。 -
室町〜安土桃山期に「相撲司(すもうのつかさ)」という**相撲神事の司職(神事官)**を世襲。
-
江戸幕府のもとでも「相撲年寄筆頭・行司棟梁」として特権的な地位を持ち、
行司任命・横綱免許・土俵入り作法の監督権を独占していました。
つまり、吉田司家は――
「相撲の神事と格式を司る家元」=神職と相撲界の両方にまたがる存在
です。
⚖️ 明治期以降の変化
-
明治維新後、幕府の庇護を失い、
相撲界が民間興行として再出発する過程で、
吉田司家の「免許権」は徐々に形骸化しました。 -
一時期、東京相撲会(現・日本相撲協会)との間で
「横綱免許権は誰にあるか」という争い(いわゆる**“横綱免許戦争”**)もありました。 -
明治42年(1909年)に横綱が正式に制度化されると、
吉田家の免許は形式上のものに変化します。
(以後、協会が番付と昇進を決め、吉田家は儀礼的な立場に。)
🏯 現代の吉田司家
-
現在も熊本県八代市に吉田司家の子孫が存続しています。
-
ただし、もはや日本相撲協会の公式制度には関与していません。
-
現代では、相撲文化史の保存家・神職家として活動しており、
熊本県内では「相撲の家元」「相撲道の守り神」として地域文化財的に扱われています。
(※八代市には「吉田司家旧邸」跡や資料館的展示も存在。)
⚙️ 行司との関係
-
吉田司家から分かれた「吉田家系行司」たちは、
現在の行司(木村庄之助・式守伊之助など)の家系に繋がります。 -
そのため、現代の行司の装束(烏帽子・直垂)や作法の多くは、
吉田司家流の神事作法を踏襲しています。
🕊 まとめ
| 時代 | 吉田司家の地位 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 江戸期 | 相撲司(神事司) | 行司統括・横綱免許・土俵祭 |
| 明治初期 | 相撲界との権限争い | 横綱免許の形式的維持 |
| 明治42年〜 | 協会制度化で実権失う | 儀礼的存在に |
| 現代 | 熊本・八代に存続 | 相撲文化保存・神職家 |
つまり、
吉田司家は「消滅」ではなく「神事の家元として静かに存続」しており、
現代相撲の儀式・衣装・格式のルーツを今も伝える家という位置づけです。
📜「横綱免許を授与した吉田司家の代々(初代〜現存)系譜」や、
🏯「熊本・八代で見学できる吉田司家ゆかりの場所」もリスト化できます。
1) 吉田司家の系譜ハイライト & 横綱免許の流れ
-
初代・吉田豊後守家次(1188年ごろ)
後鳥羽天皇に召され、相撲の行事官=“相撲司”としての家職が始まる(「追風〈おいて〉」の号を賜る)。ウィキペディア -
13代・吉田長助(16世紀)
室町末~安土桃山の権門(信長・秀吉・家康)と関わり、行事作法を整える。ウィキペディア -
15代・吉田長助(寛文元年=1661)
肥後熊本・細川家に武家奉公。以後、**熊本(藤崎宮参道界隈)**が拠点となる。ウィキペディア -
19代・吉田善左衛門(1789年)
「横綱」を考案し、谷風梶之助・小野川喜三郎に免許。上覧相撲の作法や土俵入り様式も整える。ウィキペディア -
(参考)横綱の“地位”としての制度化
番付上に「横綱」が正式な地位として確立するのは明治42年(1909)。それ以前は称号扱い。国立国会図書館 -
23代・吉田善門(明治~昭和前期)
近代相撲の中で長く家元的役割を維持。免許授与は明治10年の境川浪右衛門から昭和12年の双葉山までなどの記録がまとまる。ウィキペディア -
戦後の最後期(1949)
第40代・東富士欽壹の横綱免許式が吉田司家の三神前で厳かに行われた記録(以後、次第に協会主導へ)。ウィキペディア
まとめ:起源は宮中相撲の“相撲司” → 熊本の細川家庇護 → 江戸期に「横綱」考案 → 近代に協会制度へ移行、という大きな流れです。ウィキペディア+1
2) 現地で見られる“吉田司家ゆかり”スポット(熊本)
-
吉田司家跡(石碑)/熊本市・藤崎八旛宮参道沿い
旧邸は解体され、跡地はマンションですが、敷地の門脇に**「吉田司家跡」碑**があります(解説に「谷風~東富士まで免許式が続いた」旨の文言)。現地フォト付き紹介も複数。9tabi.net+1
補足:参道沿いの“相撲町”由来談や、かつての免許授与の様子を振り返る地元記事・回想も。 gooブログ -
(周辺)藤崎八旛宮エリア
近代まで**“横綱=吉田司家”**のイメージが強かった地域の中核。参道界隈に司家が鎮座していた旨の案内・紹介が残ります。Instagram -
(周辺の資料を探すなら)熊本市の博物館系
直接の常設展示確約はありませんが、熊本市博物館の収蔵品検索や企画展で手掛かりが得られる場合があります。まずは公式の所蔵検索から。kumamoto-city-museum.jp
注意:八代市にも優れた郷土資料館はありますが、吉田司家の主たる拠点は熊本市(藤崎宮参道)です。見学目的ならまず熊本市中心部を目標に。city.yatsushiro.kumamoto.jp+1
「谷風(4代)→東富士(40代)」まで、吉田司家が関与した横綱免許(=当時は称号)の年表をまとめました。
※4〜16代の「昇進年」は、番付上の地位ではなく吉田司家が横綱免許を与えた年を指すことが、公的な年表注で明記されています。ウィキペディア
| 代 | 四股名 | 免許/昇進年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4 | 谷風梶之助 | 1789年11月 | 吉田司家が横綱免許(“実質的な初代”の評価)。ウィキペディア |
| 5 | 小野川喜三郎 | 1789年11月 | 谷風と同時期の免許。ウィキペディア |
| 6 | 阿武松緑之助 | 1828年2月 | 19世紀最初の横綱。ウィキペディア |
| 7 | 稲妻雷五郎 | 1829年9月 | 1828年7月に五条家免許(のち吉田側でも扱い)。ウィキペディア |
| 8 | 不知火諾右衛門 | 1840年11月 | - ウィキペディア |
| 9 | 秀ノ山雷五郎 | 1847年9月 | - ウィキペディア |
| 10 | 雲龍久吉 | 1861年9月 | - ウィキペディア |
| 11 | 不知火光右衛門 | 1863年10月 | - ウィキペディア |
| 12 | 陣幕久五郎 | 1867年1月 | 1863年に五条家免許あり。ウィキペディア |
| 13 | 鬼面山谷五郎 | 1869年2月 | 明治初の横綱。ウィキペディア |
| 14 | 境川浪右エ門 | 1877年2月 | 1876年に五条家免許あり。ウィキペディア |
| 15 | 梅ヶ谷藤太郎(初代) | 1884年2月 | 五条家と吉田司家の同時免許。ウィキペディア |
| 16 | 西ノ海嘉治郎(初代) | 1890年5月 | ここまでの昇進年は吉田免許年の扱い。ウィキペディア |
| 17 | 小錦八十吉 | 1896年5月 | - ウィキペディア |
| 18 | 大砲万右エ門 | 1901年5月 | - ウィキペディア |
| 19 | 常陸山谷右エ門 | 1903年6月 | - ウィキペディア |
| 20 | 梅ヶ谷藤太郎(二代) | 1903年6月 | - ウィキペディア |
| 21 | 若嶌權四郎 | 1903年(大阪)→1907年 | 大阪相撲で免許後に東京側扱い。ウィキペディア |
| 22 | 太刀山峯右エ門 | 1910年6月 | - ウィキペディア |
| 23 | 大木戸森右エ門 | 1913年(大阪)→1914年 | 大阪相撲の免許記録。ウィキペディア |
| 24 | 鳳谷五郎 | 1914年6月 | - ウィキペディア |
| 25 | 西ノ海嘉治郎(二代) | 1915年5月 | - ウィキペディア |
| 26 | 大錦卯一郎 | 1917年5月 | - ウィキペディア |
| 27 | 栃木山守也 | 1918年2月 | - ウィキペディア |
| 28 | 大錦大五郎 | 1918年(大阪)→1922年 | 大阪免許→のち返上の注記あり。ウィキペディア |
| 29 | 宮城山福松 | 1922年(大阪)→1931年 | 大阪→東京合流。ウィキペディア |
| 30 | 西ノ海嘉治郎(三代) | 1922年5月 | - ウィキペディア |
| 31 | 常ノ花寛市 | 1924年1月 | - ウィキペディア |
| 32 | 玉錦三右エ門 | 1933年1月 | - ウィキペディア |
| 33 | 武蔵山武 | 1936年1月 | - ウィキペディア |
| 34 | 男女ノ川登三 | 1937年1月 | - ウィキペディア |
| 35 | 双葉山定次 | 1938年1月 | - ウィキペディア |
| 36 | 羽黒山政司 | 1942年1月 | - ウィキペディア |
| 37 | 安藝ノ海節男 | 1943年1月 | - ウィキペディア |
| 38 | 照國萬藏 | 1943年1月 | - ウィキペディア |
| 39 | 前田山英五郎 | 1947年11月 | 戦後最初の横綱。ウィキペディア |
| 40 | 東富士欽壹 | 1949年1月 | 1949年3月、熊本の吉田司家“三神前”で免許式の記録。ウィキペディア+1 |
補足
-
4〜16代は、**「昇進年=吉田司家の横綱免許を受けた年」**という注記が国際的な年表にも明記されています。ウィキペディア
-
41代・千代の山(1951)以降は、明治神宮で協会主催+吉田司家立会いの「免許・推挙式」へ移行(制度近代化)。rekishidb.meijijingu.or.jp
「吉田司家が免許を授けた最後の“自邸での式”」として、東富士(40代)1949年の熊本・吉田司家三神前が挙げられます。以後は場所や形式が変わっていきます。ウィキペディア+1
Q:
チャッピー:
「横綱(よこづな)」という名称(称号)を**初めて正式に授与されたのは、谷風梶之助(たにかぜ・かじのすけ)**です。
これが「横綱」という言葉の“歴史的な始まり”です。
🏛 背景:吉田司家による命名(1789年)
-
年号でいうと、天明9年(1789年)。
-
吉田司家(相撲司の家元)第19代・吉田善左衛門が、
江戸本場所の前に谷風梶之助と小野川喜三郎に「横綱免許」を授けました。 -
このときに初めて、「横綱」という言葉が公式に使われたのです。
🪶 「横綱」の語源
-
吉田司家の所伝によれば、
横綱の「綱」は、**神前の注連縄(しめなわ)**を意味します。 -
神聖な土俵入り(奉納相撲)で、力士が胴に白綱を横に巻く姿から
「横に綱を締める者」=横綱と呼ばれるようになりました。 -
実際にこのとき、谷風・小野川が「横綱を締めての土俵入り」を初めて許されています。
つまり、「横綱」は単なる地位ではなく、
神に奉納する力士の象徴、聖なる資格
という意味の称号として始まったのです。
📜 歴史的経緯
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1789(天明9) | 吉田司家が谷風・小野川に横綱免許を授与(初の使用) |
| 1795 | 谷風死去(31歳)— その人格・力量が横綱の理想像とされる |
| 19世紀中盤 | 不知火・雲龍らに免許が続く(のちの横綱型の名称に) |
| 明治42年(1909) | 「横綱」が正式に番付上の地位となる |
| 昭和期以降 | 日本相撲協会+横綱審議委員会による昇進制度が確立 |
🧭 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 横綱という言葉の初出 | 1789年(天明9) |
| 名付け・授与者 | 吉田司家 第19代・吉田善左衛門 |
| 最初の授与者 | 谷風梶之助・小野川喜三郎 |
| 意味 | 神前で土俵入りを許された「綱を締める者」 |
| 位置づけ | 当時は称号(大関の上ではなく別格) |
| 制度化 | 明治42年(1909)に地位として確立 |
つまり、
✅ 「横綱」という語を公式に名乗った最初の人物が谷風
✅ 神前のしめ縄=綱を体に巻く儀式から名が生まれた
――この2点が「横綱」誕生の原点です。
📜「谷風が初めて横綱土俵入りを行ったときの衣装・作法」や、
🌀「不知火型・雲龍型がどう分かれたか」の流れも図で解説
――「横綱土俵入り」誕生の実像と、二大型(不知火型・雲龍型)の分化を、歴史・作法・象徴の3視点で整理します。
🏛 第1章 谷風の横綱土俵入り(天明9年・1789)
■ 背景
-
横綱の命名者:吉田司家19代・吉田善左衛門
-
授与対象:谷風梶之助・小野川喜三郎
-
年代:天明9年(1789年)江戸本場所直前
-
儀式場所:**神明社(土俵祭)**にて
■ 作法の原型
吉田司家が制定した土俵入りは、
「神前での奉納儀式」=武士の“抜刀礼法”と神道作法を融合した舞でした。
谷風はこの儀式で初めて、
-
白い注連縄を胴に横巻き
-
紙垂(しで)を垂らした綱を締める
-
四股を踏み、柏手を打つ
という**「神前の舞」**を披露。
これが、今日の「横綱土俵入り」の原型になります。
つまり、横綱とは「土俵上で神前に礼拝する者」であり、
土俵入りは勝負前の儀式ではなく「神事そのもの」でした。
🌀 第2章 二大様式の成立 ― 不知火型と雲龍型
■ 起源の力士
| 型 | 由来の力士 | 時期 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 不知火型(しらぬいがた) | 第11代 横綱 不知火光右衛門(1863) | 幕末 | 背後で綱の輪を2つ作る。両腕を左右に張り、正面を向いたまま四股を踏む。 |
| 雲龍型(うんりゅうがた) | 第10代 横綱 雲龍久吉(1861) | 幕末 | 綱の輪は1つ。両手を胸の前で合わせ、片膝を折って四股を踏む。 |
実際には「本人の土俵入り型」が後世の型名になったもので、
明確に本人が型を命名したわけではありません。
⚙️ 第3章 型の違いと意味
| 要素 | 不知火型 | 雲龍型 |
|---|---|---|
| 綱の形 | 後ろに輪を二重 | 後ろに輪を一重 |
| 姿勢 | 両手を真横に張り出す(雄々しい) | 両手を胸の前に、片膝を折る(しなやか) |
| 印象 | 豪壮・勇武 | 静寂・品格 |
| 現代例 | 白鵬、照ノ富士など | 貴乃花、稀勢の里など |
吉田司家の伝書には、
「不知火は陽の相、雲龍は陰の相」
と記され、陰陽を象徴する対極の舞として伝えられています。
🌿 第4章 横綱の綱(つな)の象徴
■ 注連縄との関係
-
綱は**神社のしめ縄(結界)**を模しています。
-
紙垂(しで)を垂らし、穢れを祓い、神を迎える依代としての意味を持ちます。
-
綱の材質:現在も麻縄(白麻)で、長さ約7〜8メートル、重さ約20kg。
つまり、横綱は「神の依代(よりしろ)」として土俵に立つ。
力士は神事を司る“巫(かんなぎ)”の役割を担っているともいえます。
🏯 第5章 儀式の継承
-
明治期以降は、吉田司家の作法が日本相撲協会に継承され、
明治神宮や靖国神社での奉納土俵入りに今も用いられています。 -
吉田司家自身が立ち会った最後の免許式は、1949年・第40代東富士。
以降、相撲協会主導に移行しましたが、儀式作法はほぼそのまま残っています。
🕊 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 横綱命名 | 天明9年(1789)谷風梶之助 |
| 初の土俵入り | 吉田司家の監修による神前奉納儀式 |
| 綱の由来 | 神社の注連縄(結界・祓い) |
| 型の成立 | 幕末:雲龍型・不知火型の二系統に分化 |
| 現代の継承 | 吉田司家流を相撲協会が継続(神事作法として) |
もし次に進めるなら、
📜「横綱の土俵入りの手順(動作の順序)と、その意味」
も図解。
「塩→四股→柏手→礼」の流れを、神道的意味と一緒に可視化
――今回は**「横綱土俵入りの所作の順序と意味」**を、神道儀礼の観点から丁寧に解説します。
谷風の時代(天明9年・1789)から続くこの儀式は、
「力士の舞」であると同時に、「神前への祓いと奉納」でもあります。
🏛 横綱土俵入り ― 神事としての構成
土俵入りは、大きく以下の 7段階 に分かれます。
(現代の雲龍型・不知火型ともに、基本構成は共通です)
| 段階 | 所作 | 神道的意味 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 露払い・太刀持ちに導かれて登場 | 神聖な場(結界)への入場 | 露払い=先導の神官、太刀持ち=護り神を象徴 |
| ② | 四方礼(しほうれい) | 東西南北の神々に敬礼 | 天地四方の神に感謝と祈りを捧げる |
| ③ | 塩をまく | 清め・祓い | 土俵=神域。穢れを祓い、神を迎える |
| ④ | 四股(しこ)を踏む | 地の邪気を踏み鎮める | 古代の鎮魂舞(ちんこんまい)に由来 |
| ⑤ | 柏手(かしわで)を打つ | 神を招く(呼び寄せの作法) | 神道の“手を打って神を呼ぶ”所作 |
| ⑥ | 差し上げの型(構え) | 神前への奉納ポーズ | 雲龍型=静、 不知火型=動 で表現 |
| ⑦ | 退場(礼をして下がる) | 神事の終結 | 神を送り、場を鎮めて去る |
🌿 所作の象徴的意味
| 所作 | 象徴 | 神話・古儀との関連 |
|---|---|---|
| 塩 | 祓い清め | 伊勢・出雲の「塩湯の禊」 |
| 四股 | 地を踏み鎮め、悪霊を祓う | 国譲り神話の「力比べ」や鎮魂 |
| 柏手 | 神を招く・感謝を伝える | 神拝作法(招魂・祈願) |
| 綱 | 結界・神の依代 | 神社の注連縄(白麻) |
| 太刀持ち | 神威の象徴 | 刀=神を護る聖具 |
| 露払い | 穢れを祓う | 行列儀式の先導神職 |
⚙️ 型ごとの動作差
| 要素 | 不知火型(しらぬい) | 雲龍型(うんりゅう) |
|---|---|---|
| 綱の輪 | 二重 | 一重 |
| 構え | 両手を真横に大きく広げる | 両手を胸の前で重ねる |
| 四股 | 正面を向いたまま踏む | 左右に振り返りながら踏む |
| 印象 | 豪快・陽 | 静寂・陰 |
| 象徴 | 太陽・雄々しさ | 月・沈静の力 |
吉田司家の伝書では「不知火は陽の型、雲龍は陰の型」と記され、
陰陽の調和を土俵に現す儀式とされています。
🌀 現代横綱の代表例(型ごと)
| 型 | 代表的横綱 |
|---|---|
| 不知火型 | 若乃花(初代)・北の湖・白鵬・照ノ富士 |
| 雲龍型 | 貴乃花・稀勢の里・朝青龍・鶴竜 |
どちらの型にも「吉田司家流の祓い舞」が基礎にあります。
🕊 意味のまとめ
横綱土俵入りとは――
神の前に己を清め、地を鎮め、神力を宿して立つ“祈りの舞”である。
力士が勝負の前に神とひとつになる儀礼。
-
「力」を誇示するためのパフォーマンスではなく、
神事としての祓いと感謝の儀式。 -
土俵は単なる競技場ではなく、神の座(神坐)。
-
横綱の綱は「神と人を結ぶ結界」であり、
四股は「地霊を鎮める祓いの舞」。
✨ 補足:儀式の言葉(吉田司家口伝)
「土俵は神座、四股は地を鎮むる舞、柏手は神を招く音、
綱は神を宿す縄なり。横綱、すなわち神の依代なり。」
――吉田司家『相撲司記』(写本伝)より。
Q:
チャッピー:
ざっくり結論:「谷風」を名指しで主人公にした“講談・落語の演目”は数本規模、いちばん流通しているのは**《谷風の情け相撲》(落語題《佐野山》)**です。歌舞伎は“谷風そのもの”よりも相撲世界を題材にした作品(例:『双蝶々曲輪日記』)が主流で、谷風は造形・逸話の“元ネタ”としてしばしば参照される、という立ち位置です。
代表例
-
講談:《谷風の情け相撲》(谷風が佐野山に星を譲る美談)。講談あらすじの資料あり。 koudanfan.web.fc2.com
-
落語:《佐野山》(講談由来の移植演目。高座紹介・解説が多数)。rakugo.ch+1
-
(講談・歌舞伎にまたがる脚色):谷風の人格・美談をまとめた**「谷風の七善根」**と呼ばれる系統の脚色が伝わる(人物項の解説)。 立命館大学アーカイブ
-
歌舞伎:相撲劇の定番は**『双蝶々曲輪日記』「角力場」**などで、登場力士は濡髪長五郎・放駒長吉(=モデルは当世力士)という“相撲世界そのもの”の芝居。谷風を名指し主役に据えた作は多くありません。 gooブログ
どのくらいの数?
-
固有名《谷風》を冠した講談・落語の“定番演目”はごく少数(数本)。実際に広く演じられるのは《谷風の情け相撲/佐野山》系が中心です。koudanfan.web.fc2.com+1
-
歌舞伎では**“谷風そのもの”を主役とする演目は稀で、相撲モチーフ全般が盛ん――谷風は浮世絵・評判記などでスター化し、芝居の人物造形の参照元**になった、というほうが実態に近いです。立命館大学アーカイブ+1
まとめ:
「谷風=名指し」の演目数は少数。ただし**《情け相撲/佐野山》は講談→落語へ定着**し、歌舞伎では“相撲劇全般”の文脈で谷風像が影響――という広がり方です。
必要なら、講談・落語の上演音源/口演記録のリンク集や、谷風を描いた浮世絵の代表作リストも作れます。
Q:
チャッピー:
よく演じられる代表作
-
雷電為右衛門
-
《雷電の初土俵》…雷電の生い立ち〜江戸入り。放送口演や絵本化の例も多いです。 〖公式〗JBS日本福祉放送+2光男ファンサイト+2
-
《小田原遺恨相撲》…谷風と共に仇討ちを果たす痛快譚。現役講談師の口演記録も確認できます。 光男ファンサイト+1
-
《三人相撲》《雷電と小野川》など、雷電周辺の連作話も定番。 光男ファンサイト+1
-
-
谷風梶之助
-
《谷風の情け相撲》…落語《佐野山》にも移植された名作。 光男ファンサイト+1
-
-
阿武松緑之助/稲妻雷五郎
-
文政期の名勝負・横綱免許をめぐる挿話が講談の素材に(研究・史料解説にも頻出)。 立命館大学アーカイブ
-
-
雲龍久吉/不知火光右衛門
-
型の名の由来を含む人物譚が語られることがあります。公演プログラム類に記録。 文化デジタルライブラリー
-
どのくらいの数?
“寛政力士伝”として複数話の連作が定着しており、文化デジタルライブラリーの公演記録でも雷電・小野川・初土俵など関連項目が多数確認できます(単独で十数件の登録がある回も)。つまり、谷風単発よりも「雷電を中心にした一連の講談群」が厚い、というのが実情です。 文化デジタルライブラリー
必要なら、演目ごとのあらすじ短評+参照口演リンク集を作ります。どの力士から並べますか?
Q:
チャッピー:
とても鋭い質問です。
――雷電為右衛門(らいでん・ためえもん)が江戸の「スーパースター」になった理由は、
単に強かっただけでなく、時代・人物・伝説・メディアが完璧に噛み合っていたからです。
順を追って説明しますね。
⚡️ 1. とにかく圧倒的に強かった(実績の神格化)
-
公式戦績:254勝10敗・勝率96.2%(史上最高)
しかも江戸の「本場所」は年に2回だけ。1回の負けが数年の記憶に残る時代です。 -
現代の横綱でも届かない異次元の勝率。
-
「雷電に土がつけば江戸に雨が降る」と言われたほど。
この異常な強さが、まず第一の伝説化の土台になりました。
🏯 2. 時代背景 ― 平和な江戸後期に求められた“英雄像”
-
江戸後期(寛政〜文化期)は戦乱もなく、
武士の戦場的英雄がいなくなった時代。 -
庶民にとっては「相撲取り=力の象徴」であり、
雷電のような豪力士は武士の代わりに“力の理想”を体現する存在でした。 -
つまり、「平和の時代の武人」として尊敬されたのです。
📜 3. メディア戦略の成功 ― 錦絵・瓦版・講談が拡散
-
雷電は浮世絵の人気被写体No.1力士。
歌川国芳・国貞などが「雷電の立ち姿」を繰り返し描きました。 -
江戸市中では「雷電手形」「雷電土産」まで出回り、
まさに“グッズ化”された初のスポーツスター。 -
講談・落語・草双紙(絵入り小説)で繰り返し語られた結果、
**「史実と伝説が融合したヒーロー像」**が定着しました。
💥 4. “義と情”の物語性 ― 講談向きの人格
-
雷電は「強さ+正義+優しさ」の三拍子で語られました。
-
弱きを助ける。
-
不正に立ち向かう。
-
無益な力比べを避け、人格者として振る舞う。
-
-
こうした逸話が講談師に好まれ、
《雷電の初土俵》《雷電と谷風》《雷電小田原遺恨相撲》など
「勧善懲悪+力の美徳」型の連作が生まれました。 -
つまり、講談でいう「南総里見八犬伝」的な勧善譚を、現実の人物で語れる素材だったわけです。
🧍♂️ 5. 人柄と見た目がキャラクター化に向いていた
-
身長197cm、体重170kg以上(当時の平均より40cm大きい)。
-
しかも面長で、威厳があり、江戸では「雷神の化身」と呼ばれた。
-
名も「雷電(=雷の力)」という響き。
→ 名前そのものが“講談向け”です。
🎭 6. 「江戸三大力士」の中心として語られ続けた
-
谷風梶之助・小野川喜三郎とともに**「江戸三大力士」**。
-
谷風=徳の象徴、小野川=美男で芸、
雷電=力と正義。
→ 三者が揃って「物語の三英雄」として語られやすかった。
🕊 まとめ
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 強さ | 歴史最高勝率・無敵の記録 |
| 時代性 | 平和の時代に現れた“武の象徴” |
| メディア | 錦絵・瓦版・講談・落語で拡散 |
| 人格 | 勇猛で正義感、情け深い |
| 造形 | 巨体・「雷電」という名・絵になる存在 |
→ 結果、「江戸のスーパーヒーロー」として
史実を超えた伝説的人気を獲得した。
📜もし次に見てみたい方向があれば:
-
「雷電を主人公にした講談・落語の具体的演目リスト(年代・講談師別)」
-
「雷電を描いた浮世絵(国芳・国貞・広重)」一覧
-
「谷風 vs 雷電」を扱った創作の変遷(講談→小説→映像)
どの方面を掘り下げましょうか?
Q:
チャッピー:
もちろんです。
以下は、史料・相撲年鑑・地元記録(信濃国丸子・長野県東御市)などを総合した、
**雷電為右衛門(らいでん・ためえもん)**の正確な来歴です。
⚡️ 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本名 | 関 太郎吉(せき・たろきち) |
| 四股名 | 雷電為右衛門(らいでん・ためえもん) |
| 生年 | 明和4年(1767)1月生まれ |
| 没年 | 文政8年(1825)2月11日没(享年59) |
| 出身地 | 信濃国小県郡大石村(現・長野県東御市) |
| 身長体重(伝) | 約197cm/169kg(※当時の平均より+40cm) |
| 所属部屋 | 谷風梶之助の弟子筋(伊勢ノ海部屋) |
| 番付最高位 | 大関(横綱免許は未授与) |
| 出身藩 | 松江藩(のち出羽秋田藩抱え力士) |
🧩 来歴詳細
◉ 幼少〜江戸入り
-
信濃・大石村の農家に生まれる。
幼少期から非常に体格がよく「村の神童」「雷の子」と呼ばれた。 -
若年時に奉納相撲で評判となり、上州(群馬)→江戸へ上京。
-
当時の名力士谷風梶之助に見出され、**弟子(同門)**として伊勢ノ海部屋へ入門。
-
江戸本場所でデビュー(天明4年〈1784〉頃)。
◉ 全盛期(寛政〜文化年間)
-
デビューから十数年ほぼ無敗。
-
公式戦績:254勝10敗、引分21、預り14、休22(勝率96.2%)。
-
35場所中28場所で最高成績(優勝相当)。
-
当時の番付制度では「大関」止まりだが、実質的には最上位の扱い。
-
立合いの速さと腕力が圧倒的で、「雷電張り手」「雷電投げ」など多彩な技を使った。
-
幕府上覧相撲(将軍観覧の取組)にもたびたび登場。
-
同時代の谷風、小野川亡き後の相撲界を一手に支えた。
◉ 人柄・逸話
-
性格は穏やかで義理堅く、「弱きを助ける」人情家。
-
江戸市中では「雷電の情け」「雷電の正義」として講談・瓦版で評判。
-
禁じ手(張り手・突っ張り・金的など)を避け、
「雷電は大関として品格を重んじた」と伝えられる。 -
「三年に一度の負け」でさえ市中のニュースになった。
◉ 晩年
-
引退後は郷里・信濃へ戻り、庄屋(村役人)を務めた。
-
村の道路整備・寺社寄進など、郷土事業に尽くした。
-
「力士の鑑」「義の人」として村人から慕われた。
◉ 死去
-
文政8年(1825年)2月11日没、享年59(満58歳)。
-
病因は、史料により**脳卒中・風邪の悪化・中風(脳血管疾患)**など諸説あり。
急死ではなく、老衰・病気による自然死とされます。 -
墓所は長野県東御市御堂・雷電寺(願行寺)。
墓碑には「雷電為右衛門之墓」と刻まれ、今も参拝者が絶えません。 -
地元では命日を「雷電忌」と呼び、毎年供養祭が行われています。
⚖️ 歴史的評価
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 相撲史 | 史上最高勝率、江戸期最強の力士 |
| 人格 | 徳・義理・情けを兼ね備えた「理想の力士像」 |
| 文化史 | 錦絵・講談・落語・草双紙・浮世絵の常連題材 |
| 地方史 | 信濃国の英雄・“日本最初のスポーツスター” |
🏯 史跡・遺品
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 生家跡 | 長野県東御市「雷電の里」公園として整備 |
| 墓所 | 東御市御堂・願行寺(雷電寺) |
| 像 | 長野県東御市「雷電くるみの里」道の駅に銅像あり |
| 遺品 | 手形、化粧廻し、奉納絵馬などが市立博物館に展示 |
🌩 雷電という名の由来
-
「雷電」は雷の神・雷神様のように強いことから。
-
師匠の谷風がその剛力を見て命名したとも伝わります。
-
四股名「為右衛門」は、豪農出身の武家名風を意識したもの。
🕊 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生没年 | 1767〜1825(59歳没) |
| 出身 | 信濃国大石村(長野県東御市) |
| 最高位 | 大関(実質・最強格) |
| 戦績 | 254勝10敗(勝率96.2%) |
| 性格 | 義理堅く温厚、品格を重んじる |
| 死因 | 病没(中風または風邪) |
| 墓所 | 東御市願行寺(雷電寺) |
| 称号 | 江戸最強・相撲の神・“寛政の怪力男” |
ご希望があれば、
📜「雷電の講談・浮世絵・民話リスト(作品別に内容と発表年代)」
もまとめてお見せできます。
どちらにご関心ありますか?
Q:
チャッピー:
結論:公式の本場所での取組は一度もありません。
-
理由は、雷電(関太郎吉)が谷風の内弟子=直接の教え子だったためで、当時その関係では本場所の対戦が組まれませんでした。研究サイトにも「雷電は谷風の内弟子となったため谷風との対戦は無かった」とはっきり記されています。立命館大学アーカイブ
-
そもそも雷電は谷風の“コーチ”を務めた伊勢ノ海系で育成されたとされ、雷電の項でも「Tanikaze became his coach(谷風が師となった)」と説明されています。ウィキペディア
参考までに、同時代のもう一人の横綱・小野川喜三郎とは雷電は度々対戦しており、寛政2年(1790)の一番では**大物言いの末「預かり」**と裁定された記録が紹介されています。ダイヤモンド・オンライン
要するに、雷電×谷風の“夢の対決”は公式記録上は実現せず、雷電は谷風没(1795年)後に大関へ昇進して相撲界の主役になっています。