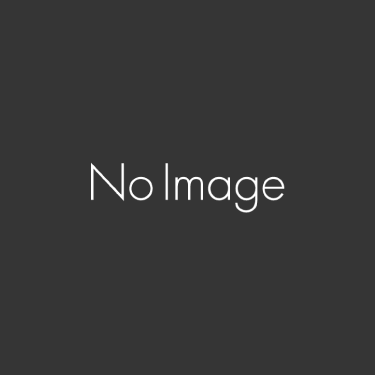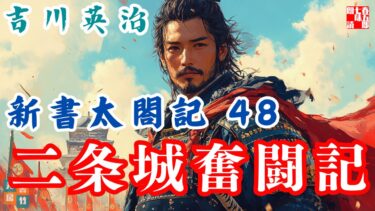戊辰戦争没発
そのさなか、江戸城明け渡し後の混乱の中、徳川慶喜の警護と、江戸市中の治安維持を行ったが、慶喜水戸退去後も寛永寺にとどまりつづけ、隊士は四千名にまでふくれあがる。
新政府軍と衝突を繰り返した結果、1868年7月4日の上野戦争につながりました。
彰義隊は敗北し、江戸は東京にかわりました。
1874年、作中登場の小川椙太の陳情で、彰義隊の墓を上野に建立。1881年に立て直された墓の揮毫は山岡鉄舟が行いました。なお、小川家は、2003年まで、墓守をしつづけました。
作中、沼津の仲間を裏切って、仕官願いの書類をだしていたもの、これも史実なんですが、もう一人、上野岩太郎というものと二名で出しており、
吉沢と藤田が討ち取ったのはこの二名。沼津勤番組長の屋敷に、この首をおいたという。
事件後に、大谷内らの建白書は受け入れられ禄米の支給もはじまりました。
とはいえ、牧野原開墾が条件でした。
牧之原にはすでに新番組(精鋭隊)が中條潜蔵の指揮で開墾にあたっており、ここに旧彰義隊85戸が加わる形になりました。
問題は駿河政府に「仇討許可申請」を出していた遺族らの処理でした。
新政府は仇討ち禁止令をすでに出しており、駿河藩も許可を出していませんでした。
粛清事件の責任は、龍五郎一人が負うことになり、龍五郎は医王寺で腹をきり、源六の手で介錯されています。
大谷内は親分肌で面倒見が良く、農民からの感謝状なども残っているそう。
享年37歳。
辞世の句は
「むら雲に 月はかくれて ありしかど 今日はれて行く 死出の山みち」
十八人いた兵隊組頭の一人で、戦争では両腕に通銃創を負い、牛込箪笥町の自宅に潜伏した後、駿河へ移住しました。錦絵の題材にもなっております。
■登場人物
大谷内龍五郎……彰義隊九番隊隊長
吉沢市之輔……幕臣。彰義隊に加わる。
藤田寛二……吉沢の友人
斎藤金左衛門……大谷内の盟友
歌……大谷内の娘
天野八郎……彰義隊隊長
渋沢成一郎……彰義隊設立にかかわる。
土肥庄次郎……露八の幕臣時代
与茂作……庄屋
源六郎……斉藤金左衛門の息子
露八……幇間
中条潜蔵……剣客、源六郎を預かる。
■用語集
・澎湃(ホウハイ)
勢いよく波が打ち寄せる様子。または、物事が大きく動き出すさまを指す。転じて、力強く感情があふれる状況を表すこともある。
・方丈(ホウジョウ)
禅寺の住職が住む部屋や建物を指す。転じて、簡素な住まいを表す場合もある。
・血判(ケッパン)
血を使って署名や印を押すこと。誓約や覚悟を示す際に行われた。
・公憤(コウフン)
公の場で共有される怒り。社会全体が不正や不義に対して抱く憤り。
・痛罵(ツウバ)
激しい言葉で罵倒すること。相手を厳しく非難する際に使われる表現。
・殺誅(サッチュウ)
罪を犯した者を処刑すること。厳しい刑罰としての殺害を指す。
・偉軀(イク)
大きく立派な体格。特に、堂々とした体つきを指す。
・鬱勃(ウツボツ)
感情や力が内にこもり、湧き上がってくるさま。特に、抑えきれない情熱や気力を表す。
・大旆(タイハイ)
大きな旗。特に、戦場や儀式で掲げられる壮大な旗を指す。
・塵芥(ジンカイ)
役に立たない物や人。特に、不要とされるものを指す侮蔑的な表現。
・磊落(ライラク)
心が大きく、細かいことにこだわらない様子。度量が広く、豪放な性格。
・四斤砲(シキンホウ)
江戸時代や明治初期に使用された火砲で、砲弾の重さが四斤(約2.4kg)であることを指す。
・隊伍(タイゴ)
整列した隊列や組織的な集団。軍隊や団体が整然と並んだ状態を表す。
・木柵(モクサク)
木で作られた柵や囲い。防御や区切りとして設置される。
・反間(ハンカン)
敵を内部から崩すために仕掛ける策略。特に、敵側の信用を失わせる陰謀を指す。
・睥睨(ヘイゲイ)
傲慢な目つきで周囲を見下すこと。特に、強い権力や威圧感を示す場合に使われる。
・小普請(コブシン)
江戸時代の旗本や御家人の中で、特定の役職や仕事を持たない者を指す。地位はあるが実務を伴わない状態。
・愧死(キシ)
恥ずかしさのあまり死にたくなるほどの気持ち。極度の羞恥心を表す。
・焦眉(ショウビ)
眉が焦げるほど緊急な状態や危機。特に、差し迫った危険を表現する言葉。
・警史(ケイリ)
警官を指す。
・安気(アンキ)
心が穏やかで平静なこと。安心して落ち着いた状態。
・詮考(センコウ)
物事を詳しく考え、解決策を探ること。
・衣鉢(イハツ)
師匠や先人から受け継いだ技術や教え。特に、学問や芸道の継承を指す。
・名取(ナトリ)
特定の流派で正式に名を与えられた人。特に、芸能や武道で師匠から認められた者。
・荻江(オギエ)
荻江節(おぎえぶし)を指す言葉。江戸時代に発展した浄瑠璃の一種で、情緒豊かな音楽形式。
■目次
0:00 夜明け前 一
7:17 夜明け前 二
13:31 夜明け前 三
21:03 夜明け前 四
27:23 夜明け前 五
32:34 気ちがい茄子 一
36:50 気ちがい茄子 二
41:35 気ちがい茄子 三
46:03 気ちがい茄子 四
54:59 気ちがい茄子 五
1:02:45 気ちがい茄子 六
1:07:16 東京新誌 一
1:13:33 東京新誌 二
1:19:55 東京新誌 三
1:23:29 東京新誌 四
#吉川英治 #朗読 #七味春五郎 #サムライ